2024.3.12
毎年3月前半は仕事が忙しいので、コンサートは諦めているのですが、ピリオド楽器専門のピアニスト、川口成彦さんが18世紀オーケストラと共演するので、これだけは行こうと決めていました。
「The Real Chopin x 18世紀オーケストラ」
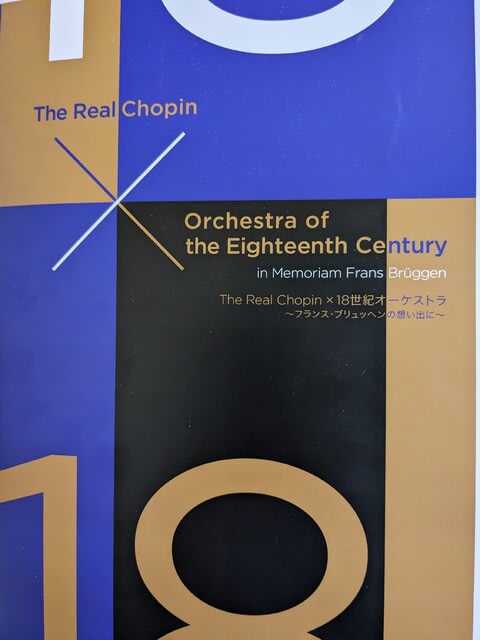
川口成彦さんについては、一昨年の12月に昭和音楽大学で開かれた大学所蔵の19世紀のピアノ・プレイエルの修復後お披露目コンサートで初めて演奏を聴いて感銘を受け、気になるピアニストの一人となっています。(このコンサートについては昨年中のブログに書いています。)
第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位受賞者。
当日は夕方になって土砂降りの雨となりましたが、頑張って東京オペラシティコンサートホールへ出かけました。地下鉄の初台駅からホールへは直結なので濡れることはないのですが、私の足元は長靴という出で立ち。😁
18世紀オーケストラは、1981年にフランスの故フラン・ブリュッヘンという方が友人達と結成したものですが、現在は世界20カ国以上の演奏家55名によって構成されていて、全員が18世紀から19世紀初頭の音楽を専門とする古楽器や復元楽器の専門奏者です。
私が到着すると、ステージの真ん中に置かれたプレイエルピアノを調律師の方が念入りに調整しています。ピアノの脚元に運搬用のキャスターが付いていましたが、現代になって後から付けたものでしょう。
ピアノは、1845年製のプレイエル。所有者はエンマ・秋山氏。


演奏曲目とソリスト:
1. モーツァルト 交響曲第35番ニ長調K.385「ハフナー」
チェロ以外は、ヴァイオリン、コントラバス、金管楽器も全員立って演奏していました。
チェリストだけ座っていた理由は、現代ではチェロの下にエンドピンを付けて立てていますが、昔はそれがなかったため、チェロを両足に挟んで支える必要があるというわけです。大変でしたね。
また、ヴァイオリンですが、全員、顎当ても肩当ても付けていません。顎が当たるところに布のようなものを充てているだけでした。
これは驚きでした。昔はこうだったのですね。
顎当て、肩当てがないと滑って演奏どころではないような気がするし、いかり肩の人ならまだ良いですが、なで肩の人は無理でしょう。肩に力が入って、肩凝りに悩まされそうです…。
2.ショパン 「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」による変奏曲変ロ長調Op.2
ピアノ: 川口 成彦
ショパンが学生時代に作曲した作品で、モーツァルトのオペラを題材にしています。この曲をちゃんと聴いたのは初めてでしたが、ピアノが主役で、オーケストラは伴奏という印象。通常のピアノほどフォルテが強く出ないこのピアノで川口さんはエレガントに演奏していました。
3.藤倉 大 Bridging Realms for fortepiano
第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクールとコンサート企画カジモトとの共同委嘱作品 (日本初演)
ピアノ: ユリアンナ・アヴデーエワ
水滴の音を感じさせるような響きで始まり、もう一度聴きたいと思える美しい曲でした。
ここで、調律師がピアノの調整を行いました。
4.ショパン アンダンテ・スピオナートと華麗なる大ポロネーズOp.22
ピアノ: ユリアンナ・アヴデーエワ
この曲は、ピアノ独奏作品と思われがちですが、ショパンがピアノとオーケストラのために書いた最後の作品です。
アヴデーエワさんは2010年のショパン国際コンクールでの優勝者。アルゲリッチさんに続く女性で2番目の優勝者です。
ダンパーペダルを何度も強く踏んでいたので、ピアノが壊れないか気になりましたが、素晴らしい演奏でした。現代ピアノでも演奏を聴いてみたいピアニストです。
4番目の曲の演奏中、ピアノの響きがどんどん変化して行くのに気づきました。調節が大変なピアノです。
休憩となり、調律師によりまた調律です。
5.ショパン ピアノ協奏曲第2番へ短調Op.21
ピアノ: トマシュ・リッテル
ポーランド生まれ。川口さんが2位を受賞した同じ年のコンクールでの優勝者です。
ピアノの響きの変化を強く感じた演奏でした。リッテルさんが弾き始めると、前曲まで表れなかったクリアな音が流れてきました。アヴデーエワさんがペダルを強く踏んでも出てこなかった音響です。リッテルさんはプレイエルのピアノの特性をよく捉えていると感じました。
興味深いコンサートでしたね。
とても貴重な経験だったと思います。




















