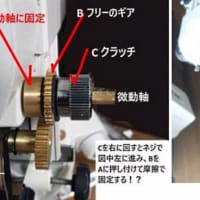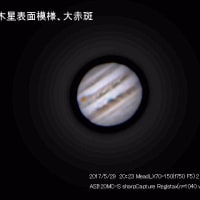11月22日の朝日新聞土曜特別版「be」に、かって「かぐや姫」が歌って大ヒットしたフォークソング、「神田川」の作詞作曲にまつわるエピソードがつづられていた。
当時、早稲田の学生だった作詞家、喜多條忠(まこと)の実体験から生まれた詞だという。
当初、「憑依したように」一気に書きあげられた詞は、「なにも怖くなかった」で終っていた。
「ところが、ふと『何か怖いものがあったかな』と考えた。そのとき頭に浮かんだのがデモから帰った下宿でカレーライスを作る彼女の後姿だ。このまま一市民として安穏と生きる人生。それは拒まなければならないと思った。
とっさに、<ただ、貴女のやさしさが怖かった>と付け加えた。」
この詩の中の「アナタ」は、「貴方」だと思っていたが、実は最後のこの部分でだけ「貴女」なのだという。
このエピソードに思わず涙がでそうになった。
「このまま一市民として安穏と生きる人生。それは拒まなければならないと思った。」というのは、あの、体制批判から「自己否定」へと身の程知らずな闘いを意思した全共闘世代にしか分からない心情だろう。
それとも、いつの時代にも同じような矜持を持つ若者もいるのだろうか。
いやいや、考えてみれば、当時は「一市民として安穏に生きる」ことが、当たり前にできていた時代だからこそ、若者らしい突っ張りをそういう形で表せたのであって、今、多くの若者が安穏に生きること自体が許されない中では、おそらくそんな台詞は出ないのだろう。
記事を読み進めていて、もう一箇所、不覚にも涙が出そうになったのが、記事の終わりのほうの一節。
「金をもうけて高級車に乗るのがアメリカンドリームなら、『家は漏らぬほど。食は飢えぬほど』という茶の湯の価値観に、日本人のプライドがある。」
「漏らぬほど、飢えぬほど」と言えるほど清貧に生きてきたわけではない、いやむしろそんな覚悟とは程遠いところでおどおどと生きてきたように思うけれど、それでも金銭欲や上昇志向に飲み込まれることだけはしなかったつもりだ。この一節にグッと来てしまったのは、そんな自分へのねぎらいの一言に聞こえてしまったのかもしれない。
当時、早稲田の学生だった作詞家、喜多條忠(まこと)の実体験から生まれた詞だという。
当初、「憑依したように」一気に書きあげられた詞は、「なにも怖くなかった」で終っていた。
「ところが、ふと『何か怖いものがあったかな』と考えた。そのとき頭に浮かんだのがデモから帰った下宿でカレーライスを作る彼女の後姿だ。このまま一市民として安穏と生きる人生。それは拒まなければならないと思った。
とっさに、<ただ、貴女のやさしさが怖かった>と付け加えた。」
この詩の中の「アナタ」は、「貴方」だと思っていたが、実は最後のこの部分でだけ「貴女」なのだという。
このエピソードに思わず涙がでそうになった。
「このまま一市民として安穏と生きる人生。それは拒まなければならないと思った。」というのは、あの、体制批判から「自己否定」へと身の程知らずな闘いを意思した全共闘世代にしか分からない心情だろう。
それとも、いつの時代にも同じような矜持を持つ若者もいるのだろうか。
いやいや、考えてみれば、当時は「一市民として安穏に生きる」ことが、当たり前にできていた時代だからこそ、若者らしい突っ張りをそういう形で表せたのであって、今、多くの若者が安穏に生きること自体が許されない中では、おそらくそんな台詞は出ないのだろう。
記事を読み進めていて、もう一箇所、不覚にも涙が出そうになったのが、記事の終わりのほうの一節。
「金をもうけて高級車に乗るのがアメリカンドリームなら、『家は漏らぬほど。食は飢えぬほど』という茶の湯の価値観に、日本人のプライドがある。」
「漏らぬほど、飢えぬほど」と言えるほど清貧に生きてきたわけではない、いやむしろそんな覚悟とは程遠いところでおどおどと生きてきたように思うけれど、それでも金銭欲や上昇志向に飲み込まれることだけはしなかったつもりだ。この一節にグッと来てしまったのは、そんな自分へのねぎらいの一言に聞こえてしまったのかもしれない。