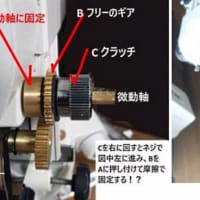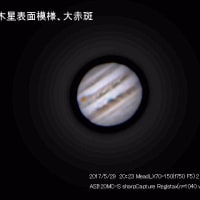あるところでたまたま目にとまった本(「核戦争の心理学」ジェイムス・トンプソン編著 黒澤満訳 西村書店)の中に印象的なエピソードが綴られていた。
それは1978年9月にアメリカのカーター大統領が仲介役となってキャンプデービットで開かれたイスラエルのベギン首相とPLOアラファト議長の和平会談の話である。
会談は、非公式で格式ばらない雰囲気の中で繰り返され、率直な議論が続いたが、会談を重ねるほど感情を剥き出しにした対立が深まり、抜き差しならぬ事態となった。約2週間にも及ぶ会談の末、3首脳は勿論、関係者のすべてが、いかなる合意も不可能であり会談は失敗だと確信した。
最後に3首脳が揃って写真を撮った。ベギンが、孫たちのために写真が欲しいと言い、互いに裏にサインをして交換することになった。そのときカーターの秘書が、ベギンの孫たちの名も書くようにとカーターに耳打ちした。カーターは言われるままにベギンの孫たちの名を書き添えた。
孫たちの名を見たベギンは、感激の涙とともに孫たちについて語った。その1時間後、ベギンは会談の再開を申し出た。
こうして和平に向けた画期的な合意が達成された。
著者は言う。「個人の態度に変化が起こるのは、個人の深層にある感情に触れたときである。」
それは、言うまでもなく世界の首脳や重要人物にだけではなく、全ての人について真実に違いない。
しかし、こうして歴史的な和解の道を歩み始めたベギンも、彼を変えた深い心理的経験を共有できなかった盟友たちの反発を受け、ついに暗殺されてしまった・・。その結果が現在のイスラエルによるパレスティナへの際限のない侵略、虐殺であり、さらに「テロ」による反撃と身勝手な「報復」である。
「世の中を変えたい」と身のほど知らずな思いに突き動かされ、理屈で説き伏せれば人が動くと思い込んでいた学生時代。
その浅はかな人間理解の果てに一面的な理屈の物差しで他者を裁き、命を奪うまで暴走した者たちも、確かに我が同世代人だった。
世間知らずなまま「職場闘争で本物の労働運動を」と、もがいていた20代の頃、学生とは違う「酸いも甘いもかみ分けた」大人たちを前にして、人の態度、考えを変えるのは理屈ではないと思い知ったものの、かといって「とにかく一緒に飲めば良い」「冠婚葬祭は大事にしろ」という先輩たちのスタイルにもなじめず、どうすれば良いのか、皆目わからなかった。
個々の立場やしがらみや保身や思い込みや党派的帰属意識や、ありとあらゆる障害を超えて、たった一人の「心の琴線に触れる」ことは容易ではない。まして、次々と多くの人の心を動かすことは、山を動かすに等しいかもしれない。
しかも、往々にしてそんな地道な努力をあざ笑うように、マスとしての人心は一気に雪崩をうって危険な方向へと動いてしまう・・・。
たまたま目にとまった本の、たまたま開いたページのエピソードが、私に、世界のこと、平和のこと、この国の政治のこと、組合運動のこと、自分の資質や生きてきた姿勢のこと・・などなど無限のテーマを突きつけてくる。
それは1978年9月にアメリカのカーター大統領が仲介役となってキャンプデービットで開かれたイスラエルのベギン首相とPLOアラファト議長の和平会談の話である。
会談は、非公式で格式ばらない雰囲気の中で繰り返され、率直な議論が続いたが、会談を重ねるほど感情を剥き出しにした対立が深まり、抜き差しならぬ事態となった。約2週間にも及ぶ会談の末、3首脳は勿論、関係者のすべてが、いかなる合意も不可能であり会談は失敗だと確信した。
最後に3首脳が揃って写真を撮った。ベギンが、孫たちのために写真が欲しいと言い、互いに裏にサインをして交換することになった。そのときカーターの秘書が、ベギンの孫たちの名も書くようにとカーターに耳打ちした。カーターは言われるままにベギンの孫たちの名を書き添えた。
孫たちの名を見たベギンは、感激の涙とともに孫たちについて語った。その1時間後、ベギンは会談の再開を申し出た。
こうして和平に向けた画期的な合意が達成された。
著者は言う。「個人の態度に変化が起こるのは、個人の深層にある感情に触れたときである。」
それは、言うまでもなく世界の首脳や重要人物にだけではなく、全ての人について真実に違いない。
しかし、こうして歴史的な和解の道を歩み始めたベギンも、彼を変えた深い心理的経験を共有できなかった盟友たちの反発を受け、ついに暗殺されてしまった・・。その結果が現在のイスラエルによるパレスティナへの際限のない侵略、虐殺であり、さらに「テロ」による反撃と身勝手な「報復」である。
「世の中を変えたい」と身のほど知らずな思いに突き動かされ、理屈で説き伏せれば人が動くと思い込んでいた学生時代。
その浅はかな人間理解の果てに一面的な理屈の物差しで他者を裁き、命を奪うまで暴走した者たちも、確かに我が同世代人だった。
世間知らずなまま「職場闘争で本物の労働運動を」と、もがいていた20代の頃、学生とは違う「酸いも甘いもかみ分けた」大人たちを前にして、人の態度、考えを変えるのは理屈ではないと思い知ったものの、かといって「とにかく一緒に飲めば良い」「冠婚葬祭は大事にしろ」という先輩たちのスタイルにもなじめず、どうすれば良いのか、皆目わからなかった。
個々の立場やしがらみや保身や思い込みや党派的帰属意識や、ありとあらゆる障害を超えて、たった一人の「心の琴線に触れる」ことは容易ではない。まして、次々と多くの人の心を動かすことは、山を動かすに等しいかもしれない。
しかも、往々にしてそんな地道な努力をあざ笑うように、マスとしての人心は一気に雪崩をうって危険な方向へと動いてしまう・・・。
たまたま目にとまった本の、たまたま開いたページのエピソードが、私に、世界のこと、平和のこと、この国の政治のこと、組合運動のこと、自分の資質や生きてきた姿勢のこと・・などなど無限のテーマを突きつけてくる。