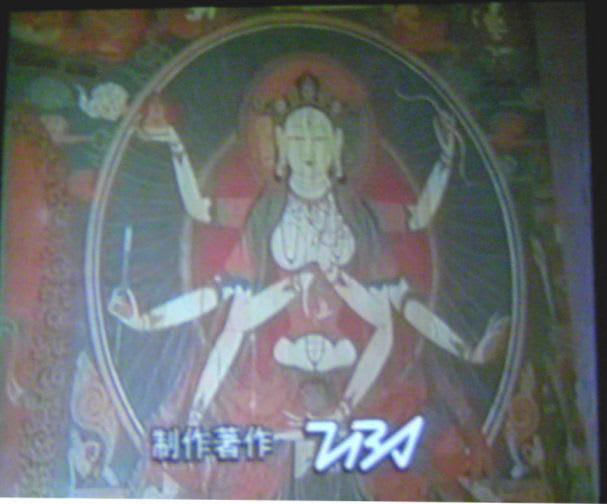2009/2/23
住民と博物館の連携によるフィールドミュージアムの展開
現地ワーキング
東京湾三番瀬とその周辺
主旨:地域の文化、歴史、自然などの貴重な資源を発見・認識し、守り育むために地域住民と博物館が協力して行えるフィールドミュージアム活動について、現地を見て歩きながら意見交換等タウンミーテイングを行います。当日は、大潮ですから干潟が遠くまで広がります。
まず現地を知ろう
日 時:2009年3月28日(土)9:00 ~ 10:30
場 所:船橋漁港から乗船 三番瀬へ、その周辺と干潟を歩く (500円) *持ち物:長靴など濡れてもいい履き物を持参ください
交通の案内
乗船希望者は、京成線大神宮下車:船橋漁港へ徒歩15分(ららぽーと側の漁港)船橋漁港倉庫前から船が出ます。
直接三番瀬海浜公園には:バス 京成線船橋駅前:京成バス乗場「ふなばし三番瀬海浜公園」行き下車です。
JR京葉線:二俣新町下車徒歩25分 駐 車 場 有料
お問い合わせ先:千葉県立中央博物館(電話 043-265-3111)
タウンミーテイング
解説1:東京湾三番瀬の干潟の生きものと漁業について
10:30~ (財)日本自然保護協会 会長 ・・・田畑貞寿氏
船橋市漁業恊同組合長 ・・・大野一敏氏
千葉県野鳥の会 ・・・田久保晴孝氏
解説2:フィールドミュージアムについて
13:00 ~ 千葉県立中央博物館 副館長 ・・・中村俊彦氏
タウンミーティング
フィールドミュージアム活動についての意見交換 (16時30分 解散予定)
場所 船橋海浜公園学習室 (2F)
* 昼食:各自用意してください(近くにコンビにはあります)
フイールドミュージアム タウンミーティング 今後の予定
●3月1日 (日):千葉県立中央博物館大利根分館とその周辺
●5月16日(日):関宿城周辺
●6月20日(土):勝浦・理想郷周辺
主 催:NPO法人千葉まちづくりサポートセンター/千葉県フィールドミュージアム事業推進委員会
協 力:(財)船橋市公園協会/船橋市漁業恊働組合/里山シンポジューム実行委員会
この事業は「花王・コミュニティミュージアム・プログラム2008の助成金を受けました。
住民と博物館の連携によるフィールドミュージアムの展開
現地ワーキング
東京湾三番瀬とその周辺
主旨:地域の文化、歴史、自然などの貴重な資源を発見・認識し、守り育むために地域住民と博物館が協力して行えるフィールドミュージアム活動について、現地を見て歩きながら意見交換等タウンミーテイングを行います。当日は、大潮ですから干潟が遠くまで広がります。
まず現地を知ろう
日 時:2009年3月28日(土)9:00 ~ 10:30
場 所:船橋漁港から乗船 三番瀬へ、その周辺と干潟を歩く (500円) *持ち物:長靴など濡れてもいい履き物を持参ください
交通の案内
乗船希望者は、京成線大神宮下車:船橋漁港へ徒歩15分(ららぽーと側の漁港)船橋漁港倉庫前から船が出ます。
直接三番瀬海浜公園には:バス 京成線船橋駅前:京成バス乗場「ふなばし三番瀬海浜公園」行き下車です。
JR京葉線:二俣新町下車徒歩25分 駐 車 場 有料
お問い合わせ先:千葉県立中央博物館(電話 043-265-3111)
タウンミーテイング
解説1:東京湾三番瀬の干潟の生きものと漁業について
10:30~ (財)日本自然保護協会 会長 ・・・田畑貞寿氏
船橋市漁業恊同組合長 ・・・大野一敏氏
千葉県野鳥の会 ・・・田久保晴孝氏
解説2:フィールドミュージアムについて
13:00 ~ 千葉県立中央博物館 副館長 ・・・中村俊彦氏
タウンミーティング
フィールドミュージアム活動についての意見交換 (16時30分 解散予定)
場所 船橋海浜公園学習室 (2F)
* 昼食:各自用意してください(近くにコンビにはあります)
フイールドミュージアム タウンミーティング 今後の予定
●3月1日 (日):千葉県立中央博物館大利根分館とその周辺
●5月16日(日):関宿城周辺
●6月20日(土):勝浦・理想郷周辺
主 催:NPO法人千葉まちづくりサポートセンター/千葉県フィールドミュージアム事業推進委員会
協 力:(財)船橋市公園協会/船橋市漁業恊働組合/里山シンポジューム実行委員会
この事業は「花王・コミュニティミュージアム・プログラム2008の助成金を受けました。