魂 魄 の 宰 相 第三巻
前書き
現代は、世界中のどの国家も、その国民の大部分が譬え狂信する宗教があろうと、その宗教の教義を尊重して国家を運営していくことは殆ど不可能となっている。国民の生活をより豊かなものにするにせよ、外国との紛争を深刻な解決手段に頼ること無く解決するにせよ、地球規模での国際社会との協力関係を構築しておかなければならず、そのことは今日では近代国家成立の必至の条件であろう。随って、如何なる国に於いても、その国独自の国民の持つ価値観とは別に、国際基準としての中道の価値体系を大きく取り込んで国を運営していかざるを得ないのが現状となっているのだ。然し、現実は、この国際的な統一基準も力の論理によって歪められ、大国同士の国益独占の道具として使われることも頻繁であるのだ。更に言えば、国際基準は如何なる国の伝統的或いは地域的特異性を無視して仕舞、結果、国の存在意義をも不明確にする両刃の本質を持っている代物と言えよう。
何れにせよ、今日の現実では何れかの国家に属すこと無く個人の存在は有得無いのであり、又、世界を股に掛けなければ生きていけないような人は今日にあっても稀な存在であるのだから、普通の国民の価値観は、その属する国の伝統や地域性と深く関わりを持てる範囲の規模に収まるものでなければ、日々の暮らしは成り立たない。
国家運営の根本原理が国民生活の安定や向上にあるとするならば、国民が持つ価値観とかけ離れた政策は全く的外れなものである。為政者が確りとした『価値観』(それを論理的に体系化していくと『思想』が生まれる)を持っていなければ、国の方向性は定まらず、やがて国家は衰亡して仕舞うだろう。 王安石は改革に向かって、先ずは基本的価値観の統一をどう纏め上げていくかに心血を注いだのだ。
上古の時代では国家は必然のものでは無く、君主を神輿に担ぎ上げる者の忠誠心が強くなければ、忽ち国家は転覆或いは壊滅されて仕舞っただろう。譬え暴君であろうと臣が権威の象徴としての君への忠誠を通さなければ、幾ら善政を積んでも、臣が君に権威を認めなければ、国は滅亡するだろう。その権威は忠臣が不断に守らなければ、周囲は恐れ入ら無いのだ。 忠臣の寝返りは、新政権にとっても、喜ばしいものでは無いのだ。
さて、稀代の転向派馮道は為政者が変わる度に転向したのだが、力任せの政権交代には行儀良い理屈は通ら無い。 民の為には忠義など糞食らえだ。
理念無き改革は意味が無い。改革には初め理念ありきであり、その理念は確固たる思想によって打ち立てられなければならず、その思想は価値観に裏打ちされたもので無ければならないのだ。
第三巻 学者は経を全て得ることを貴び、仏教は老申韓安を軽くする
一、道は先王の法である
嘉祐八年の三月、仁宗が崩御して、四月に皇子(英宗)が即位した。 八月、王安石の妻の呉氏は北京で亡くなって、十月、王安石は金陵に妻を埋葬した。王安石は、その後三年間金陵で喪に服したので英宗の時代は世に出てい無い。金陵での数年間に、王安石は自分の長年の構想を整理して、自身で初めた変革ついての論理構成を得心して完成させた。
そうこうしている間は新学を広めることが出来無かったので、その後真っ先に彼が為したのは学術講演の学生を募集することであった。結果、陸佃、黄原、李定、侯叔献、蔡卞等の人達は、皆全て当時彼から学ぶことになった。このように、彼は同志や継承者を多く募って新学の基礎を打ち立てたのだ。
王安石は若い頃「孟、韓之心為心」と孔孟を目指す志を立て、儒学を復興することを自分の務めとしたのだが、そのことは当時の多くの儒学者の目標でもあったのだ。如何に儒学を復興するかという方法論については彼独自の抜群に優れた見解を持っていた。彼は、孔孟の言葉を只繰り返すことを是とせず、その精神を保ち乍新しい解釈をすることを試みようとしたのだ。 やっとの思いで生き延びて来た革新は漸く起動し始めたのだ。「それでは如何にして新機軸を打ち出そうか?」彼は一つの重要な方法として古いと思っていた天法を検証し、元々根源であった『先王の道』で、後に続く儒家を充実させ、再び儒家思想の源流を重視することに依って、儒教の本当の精神を求め、そうすることで再び活力を生まれさせようとしたのだ。
王安石は若い頃、志しを立て、「欲与稷契相希(五穀の神の契約を望みたいと思う)」を目指した。彼が目指すのは、[契約後、成果を挙げた五穀神の臣賢]のような偉業を成すことと、孔子以前の聖人等の『先王の道』を求めていくことであり、そのことは彼と常に繋がりをもっていた曾鞏、孫正や、王回、王令等の一群の親しい間柄の同志達が、彼との共通の目標として目指すものでもあった。彼らは復古を全うする事を自任して、然も互いに励まして、後に、孔子を尊重し儒学に専念したのだ。
王安石は決して孔子の価値を否定することは無かったが、孔子の門弟の言った「夫子賢于尭舜」の見解には同意した。彼は孔子が偉い人であったと思ってはいたが、孔子を単に「集大成者」と見做し、「集諸聖人之事、大成万世之法」と考えていたので、上座にある伏羲、尭、舜、禹、湯、文武等の聖王の功労や、同じく伊尹、伯夷、柳下恵、孔子本人など少し位が下の聖人の力の成せる業を、如何して一人孔子のみの功績に出来ようかとも思っていたのだ;孔子がいた以降の時代にあっては、社会は変化に変化を重ねてきたが、聖人の方策には変化に応じる全てが備えられていたのだ。然し、王安石は聖人が世の中に役立つことを求めて無いと思っており、法制化をして人為的に矢鱈に制度を変えて、強引に世直しをして行くことに違和感を持っていたので「人為の天下を求めて無い」を基本として、「『時が経つに連れて頻繁に法制を変えるので無く』、社会が一定の成果をあげられて無い時期は法制が十分に揃っているとは言え無い」とし、「その時に限って法を変えるのが適切であると」と考えたのだが、これも孔子が尭舜を尊んだことが大きく影響した結果であったのだ。
王安石は、「孔子が尭舜を賢いとしたのは、彼が尭と舜などの巨人の上を行こうとした為だ」と思ったが、「尭と舜の古代の聖人は歴史の彼方の人なので後代の進んだ社会の人と比べては、王としては知力に欠け、徳にも疎く、及ぶものでは無い」ということで、現代人は余り古人を崇拝することを否としているが、反面、時代の変化に応じて変える勇気も無いくせ、重い責任を感じ乍、昔の賢人を顧みようともし無いで、自分の本音を誤魔化して厳し過ぎる要求をしたのだと考えていた。王安石のこのような見解は結論として全く公平公正のものと云える。
王安石は、「『先王の道』は伏羲から発し、尭と舜で完成させ、禹、湯、文武で大きく成り、孔子を輩出したのだ」と堅く信じていたのだ。 彼も「孔子は後世の諸人が成した偉業こそ成し得無かったが、聖人であることに変わりが無い」とも思っていたのだ。併し、彼は絶えず進取の気概を以て観察するので、儒学を決して孔子の時代のそれに戻す必要が無いと思っており、時代は常に変化する為、思想に関する学説は時代の趨勢に応じて必ず新しい変化を補充しなければならないと考えていた。この考えに、彼は充分自信があったので、自分の新説が孔子の思想に引けを摂るもので無いと信じて、儒学と『先王の道』の新しい段階を担ったのだ。
三世代を称えるのが当時の風潮であったのだが、このことが即王安石を利するものとはなら無かった。先ずは先王を只管尊ぶことと、孔子を尊ぶこととに対して、『正統な六経』と『正統な儒学』との関係についての両面で、多くの人の意見が分かれていたのだ。儒家が董仲舒の時代に王権からの力を借りて、その後も唯我独尊の地位を得たことに対して声を高く提唱したことが、後世においても『先王の道』と孔子の言うことと、経学と儒学の境界線をぼんやりさせて、甚だしきに至っては両者を一緒くたにして仕舞ったのだ。実は儒学は経学の一つの単なる構成部分でしかなく、多分、その中で最も主要な部分の一つであろうが、併し、決して経学の全てを代表するもので無く、孔子は『先王の道』を集大成したのだとされたが、完全には『先王の道』を体現することは出来無かったし、完全には『先王の思想』に取って代わることが出来ても無かったのだ。
孔子を重んじた隷書で書かれた経学書においては、六経全てが必ず孔子によって書き替えられていると考えられているので、その書には孔子の「微妙な言葉で隠された重要な意義」を含んでいると云われている。文語文の経学では「六経は全て史書だ」と思われているので、全てが先王の政治の記録で、上古の御世の思想と政治を著したものとされている。王安石はどちらからと言うと文語文の経学を尊重したので、孔子には「創作性が無い」と思っていても、決して六経が書き替えられていると決め付けることは出来無かったのだ。
経学と儒学を分けた上で、経学を重視するのは、新学の一つの重要な特徴だ。王安石は若い頃《易》を注釈したことがあって、《春秋》にも詳しい解釈の作品がある上に、《周礼》、《詩経》、《尚書》の三つを弟子が考証をし、更に有名な《三経新義》を著作していた等のことは、彼が如何に経学を重視したかを表している。
王安石には《周礼義序》の中で指摘したことは、《周官》が周朝の習わしとする庚が先代の王政を引き継ぎ、更に文、武、周公の力を加えて、道政相合わせた経典だとしたのだ。《詩義文》の中で、彼は「道が上で、礼を下に留める」と言っており、聖人王の時代の作品の「道」の言葉にも、君子や聖人でも駄々を捏ねるものがあると言っている。 彼は《本義序》の中でも《尚書》が「虞、夏、商、周」の故人が遺した原稿であることを指摘している。要するに、諸書は全て先代の作品であるということで、孔子と何も関係無いということを言いたかったのだ。
王安石の《春秋》対する見解については、後世に於いても、その後長期に亘る激烈な論争が誘発されたのは紛れも無いことである。反対派の勢力は王安石が《春秋》の学課を廃棄したことに反感を持ち、彼が「朝廷の勅書を細かく引き千切った」と捏造して、彼を罪に陥れた。支持者は、「王安石が本当は非常に《春秋》を大切に思っているのだが、ただ彼が《春秋》は『夫の書に非ず』と思ったので、『科挙の試験の科目とすることに適して無い』というだけのことと」と懸命に弁解した。
王安石が「朝廷の勅書を(《春秋》を)細かく引き千切った」と言うのは悪意の中傷だった。実は王安石の弟子の黄原が《春秋》に注釈を為したのだが、余りに慎重に解釈した為、多くの文が空白の儘で意味不明になって仕舞い通読出来無くなって仕舞ったのだが、王安石はこのように厳しく慎重に研究する態度を誉め称えていた。亦、王安石に対して面と向かって文句を言っては争いが起きるので、学者らしく無益の争いを避け乍冗談混じりに文句を言ったというのが正解で、そのことが、「朝廷の勅書を(《春秋》を)細かく引き千切った」になったのだ。反対派は、文章の断片から意味を取るように事によせて個人攻撃を行うことで自分の真意を単に述べただけであったのだ。
反対派は嘘を捏造したのだが、併し、《春秋》に対して王安石が不満に思っていることには思いを同じくしていた。彼は経文が簡略過ぎるので理解することが出来無いからと言って注釈を付けることには反対であったが、三書が伝えるもの自体も信用出来無かったので、その為読んでも殆ど理解出来ず、人に解いて上げようとしても無理に当て嵌めて、字面だけを見て憶測して解釈するしか無くて、信用することが出来る代物とは思え無いと言っていたのだ。これは一方の言い分であって、反対側の言い分は、《春秋》は衰退の時代に出来たものであり、孟子も「王者の道は消えかけ、《詩》も消えて亡くなって、《詩》は亡くなって《春秋》を行う」と言っているというものであったのだ。
王安石は《春秋》に孔子が手を加えたと訴えたが、それに反対する声が沸き上がった。ここで勿論、反対派の攻撃に屈服することは出来無く、将に文革の時期に王安石を法家の代表として、孔子が英雄だとすることに反対したことも根拠があり、確かに孔子に対してある程度の不満を王安石が感じていたことを認め無い訳にはいか無いのだ。
鄧広銘先生は、王安石が成年になった後、一度も孔子に「少しも不満を言うこと無かった」のは間違い無いとするが、併し、不満の声が無いからと言って彼が孔子に対して心から承服することを決して意味することでは無くて、当時は、孔子に対して公に反対をすることが出来る人はい無いような時代なので、司馬光が孟子を攻撃することが出来ても、王安石が荀子を批判することが出来ても、孔子を批判することなど絶対に出来るものでは無かったのだ。
王安石は六経の中に在って《春秋》は儒家の色が濃過ぎると不満に思ったので、遂に、孔子の自筆に因る物であると公言した。王安石は神宗に仕えていて講義をした時《礼記》を批評して、「此れ難解とするもの数知れず」と、神宗を説得すると、神宗は直ぐに安石の願いに応じて、《礼記》を「適当なものでは無い」と思って、《尚書》に読み替えた。王安石は中年と成った以降には儒家に対して不満を表し始めて、《春秋》を廃棄して、《礼記》を貶し、彼は儒学を聖王の道に取って代えて、先王を大いに称賛し密かに孔子を貶していのだ。
王安石は、儒に対して距離を置くようになって『先王の道』を尊重したのは、[幽体分離の術]を儒家の重大な過ちであると唱える為だった。彼は《謝除左僕射表》中で指摘している: 「曲者が経術を使って乗っ取り、『本物の盛王の時代が始まった』と人民に偽りを言いうのは、衰退期の証である。自ら筋道を立てて論じることが無い儘、闇雲に下の者に学問を押付けようとする狡賢い輩がいる。然れども孔子の一派は官僚を制御して未だ礼節に拘り、孟子派は途惑乍も亡くなった聖人を承継し、時には道は外すが、義を尽すことだけは欠かすことは無い」と彼は孔孟を推奨して聖人を救って道学を引っ張り上げて来たが、衰退期になったと指摘し、やむを得ず功労を断ち切って学ぶのを止めたのだ。盛徳の帝王の時代は経術に依って士を造り、道は聖人の王道に戻り、民は異議を唱えることも無く、聖人の王が道統、政統、学統の三つを統合して一つに為したので、道を教え説き、亦、学び舎を設立し、運営していくことも全て王者の仕事となっていたのだ。只、衰世の時にあっては王者が道を無くし、現世を悲しみ、官学は興らず、人民を惑わす嘘説罷り通る。孔子は私学を開設した第一人者かもしれないが、王安石が如何しても腑に落ちず心の中で大いに不満を示していたのは、「孔子は単に一介の臣下として仕えていた身を下野して仕舞い、王でも無く官でも無かったのに、学校を設立運営する資格は無かった筈である」と言うことであった。
彼は言う: 「盛王の時代にあっては、聖人の王の身は全部で三つ働きを兼ねていたが、晩期には政治は乱れて道を無くし、孔子は分を超えることも構わず、臣下であるにも拘らず本来王事に関る《春秋》に手を加えたのだが、翻って、自分(王安石自身)を省みて、改めて考えると余り大きな顔も出来無い筈で、譲って孔子の功罪は半々としよう。その為、孔子が学校を始めたのも、『先王の道』を完全に廃止させ無い為にやむを得ずに行ったことで、同様に、孟子も布教する資格が無かったのだが、只管『先王の道』を完全に廃止させ無い為に止むを得ず務めたことだったのだろう」。
孔子の時代から、三統は分散し、道統、学統は儒者に帰し、政統は帝王に帰すことになり、詰り、政治は全て帝王が統合したのだが、伝統の伝道に依って儒学を学んだ者は全てが儒学者に成り得、「内では儒家なる聖人で外では王である」という理想は崩壊し始めていたのだ。儒学者が只布教して業を授けるだけであったくらいでは、政治を動かすことなぞ出来る訳も無く、その学説も中身が無く徒に文字を羅列するのみで実行性の無い内容に留まっていただけで無く、実践の検証も得たことも無かった。帝王は「思うが侭」官僚を相手に国を治めたが、学識と教養と徳の全てが、三世代の聖王との比較を十分に検討されること無しに、只其の時々に政治を掌握する者に引き継がるだけであった。皇帝は皆聖人として尊ばれる筈だが、其の全ての者が「心は聖人であり、外面では王として振舞う」という表票を貼っていたが、実は全くの虚構であった。内面を持ち合わせて無い聖人が、外面では王の面だけでお茶を濁すということは、聖王の意義を全くの空論にして仕舞ったのであり、実は歴代の帝王も決して聖人であったわけで無く、王道のみを誇示するだけであったのだ(人格は最終的に政策に反映される?)。内なる聖人は最早、空中楼閣であって、同様に、外に措いては王としての役割を貫徹はするが、其の業績を検証して行く姿勢は見られず、「鏡月の水飛沫になって」、実際、惨憺たるものであった。「内の聖人と外での王の問題」は、最大の問題として儒家の間に存在し、悲劇的に意見が分かれ、全く解決することが出来無い問題で、三つ全部を帝王に伝承されて始めて聖王になれるということも全く望み薄なこととなり、儒者になるよう要求された帝王が武力を着けて崇め尊ばれるようになった末世ですら、大改革をやろうとする気など更々起こさず 、智謀の限りを尽くして話しに行っても逆に「不可説、不可説」と嫌われて仕舞うのだ。
王安石は特に儒学伝道の系統と政統とを、詰り、学説と政治とを一つにすることを主張している(政治は思想の現実化である)。彼は《与祖択之書》中で次のように指摘している: 「政令を教え治すのは、聖人の所謂言葉也。書による策は、天下の人民を誘導し、一つに纏める。聖人の道の精神を抑制し、政令を作って、治め教えることは、一面から言えば本末転倒である。そういった書による策略も、道学に則り政治を治めることになる。 ……二帝の三王子は、天下の人民を善き民に導き、孔子、孟子の書にある策で全ての者を善人と為し、聖人に近づくことが出来るのだ。二帝の三王子とは、農業政策の政令を作って教え治して、全国に流布し、唯一孔孟の本の策だけで天下の人民を制御しようとしたことが、史書に記録されている。譬え、両者(孔孟)を一所くたにしょうとしても、広く実践に付すと結局効果が異なって仕舞うことが史書に記録されているのだ」。これは王安石の二十五歳の時の作品で、その時彼は未だ孔孟をある程度は尊重していたので、二者共聖人であることを強調したが、実際には、お互いの優劣を付けており、既に二者の違いも理解していたのだ。彼はそれから聖王が三を一に統合したのを強調して、孔孟を流浪の賢者の身分から聖道を継承した忠実な臣下であるとし、名のある書も歪められて仕舞ったのでやむを得ずこう顕わしたのだ。
《大人論》の中で、彼は大人、聖人、仙人を区分して、次のように指摘している: 「其道から言って神と謂い、其徳から言って聖人と謂い、その事業から言って大なる人と謂う。 古い聖人、その心を量ってみても、道理からしても未だ神に加わることも無く、其の時は入神のことは道として存在するかということは寂莫たる虚無を呼び込み深く考えることも無かったのだ。仮初にも人としての、所謂道の問題か。道は、神では無く、人を以って為し、神と言うものからは何も得ず、得るものは徳を以ってする。夫が神に成ろうとしても、聖人には成れず、聖人に成れても、大きく無く形も定まることが無いのだが、古の粗七割の者は皆聖人であり、だから神と聖人は同じ‘もの’で無いと言うことに依って、異なる者であることを示した」。此では、彼は事業の功績と価値を強調して、古い聖人については其道は神まで届くと思ったが、今ではそんな聖人は誰一人世に出て無く、亦、その様なことを認める偉業にも会ったことも無く、だからと言って其道で仙人と称することも出来無いので、責めて其徳から聖人と称することは許され、詰る所、超一級のことを成せる者が唯独りとして無かったということで、一流と見為される事業を成した人達のみ仙人と称することが出来、「神となると、盛徳の大事業に見合う者でなければ無理であった」とした。此処に措いて彼は徳業を軽視して、道のみを重視するとし、「徳業を捨て何も為さず」という人が三割方と強調して、「古人にとって天地は全ての筈だった」と批判を出した。事実、彼は儒家が徳を重く捉えるのに、それらを軽くあしらった事業に対する功績を評価する作法に不満を感じて、孔孟に較べて位や事業と功績で劣ることに遺憾の意を表したのだ。
王安石の心の中で、先王は、徳、業が三割方揃っている神人である筈だが、孔子程の事業も為して無かったので、精々聖人を称するに止まったのであった; 『先王の道』は天地の「全経」であるする大半の儒家の学説に一家言あった; 『先王の道』には儀式で奏でる音楽と刑罰と政(まつりごと)とを総て共有するものとなっていたのであったが、後、儒学では躊躇無く仁義徳を重要としたものであると言ったのだ。要するに、代表的な『先王の道』の経学は儒学と比較して更に広く捉えるものと成っており、更に深く、更に合理的で、更に富んだ生命力と創造性を持つものであるとした。
王安石が儒家を不満に思っていたのは、彼の若い頃の志が変化したからでは無い。彼は儒家が孔子の教えを都合良く利用して多くの不正行為をしていると考えたからであるが、それを改める方法はなかなか見付から無かった。そこで、『先王の道』を外さず行動するように儒家に命じることが急務となった。王安石の思想のこの転換は、彼本人が認めて無かったと言う意味では理解出来無いということになろうが、然し、歴史の事実が証明している。古い制度を以って古い時代の儒家の思想に立ち帰る[『先王の道』]によって儒家を牽制することは、誰もが公然と反対は出来無いので、このことは王安石の闘争に対する策略の真骨頂となったと言えよう。
王安石の心の中では、孔子は到達出来ない最高峰に位置した。彼はかすかに伏羲、尭、舜、禹、湯、文、武、周公などの『先王の道』の継承者を気取って、孔子については決して尊重する姿勢を見せなかった。王安石の一子王雫はこのことを《画像賛》によって語っている:「居並ぶ聖人が教えて下さるのは、まちまちだ。集大成すると、所々に仲尼(孔子)も居た」。孔子は「集大成者」とされたが、王安石が孔子を大聖人とされていた前代の説を総括し、如何しても諸聖人の集大成をしようとし無かったのは、孔子と較べても遜色の無いような一種独自の雄大で精微な思想体系を構築しようとでもしたものだったか?
、
「二、命と言うこと」に続く










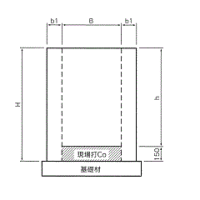









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます