今となっては先々週の日曜日の話ではありますが、東京都あきる野市にある金比羅山と戸倉城山に登ってきました。

JR五日市線沿線の武蔵五日市駅からスタート。
以前今熊山に登ったときに武蔵五日市駅で入手していたガイドマップを参考にして、まずは金比羅山を目指します。

ふもとにあった神社にお参りして、ここから山道に入っていく予定だったのですが、今日はいろいろと予定外のことばかり起こってしまいます。

最初のトラブルは、入っていった道がすぐに行き止まりになってしまったこと。ガイドマップだとあんまり細かい道は載っていないんですよね。
最初は民家の庭先に出ちゃって、さすがにここは違うだろうと周囲をうろうろしていて、ようやく民家の裏手みたいなところから入っていったんですよね。私は登山アプリのYAMAP を利用して現在位置やルートなんかを確認しているのですが、一応ルートになっているっぽいところを進んでいったはずなのですが、どうやらここは正しいルートではなかったようです。
戻るのも面倒だったので、そのまま道なき道をずんずん登っていきます。子供のころは、こういう感じで山の中を歩いたりしたこともあったなぁ。本当は、ほめられたことじゃないんですけどね。

5分ほどよじ登ったところで、ようやくちゃんとした道に出ました。やれやれ。ちょっと事前調査が不足していました。やっぱり、ちゃんとした登山向けの地図を持たないといけませんね。

しばらく進むとルートが分岐します。どうせすぐ先で合流するので、単純に距離が近そうなまき道を進みます。

整備されていて歩きやすい道です。この日は天気もよく、傾斜もさほどきつくなく、気分よく歩くことができました。
ほどなく、別ルートとの合流地点に出ました。そのまま山頂の手前にある琴平神社へ向かおうとしたのですが……。

理由は書かれていませんが、通行止め。台風の影響でしょうかね。

少し遠回りになりますが、東屋経由で琴平神社を目指します。

さっきの道が通行止めになっていなかったらこの東屋の方へは来なかったと思うんですけど、こちらに来たのは結果的に大正解。ここからの眺望はなかなかすばらしいものでした。
しばらく眺めていましたが、東屋では団体さんが休んでいたので、さっさと琴平神社へ向かいます。


神社の入り口前にも通行止めのテープが張られています。路肩崩壊の恐れあり、だそうです。
さっきの道は、本当ならここに出るはずだったんですね。

琴平神社にお参りして、金比羅山の山頂を目指しましょうか、と、思ったのですが……。

あれ? 神社の横に山頂の標識あるんですけど、山頂ってここじゃないよね?

近くにあった案内板を見ると、やっぱり琴平神社の方が金比羅山だと記されています。よくわからないけど、まあとりあえず、YAMAP のナビを信じて山頂と思しきほうへ行ってみます。案内板だと日の出山、御岳山と表示されている方ですね。

しばらく尾根道を行きます。
まだ本格的な縦走ってしたことがないんですけど、やっぱりアップダウンのそれほど激しくない山歩きっていいですね。
好きんが、尾根!

少し行ったところで、また日の出山と金比羅山の案内板が出てきたんですけど、YAMAP のナビで確認すると金比羅山山頂を通り過ぎてしまっているようです。あれ? それっぽいところなんてあったかなぁ。
金比羅山の山頂って、ルートから少し外れた位置にあるんですよね。山頂へのルートを見落としていたかもしれないので、気をつけながら来た道を引き返します。

あ、こんなところに道があった。
案内板もないし、入り口もわかりにくいし、これは知らないと見落としちゃうなぁ。


わき道に入って、ほんの数10m ほどで山頂に到着。
しかし、隣り合った木に2枚の山頂標識プレートが設置されています。しかも、それぞれ標高が異なっています。琴平神社のところにあったものも含め、金比羅山には3つの山頂標識があることになりますね。
ちなみに、YAMAP の情報では金比羅山の標高は466.0m。いったいどれが本当なんだ……。ま、少なくとも、琴平神社よりここの方が標高が高いのは確かですけどね。

周囲は木に囲まれていて、眺望はありません。 かなりがっかり度の高い山頂です。
いったん琴平神社方面に戻り、そこから小中野の方へ下りるルートを進みます。

下りはいつものように楽なもんなんですけど、落ち葉が大量に積もっていて、滑りやすくなっていました。調子に乗っていると転んでしまいかねません。

そして民家の横を抜けて人里へ。
民家の近くって、通るのに気を遣うから、もっとわかりやすい登山口になっているとありがたいんだけどなぁ。
続いて、戸倉城山へ向かいます。
城山へ登るルートは大きく3つあります。武蔵五日市駅から見て、正面方向になる光厳寺ルート、横手川になる西戸倉ルート、そして裏側になる十里木ルートです。
地図だけで見ていると光厳寺ルートが一番素直に見えるんですけど、ここは岩場の急登があって難易度が高いそうなので今回はパス。現在地から一番近い西戸倉ルートから登っていきます。

目の前にバーンと広がるのが戸倉城山です。左右が切れているので大変わかりやすくなっていますね(奥のほうには山が続いているんですけど)。

西戸倉の登り口付近で、飛び出し注意の看板を発見。
これは、網代弁天山の登り口付近にいた看板の仲間ですね。


西戸倉の登り口に、戸倉城の解説が設置されていました。
戸倉城は、元々小宮氏によって築かれた城です。後に北条氏の支配下に収まりますが、その際に滝山城を北条氏照に譲った大石定久が隠居のための城として入りました。八王子城の支城として機能しましたが、小田原征伐の後、廃棄されたようです。
さて、登っていきましょうか、と思ったのですが……。

通行止めでした。やっぱり台風の影響はでかいなぁ。
このまま帰ろうかとも思ったのですが、気を取り直して十里木ルートから登ることにしましょう。でも、だいぶ遠回りになるんだよなぁ……。
てくてく歩くこと20分。十里木の登り口に到着します。
しかし、道路沿いにあった入り口はわかりやすかったものの、その道を素直に登って行ったら、民家の敷地に出てしまいました。またこのパターンか……。

しばらくうろうろして、ようやく城山への登り口を発見。わかりにくい! もう少しで諦めて帰っちゃうところでしたよ。
しかしまあ、この日はどうも、準備不足だわ、注意力散漫だわで、本当にダメダメでした。要反省。

登り口は竹林になっていたのですが、竹や木が散乱して通路を塞いでいました。
まあ、通れないほどではありませんけど、これも台風の影響ですかね。

少し行ったところで、城山へ向かう道と、荷田子方面へ下りていく分岐に出ます。そこの案内板に、西戸倉ルートと光厳寺ルートは通行止めになっている、との表示がありました。
光厳寺の方も通行止めなのか。場合によってはそっちから降りようかとも思っていたのですが、帰りも十里木ルートを使わなくてはならないようですね。だいぶ遠回りになっちゃうなぁ。


戸倉城山はピークが2つあり、その両方に曲輪が設置されていました。十里木ルートから登った場合、まずは山頂の前に西曲輪に出ます。
ちょっと小高くなっている場所に人工的な平地が広がり、確かに曲輪っぽい感じです。

西曲輪からちょっと移動すれば、山頂はもう目の前です。
山頂の手前にも何段かに分かれた曲輪があり、山城感がよく残されていますね。

戸倉西口はこの辺りにあるのですが、やっぱり通行止めになっていました。

山頂の手前。

と、いうわけで、山頂に到着。登り口から大体30分くらいでしたかね。距離は短いんですけど、急な坂道が多く、ここより少し標高の高い金比羅山よりも大変でした。

なによりすばらしいのがこの山頂からの眺望です。
左右に広がる山並みと、遠く都心の方まで続く街。山頂についてすぐ目に飛び込んできたこの眺めには、思わず息を呑んでしまいました。

山頂にも戸倉城の説明板があります。

光厳寺口も通行止め。
ちょっと下の方を覗き込んでみましたけど、やっぱりかなり険しそうな感じですね。
山頂で昼食後、下山します。
急斜面でちょっと手をつかないといけなかったり、落ち葉が浮いていて滑りやすいところなどもあったりしましたが、あっという間に下山完了。Return trip effect!

帰りは武蔵五日市駅まで、秋川沿いを歩いていきました。
2連続とはいえどちらも400m 級の山でしたので、全体的な疲労感はそれほどでもありませんでした。ただ、今回は道を間違えたり、通行止めにあったり、あんまり良い山行とは言えませんでしたね。とりあえず、事前にしっかりルートを確認することだけは、徹底しなくてはなりません。通行止めも、台風19号以降は割とあちこちで発生しているので、なるべく情報を集めなくてはなりませんね。
しかしなにより良かったのが、戸倉城山からの眺めです。この景色は本当にすばらしかった。途中で帰ろうかと思ったポイントも何度かあったのですが、最後まで歩きとおしたのは大正解でした。
先週の土日は仕事の都合と悪天候とで山歩きはお休み。1週飛ばしただけで、なんか身体がなまってしまったようにも感じます。山に行けなかったとしても、なにかしら身体を動かしておかないといけないなぁ。
今年の山歩きも、多分あと1回。最後もまたこの近辺の、五日市線沿線で締めようかと思います。次の土日は一応予報では晴れなんですけど、ちゃんと予報どおりに晴れてくれるといいなぁ。

JR五日市線沿線の武蔵五日市駅からスタート。
以前今熊山に登ったときに武蔵五日市駅で入手していたガイドマップを参考にして、まずは金比羅山を目指します。

ふもとにあった神社にお参りして、ここから山道に入っていく予定だったのですが、今日はいろいろと予定外のことばかり起こってしまいます。

最初のトラブルは、入っていった道がすぐに行き止まりになってしまったこと。ガイドマップだとあんまり細かい道は載っていないんですよね。
最初は民家の庭先に出ちゃって、さすがにここは違うだろうと周囲をうろうろしていて、ようやく民家の裏手みたいなところから入っていったんですよね。私は登山アプリのYAMAP を利用して現在位置やルートなんかを確認しているのですが、一応ルートになっているっぽいところを進んでいったはずなのですが、どうやらここは正しいルートではなかったようです。
戻るのも面倒だったので、そのまま道なき道をずんずん登っていきます。子供のころは、こういう感じで山の中を歩いたりしたこともあったなぁ。本当は、ほめられたことじゃないんですけどね。

5分ほどよじ登ったところで、ようやくちゃんとした道に出ました。やれやれ。ちょっと事前調査が不足していました。やっぱり、ちゃんとした登山向けの地図を持たないといけませんね。

しばらく進むとルートが分岐します。どうせすぐ先で合流するので、単純に距離が近そうなまき道を進みます。

整備されていて歩きやすい道です。この日は天気もよく、傾斜もさほどきつくなく、気分よく歩くことができました。
ほどなく、別ルートとの合流地点に出ました。そのまま山頂の手前にある琴平神社へ向かおうとしたのですが……。

理由は書かれていませんが、通行止め。台風の影響でしょうかね。

少し遠回りになりますが、東屋経由で琴平神社を目指します。

さっきの道が通行止めになっていなかったらこの東屋の方へは来なかったと思うんですけど、こちらに来たのは結果的に大正解。ここからの眺望はなかなかすばらしいものでした。
しばらく眺めていましたが、東屋では団体さんが休んでいたので、さっさと琴平神社へ向かいます。


神社の入り口前にも通行止めのテープが張られています。路肩崩壊の恐れあり、だそうです。
さっきの道は、本当ならここに出るはずだったんですね。

琴平神社にお参りして、金比羅山の山頂を目指しましょうか、と、思ったのですが……。

あれ? 神社の横に山頂の標識あるんですけど、山頂ってここじゃないよね?

近くにあった案内板を見ると、やっぱり琴平神社の方が金比羅山だと記されています。よくわからないけど、まあとりあえず、YAMAP のナビを信じて山頂と思しきほうへ行ってみます。案内板だと日の出山、御岳山と表示されている方ですね。

しばらく尾根道を行きます。
まだ本格的な縦走ってしたことがないんですけど、やっぱりアップダウンのそれほど激しくない山歩きっていいですね。
好きんが、尾根!

少し行ったところで、また日の出山と金比羅山の案内板が出てきたんですけど、YAMAP のナビで確認すると金比羅山山頂を通り過ぎてしまっているようです。あれ? それっぽいところなんてあったかなぁ。
金比羅山の山頂って、ルートから少し外れた位置にあるんですよね。山頂へのルートを見落としていたかもしれないので、気をつけながら来た道を引き返します。

あ、こんなところに道があった。
案内板もないし、入り口もわかりにくいし、これは知らないと見落としちゃうなぁ。


わき道に入って、ほんの数10m ほどで山頂に到着。
しかし、隣り合った木に2枚の山頂標識プレートが設置されています。しかも、それぞれ標高が異なっています。琴平神社のところにあったものも含め、金比羅山には3つの山頂標識があることになりますね。
ちなみに、YAMAP の情報では金比羅山の標高は466.0m。いったいどれが本当なんだ……。ま、少なくとも、琴平神社よりここの方が標高が高いのは確かですけどね。

周囲は木に囲まれていて、眺望はありません。 かなりがっかり度の高い山頂です。
いったん琴平神社方面に戻り、そこから小中野の方へ下りるルートを進みます。

下りはいつものように楽なもんなんですけど、落ち葉が大量に積もっていて、滑りやすくなっていました。調子に乗っていると転んでしまいかねません。

そして民家の横を抜けて人里へ。
民家の近くって、通るのに気を遣うから、もっとわかりやすい登山口になっているとありがたいんだけどなぁ。
続いて、戸倉城山へ向かいます。
城山へ登るルートは大きく3つあります。武蔵五日市駅から見て、正面方向になる光厳寺ルート、横手川になる西戸倉ルート、そして裏側になる十里木ルートです。
地図だけで見ていると光厳寺ルートが一番素直に見えるんですけど、ここは岩場の急登があって難易度が高いそうなので今回はパス。現在地から一番近い西戸倉ルートから登っていきます。

目の前にバーンと広がるのが戸倉城山です。左右が切れているので大変わかりやすくなっていますね(奥のほうには山が続いているんですけど)。

西戸倉の登り口付近で、飛び出し注意の看板を発見。
これは、網代弁天山の登り口付近にいた看板の仲間ですね。


西戸倉の登り口に、戸倉城の解説が設置されていました。
戸倉城は、元々小宮氏によって築かれた城です。後に北条氏の支配下に収まりますが、その際に滝山城を北条氏照に譲った大石定久が隠居のための城として入りました。八王子城の支城として機能しましたが、小田原征伐の後、廃棄されたようです。
さて、登っていきましょうか、と思ったのですが……。

通行止めでした。やっぱり台風の影響はでかいなぁ。
このまま帰ろうかとも思ったのですが、気を取り直して十里木ルートから登ることにしましょう。でも、だいぶ遠回りになるんだよなぁ……。
てくてく歩くこと20分。十里木の登り口に到着します。
しかし、道路沿いにあった入り口はわかりやすかったものの、その道を素直に登って行ったら、民家の敷地に出てしまいました。またこのパターンか……。

しばらくうろうろして、ようやく城山への登り口を発見。わかりにくい! もう少しで諦めて帰っちゃうところでしたよ。
しかしまあ、この日はどうも、準備不足だわ、注意力散漫だわで、本当にダメダメでした。要反省。

登り口は竹林になっていたのですが、竹や木が散乱して通路を塞いでいました。
まあ、通れないほどではありませんけど、これも台風の影響ですかね。

少し行ったところで、城山へ向かう道と、荷田子方面へ下りていく分岐に出ます。そこの案内板に、西戸倉ルートと光厳寺ルートは通行止めになっている、との表示がありました。
光厳寺の方も通行止めなのか。場合によってはそっちから降りようかとも思っていたのですが、帰りも十里木ルートを使わなくてはならないようですね。だいぶ遠回りになっちゃうなぁ。


戸倉城山はピークが2つあり、その両方に曲輪が設置されていました。十里木ルートから登った場合、まずは山頂の前に西曲輪に出ます。
ちょっと小高くなっている場所に人工的な平地が広がり、確かに曲輪っぽい感じです。

西曲輪からちょっと移動すれば、山頂はもう目の前です。
山頂の手前にも何段かに分かれた曲輪があり、山城感がよく残されていますね。

戸倉西口はこの辺りにあるのですが、やっぱり通行止めになっていました。

山頂の手前。

と、いうわけで、山頂に到着。登り口から大体30分くらいでしたかね。距離は短いんですけど、急な坂道が多く、ここより少し標高の高い金比羅山よりも大変でした。

なによりすばらしいのがこの山頂からの眺望です。
左右に広がる山並みと、遠く都心の方まで続く街。山頂についてすぐ目に飛び込んできたこの眺めには、思わず息を呑んでしまいました。

山頂にも戸倉城の説明板があります。

光厳寺口も通行止め。
ちょっと下の方を覗き込んでみましたけど、やっぱりかなり険しそうな感じですね。
山頂で昼食後、下山します。
急斜面でちょっと手をつかないといけなかったり、落ち葉が浮いていて滑りやすいところなどもあったりしましたが、あっという間に下山完了。Return trip effect!

帰りは武蔵五日市駅まで、秋川沿いを歩いていきました。
2連続とはいえどちらも400m 級の山でしたので、全体的な疲労感はそれほどでもありませんでした。ただ、今回は道を間違えたり、通行止めにあったり、あんまり良い山行とは言えませんでしたね。とりあえず、事前にしっかりルートを確認することだけは、徹底しなくてはなりません。通行止めも、台風19号以降は割とあちこちで発生しているので、なるべく情報を集めなくてはなりませんね。
しかしなにより良かったのが、戸倉城山からの眺めです。この景色は本当にすばらしかった。途中で帰ろうかと思ったポイントも何度かあったのですが、最後まで歩きとおしたのは大正解でした。
先週の土日は仕事の都合と悪天候とで山歩きはお休み。1週飛ばしただけで、なんか身体がなまってしまったようにも感じます。山に行けなかったとしても、なにかしら身体を動かしておかないといけないなぁ。
今年の山歩きも、多分あと1回。最後もまたこの近辺の、五日市線沿線で締めようかと思います。次の土日は一応予報では晴れなんですけど、ちゃんと予報どおりに晴れてくれるといいなぁ。










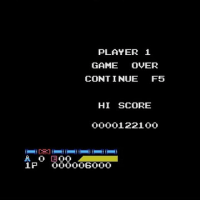

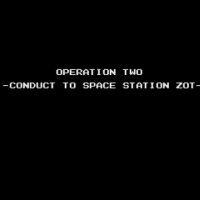












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます