埼玉県比企郡にある仙元山から小倉城跡を通って、大平山に登ってきました。
スタートは東武東上線の小川町駅。仙元山への登山口は小川町駅から南の方なのですが、その前に駅の北側にある富士山に登ってきます。

小川町駅から見上げる富士山。正面の電波塔の立っているところが富士山になります。
地方に富士の名を冠する山は結構あり、そういうところは一応山容が富士山っぽかったりするものですけど、あんまり富士山らしさは感じませんね。

住宅地の横を抜けていきます。

舗装路は配水場で終わり、そこから山道に入っていきます。

ほんの数分で、電波塔に到着。

富士山は標高182m。立派な石碑もありますが、背景が電波塔なのであんまり風情はありませんね。

富士山から東の方へ下りていきます。
ここからしばらくは山道が続きます。全体の順路を考えるとちょっと難しいのですが、富士山に登るならこっちから登った方が良かったですね。

一旦町に出て、仙元山登山口を目指します。目の前に見えるのが仙元山ですかね。

途中、コメリもありました。

民家の横を抜けて登山口へ。仙元山の近くには、ローラーすべり台が名物となっている、見晴しの丘公園があります。ガイドブックにはそちらを回るコースを紹介しているものもあるのですが、今回はパスしてまっすぐ仙元山を目指します。

神社へ登っていくルートもあったのですが、そちらへは寄らずに仙元山方向へ。

細くて湿り気のある道を登っていきます。

荒れているというほどでもないですけど、神社を経由してくるルートと合流した辺りで、若干道がわかりにくくなっていました。

見晴しの丘公園へは車でも行けるので、割とすぐ近くを車道が走っていたりします。

途中、百庚申というところがあったので寄ってみました。


ここにはたくさんの庚申塔が並んでいます。1860年に地元の人々が中心になって造立されたもので、この辺りでは庚申信仰が盛んだったそうです。

山頂手前に見晴台がありました。

木がよく見えます。


見晴台の反対側からは浅間山が見えました。

見晴台からすぐ、仙元山山頂に到着です。
仙元山は標高298.9m。登山口から約25分。それほどきつい場所もなく、すいすい登れました。

仙元山山頂は1か所だけ眺望が開けていて、小川町方面がよく見えます。

このまま尾根沿いに進んでいきます。次の目的地青山城跡です。

しばらくはずっと下り道。

青山城跡の手前でまた上り道になります。

青山城は尾根上に作られた連郭式の山城です。大きな堀切や、曲輪の様子もよく残っています。
ここはなかなか見所のある城跡なので、この後行く小倉城跡と併せて、別の記事にしようと思います。

次は大日山へ。

あんまりアップダウンもなく、サクサク歩けます。

あっという間に大日山に到着。
大日山は標高252.6m。仙元山から下り基調だったので、だいぶ楽な行程でした。

大日山からは、堂平山と笠山がよく見えます。左の平らな感じの山が堂平山、右のとんがっている山が笠山(通称おっぱい山)です。
この2座もいずれ登りたいとは思っているのですが、登山口までは基本バス利用になるので、ちょっと面倒だから避けちゃっているんですよね。バスってどうしても電車と比べて、時間も運賃もかかっちゃうからなぁ……。いろんな山に登ろうとすると、バス利用は必須になるのは分かっているんですけどね。

さて、ここでちょっとトラブルが。大日山を過ぎてしばらく歩いていたのですが、尾根歩きだから、緩やかに上ったり下ったりするはずなのに、なんかずっと下りばかり続くんですよね。おかしくね? と思ってGPS を確認したら、道を間違えていました。
どうも、笠山、堂平山の眺望が開けているところから、山を降りる道が伸びているのですが、間違えてそっちに行っちゃったようです(画像の左方向のルート)。
標高にして、大体70mくらいでしたけど、ちょっと急めのところを一気に登り返したのはちょっとキツかったです。いやまあ、急ぐこともなかったんですけど、こういうトラブルがあったときは、なるべく早く挽回したくなっちゃうんですよね。今回はなんてことのない低山だからいいけど、もっと心に余裕を持たなくてはなりませんね。

気を取り直して、物見山へ。

巻き道もありますが、当然ピークを踏んでいきます。

物見山に到着。
物見山は標高284m。ルートの途中であまり見所はありません。

物見山を過ぎると、多くの石碑が並んだ広場に出ました。




この自然石を活かした石灯籠がお気に入りです。
ベンチがあったので、ここで休憩していきました。

この広場を出るところで、急坂と巻き道が分かれていました。
当然、急坂を選んだのですが……。

この画像だとわかりにくいかもしれませんが、本当に急な下り坂で、少し危険でした。
巻き道を巻かないのはまあいいとして、上りならまだしも、下りの急坂は避けられるなら避けた方が良かったですね。

さて、小倉城跡が近づいてきました。

仙元山方面から歩いてくると、小倉城跡の裏側に出ます。

小倉城跡は、近くにある菅谷館跡、杉山城跡、武蔵松山城跡と併せ、比企城跡群として国の史跡に指定されています。
ずっと山道を歩いてきたし、途中の青山城跡もほぼほぼ山だったので、小倉城跡もその延長だと思っていたのですが、のぼりが立っているなど、思っていたより整備されていて観光地化していました。
小倉城についても、青山城とセットで、別途記事にする予定です。

小倉城跡を下りて、一旦人里へ。
この目の前に、2つの低山があります。

北に見えるのが大平山。

南に見えるのが正山です。
まずは正山に登るべく、道を南へと進みます。

ただ、正山へ登る道はちょっとわかりにくいんですよね。と、言うか、道のように見える場所を発見することができませんでした。

道なき道だけど、上を目指して登っていけば、なんとか登れないこともなかったかもしれません。でも、あんまりそういう気分でもなかったので、正山へ登るのは諦めました。

正山への登り口の近くには、小倉城の周囲を囲む槻川が流れています。

その槻川と大平山周辺は嵐山渓谷という景勝地となっています。京都の嵐山と似ているからそう名付けられたのですが、京都の方は“あらしやま”、埼玉の方は“らんざん”と読みます。
秋の行楽シーズンということもあり、嵐山渓谷にはかなり多くの人が集まっていました。

本来なら正山に登ってから嵐山渓谷へ行き、その後南から大平山に登る予定だったのですが、正山を取りやめたので、大きく回り込んで大平山の北部からアプローチします。

南からだと結構急坂になるんですけど、北からだと傾斜がかなり緩やかで、とても登りやすくなっています。

そんなわけで、大平山の山頂に到着。
大平山は標高178.9m。街の近くにあるほどほどの山ということで、家の近所にあると嬉しい山ですね。

少し南に移動した辺りから。南の方の街並みがよく見えます。







説明を省いて一気に進みますが、嵐山渓谷を一回りして、武蔵嵐山駅まで歩き、この日の山行は終了です。

小川町駅スタート、武蔵嵐山駅ゴールで、行動時間は休憩含めて5時間31分、移動距離は19.4㎞、累積上りは978m、累積下りは1007mでした。
正山だけは別ですが、全体的にはとてもよくルートが整備されていて、快適に歩くことができました。そういうこともあり、特に大平山や嵐山渓谷周辺は人が多すぎでしたけどね。
武蔵嵐山駅近くには、比企城跡群であり、続日本100名城でもある、菅谷館跡と杉山城跡がありますので、そのうちこの二つもセットで訪れたいと思います。
スタートは東武東上線の小川町駅。仙元山への登山口は小川町駅から南の方なのですが、その前に駅の北側にある富士山に登ってきます。

小川町駅から見上げる富士山。正面の電波塔の立っているところが富士山になります。
地方に富士の名を冠する山は結構あり、そういうところは一応山容が富士山っぽかったりするものですけど、あんまり富士山らしさは感じませんね。

住宅地の横を抜けていきます。

舗装路は配水場で終わり、そこから山道に入っていきます。

ほんの数分で、電波塔に到着。

富士山は標高182m。立派な石碑もありますが、背景が電波塔なのであんまり風情はありませんね。

富士山から東の方へ下りていきます。
ここからしばらくは山道が続きます。全体の順路を考えるとちょっと難しいのですが、富士山に登るならこっちから登った方が良かったですね。

一旦町に出て、仙元山登山口を目指します。目の前に見えるのが仙元山ですかね。

途中、コメリもありました。

民家の横を抜けて登山口へ。仙元山の近くには、ローラーすべり台が名物となっている、見晴しの丘公園があります。ガイドブックにはそちらを回るコースを紹介しているものもあるのですが、今回はパスしてまっすぐ仙元山を目指します。

神社へ登っていくルートもあったのですが、そちらへは寄らずに仙元山方向へ。

細くて湿り気のある道を登っていきます。

荒れているというほどでもないですけど、神社を経由してくるルートと合流した辺りで、若干道がわかりにくくなっていました。

見晴しの丘公園へは車でも行けるので、割とすぐ近くを車道が走っていたりします。

途中、百庚申というところがあったので寄ってみました。


ここにはたくさんの庚申塔が並んでいます。1860年に地元の人々が中心になって造立されたもので、この辺りでは庚申信仰が盛んだったそうです。

山頂手前に見晴台がありました。

木がよく見えます。


見晴台の反対側からは浅間山が見えました。

見晴台からすぐ、仙元山山頂に到着です。
仙元山は標高298.9m。登山口から約25分。それほどきつい場所もなく、すいすい登れました。

仙元山山頂は1か所だけ眺望が開けていて、小川町方面がよく見えます。

このまま尾根沿いに進んでいきます。次の目的地青山城跡です。

しばらくはずっと下り道。

青山城跡の手前でまた上り道になります。

青山城は尾根上に作られた連郭式の山城です。大きな堀切や、曲輪の様子もよく残っています。
ここはなかなか見所のある城跡なので、この後行く小倉城跡と併せて、別の記事にしようと思います。

次は大日山へ。

あんまりアップダウンもなく、サクサク歩けます。

あっという間に大日山に到着。
大日山は標高252.6m。仙元山から下り基調だったので、だいぶ楽な行程でした。

大日山からは、堂平山と笠山がよく見えます。左の平らな感じの山が堂平山、右のとんがっている山が笠山(通称おっぱい山)です。
この2座もいずれ登りたいとは思っているのですが、登山口までは基本バス利用になるので、ちょっと面倒だから避けちゃっているんですよね。バスってどうしても電車と比べて、時間も運賃もかかっちゃうからなぁ……。いろんな山に登ろうとすると、バス利用は必須になるのは分かっているんですけどね。

さて、ここでちょっとトラブルが。大日山を過ぎてしばらく歩いていたのですが、尾根歩きだから、緩やかに上ったり下ったりするはずなのに、なんかずっと下りばかり続くんですよね。おかしくね? と思ってGPS を確認したら、道を間違えていました。
どうも、笠山、堂平山の眺望が開けているところから、山を降りる道が伸びているのですが、間違えてそっちに行っちゃったようです(画像の左方向のルート)。
標高にして、大体70mくらいでしたけど、ちょっと急めのところを一気に登り返したのはちょっとキツかったです。いやまあ、急ぐこともなかったんですけど、こういうトラブルがあったときは、なるべく早く挽回したくなっちゃうんですよね。今回はなんてことのない低山だからいいけど、もっと心に余裕を持たなくてはなりませんね。

気を取り直して、物見山へ。

巻き道もありますが、当然ピークを踏んでいきます。

物見山に到着。
物見山は標高284m。ルートの途中であまり見所はありません。

物見山を過ぎると、多くの石碑が並んだ広場に出ました。




この自然石を活かした石灯籠がお気に入りです。
ベンチがあったので、ここで休憩していきました。

この広場を出るところで、急坂と巻き道が分かれていました。
当然、急坂を選んだのですが……。

この画像だとわかりにくいかもしれませんが、本当に急な下り坂で、少し危険でした。
巻き道を巻かないのはまあいいとして、上りならまだしも、下りの急坂は避けられるなら避けた方が良かったですね。

さて、小倉城跡が近づいてきました。

仙元山方面から歩いてくると、小倉城跡の裏側に出ます。

小倉城跡は、近くにある菅谷館跡、杉山城跡、武蔵松山城跡と併せ、比企城跡群として国の史跡に指定されています。
ずっと山道を歩いてきたし、途中の青山城跡もほぼほぼ山だったので、小倉城跡もその延長だと思っていたのですが、のぼりが立っているなど、思っていたより整備されていて観光地化していました。
小倉城についても、青山城とセットで、別途記事にする予定です。

小倉城跡を下りて、一旦人里へ。
この目の前に、2つの低山があります。

北に見えるのが大平山。

南に見えるのが正山です。
まずは正山に登るべく、道を南へと進みます。

ただ、正山へ登る道はちょっとわかりにくいんですよね。と、言うか、道のように見える場所を発見することができませんでした。

道なき道だけど、上を目指して登っていけば、なんとか登れないこともなかったかもしれません。でも、あんまりそういう気分でもなかったので、正山へ登るのは諦めました。

正山への登り口の近くには、小倉城の周囲を囲む槻川が流れています。

その槻川と大平山周辺は嵐山渓谷という景勝地となっています。京都の嵐山と似ているからそう名付けられたのですが、京都の方は“あらしやま”、埼玉の方は“らんざん”と読みます。
秋の行楽シーズンということもあり、嵐山渓谷にはかなり多くの人が集まっていました。

本来なら正山に登ってから嵐山渓谷へ行き、その後南から大平山に登る予定だったのですが、正山を取りやめたので、大きく回り込んで大平山の北部からアプローチします。

南からだと結構急坂になるんですけど、北からだと傾斜がかなり緩やかで、とても登りやすくなっています。

そんなわけで、大平山の山頂に到着。
大平山は標高178.9m。街の近くにあるほどほどの山ということで、家の近所にあると嬉しい山ですね。

少し南に移動した辺りから。南の方の街並みがよく見えます。







説明を省いて一気に進みますが、嵐山渓谷を一回りして、武蔵嵐山駅まで歩き、この日の山行は終了です。

小川町駅スタート、武蔵嵐山駅ゴールで、行動時間は休憩含めて5時間31分、移動距離は19.4㎞、累積上りは978m、累積下りは1007mでした。
正山だけは別ですが、全体的にはとてもよくルートが整備されていて、快適に歩くことができました。そういうこともあり、特に大平山や嵐山渓谷周辺は人が多すぎでしたけどね。
武蔵嵐山駅近くには、比企城跡群であり、続日本100名城でもある、菅谷館跡と杉山城跡がありますので、そのうちこの二つもセットで訪れたいと思います。










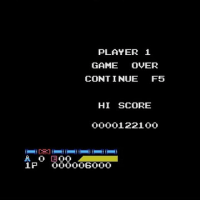

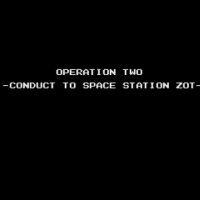











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます