10月26日
全国的にいい天気の予報。こちらも朝からいいお天気。でも朝はストーブがかかせません。
月に2回の定例シダの会観察会です。今日は八峰町の真瀬川の下流から上流に向かっての観察会になりました。真瀬川は鮭の遡上で知られていますが、今回はもう遅く鮭の遡上は終わっており見られませんでした。その代わりと言っては何ですが線虫を見付けています。この線虫は何という名前でしょうか。解る方がおられましたら教えて下さるようにお願い致します。
今日の観察会は紅葉狩りでもあり又アザミを沢山観察できました。少しはアザミについて解ってきましたが来年になると忘れているかもしれません。
01.朝6時半の日の出。下は白神岳です。今日はいいお天気になりそうです。

02.八峰町で熊の罠です。始めて見ました。こんな所でも熊がでるんだ。

03.真瀬川河口で鮭のの遡上を見に行きましたがもう終わっていました。三十釜付近で鮭を見ました。

04.三十釜の紅葉です。

05.黒滝です。右写真は黒滝の右にある大木ですが何の木かは解らず。凄い根が張りだしています。

06.黒滝を見るいつものメンバー。今日もご迷惑をかけています。

07.サワアザミ(キク科)総苞の基部にある4-6枚の苞葉が特長で、花の下から立ち上がる。

07-1.サワアザミの種子。

08.ナットウダイ(トウダイグサ科)果実期も終わっていました。残念。

09.枯れたナラ軒に、ノキシノブ、(ウラボシ科) 、ホテイシダ(ウラボシ科 )枯れ木を観察するのも面白い。ただ高いところ、危険な所にあるので注意が必用。

10.コケイラン(ラン科)葉だけでした。

11.クサボタン(キンポウゲ科)果実も終わっていました。

12.ゲンノショウコ別名ミコシグサ(フウロウソウ科)別名のミコシグサは、熟して裂けた果実の形から神輿(みこし)の屋根を連想したもの。

13.オヤマボクチ(キク科)花茎の先に暗紫色の4 - 5cmの頭花を下向きに付ける。葉裏が白い。語源は、茸毛(葉の裏に生える繊維)が火起こし時の火口(ほくち)として用いられたことから。

14.ヤブタバコ(キク科)どこでも見られます。

15.ダキバヒメアザミ(キク科)普通葉柄の基部が茎を抱き,中型の頭花が上向きに咲くアザミです。

16.ウゴアザミ(キク科)1他のアザミは、葉が羽状深裂するのに対し、この花は普通切れ込みのないことが多く、葉の基部が茎に沿下し翼となることが異なる。 登山道脇に群生していることが多いので、まず見逃すことはないと思います。

17.ウゴアザミ2。

18.ウゴアザミ3。頭花は上向きに咲き、、紅紫色で径2.5~3.5cm。総苞は球状鐘形でクモ毛があり、総苞片は6列、外片と内片は同長で真っ直ぐのびる。

19.クロモジ(クスノキ科)果実は中々に見られない。和名である「黒文字」の名は、若枝の表面に黒い藻類が付着し、黄緑色の地色に黒いまだら模様の斑紋が入るため、これを文字に見立てたものといわれる。

20.サルメンエビネ(ラン科)葉だけです。和名の「サルメン」は唇弁が赤みを帯びてしわが寄っているのをサルの顔に見立てたことに由来。

21.トチバニンジン(ウコギ科)熟して着た果実。日本原産。和名の由来は、葉の形状がトチノキに似ることからきている。

22.22年10月25日 八峰町真瀬川河口。何の「線虫その1」。
23.22年10月25日 八峰町真瀬川河口。何の「線虫その2」。
24.22年10月25日 八峰町真瀬川河口何の「線虫その3」。
25.22年10日26日 毎日新聞 季語刻々。
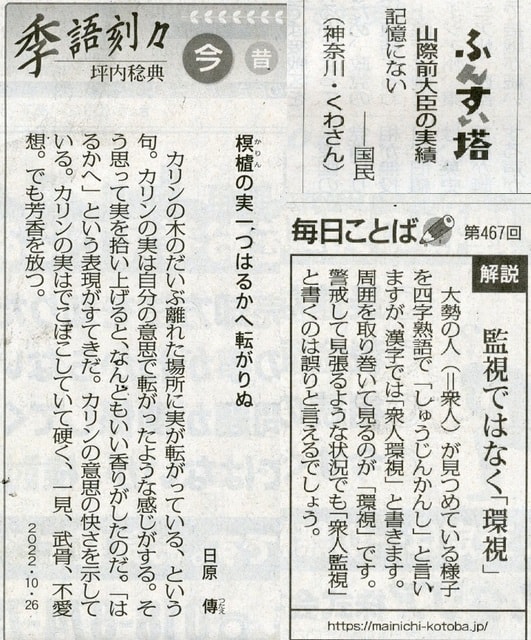
26.22年10日26日 毎日新聞仲畑流万能川柳。
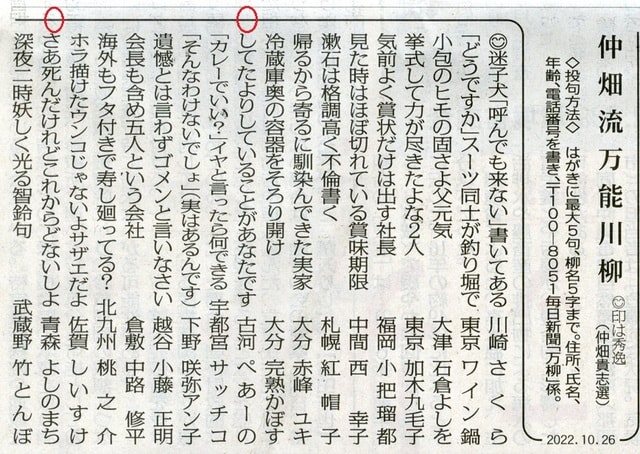
できたこと:今日の観察会を纏めきったこと。
楽しかったこと:去年以来久し振りに山野の紅葉を愛でました。
感謝すること:メンバーに教えられ助かりました。
それにしても真瀬川の河口でこのような線虫を見た事にびっくりです。
誤字脱字がありましたらご容赦を。













