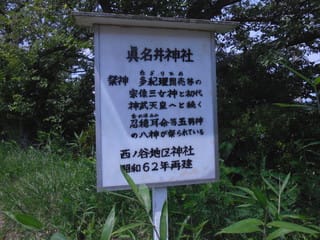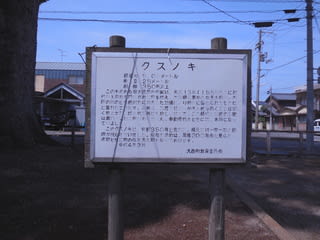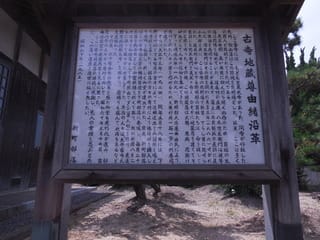宍甘第2遊園地(宍甘128-5)から案内標識を頼りに山王山に登る。5分ほどで岡山市立宍甘遊園地(同445‐2)に辿り着いた。明治天皇宍甘御野立所と記された石碑が端の方に建っていた。



龍駕駐蹕記念碑=明治四十三年秋陸軍特別大演習を我吉備の野に於て行はる〱に當り、明治天皇は御総監として行幸あらせられ、大本營を岡山後樂園に置かれ演習地に行幸あらせられたり。演習第三日(十一月十五日)東軍は司令部を藤井に置き、岡山西大寺道上横割附近より龜井頭、土田を經て四御神西北方高地に亘りて陣地を占領し以て機の熟するを待ち、西軍は司令部を原尾島に置き、旭川の左岸に展開して東軍を追擊せんとす。時に東軍は有力なる部隊の來着をに依り俄然攻勢に轉じ笠井山、龜井頭にある兩軍陣地より砲聲起り、續いて全線の歩兵戰鬪を開始し砲聲銃聲殷々轟々加ふるに機關砲の響は砰礚として耳を劈くが如く、午前九時東神下、長岡の線にて衝突狀况となり演習中止となる。此日明治天皇は古都村大字宍甘山王山の高地に行幸あらせられ、親しく兩軍を御総監あらせられたり。依りて其附近數百歩の地を併て公園となし、櫻楓樹を植ゑ小亭を造り御野立あらせられたる御跡には石碑を建て、之を後世に傳ふること〱なりぬ。苟も一たび去つて此聖蹟に過ぎるあらば、誰か天皇の御偉德を瞻仰熱烈の至誠を起さざるものあらんや况んや。又當時に在りて畏くも龍顔に咫尺し餘光を拜せし臣民に於てをや。(後略)
『上道郡誌(大正11年・1922)』

現地を訪れた時には近くの記念碑について詳細は分からなかったが、上道郡誌の記述に目を通して漸く胸のモヤモヤが解消したのだった。これほどの史跡が郷土史家やコアな鉄道ファンにしか知られていないのは実に惜しい。説明板(漢文碑文の口語訳など)を設置して内外に大いにPRしてもらいたいものだ。

藩政時代に山王山周辺で屑中の屑が仕置されたことを明治天皇は恐らくご存知なかったと思う。天子様がご覧になった田舎の風景は今や様変わりしたが、見晴らしの良さは全く同じだ。真下を通過する新幹線や南方を行き来する在来線を撮影出来て嬉しかった。




龍駕駐蹕記念碑=明治四十三年秋陸軍特別大演習を我吉備の野に於て行はる〱に當り、明治天皇は御総監として行幸あらせられ、大本營を岡山後樂園に置かれ演習地に行幸あらせられたり。演習第三日(十一月十五日)東軍は司令部を藤井に置き、岡山西大寺道上横割附近より龜井頭、土田を經て四御神西北方高地に亘りて陣地を占領し以て機の熟するを待ち、西軍は司令部を原尾島に置き、旭川の左岸に展開して東軍を追擊せんとす。時に東軍は有力なる部隊の來着をに依り俄然攻勢に轉じ笠井山、龜井頭にある兩軍陣地より砲聲起り、續いて全線の歩兵戰鬪を開始し砲聲銃聲殷々轟々加ふるに機關砲の響は砰礚として耳を劈くが如く、午前九時東神下、長岡の線にて衝突狀况となり演習中止となる。此日明治天皇は古都村大字宍甘山王山の高地に行幸あらせられ、親しく兩軍を御総監あらせられたり。依りて其附近數百歩の地を併て公園となし、櫻楓樹を植ゑ小亭を造り御野立あらせられたる御跡には石碑を建て、之を後世に傳ふること〱なりぬ。苟も一たび去つて此聖蹟に過ぎるあらば、誰か天皇の御偉德を瞻仰熱烈の至誠を起さざるものあらんや况んや。又當時に在りて畏くも龍顔に咫尺し餘光を拜せし臣民に於てをや。(後略)
『上道郡誌(大正11年・1922)』

現地を訪れた時には近くの記念碑について詳細は分からなかったが、上道郡誌の記述に目を通して漸く胸のモヤモヤが解消したのだった。これほどの史跡が郷土史家やコアな鉄道ファンにしか知られていないのは実に惜しい。説明板(漢文碑文の口語訳など)を設置して内外に大いにPRしてもらいたいものだ。

藩政時代に山王山周辺で屑中の屑が仕置されたことを明治天皇は恐らくご存知なかったと思う。天子様がご覧になった田舎の風景は今や様変わりしたが、見晴らしの良さは全く同じだ。真下を通過する新幹線や南方を行き来する在来線を撮影出来て嬉しかった。