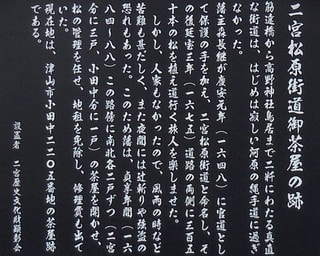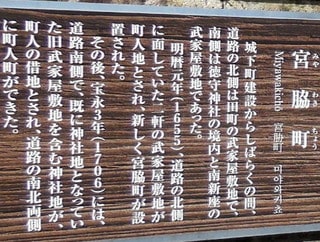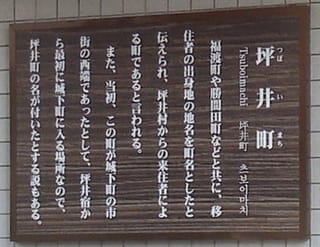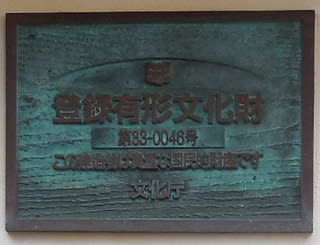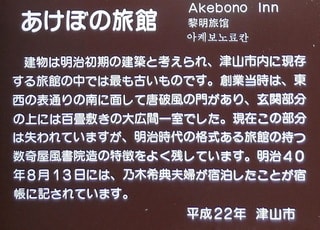高野神社参道を引き返して瀬島商店前から南下し吉井川沿いに出た。私が津山を旅した時には宮下橋(車道部)補修工事中で「終日全面通行止(歩行者と自転車は通行可)」になっていた。


施工業者は地元の近藤組だった(※諸問題が発覚して車両が行き来できるようになったのは予定より2ヶ月遅れの今年6月から)。川べりの道を進むと青野石油店が見えてきた。



施工業者は地元の近藤組だった(※諸問題が発覚して車両が行き来できるようになったのは予定より2ヶ月遅れの今年6月から)。川べりの道を進むと青野石油店が見えてきた。