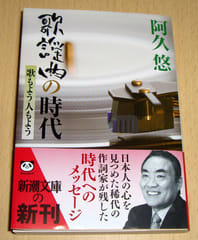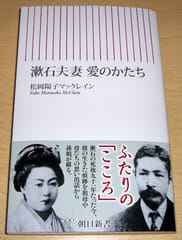「便利さを追求すれば必ず失うものがある」というテーマで現在の日本が抱える問題を指摘した本である。
確かに携帯電話の進化によって、様々な情報が即座に入手でるようになった。その反面、「待つ」ことや「自分で調べる」ことの意味や楽しさを忘れ、思考能力の低下が人格形成にも悪影響を及ぼしていることは否めない。
携帯、パソコンに依存しすぎない生活を送ることが望ましいと、柳田さんは提唱している。仮想現実の中で己が皇帝になり、いけ好かない他人を(匿名で)激しくかつ執拗に攻撃するのはどう見ても病気である(笑)
「人の悪口を言ってる間はまだまだ子ども」と昔の年寄りは教えてくれたものだが、今ではまともな親を見ることすら難しくなっている。「他人の痛みを理解する」ことが出来なくなった理由の一つは「仏教哲学」の無理解にあると、私は考えている。

確かに携帯電話の進化によって、様々な情報が即座に入手でるようになった。その反面、「待つ」ことや「自分で調べる」ことの意味や楽しさを忘れ、思考能力の低下が人格形成にも悪影響を及ぼしていることは否めない。
携帯、パソコンに依存しすぎない生活を送ることが望ましいと、柳田さんは提唱している。仮想現実の中で己が皇帝になり、いけ好かない他人を(匿名で)激しくかつ執拗に攻撃するのはどう見ても病気である(笑)
「人の悪口を言ってる間はまだまだ子ども」と昔の年寄りは教えてくれたものだが、今ではまともな親を見ることすら難しくなっている。「他人の痛みを理解する」ことが出来なくなった理由の一つは「仏教哲学」の無理解にあると、私は考えている。