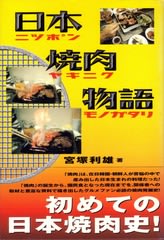集英社新書、2007年2月21日第1刷発行、定価998円(税込み)
桑田佳祐さんはデビューから第一線で活躍し続けている。小学生の時、短パン姿で“勝手にシンドバッド”をだみ声で歌う男を見て「なんじゃ、こりゃ~」と思った。数日して私は掃除の時間にホウキを持って「今何時。そうね、大体ね」の掛け合いをやった。歌詞の大部分は聴き取り不能だったが、不思議と耳に残った曲ではあった。
中学に上がると、誰もがサザンを聴いた。悪友は『ヌードマン』のジャケットを手にとってニタニタ笑っていた。そのアルバムは私の愛聴盤になった。
小学時代のベスト『女呼んでブギ』
中学時代のベスト『匂艶(にじいろ)THE NIGHT CLUB』
高校時代のベスト『ミス・ブランニュー・デイ』
大学時代のベスト『悲しい気持ち』
社会人になってからのベスト‥90年代『真夜中のダンディー』
社会人になってからのベスト‥21世紀『白い恋人達』
中山さんの評価と私のそれが近いのはただの偶然か(笑)。音楽は理屈で聴くものではない。自分がいいな、と思ったものが名曲なのだ。












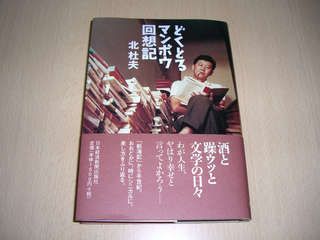






 「本当によく調べたものだ」と私などは感心するばかりだ。この本のおかげで随分と無駄遣いせずに済んでいる。よく考えれば今年はZEPPELINに関しては一つも購入していない。収集対象を1972年までとしているので凄いブツがリリースされなかったということだろう。
「本当によく調べたものだ」と私などは感心するばかりだ。この本のおかげで随分と無駄遣いせずに済んでいる。よく考えれば今年はZEPPELINに関しては一つも購入していない。収集対象を1972年までとしているので凄いブツがリリースされなかったということだろう。