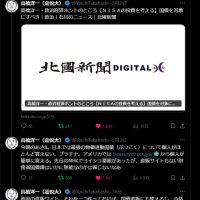兵庫県姫路市が誇る世界遺産・姫路城は、街一帯が焦土と化した昭和20年7月の姫路空襲で焼失を免れた。「米軍が意図的に攻撃対象から外した」との説がいまだ語り継がれるが、真相は別にあった。3日で空襲から74年。当時を知る「語り部」らの証言から浮かび上がったのは、複数の偶然が重なった奇跡だった。
■自宅燃え家族犠牲
昭和20年7月3日の深夜、「ウー」と空襲警報のサイレンが姫路の中心街に鳴り響いた。107機の米軍爆撃機B29から焼夷弾が「雨のように」投下された。火災が一気に広がり、空が真っ赤に染まった。
当時、姫路城内にあった旧制鷺城(ろじょう)中学の4年生だった元高校教諭、黒田権大(ごんだい)さん(90)もこの空襲で自宅が焼失。自身は何とか難を逃れたものの、祖父母が犠牲となった。
空襲の翌朝、煙がかすむ一面の焼け野原の先に、黒い姫路城がぽつんとそびえていた。敵機の爆撃目標にならないよう、白しっくいの美しさなどから「白鷺城」の異名を持つ大天守が黒い偽装網で覆われていたのだ。黒田さんは、家族を失った失意の中で城の無事に目頭が熱くなった。
「米軍は文化遺産の価値を理解し、爆撃を回避した」。いつしかそんな逸話が広がった。
■搭乗員は「偶然」
空襲から50年目の平成7年7月。姫路に焼夷弾を落としたB29の搭乗員ら元米兵5人が、大学教授らの招きで姫路を訪れた。
市戦災死没者遺族会会長だった黒田さんも同行し、姫路城の石段を上がる途中で、当時74歳だった元機長のアーサー・トームズさんに英語で問うた。「なぜ城を爆撃しなかったのか」
トームズさんは答えた。
「上官から避けろとの命令はなく、城の存在さえ知らなかった。残ったのは偶然だ。神の意志だったのかもしれない」
暗闇での空襲。当時の爆撃機の標的捕捉レーダーは、水面と陸地の区別しかできなかった。元搭乗員らが城を囲む堀を池や湖と誤認し、焼夷弾の投下を控えた可能性も示唆した。
■大天守に不発弾
米軍が当時作成した「戦術作戦任務報告書」によると、空襲指令時に米軍が配った姫路市街地の作戦地図では、赤インクで線引きされた爆撃範囲のちょうど北端の線上に姫路城が位置していた。姫路市平和資料館の梶原久義副館長は「焼夷弾は空中で散らばるので、米軍に姫路城を守る意図があったとは考えにくい」と指摘する。
実際、姫路城三の丸にあった旧制鷺城中は校舎3棟が全焼。さらに大天守最上階に焼夷弾が直撃したものの不発で炎上を免れていたことが近年、不発弾処理にあたった日本側将校の手記から明らかになった。
空襲から74年。黒田さんは、平成の大修理を終えてしっくいの白さが輝きを増した城を見るたび、「後世に残ったことを誇りに思い、平和に対する感謝の気持ちが強くなる」と目を細める。7日には姫路市平和資料館で講演し、戦争の悲惨さと平穏な日々の尊さを改めて訴えるつもりだ。(植木芳和)
●姫路空襲
米軍が昭和20年6月と7月、2度にわたり姫路市を狙った空襲。1回目は6月22日午前、姫路城近くの川西航空機(現・新明和工業)姫路製作所付近。2回目は7月3日深夜から4日未明まで1時間39分間続き、市街地を焼夷弾で無差別爆撃した。計514人が死亡し、約5万5400人が被災。全市街地の76%が壊滅した。