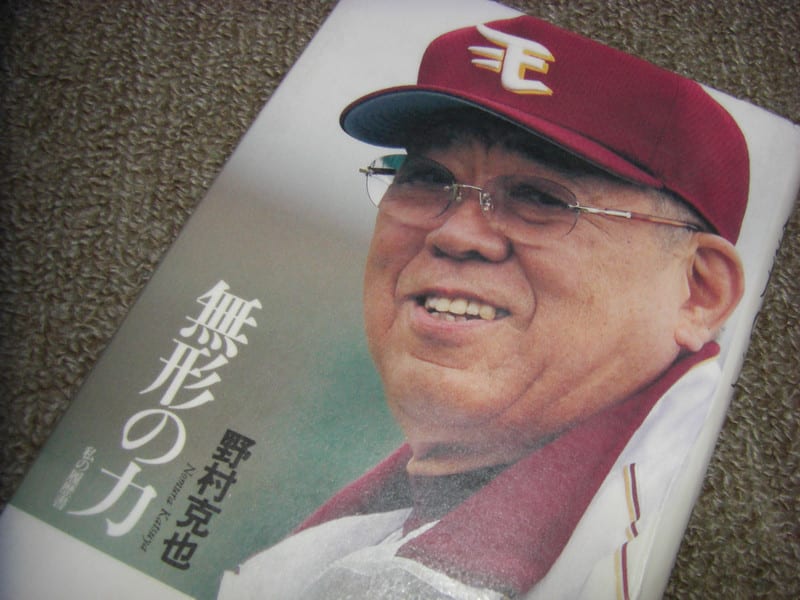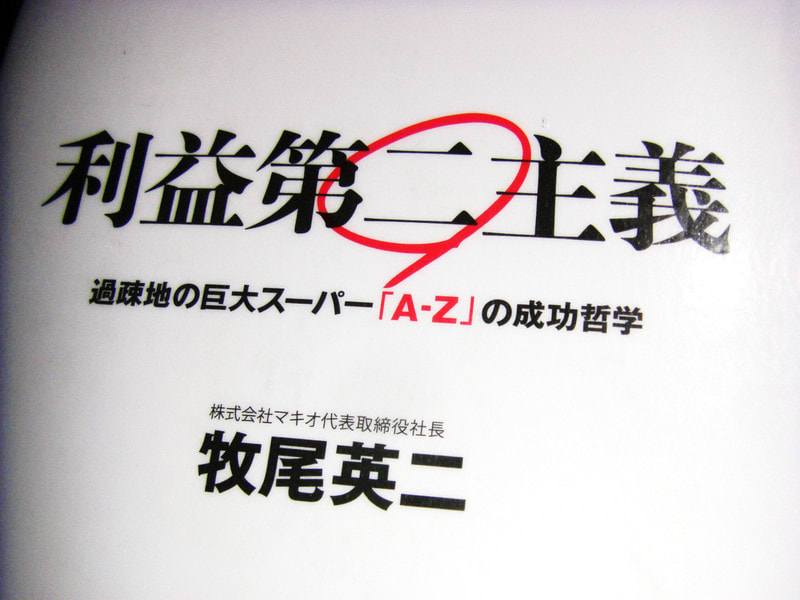第173回記事(2013年12月9日(月)発行)
(次回12月16日(月)発行予定)
「イヤならやめろ!」という衝撃的なタイトルにはとにかくビックリしてしまいます。しかし、これは本を売るために付けられタイトルと認識され、言葉足らずの部分を補うと、
会社の中で「おもしろおかしく」仕事をするようにいかに努力しても会社の仕事が「おもしろおかしく」ならない時は、その会社と決別すべき時だ
ということです。ですので、大切なことは仕事を「おもしろおかしく」するように変えることです。この考えは著者の考え方そのものであり、著者が会長(当時)をされている堀場製作所の社是にもなっています。また、本のサブタイトルは、「社員と会社の新しい関係」となっています。
著者の堀場雅夫さんは、戦後すぐ現在の堀場製作所の元となる堀場無線研究所を創業され、紆余曲折を経て分析機器で有名な現在の堀場製作所をつくられました。堀場製作所は、研究開発型ベンチャーのモデルともいえる企業です。現在でもベンチャー企業の支援等で活躍されており、最近TVでもお見かけしました。
そんな著者の経験から、仕事は「おもしろおかしく」やらないといけないというポリシーが出てきています。確かに研究開発を私もやっていましたが、なかなかうまく行きませんでした。最後には、事業的な点から縮小の決心がされ、私は転属となり、ある意味で悔しい思いをしました。
しかし、この本を読むとまだまだあなたの努力は足りないよと言われているように感じます。たとえば、①自分自身に尖った点がなかった・尖った点をつくれなかった(「千人に一人」(の世界的なエキスパート)を目指せ:48p)、②これくらいでいいやと自分の中で妥協し、毎日毎日の努力が足りなかった(トイレの中で新商品のアイデアが閃いた:60p)(金魚屋にあった解決策:60p)といった点です。
上記のような点に思い当たる方がおられれば、出版は約20年前になりますが、読まれたらいかがでしょうか。
<データ>
出版社:日本経済新聞社
定価:1000円(当時)
出版年:1995年
ページ:221p
写真:

<参考>
ベンチャー企業を実際に起業されている方や、今後ベンチャー企業の起業を考えておられるかたは、以下の本も参考になると信じます。むしろ、会社経営全般を見る中ではバランスがとれており、こちらの本の方が有益だと思われます。
タイトル:堀場雅夫の社長学
著者:キング・オブ・ベンチャー 堀場雅夫
出版社:ワック株式会社(ワック文庫)
価格:880円+税
出版年:2005年(ただし、それ以前に出版された「堀場雅夫の経営心得帖」(東洋経済新報社)を改訂・改題したもの)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
訃報
上記の経営の本棚④(第173回記事 2013年12月9日(月)発行)で紹介させて頂いた、
「イヤならやめろ!」の著者の堀場雅夫さんが2015年7月14日亡くなられました。
ご冥福をお祈り致します。享年90歳。
(私のようなものが書くのもおこがましいところがありますが)
堀場さんは、「イヤならやめろ!」の本の中にも記載がありますが、
「おもしろおかしく」を基本にされて、それを実践されてきた、
ユニークな経営者と言えます。
しかし、最も注目されるべきは、
戦後すぐにベンチャー企業の堀場製作所という会社を立ち上げられ、苦労をされた経験から、
経営の第一線都を退かれた後は「ベンチャー企業の育成」に努められていた点と思います。
合掌。
井上三郎右衛門