やっと「中庸」を詠み解く作業を終えて、今回公開にこぎ着けることが出来た。儒学四書の一つ「中庸」は、儒学者が最後に学ぶべき深遠なものとされている。今日、中庸なる言葉は「どちらにも偏らず中正なこと」という意味に広く使われているが、朱子学で云う「中庸」とは「過不及なき一定不易の徳」の意味で、倫理面に重点を置いているところに違いがある。例えば、いろいろな意見をまとめる場合でも、単にその中間の意見を採用するのではなく、それが倫理面に適ったものであるかどうかが問われる。もう一つ重要なことは、「中庸」は三千五百字ほどの短文だが、その中で「中庸」という言葉の他に目立つのが「誠」なる言葉で、「中庸」の倍以上の使われ方をしていることである。これは「中庸の徳」が、人間の天与の「善なる本性」である「誠」を持って完成するという思想の表れである。武士道の最高の徳とされる「誠」、そしてあの新撰組の旗印の「誠」は、いずれもここに根ざしたものである。さて、今回も「訓読漢文」を併記した詳しいものも紹介しているので以下のホームページも是非見て頂きたい。
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町
田 原 省 吾
http://homepage2.nifty.com/tokugitannka-ronngo/
◎中庸章句序(表章経緯)
(中庸の作成の意義)
中庸は儒の心髄を永遠に伝えんがため子思これ作る
(道統の継承)
上代の聖人は皆天命を受けて天子の位につけり
その上で天意受け継ぎ万世の軌範を立てて民に示せり
儒の教えこの様にして正統にその伝統が受け継がれたり
(教典に見る聖王の言葉)
(堯王の一言)
王として中庸の道守ること政治行う要諦となる → (執中)
(舜王の三言)
人間の欲から発す人心は道逸脱の危うさを持つ
道徳に基づく意識道心は人心により影薄れ勝ち
従ってこの道心を精察し物欲を棄て中庸はかれ → (精一)
(執中の実現策)
執中は舜王の言う精一の方法により現実となる
執中に人・道心と精一を加えて王ら中庸を説く
堯王の一言と舜王の三言が相まって中庸の実現が計られる。
(心の働き)
心とは影形なく霊妙な知覚働く唯一のもの
さりながらその働きに二面あり人の心と道の心と
人心は個の肉体に基づいて私欲となって現れるもの
道心は天が与えし本性の正しさにより現れるもの
人心は悪には非ずさりながら悪に陥る危うさを持つ
道心は完全にして至善だが幽微なるため見極め難し
人心は本来生きて行く上で必要な人欲にして、個々人に属する
特有のものだが、過度になりやすく悪に陥る危険を持つ。
人は皆その肉体を持つが為上智の人も人心を持つ
人は皆また本性を持つが為下愚なる人も道心を持つ
この二つ心の中でせめぎあうために収める策が必要
さりながら上手く収める策なくば危うきものはさらに危うく
さらにまた上手く収める策なくば幽微なるものさらに幽微に
その結果天が与えし本性は人欲のもと影うすれがち
(精一・執中とは)
精の意は人・道心を精密に識別をして交えざること
一の意は我が本心の正しさを堅く守って失わぬこと
精一を常に守って身を処せば人・道心は正常保つ
かくすれば道心常に主となって人心をして従わしめる
人心がその命令に従えば悪に陥る心配もなし
幽微なる道心も亦かくすればその存在も著明なものに
結局はその言動が過ぎもせずまた及ばざる事もなくなる
このことが堯王の言う執中で「中守る」こと実現できる
(四言の伝承)
大聖が天下統治の大権を伝えることは天下の大事
大権の授受に際して戒めて伝えしものがこの四言のみ
したがって天下の道理表すにこの四言にて極まることに
この後も聖人達はこの四言堅く守って伝承したり
君主としては殷の湯王、周の文王・武王、臣としては舜の
皐陶・伊尹・傅説、周の周公・召公などの聖人達。
(その後の道統)
統治者の地位を得られぬ孔聖もまた道統を継承したり
孟子言う未来の学徒導きし孔子は古王より勝れりと
そのあとも顔回および曾参がその正統を継承したり
子思の代聖人の世遠くして異端の邪説大いに興る
所謂諸子百家の類。
(子思の業績)
時を経て道の真相失われ絶たれることを子思恐れたり
それ故に伝承されし真の道よく推し測り基かためたり
さらにまた教えを受けし父や師の言葉をもって真意正せり
父は孔鯉、師は曾子。
かく正しこの「中庸」を著して後学の徒に告げ示したり
(中庸の心髄)
述聖の憂う思いは深くしてその言言や懇切極む
述聖とは子思のこと。
さらにまたその考えは遠大でその説論は詳細極む
「天の命、性に従う」との謂いはこれぞ即ち「道心」のこと
「善選びこれ固執する」との謂いはこれぞ即ち「精一」のこと
「その君子時に中す」のその謂いはこれぞ即ち「執中」のこと
堯舜の時より子思の時代までその隔たりは千有余年
さりながら両者の言は明白に割り符の如くぴたりと一致
いにしえの道に関する聖人の書き記したる書物多々あり
さりながら「中庸」ほどに洞察し明確にして實なるはなし
(孟子の伝承)
子思の後この「中庸」は直弟子に伝承されて孟子に至る
孟子よくこの「中庸」を推察し意を明らめて伝承したり
孟子死し伝承絶えて道統は典籍としてただ残るのみ
そのうちに異端の邪説日に月に盛んとなりて世に流行す
さらにまた老氏・仏氏の輩の出現により道理乱れる
その説はまこと道理に似て非なり真正の道ために乱れる
(程夫子の業績)
幸いに「中庸」の書失せざれば二程子出でてこれを考究
孟子以後千歳を超える時を経て道統の道再起し得たり
「中庸」にその根拠得て邪説たる道・仏教を斥け得たり
述聖が「中庸」作り後世に残せし功は実に大なり
しかもなお世に二程子が出でずんば子思の心は継承されず
(二程子の中庸解)
さりながら惜しきことには二程子の「中庸」の解世に伝わらず
石子重、北宋の儒者十人の説をまとめて「集解」を編む
それにより大意の把握できうれど微なるところは明らかならず
さらにまた自説に頼り老仏の邪説に堕するもの見られたり
(朱子の見解)
朱子は先ず多くの説を精選し「中庸章句」一編著作
朱子慕う門人達が「集解」の整理を為して「輯略」著作
さらにまた朱子の語録を記録してこれを整理し「或問」著作
「輯略」に「或問」を附す事により「中庸」の趣旨極まることに
(朱子附言)
聖人の道の伝統受け継いだ者については敢えて論ぜず
とは言え道統の伝承者として朱子は窃かに自らを任じた。
さりながら「中庸章句」学ぶこと初学者にとり一助となろう
◎本文宋朱熹章句
(序)
二程子は偏らざるを「中」と言い変わらざる事これ「庸」と言う
さらにまた「中」は天下の正道を「庸」は天下の定理とも言う
正道とは不偏なる大綱にして全ての基となり、定理とは不易
なる条理にして細目をあらわす。
「中庸」は孔子門下に伝わりし聖者伝授の心の法なり
後世の誤伝の事を子思恐れ「中庸」作し孟子に授く
(中庸の要旨)
先ず始め天命により生まれつき備わりしもの「性」を提言
中ほどはこの天性を展開し種々の事象について解説
三達徳(知・仁・勇)、五達道(君臣道・父子道・夫婦道・兄弟道
・交友道)、九経(周礼・儀礼・礼記・春秋三伝・易経・書経・詩経)
など。
終わりでは集約をして一理とし天帝の徳明らかにせり
「中庸」は現に役立つ学にしてその味わいは無限に深し
熟読しその心髄を会得せば一生涯の宝たるべし
◎第一章
(性と道と教え)
万物が天命により生まれつき具有するものそれが性なり
本然の性。
その性の導くままに行えば具現するものそれが道なり
天道にして人道。
その道を明らかにして聖人が啓示せしものそが教えなり
天下の法則。
(慎独)
この道は寸時も離れ得ざるもの離れうるもの道には非ず
君子とは人に聞かれぬ所でも道励むため慎み戒む
君子とは人に見られぬ処でも道励むため恐れ慎む
隠すほど外に悪事ははっきりと形現すそが世の習い
微細なる事ほど過失はっきりと姿現すそが世の習い
それ故に君子は独り居るときもその言動を固く慎む
(未発の中)
心中に喜怒哀楽の感情がまだ現れぬそを「中」という
本然の性がそのままで、心の平静な状態。
(已發の和)
心中に感情発ししかもなお節度があればそれを「和」という
感情が現れてはいるが、依然として本然の
性はそのままの状態。 和は「か」と読む。
本然の性に基づき過不及がなき「中」こそが天下の基本
感情を発してしかも節度あるその「和」なるものこそが達道
「中」と「和」を押し窮めればこの天地正しさ保ちすべて健全
(朱子見解)
以上第一章は、子思が孔子より伝承されてきた教えの趣意
を述べたもので、その言わんとする処は、
一、人の守るべき道の根源は天から出ており、其れを変更
する事は出来ず、その実体は自己に備わっていて、離れ
る事は出来ない事。
二、君子は道を究める為に、本心を見失わぬよう守り育て、
独り居るときも陰ひなたなく励み慎む事。
三、喜怒哀楽の感情が働き出さぬ時の「中」、働きだしても
節度を保っている時の「和」は、共に天下の大本・達道
であり、これを押し窮めれば天下も正しさを保ち、万物
も健全な生育を遂げる事が出来る事。
即ち、学を志す者は自身を反省し、その備わる「善」なる本然
の性を把握して、世俗に毒されやすい私欲を棄て、善行を積
む事が求められる。
以下の十章は子思が孔子の言を引用して、第一章の意義を
補完したものである。
◎第二章
(孔子の言葉一)
君子みな中庸守り小人はその中庸に違反するもの
優れたる徳を備えし君子皆時に応じて「中」守り得る
小人は私欲によって行動し遠慮なければ「中」守り得ず
◎第三章
(孔子の言葉二)
いずれにも偏りのなき「中庸」の道こそ徳の最高指標
さりながら「中庸の徳」弁えて身を処する者久しく出でず
◎第四章
(孔子の言葉三)
人の道行われざるそのわけは知者の軽視と愚者の無理解
人の道理解されざるそのわけは賢者の無視と不肖者の無知
常日頃離れられざる道なれど真にその意を知るは少なし
◎第五章
(孔子の言葉四)
明君も教化怠りその為に無道のこの世孔聖なげく
道を行うに当たり、人には過ぎた者と及ばざる者が多く、
永く「中庸の道」を行う者の少ないことに触れたもの。
「中庸」を詠み解くⅡつづく










![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg)
![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg)
![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg)
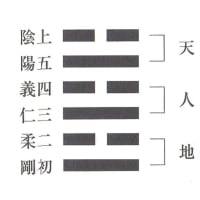
![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg)

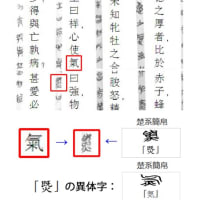
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます