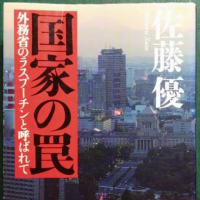友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」より
いくつかかいつまんで、紹介させていただきます。
カテゴリー: WAVE MY FREAK FLAG HIGH
ギターの歴史を変えたジミ・ヘンドリクス作曲の“If 6 was 9”の歌詞の中に出てくる言葉をヒントにしています。
(中略)
この曲は、そういう「違う生き方」を象徴する曲とされています。「異者の旗を振ろう」という意味ですね。
このタイトルのもとで、繁栄のなかの息苦しさを突破する「違う生き方」の可能性、また3.11以降の社会のありようを考える哲学的、宗教的なエセーを綴ろうと思っています。
2018年4月26日投稿
友岡雅弥
紀元前7世紀ぐらい、楚の穆(ぼく)王は、暴君で、家臣はこびへつらい、人々は暴政に塗炭の苦しみを味わっていました。周囲の国々も、穆王による侵略と略奪に疲弊していました。
穆王は急死し、その子が王となりました。これが荘王です。ところが、まだ若かったため、即位直後に、穆王のもう1人の子ども、燮(しょう)が、クーデターを起こし、これが成功。一時は全権を掌握します。
しかし、さらに内乱が起こり、燮は殺されます。
そして、荘王が宮に戻るのですが、ごろごろ寝てばかり、前の穆王が暴君であったため、みな恐れて、だれも諌めません。
ごろごと怠惰に耽って三年め、伍挙という臣下が遠回しに、「三年、鳴かず飛ばずの鳥がいました。その名前はなんというでしょうか?」と問うたところ、「その鳥は怠惰で鳴かず飛ばずなのではない、機が熟すと大きく飛び立つのだ」と、言い放ちました。
こんどは、蘇従という臣下が、死刑を恐れず、直接的な言葉で、荘王を諌めたところ、王は起き上がって、今までのこびへつらう佞臣たちを退け、人格、能力とも立派な人たちを引揚げたのです。
それで、楚は栄え、荘王は歴史に「名君」として名を残すことになりました。
実際、父王の死後、若すぎて内乱をもたらしたこと、そして内乱とその後の、臣下の様子を冷静に長時間見極め、自身の成長と、臣下の本質を見抜けるちからが満ちてくる時を待ち、そして、立ったわけです。
これと同じ話は、『史記』の「滑稽列伝」にも、威王の話として出てきます。
つまり、「鳴かず飛ばず」とは、無理をして見栄えのいい、みんなから大拍手をもらう「外見」をとり合えず取り繕うのではなく、時を待って、長く自分のなかの充実、また周囲の支えの充実を待つことなのです。
飛躍に備える、いい意味なのです。
実は、これと似た話が、民話「桃太郎」の原形とされるものにあります。
よく知られた「桃太郎」は、第二次大戦中、「鬼畜米英」を懲らしめる、武運長久の象徴、桃太郎として使われました。
当時の尋常小学校、国民学校の教材などを見てみると、鬼の姿が、当時のアメリカ大統領トルーマン、イギリス首相チャーチルの顔にしています。
犬、猿、雉は、陸海空の三軍です。
実際、日本が作った短編ではないアニメの第一号が、戦意高揚を狙った『桃太郎の海鷲』、次作が『海の神兵 桃太郎』 です。
(実際、これらを作った監督は、敵国アメリカのディズニー映画を研究するのですが、見ているうちに「戦争に勝てない」と思ったといいます。日本は全力で戦争に向かっているのに、アメリカは高度で予算も膨大にかかった、戦争と関係ないアニメを作る余裕がある)
さて、武運長久桃太郎と違う形の、素朴な原形桃太郎は、
桃太郎さんは爺さまと婆さまと三人で一緒に住んでいたそうです。
ある日のこと、桃太郎さんは近所の友達と山へ柴刈りへ行く約束をしました。二、三日して友達が誘いに来て呼びました。
「桃太郎さん、桃太郎さん、山へ柴刈りへ行かんか」
桃太郎さんはこう返しました。
「今日は草鞋(わらじ)を作りかけよるけん明日にしてくれ」
あくる日、友達はまた誘いに来て呼びました。
「桃太郎さん、桃太郎さん、山へ柴刈りへ行かんか」
「今日は草鞋のひきそを引つきよるけん明日にしてくれ」
またあくる日、友達はまたまた誘いに来て呼びました。
「桃太郎さん、桃太郎さん、 山へ柴刈りへ行かんか」
「今日は草鞋の緒を立てよるけん明日にしてくれ」
更にあくる日になって友達が呼びに行くと、桃太郎さんは「今度はさぁ行こう」と言って、二人で連れ立って山へ行きました。
山に着くと、友達は一生懸命に柴を刈りますが、桃太郎さんは一本の大木にもたれて昼寝ばかりしています。そうこうするうちに友達は一荷拵(こしら)え終わったので帰ろうとしますと、桃太郎さんは凭れていた大木をヤッと引き抜いて、それを荷物にして持って帰りました。
家に帰り着くと、桃太郎さんは「ヤレヤレ、疲れた」と、持って帰った大木を家のひさしにポンと立て掛けました。ところが、あんまりにも大きい木だったので、家はガラガラと崩れて、爺さまと婆さまは下敷きになって死んでしまいました。
桃太郎さんは爺さまと婆さまを助けようと瓦礫の中を探し回りました。すると大きな盥(たらい)を見つけたので、それを舟にして川を下っていきました。
盥は、やがて海の真ん中の島に流れ着きました。そこでは青鬼と赤鬼が相撲を取っていて、見ていると赤鬼がコロン、と投げ飛ばされて負けていました。
「赤鬼、ウワーイ!」
桃太郎さんが野次を飛ばすと、赤鬼は怒って「赤い豆やるきん黙っとれ」と言って赤い豆をくれました。それからまた見ていると、今度は青鬼がコロン、と投げ飛ばされて負けていました。
「青鬼、ウワーイ!」
桃太郎さんが野次を飛ばすと、青鬼は怒って「青い豆やるきん黙っとれ」と言って青い豆をくれました。それからまた見ていると、今度は赤鬼と青鬼が一緒にコロン、と転んでいました。
「赤鬼、青鬼、ウワーーイ!」
赤鬼と青鬼は怒って、桃太郎さんに撃って掛かりました。桃太郎さんは二匹の鬼を束にして、海の中へポーーンと投げ込んでしまいました。それから鬼の住処の宝物を取って、家へ帰ったそうです。これでおしま い。
これは、『日本昔話集成』の讃岐篇にあるものです。
昔話の分類では、「桃太郎・三年寝太郎」系と呼ばれるもので、三年間とか長い間、ぐうたらしていた桃太郎、三年寝太郎が、機が熟して活躍する(この讃岐のは、活躍しすぎて、おじいさん、おばあさんが犠牲になりましたが)ものです。
きれいに、作り込まれた美談の「りりしき桃太郎」ではなく、無理せず、自分のなかの充実を待つ、ぐうたら桃太郎のほうがいいですね。
目立たなくてええやん、自分を育み、育てていきたいと思います。
【解説】
つまり、「鳴かず飛ばず」とは、無理をして見栄えのいい、みんなから大拍手をもらう「外見」をとり合えず取り繕うのではなく、時を待って、長く自分のなかの充実、また周囲の支えの充実を待つことなのです。
飛躍に備える、いい意味なのです。
なるほどなと思いました。いい話ですね。
私も今、自身のなかの充実を待っています。
充電中です。
友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」はお勧めです。
獅子風蓮