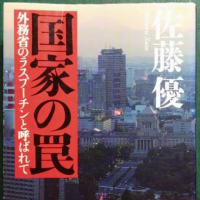友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」より
いくつかかいつまんで、紹介させていただきます。
カテゴリー: WAVE MY FREAK FLAG HIGH
ギターの歴史を変えたジミ・ヘンドリクス作曲の“If 6 was 9”の歌詞の中に出てくる言葉をヒントにしています。
(中略)
この曲は、そういう「違う生き方」を象徴する曲とされています。「異者の旗を振ろう」という意味ですね。
このタイトルのもとで、繁栄のなかの息苦しさを突破する「違う生き方」の可能性、また3.11以降の社会のありようを考える哲学的、宗教的なエセーを綴ろうと思っています。
2018年4月12日投稿
友岡雅弥
「大黒舞」は、今では、民謡、およびその踊りとして、とても、ポピュラーです。ほんとに、東北から中国地方まで、あちこちに分布しています。
たとえば、山形の大黒舞はこんな感じ(もちろん、さらに山形でも地域地域で変化あり)
サアー 舞い込んだ 舞い込んだナー
何がさてまた 舞い込んだナー
御聖天が先に立ち 福大黒が舞い込んだナー
四方の棚をながむればナー
飾りの餅は十二重ね 神のお膳も十二膳
代々この家は未繁盛と打ちこむ所はサー 何よりも目出度いとナー
この歌詞と、全国に分布しているということから、次のことがピンと来るかたもおおいでしょう。
――もともと、放浪の門付け芸人たちが各地に広げたのではないか?
そうですね。正月に、放浪の門付け芸人さんが、家々の玄関先で、おめでたい文句(祝詞)を並べ、また滑稽なしぐさで、笑いを誘った芸能です。
「祝詞(のりと)」というと、今は、神社でお参りに来た人が、神妙な態度でうけたまわるものを言いますが、室町、江戸時代、明治、昭和初期までは、万歳(まんざい)厄払い、鳥追い、節季候(せきぞろ)、春駒など、特に正月には、家々の軒先で、めでたい言葉、またその年の多幸を寿ぐ言葉を、節やしぐさをつけて語る、放浪の門付け芸人の祝詞が、津々浦々にこだましておりました。
そして、それを聴く人々は、神妙な顔ではなく、大笑いの顔で。
さて、鎌倉から江戸時代にかけて(特に室町)、庶民の説話が集められて成立・発展したのが、「御伽草子(おとぎぞうし)」です。
この「御伽草子」のなかに、「大黒舞」の由来について語られた物語があります。
おそらく室町時代。
大悦の助(だいえつのすけ)という男の人がいました。親孝行で評判でしたが、貧乏のため、暮らしは思うに任せません。
清水寺に参詣し、観音に親孝行をさせ給えと念ずると、清水寺の楊柳観世音菩薩が現われ、わらしべ(いなわら)をくれる。
なんか、あとは、想像できますね。
それを持って帰ろうとした大悦の助。途中で、三メートルほどの大きな鬼神が現われます。それをよこせ、よこさなかったらお前を殺すぞ、と言われますが、貴い観音菩薩からの頂き物、いかに、わらしべと言っても渡すわけには行かないと、拒否し、先を急ぎます。
すると、道端でありの実売りが、ケガをしている。
「ありの実」って分かりますか?忌言葉を避けたものですね。「梨」のことです。nothingの「ナシ」につながるので、寄席とか、花柳界とかで使われます。
ここは、全体がおめでたいお話なので、「忌言葉」を避けたのでしょう。
主人公も、「大悦」ですからね。
そのありの実売りがかわいそうで、傷の血止めに、わらしべを使います。
そうすると、ありの実売りが、ありの実を三つくれます。
手玉に取りながら(「手玉に取る」というのは、ジャグリングやお手玉みたいにすることです)、家路を急ぐと、何か、人々がワイワイ騒いでいます。
大悦の助が、日ごろみたこともないような「上流階級」の男女が右往左往しています。
立派な輿に乗りたる内裏の姫が、気分が悪くて水が飲みたいと。
大悦の助は、かわいそうになり、「もしありの実でよければ」と、さしだします。
姫は、ありの実を食べて、すっかり気分がよくなります。
「褒美をとらせよう」
と、絹二疋をもらいました。
これは、父母が喜ぶぞと、帰りを急ぐ途中。
三条の橋のたもとで、由緒がありそうな侍と従者たちが騒いでいる。大番役(御所の警備)の任務を終わって帰るところだが、予備の馬が倒れた。予備の馬なので、必要が無いといえば必要がない。
なんと、侍は、馬をほって行こうとする。身分の低い従者だけ、おろおろと馬の看病をしている。
大悦の助は、馬も馬でかわいそう、従者も従者でかわいそう、と思います。
そして、その「立派な」侍に、絹をあげるから、その馬をください、と言うわけです。
大悦の助が、懸命に看病すると、馬はようやく元気を回復します。
そして、とても立派な馬で、大悦の助の生活には必要ない。それで馬市で売ると、とても高い値段で買ってもらえた。
そのお金で、大悦の助は、家を建て、父母と楽しく暮らしていました。
あらたまの新春。まだ夜が明けやらぬのに、窓をコツコツたたく音がする。
でてみると、背が低く、顔は藍染めのように青黒い。
大黒天です。
まだ、この場合は、江戸時代のかなり変化した七福神の「大国様」のような愛嬌のある姿ではなく、もともとのインド神話の「マハーカーラ(大いなる暗黒)」の姿を維持しています。
従者として、ねずみもいます。
大黒天は、大悦の助の善行を愛でて、宝珠や様々な宝物を与えます。
やがて、蛭子(えびす)三郎もやってきました。
まだ、七福神の恵比寿様になる前の、身体に障がいがある存在、もしくは異国人(夷)の異形性も感じられる蛭子です。
ただし、蛭子三郎、大黒天ともに、ニコニコとして、大悦の助の善行を讃えます。
その日は節分でした。
今は、新春、正月は一月初めで、節分は二月ですが、旧暦なので、基本、節分と正月は重なります。
この日は、季節の変わり目で、体調を崩しやすいというところから、鬼神が跋扈すると考えられていたわけです。
やはり、鬼神がやってきました。
それで、大黒天が、「豆を煎って、鬼に投げつけよ」と言います。
それで、大悦の助は、「鬼は外、福は内」と言って、鬼に豆を投げつけると、鬼神は目を隠して、逃げていきました。
それで大団円となり、 舞を舞うわけです。
「節分の豆まき」の由来譚でもありますし、放浪の芸人たちが舞う「大黒舞」の由来譚でもあります。
また、「わらしべ長者」と昔話の類型でいうと、典型的な長者譚となるわけですが、
特に示唆的なのは、大悦の助が交換する「動機」 です。
「換えてくださいな」と頼まれる類話が多いですが、すべて、かわいそうに思っての「無償の贈与」です。結果として、交換になりましたが、動機の段階では、与えるだけの「贈与」です。
与えるだけの無償の行為って、とっても大事だと思いますね。
ちなみに、「功徳」の原語は、主に「guna」で、人徳。時に、punyaで、「善き行い」、稀にanuśamsaで、「人助け」です。
(サンスクリット語の表記は正しくできませんでした)
【解説】】
「わらしべ長者」と昔話の類型でいうと、典型的な長者譚となるわけですが、
特に示唆的なのは、大悦の助が交換する「動機」 です。
「換えてくださいな」と頼まれる類話が多いですが、すべて、かわいそうに思っての「無償の贈与」です。結果として、交換になりましたが、動機の段階では、与えるだけの「贈与」です。
与えるだけの無償の行為って、とっても大事だと思いますね。
賛同します。
勤行唱題も、何かの願い事を「功徳」として求めるのではなく、本尊や本仏に対する「無償の奉仕、善行、感謝」でありたいものです。
それにしても、友岡さんは古典芸能などに造詣が深いですね。
友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」はお勧めです。
獅子風蓮