しかしながら、教育現場の端くれにいる私としては、依然として学力状況は厳しいといわざるを得ないいくつかの材料がある。例えばこれ。
【岩手】数学落ち込む中学、2割が円面積の正解出せず(朝日さん 10.11.16)
円の面積の求め方は「半径×半径×円周率(3.14)」。これは、小学5年生で習う。
今から3年前、全国学力調査で、岩手県内の小学6年生のうち23.9%が、円の面積を求める問題の正解を出せなかった。
そして今年。彼らが中学3年生となり、再び全国学力調査を受けた。そこで出された問題は、円柱の体積の求め方。「円の面積×高さ」が正解だが、 県内の誤答と無回答を合わせると67.8%となった。誤答のうちの約3割が、円の面積を求めるところで円周(直径×円周率)を求めていた。
小6で理解しなければならないことをおろそかにしたまま、中3になっている生徒が多いことが、推測される。
この傾向は全国的にも見られることだが、岩手はより深刻だ。
全国学力調査は、小6と中3を対象に、国語と算数・数学の2教科(Aは基礎、Bは活用)で行われる。
過去4年の調査を見ると、小6の正答率は全国平均以上だが、中3になると平均を下回るのが、岩手の特徴だ。今年度の成績(表参照)では、小6は算数B以外は平均以上だったが、中3では国語A以外は平均を下回った。
「小学校から中学校へのホップ・ステップの接続がうまくいっていないのでは」と指摘するのは、教育雑誌「蛍雪時代」の元編集長で、学力問題に詳しい代田恭之さん(78)。小学校の時は良かった成績が学年を追うごとに下がっていくことを、代田さんは「小中学校間のねじれ現象」と呼んでいる。
特に問題なのは、算数・数学。今年の中3が小6だった時、算数Aの正答率は83.7%(全国平均82.1%)で全国10位だったのが、今年の数学Aは45位だった。
「数学は系統性がはっきりした教科。積み重ねることが大事」と話すのは、盛岡市教育委員会で算数・数学を担当する金野治指導主事。その積み重ねが順調にできているとはいえない。
環境が変わる中学に上がる時に、勉強についていけなくなる「中1ギャップ」。これをなくすため、県内の小学校では新たな取り組みをするところも出てきた。
北上市にある市立黒沢尻北小学校。全国学力調査の活用法として、正答率の低かった問題を繰り返し解く「復習」に、力を入れるようになった――。 (後略)
気をつけていただきたいが、
中3で、円柱の「表面積」を求めさせたのではなく、「体積」を求めさせた。
正答率が67.8%なのではなく、誤答率+無回答率が67.8%である
ということである。すなわち、中3の32.2%しか、円柱の体積が求められなかったということだ。
材料はもう一つある。私の実際の教え子で、高3で予備校内偏差値が60程度あるにもかかわらず、
「村」を"billage"と黒板に書いた(言うまでもなく正しくは"village"である)。
また、"restaurant"が書けなくても、明治大学法学部に合格した生徒がいる。これは私が直接担当した生徒ではないが。
言うまでもなく、どちらも厳然たる、中学レベルの単語である。しかも、いわゆる「ゆとり教育」の世代で、教科書の巻末に載っている600語程度の索引(もちろん中学3年間合わせてだが)にも必ず載っているレベルの単語である。
私のような、「準ゆとり教育の世代」であっても、このレベルの単語は、中学時代に今や懐かしい「4線ノート」にひたすら書かされたというか、自分で危機感を持って練習したレベルの単語である。
これらの材料から、かなり強引ではあるが、肌として感じる仮説は以下の通り。
いわゆる読解力の成績が上がってきたというのは、マスコミやマスゴミが取材しているように、全国各地で読書を重視した取り組みがある程度功を奏している結果だと思う。逆に言えば、文科省が設定する重点目標が、日教組の影響が強い学校でもある程度実践されている可能性を感じる。もちろん、都道府県別や、日教組の影響が強い学校の結果はどうだったのかという精査は必要ではあるが。
ただ、その一方で、
「調べればわかるからと言って、あらゆることを『覚えなくて良い』というわけではない。すぐに引き出せるmaterial(材料、マテリアル)としての『基礎的知識』も極めて重要なのだ」
という価値観を浸透させることは、我々現場も含めて、あまり成功していない可能性が大きいということである。
よく教育者のブログに書かれていることだが、ほとんどの高校生は学校でも予備校でも、授業中に机の上に電子辞書を置いている。実感としては9割以上である。そのほとんどが2万円以上もする高価なものだ。当然英和だけでなく、少なくとも和英や国語辞典、古語辞典、漢和辞典が入っているモデルだ。日本史用語集や世界史用語集が入っているモデルもある。
もちろん、電子辞書を授業中に机上に置いておくこと自体は何ら不思議ではないと私も考えている。私も高校時代は紙の辞書を机上に置いていた。ところが、
その電子辞書を、英語の時間に、教師に当てられてからおもむろに引くのである。※「おもむろに」がポイント。こういうバカは決して焦ったりしない。
・・・少なくとも私の高校時代は、当てられてから紙の辞書を引く生徒はいなかった。いたとしても周りから(教師からではなく)「バカ」扱いされていたものだ。
私のクラスでは「当てられてから電子辞書は引くな」ということを勝手に(?)ルールにしているが、そのルールに「内心の自由(笑)」などの理由で従わなかったり、新たに参入した生徒などは、実に脳天気に
当てられてから電子辞書を引く。
生徒がそうするたびに、私は理由も含めて説教することにしているが、こういう生徒側の「内心の自由(笑)」の根本的動機として、
調べりゃわかるんだから、なんで調べちゃいけないの?
という気持ちが前提にあるような気がしてならない。そして、こういう気持ちは安易に
調べりゃわかるんだから、覚えなくてよくね?
とズレていくことも予想できる。その蓄積が、知識を軽視する高3生という現状に結びついているように感じられる。これが現時点での私の実感だ。
一方で、読解力というのは、その場で書かれていることの意味や意図さえ理解できれば良いのだから、教育現場で文字を追いかける練習を積み、呼んだ内容をその場で発表させることで、ある程度向上させることができる。
今日の結論:読解力向上が、必ずしも「必須の知識習得」に結びついていない可能性がある。この仮説が正しければ、少なくとも、今の高校生の学力状況は、PISAの結果とは関係なく、かなり深刻である。
※「内心の自由(笑)」を皮肉っている理由を知りたい方はこちらの記事を。










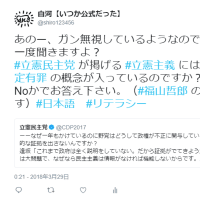
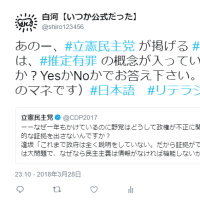

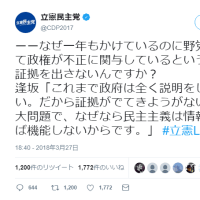
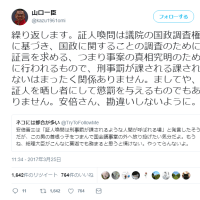
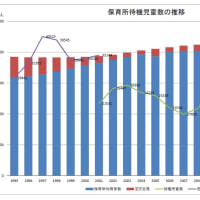
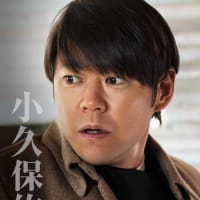




遅くなりましたが
満6年おめでとうございます!
(その間私は何度ブログを変更したことか…。
白河様のその継続力がすばらしいです。)
ところで、その「内心の自由(笑)」!!
うちのゆとりな新入社員に感じます…!
日程調整をするときに、普通の営業なら「自分もそうだけど相手も間違えないように何度も確認」しますよね?
その子はしないんです!
相手が間違えたから自分は悪くない、という態度を貫くんです…
若干ずれましたが、「内心の自由(笑)」は恐ろしい(><)
そういう人たちが、社会に出てそのうちの一部は教師になり、母親になり…
ゆとりは増殖を続ける一方ですね(^^;
「当てられてから電子辞書は引くな」なんて当たり前ですけど、学校現場では当たり前ではないかもしれないのですね!?
息子にはよく言い聞かせます!
>相手が間違えたから自分は悪くない、という態度を貫くんです…
日程調整も「営業」をするための手段なのだから、営業ができるかどうかが重要という「優先順位」が全然わかっていないのでしょう。
ああ、同業の若い人にもいますねえ。。確かに。ヘタすると年上にも・・・
小中高時代に「これは強制」という体験をして来なかった「自称大人」が多いんでしょうな。すべては「思想の自由、良心の自由、内心の自由」ですよ(笑)。
日教組の「内心の自由」の恣意的な使い方には毎度あきれ果てていますが、今ブームになっているのは「朝鮮学校を差別するな!」ですな(笑)。何も差別などしていないのにね。早く日本の「学校」に転校していらっしゃいよと。
あ、「当てられてから電子辞書は引くな」は学校では当たり前じゃないのでしょうね。初期状態では当てられてから引くバカが半数はいますから。