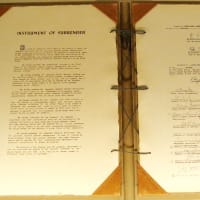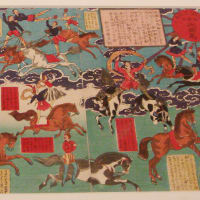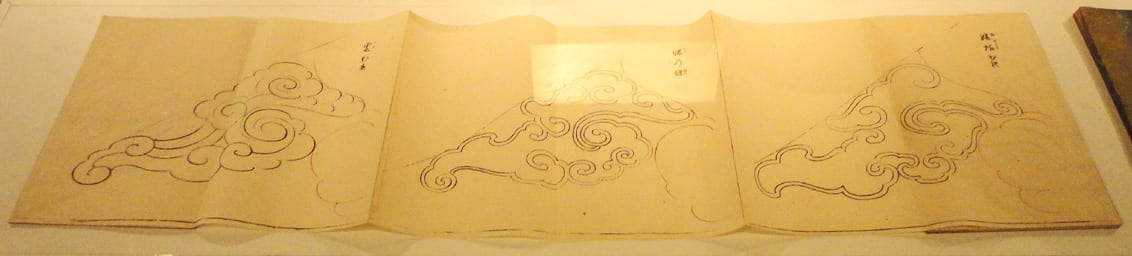
“絵様”とは、彫り物をするための下図のこと。
江戸時代までは建築彫刻は大工の仕事とされ、その当時の大工技術
書「匠明」に大工が修練する技のひとつとして、この絵様と彫り物が
挙げられている。

展示されていた「大和絵様集」(宝暦13年・1763)は、立川小兵衛に
よって著された絵様の雛形本で、様々な見本と一筆ごとの描き方が説
明されている。
大工は道具の扱いの器用さと共に、筆さばきの心得も必要だった。

また、建物の一部に華やかなアクセントを添える彫物は、桃山時代
あたりから豪華絢爛を極めていく。しかし、絵様は時代と共に大工仕
事から別れ、彫物の専門職へと移っていく。
(神戸市中央区中山手通4-18-25)
江戸時代までは建築彫刻は大工の仕事とされ、その当時の大工技術
書「匠明」に大工が修練する技のひとつとして、この絵様と彫り物が
挙げられている。

展示されていた「大和絵様集」(宝暦13年・1763)は、立川小兵衛に
よって著された絵様の雛形本で、様々な見本と一筆ごとの描き方が説
明されている。
大工は道具の扱いの器用さと共に、筆さばきの心得も必要だった。

また、建物の一部に華やかなアクセントを添える彫物は、桃山時代
あたりから豪華絢爛を極めていく。しかし、絵様は時代と共に大工仕
事から別れ、彫物の専門職へと移っていく。
(神戸市中央区中山手通4-18-25)