1930年、フェデールがガルボの『アンナ・クリスティ』のドイツ語版を作っていた頃、ジョセフ・フォン・スタンバーグがマレーネ・ディートリッヒ主演のドイツ映画『嘆きの天使』(1930年4月ドイツ公開)を作って成功し、ディートリッヒを連れてスタンバーグが再びハリウッドへ帰って、パラマウント映画で『モロッコ』(1930年12月米国公開、翌年2月日本公開)を作る。パラマウントがライバル会社のMGMの大スター・ガルボに対抗して、ドイツから呼んだディートリッヒを売り出そうという作戦であった。これが見事に的中して、『モロッコ』は大ヒットし、主演のゲーリー・クーパーもディートリッヒも以後国際的な大スターへの道を歩んでいく。

『モロッコ』は、フランスの外人部隊の兵士トム・ブラウン(クーパー)とモロッコに流れ着いた女性歌手アミー・ジョリー(ディートリッヒ)との恋愛を描いたロマンチックな映画であるが、いかにもハリウッド調の娯楽作品で、エキゾチズムを漂わせるための借り物としてモロッコという背景と外人部隊を取り上げたにすぎなかった。カリフォルニアでの野外撮影とハリウッドのスタジオのセットで撮影された映画で、外人部隊もモロッコのアラブ人も偽物で、フランス人が見たら滑稽に思えるような代物だった。クーパーの色男の兵士も格好が良すぎて、あんなアメリカ人が外人部隊にいるはずもなく、一方のディートリッヒはフランス語と英語で歌い(彼女の母国語はドイツ語だが、フランス語も達者だった)、英語の台詞は少なめで、時々フランス語を話すが、この二人の登場人物の設定からして非現実的で、人物の背景も性格描写も浅薄であった。

『モロッコ』は、アメリカだけでなく世界中でヒットした。日本でも大ヒットして、過大評価とも言えるほどの絶賛を博した。しかし、フランスでの評判は非常に悪かったそうだ。とくにラスト・シーンは酷評されたという。ディートリッヒが裸足になって、砂漠を行くクーパーを追いかけていく、あの最後の場面であるが、日中モロッコの砂の上など熱くて、裸足で歩けるはずがないというのである。
ハリウッドで不遇をかこっていたフェデールもきっとカリフォルニアのどこかで『モロッコ』を見て、苦々しく感じたにちがいない。
フェデールがフランスを離れているうちに、フランス映画もトーキーの時代に入り、後輩の若手監督たちが活躍を始めていた。クレールは、『巴里の屋根の下』(1930年)、『ル・ミリオン』(1931年)、『自由を我等に』(1931年)、『巴里祭』(1932年)を作り、デュヴィヴィエは『資本家ゴルダー』(1931年)、『にんじん』(1932年)などを作り、注目を浴びていた。少し遅れてルノワールが『素晴らしき放浪者』(1932年)を発表して頭角を現す。まさに1930年代、トーキー初期のフランス映画黄金期が幕開けしていた。フランスには演劇の長い伝統があり、舞台俳優たちがトーキー映画に出演し、その個性を存分に発揮し始めたのである。
1933年2月、フェデールはおよそ5年ぶりにフランスへ帰ってきた。そして、脚本家のシャルル・スパークと再会し、二人でオリジナル脚本を練り、満を持して作った映画が『外人部隊』であった。これは、フェデールがフランスで初めて作ったトーキー映画だった。
『外人部隊』は、フェデールが明らかに『モロッコ』を意識し、しかもそれを反面教師のようにして、リアリズムを貫いて作った映画である。現地でのロケ撮影を行い、ハリウッド的な甘美なロマンチズムとは反対に、人生の現実を見つめたドラマを作り上げた。
『モロッコ』でディートリッヒが歌う場面と『外人部隊』でリーヌ・クレヴェールが歌う場面を比較して見ると、フェデールはキャバレーでフランス人のプロの歌手が唄うシャンソンは、本当はこういうものだと見せつけているような気がしてならない。『モロッコ』には、男装のディートリッヒが歌いながらリンゴを配り、色男のクーパーがリンゴを買う有名な場面があるが、スターを引き立てるあのような演出にフェデールは反感を覚えたにちがいない。
また、『モロッコ』にも外人部隊が行進している様子を撮った画面が出てくるが、制服もバラバラの借り物でエキストラを使って適当に歩かせているだけだが、フェデールは『外人部隊』では兵隊の本式の行進をあえて長々と撮影し、小休止中や道路工事中の兵隊の様子、将校や隊長に対する下士官の態度などもきっちりと描いている。
『外人部隊』は、1930年代フランス映画黄金期(トーキー初期)の数ある名作のなかでも傑作の一本になった。しかし、この映画は、フェデールの『モロッコ』に対する挑戦状であったにもかかわらず、米国では公開されず、フランスとヨーロッパの数国と日本でしか公開されなかったようである。それらの国々では大ヒットしたが、スタンバーグの『モロッコ』に比べれば、雲泥の差のある興行成績であった。フランス映画を愛好する日本では『モロッコ』に負けないほどヒットし、外人部隊という言葉が流行語になった。フランス国内では『モロッコ』よりはるかに好評で、フェデールが再評価され、彼はフランソワーズ・ロゼーとともに次の『ミモザ館』と『女だけの都』を作ることができたわけである。『外人部隊』という映画がなければ、ジャック・フェデールは忘れられた存在になっていたであろう。その意味で『外人部隊』は、彼の名を世界映画史上不朽なものにした記念碑的作品でもあった。

フェデールとロゼー
フェデールと共同でオリジナル脚本を書いたシャルル・スパークにとっても、後年フランス映画を代表する脚本家としての名声を得るきっかけとなった出世作となった。シャルル・スパークは、ベルギーの名門(父は詩人で劇作家)の出身で同郷のフェデールに呼ばれて、1920年代の終りにパリへ出て、最初フェデールの秘書をやっていたが、『俄成金紳士たち』でフェデールに協力して脚本を書き始めた。しかし、頼りにしていたフェデールが渡米してしまい、フランスに残って、ジャン・グレミヨンやジョルジュ・ラコンブといった監督たちの作品の脚本を書いて、脚本作りの腕を磨いていた。スパークは、『外人部隊』ののち、『ミモザ館』『女だけの都』のほかに、デュヴィヴィエと組んで『地の果てを行く』(1935年)『我等の仲間』(1936年)の脚本を書き、ジャン・ルノアールと組んで『どん底』(1936年)『大いなる幻想』(1937年)を書く。
フランソワーズ・ロゼー(1891~1974)も、『外人部隊』で大女優としての存在感を印象付け、夫フェデールをフランス映画界にカムバックさせるために大きな貢献をした。まさに内助の功であった。そして、『ミモザ館』『女だけの都』で堂々と主役を演じ、続いて、フェデールの助監督だったマルセル・カルネの監督デビュー作『ジェニーの家』で主演し、カルネをバックアップし、その後も長いキャリアを維持していくのである。(了)

『モロッコ』は、フランスの外人部隊の兵士トム・ブラウン(クーパー)とモロッコに流れ着いた女性歌手アミー・ジョリー(ディートリッヒ)との恋愛を描いたロマンチックな映画であるが、いかにもハリウッド調の娯楽作品で、エキゾチズムを漂わせるための借り物としてモロッコという背景と外人部隊を取り上げたにすぎなかった。カリフォルニアでの野外撮影とハリウッドのスタジオのセットで撮影された映画で、外人部隊もモロッコのアラブ人も偽物で、フランス人が見たら滑稽に思えるような代物だった。クーパーの色男の兵士も格好が良すぎて、あんなアメリカ人が外人部隊にいるはずもなく、一方のディートリッヒはフランス語と英語で歌い(彼女の母国語はドイツ語だが、フランス語も達者だった)、英語の台詞は少なめで、時々フランス語を話すが、この二人の登場人物の設定からして非現実的で、人物の背景も性格描写も浅薄であった。

『モロッコ』は、アメリカだけでなく世界中でヒットした。日本でも大ヒットして、過大評価とも言えるほどの絶賛を博した。しかし、フランスでの評判は非常に悪かったそうだ。とくにラスト・シーンは酷評されたという。ディートリッヒが裸足になって、砂漠を行くクーパーを追いかけていく、あの最後の場面であるが、日中モロッコの砂の上など熱くて、裸足で歩けるはずがないというのである。
ハリウッドで不遇をかこっていたフェデールもきっとカリフォルニアのどこかで『モロッコ』を見て、苦々しく感じたにちがいない。
フェデールがフランスを離れているうちに、フランス映画もトーキーの時代に入り、後輩の若手監督たちが活躍を始めていた。クレールは、『巴里の屋根の下』(1930年)、『ル・ミリオン』(1931年)、『自由を我等に』(1931年)、『巴里祭』(1932年)を作り、デュヴィヴィエは『資本家ゴルダー』(1931年)、『にんじん』(1932年)などを作り、注目を浴びていた。少し遅れてルノワールが『素晴らしき放浪者』(1932年)を発表して頭角を現す。まさに1930年代、トーキー初期のフランス映画黄金期が幕開けしていた。フランスには演劇の長い伝統があり、舞台俳優たちがトーキー映画に出演し、その個性を存分に発揮し始めたのである。
1933年2月、フェデールはおよそ5年ぶりにフランスへ帰ってきた。そして、脚本家のシャルル・スパークと再会し、二人でオリジナル脚本を練り、満を持して作った映画が『外人部隊』であった。これは、フェデールがフランスで初めて作ったトーキー映画だった。
『外人部隊』は、フェデールが明らかに『モロッコ』を意識し、しかもそれを反面教師のようにして、リアリズムを貫いて作った映画である。現地でのロケ撮影を行い、ハリウッド的な甘美なロマンチズムとは反対に、人生の現実を見つめたドラマを作り上げた。
『モロッコ』でディートリッヒが歌う場面と『外人部隊』でリーヌ・クレヴェールが歌う場面を比較して見ると、フェデールはキャバレーでフランス人のプロの歌手が唄うシャンソンは、本当はこういうものだと見せつけているような気がしてならない。『モロッコ』には、男装のディートリッヒが歌いながらリンゴを配り、色男のクーパーがリンゴを買う有名な場面があるが、スターを引き立てるあのような演出にフェデールは反感を覚えたにちがいない。
また、『モロッコ』にも外人部隊が行進している様子を撮った画面が出てくるが、制服もバラバラの借り物でエキストラを使って適当に歩かせているだけだが、フェデールは『外人部隊』では兵隊の本式の行進をあえて長々と撮影し、小休止中や道路工事中の兵隊の様子、将校や隊長に対する下士官の態度などもきっちりと描いている。
『外人部隊』は、1930年代フランス映画黄金期(トーキー初期)の数ある名作のなかでも傑作の一本になった。しかし、この映画は、フェデールの『モロッコ』に対する挑戦状であったにもかかわらず、米国では公開されず、フランスとヨーロッパの数国と日本でしか公開されなかったようである。それらの国々では大ヒットしたが、スタンバーグの『モロッコ』に比べれば、雲泥の差のある興行成績であった。フランス映画を愛好する日本では『モロッコ』に負けないほどヒットし、外人部隊という言葉が流行語になった。フランス国内では『モロッコ』よりはるかに好評で、フェデールが再評価され、彼はフランソワーズ・ロゼーとともに次の『ミモザ館』と『女だけの都』を作ることができたわけである。『外人部隊』という映画がなければ、ジャック・フェデールは忘れられた存在になっていたであろう。その意味で『外人部隊』は、彼の名を世界映画史上不朽なものにした記念碑的作品でもあった。

フェデールとロゼー
フェデールと共同でオリジナル脚本を書いたシャルル・スパークにとっても、後年フランス映画を代表する脚本家としての名声を得るきっかけとなった出世作となった。シャルル・スパークは、ベルギーの名門(父は詩人で劇作家)の出身で同郷のフェデールに呼ばれて、1920年代の終りにパリへ出て、最初フェデールの秘書をやっていたが、『俄成金紳士たち』でフェデールに協力して脚本を書き始めた。しかし、頼りにしていたフェデールが渡米してしまい、フランスに残って、ジャン・グレミヨンやジョルジュ・ラコンブといった監督たちの作品の脚本を書いて、脚本作りの腕を磨いていた。スパークは、『外人部隊』ののち、『ミモザ館』『女だけの都』のほかに、デュヴィヴィエと組んで『地の果てを行く』(1935年)『我等の仲間』(1936年)の脚本を書き、ジャン・ルノアールと組んで『どん底』(1936年)『大いなる幻想』(1937年)を書く。
フランソワーズ・ロゼー(1891~1974)も、『外人部隊』で大女優としての存在感を印象付け、夫フェデールをフランス映画界にカムバックさせるために大きな貢献をした。まさに内助の功であった。そして、『ミモザ館』『女だけの都』で堂々と主役を演じ、続いて、フェデールの助監督だったマルセル・カルネの監督デビュー作『ジェニーの家』で主演し、カルネをバックアップし、その後も長いキャリアを維持していくのである。(了)











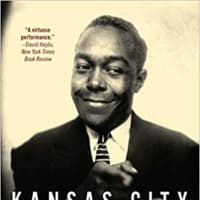

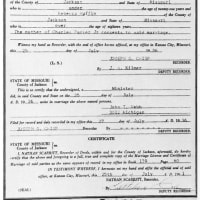







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます