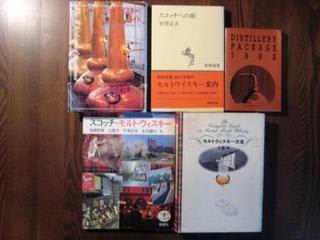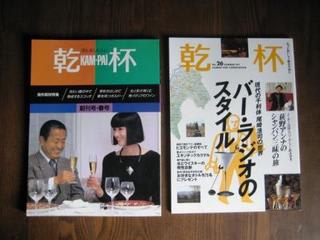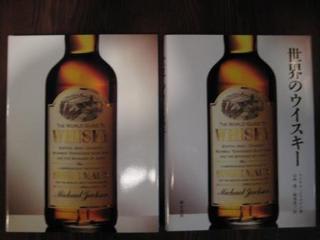10月18日(日)PM8:00よりテイスティング会をおこないます。題して「ブレンドとその原酒⑬ホワイトホース&ラガブリン」会費3000円です。興味のある方ぜひご参加ください。
目下のところ「ラガブリンは何を出そうかな~」とマスター考え中!詳細が決まったら画像を載せます。しばらくお待ちください。
ところで、前回のブログからずいぶん間があいてしまいました。ようやく再開の運びとなりましたが、健康上の理由からしばらく低空飛行でいくことになりそうです。気長にお付き合いいただければ、と思っています。
目下のところ「ラガブリンは何を出そうかな~」とマスター考え中!詳細が決まったら画像を載せます。しばらくお待ちください。
ところで、前回のブログからずいぶん間があいてしまいました。ようやく再開の運びとなりましたが、健康上の理由からしばらく低空飛行でいくことになりそうです。気長にお付き合いいただければ、と思っています。