ディルタイの「精神科学序説」を引き続き読んでいるが、仕事などが溜まっており、なかなか読み進められてはいない。前回から十数頁しか進んでいないが、メモの代わりに記しておきたい。
ディルタイは「精神科学」(現代でいう人文科学と社会科学を含む)の「自然科学」からの「相対的独立性」を証明しようとしている。したがってある面では、「精神科学から自然科学への依存の体系」を示すことになる。これは前回も書いた、「精神科学」でも「歴史学」に代表されるように、歴史的一回性の出来事が、歴史という普遍的な法則性の中でどのように体系化されているのかと問う場合、その一回性と普遍性との相互連関の体系の原理を解明しなくてはいけなくなる。このような一回性と普遍性を「体系」として構造化している原因は何かというと、認識論的な「心理学的法則」ということになる。これは単純な心の中というのではなく。「心理」の「法則性」こそが、この一回性と普遍性の「体系」を認識可能にしているという意味での、認識の条件に当たるものだと考えたほうがよい。そしてこの「心理学的法則」の「法則」を解明する際、ディルタイは自然科学的、あるいは「自然認識」の論理学を援用する。ディルタイは、「この体系ゆえに、精神科学は自然認識によって条件づけられており、したがって数学的基礎づけのうちで始まる構成のなかで最高で最後の部分を形成するのである。」(『全集1』p.25、以下同様)というのはそれを端的に表した言葉だといえる。
これはフッサールの『論理学研究』にもつながる。フッサールはこの「論理学」を、心理学的なものから超越論的主観性の構造へと展開していき、ディルタイ的な意味での「心理学」は批判していくが、しかし、この『論理学研究』の論理学は数学的なものであった。この数学的な論理学の問題は、ハイデガーが批判するわけだし、後にはデリダが『幾何学の起源』の「序」で、この数学的論理学が「歴史性」に常に既に「汚染」されているという形で、現前性批判される問題ともつながるのだと思う。
ただし、p.103でもそうなのだが、ディルタイは歴史が数学的基礎の論理学に「還元」されるとも言っていない。「歴史の経過を一つの定式または一つの原理の統一へと還元することはできない」といい、p.117でも、「精神科学は、自然科学とはまったく異なる基礎や構造を有している」という形で、「精神的現象を自然認識の連関に組み入れるというこの試みには二つのことが想定」されるとし、それらは「証明不可能」と「明らかな誤り」を招くとしている。つまり、「精神科学」は「自然科学」には「還元」できないわけだが、だとすれば、当初「精神科学」の「相対的独立性」と「精神科学から自然科学への依存の体系」とは何のことになるのだろうか。おそらくまだ100頁を越えたばかりで結論めいたことを言うのは慎まないといけないのだろう。この「精神科学」の「自然科学」への還元不可能性こそが、「精神科学」の「相対的独立性」になり、それが「歴史性」でもあるわけだが、しかしその場合の「精神科学」の法則性や論理性というのは、ディルタイが最初に予想していたような、数学的な論理性とは違うのだろうか?
今後この矛盾、即ち「精神科学」の「独立性」がここから考察されていくのだと思う。おそらくディルタイは「精神科学」を「自然科学」に「還元」して解消しようとする性急さを戒めているのであって、「精神科学」が「自然認識」の論理学と何らかの関係性を持っており、それが「精神科学」の「独立性」を可能にもしているという、複雑な「体系」を明らかにしているのだろう。そういう意味では「精神科学」の論理性が「自然認識」「自然科学」「数学的基礎」の論理学とどのような差異を持ち、あるいは相互に依存しあっているのかを、観ていきたいと思う。カントの物理的な自然法則と自律的で内的な理性(法則)の関係のようなものである。ディルタイの議論は、当然のことであるが、現代において「文系」が大事か「理系」が大事かという、通俗的でわかりやすすぎ、そしてコストと効率だけを意識したくだらない論争より、恐らく実りある議論になるだろう。
ディルタイは「精神科学」(現代でいう人文科学と社会科学を含む)の「自然科学」からの「相対的独立性」を証明しようとしている。したがってある面では、「精神科学から自然科学への依存の体系」を示すことになる。これは前回も書いた、「精神科学」でも「歴史学」に代表されるように、歴史的一回性の出来事が、歴史という普遍的な法則性の中でどのように体系化されているのかと問う場合、その一回性と普遍性との相互連関の体系の原理を解明しなくてはいけなくなる。このような一回性と普遍性を「体系」として構造化している原因は何かというと、認識論的な「心理学的法則」ということになる。これは単純な心の中というのではなく。「心理」の「法則性」こそが、この一回性と普遍性の「体系」を認識可能にしているという意味での、認識の条件に当たるものだと考えたほうがよい。そしてこの「心理学的法則」の「法則」を解明する際、ディルタイは自然科学的、あるいは「自然認識」の論理学を援用する。ディルタイは、「この体系ゆえに、精神科学は自然認識によって条件づけられており、したがって数学的基礎づけのうちで始まる構成のなかで最高で最後の部分を形成するのである。」(『全集1』p.25、以下同様)というのはそれを端的に表した言葉だといえる。
これはフッサールの『論理学研究』にもつながる。フッサールはこの「論理学」を、心理学的なものから超越論的主観性の構造へと展開していき、ディルタイ的な意味での「心理学」は批判していくが、しかし、この『論理学研究』の論理学は数学的なものであった。この数学的な論理学の問題は、ハイデガーが批判するわけだし、後にはデリダが『幾何学の起源』の「序」で、この数学的論理学が「歴史性」に常に既に「汚染」されているという形で、現前性批判される問題ともつながるのだと思う。
ただし、p.103でもそうなのだが、ディルタイは歴史が数学的基礎の論理学に「還元」されるとも言っていない。「歴史の経過を一つの定式または一つの原理の統一へと還元することはできない」といい、p.117でも、「精神科学は、自然科学とはまったく異なる基礎や構造を有している」という形で、「精神的現象を自然認識の連関に組み入れるというこの試みには二つのことが想定」されるとし、それらは「証明不可能」と「明らかな誤り」を招くとしている。つまり、「精神科学」は「自然科学」には「還元」できないわけだが、だとすれば、当初「精神科学」の「相対的独立性」と「精神科学から自然科学への依存の体系」とは何のことになるのだろうか。おそらくまだ100頁を越えたばかりで結論めいたことを言うのは慎まないといけないのだろう。この「精神科学」の「自然科学」への還元不可能性こそが、「精神科学」の「相対的独立性」になり、それが「歴史性」でもあるわけだが、しかしその場合の「精神科学」の法則性や論理性というのは、ディルタイが最初に予想していたような、数学的な論理性とは違うのだろうか?
今後この矛盾、即ち「精神科学」の「独立性」がここから考察されていくのだと思う。おそらくディルタイは「精神科学」を「自然科学」に「還元」して解消しようとする性急さを戒めているのであって、「精神科学」が「自然認識」の論理学と何らかの関係性を持っており、それが「精神科学」の「独立性」を可能にもしているという、複雑な「体系」を明らかにしているのだろう。そういう意味では「精神科学」の論理性が「自然認識」「自然科学」「数学的基礎」の論理学とどのような差異を持ち、あるいは相互に依存しあっているのかを、観ていきたいと思う。カントの物理的な自然法則と自律的で内的な理性(法則)の関係のようなものである。ディルタイの議論は、当然のことであるが、現代において「文系」が大事か「理系」が大事かという、通俗的でわかりやすすぎ、そしてコストと効率だけを意識したくだらない論争より、恐らく実りある議論になるだろう。













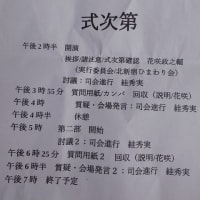






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます