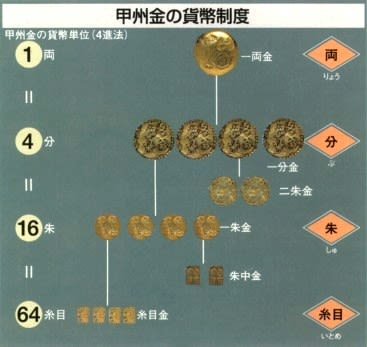お札の話の余談として、円高の謎に迫ってみた。
円が急に90円になったとき、まるでシロウトながら「これはドル買いだ」と早合点し、僅かながらもドルを買ってしまった。
すぐに97円くらいに戻した。
少し欲をだして、せめて100円台に戻ったら売るつもりでいたら、また円高に戻り、予想以外の円高が続いている。
以来、ずっと塩漬けである。悔しいから、円高の理由について、気になっていたことについて今回いろいろ調べてみた。
結論的には、容易に円安には戻らないであろうと、涙している。

現在でも多くの国の貿易では、ドル建てで行われている。
為替相場は、本来、国際決済通貨であるドルを、自国通貨に交換するために利用する。
為替相場のレートは、原則論で言えば、為替交換の実需できまる。
国際間の決済通貨が必要な時には、ドルを買う。
自国通貨に交換するには、ドルを売る。
この実需バランスが、為替相場の原則ながら、一方で変動する国際金融事情によって各国の通貨価値が変動している。
為替相場は、その国の金融事情と財政状況に左右される。
特にその「金融安定度」と「金利」、「通貨発行高」と「外貨保有高」に左右される。
まず、「金利」でみると、日本の金利は相変わらず世界最低である。
しかし日本はデフレ傾向のため、金利がゼロでも、実質プラス金利であり、新興国はインフレ率が金利を上回っているから、実質マイナス金利と判断されている。
「通貨発行高」では、アメリカが、貿易収支で赤字がつづき、また金融緩和策でドルをたくさん刷ったから、相対的にドルの価値が下がった。
貿易収支で膨大な黒字を記録している中国は、通貨高になるはずながら、弱いドルと連動している。 これは、中国の「通貨供給量」が異常に多いからである。1999年を100とすると、2009年では450近くになっている。
通貨供給量が増加するのは、経済成長率が高いことを意味し、インフレ傾向にある。
10年で4.5倍も通貨供給量が増えているから、人民元は高くならない。
その他の国でも、10年で200くらい通貨供給量が増加している。
ところが、日本だけは10年で120程度と通貨供給が押さえられている。
日本の潜在的成長率を2%とすれば、毎年4~5%通貨供給量を増やす必要があるが、金融当局では通貨供給量を抑えている。
こうした金融事情にもとづく為替市場で、その時々の通貨の価値が決められている。

つまり、円高という場合、ドルやユーロと比較して「相対的な評価」が高くなっているということを意味する。また、インフレ率が高ければ、通貨の価値が下がり、インフレ率が低ければ、上がると考えることができる。
そして、長期的にはそれが為替レートに反映される。日本は長期にわたってデフレ傾向にある。
要は、為替レートは、二つの通貨の片方が高くなれば、片方が安くなる総体取引の仕組みである。つまり「円高」の裏側には、安くなっている通貨が存在する。
一方で、為替相場は、実需ではなく「金融の力学」に従って動いている。
つまりは「通貨自体」が金融商品として扱われているのである。
実需以外の投機的な資金は、「相対的な評価」が高い円をターゲットにし、円高を誘導して高くなれば、「利ざや」を稼いで売る。
その利益で、さらに円を買い増しする。
万一、期待通りに利ざやが稼げなくとも、円を保有すること自体が、他の通貨を保有するよりも「リスク回避」と考えられているからである。

では、なぜ円を保有することが「リスク回避」なのか。
かつて日本の金融機関は、バブル崩壊で財務内容が悪化して、90年代後半には「金融危機」と言われる事態になった。
このとき、経済混乱を回避するために、政府は、金融機関の劣後債・優先株買い取りなどで金融機関に「公的資金を強制注入」した。
さらに、省庁再編の際に、旧大蔵省から銀行部門を切り離して「金融庁を設立」し、厳しく監視・監督する政策を実施して、金融機関の自己資本比率は大きく改善し、財務体質を強化してきた。こうした経緯で、現在は「日本の銀行」は世界の銀行の中で、最も安定していると見られている。
近年は、「リスク回避の円買い」傾向となっており、リスク回避的になる時には、全世界の株が下落し、円高となる傾向が強い。
つまり、株式投機に向けられるべき資金が、円買いに流れてくるからである。
国としての債務不履行の可能性はないと判断されているから、世界の経済が非常に悪化した場合でも、資産を日本円で保有しておくのが、最も安全であると判断されているからである。
このため、世界の投資家・投機家の判断が円買い招いている。
ところが一方で、「日本の国家財政」は、国債の発行残高は12年度末で708兆9千億円となる見込みである。
また借入金や政府短期証券などを加えた「国の借金」は、昨年9月末で954.4兆円にのぼっていたが、12年度は国債だけで52.4兆円増える見込みのため、12年度末には1千兆円を超えるのが確実となっている。
来年度予算案では、一般会計90.3兆円とみなされているが、税収見込みは、42兆3460億円を見込んでいる。
単純な計算では、年間税収額の23年分の借金を背負っていることになる。まさに国家財政の観点からは、財務危機といえる状況であろう。
欧州の財務危機が叫ばれているイタリアやフランスよりも、債務残高のGDP比率は日本の方が高い。
債務残高のGDP比率 日本 197.2 イタリア 127
フランス92.5 アメリカ 92.4 などとなっている。

それでも、なぜ円高が続くのか。
つまり日本の国債(債務残高)のほとんどは「日本の金融機関や個人が保有」しているため、売りが殺到する可能性がきわめて低い。
ちなみにアメリカの財務省証券(国債)の大半は、外国が所有している。その筆頭が中国22%、日本21%などとなっている。
また、いま国会で審議されているが、消費税の引き上げ余地が高い。
ドイツ 19%、フランス19.6%、イタリア21%、イギリス20%、あのギリシャでは23%などとなっている。日本の現在の5%が如何に低いかが分かる。
さらには外貨準備高が大きい。
外貨準備高の内訳は、外国債券が1兆1160億ドル、金準備が423億6600万ドル、国際通貨基金(IMF)リザーブポジションが175億5600万ドル、特別引出権(SDR)が203億8000万ドル、その他資産が4億6600万ドルとなっている。
外貨準備高の総合計は、なんと1兆2千億ドルとなる。約2兆ドルの中国に次いで二番目の外貨準備高である。
これらのことから、政府が「赤字国債」を大量に発行し続けていても、その高い評価は揺らいでいないのである。

では、この円高を止める方法は何か。
輸出立国の日本にとって、長期的異常な投機的円高を止める手立ては無いのか。
イギリスのフィナンシャルタイムスも「攻撃的な量的緩和プログラム」を取るべきだと指摘している。
経済学者の竹中平蔵氏も同意見であり、同じく経済学者の高橋洋一氏は、25兆円の政府紙幣を印刷しろと公言している。
いろんな意見があるが、「通貨供給量を増やすべ」きという意見は共通しているようである。
通貨供給量を増やせば、当然、相対的に円の価値が下がり、必然的に円安になる。
日銀の「攻撃的な量的緩和プログラム」によって大量の資金が流通すれば、当然好景気となり、失業者も少なくなる。
とくに東北地方の復興資金として投入すれば、一挙両得であろう。
さらにはGDPが大幅に伸びて、税収は一気に増加するから、国債依存度も低下する。
また、一気に通貨供給量を増やせば、インフレになるから、後進国への投資資金に円建てで融資してもよいだろう。
なぜ、日本の金融当局が、通貨供給量を増やす政策をとらないのか。
これは次の研究テーマとしたい。
円が急に90円になったとき、まるでシロウトながら「これはドル買いだ」と早合点し、僅かながらもドルを買ってしまった。
すぐに97円くらいに戻した。
少し欲をだして、せめて100円台に戻ったら売るつもりでいたら、また円高に戻り、予想以外の円高が続いている。
以来、ずっと塩漬けである。悔しいから、円高の理由について、気になっていたことについて今回いろいろ調べてみた。
結論的には、容易に円安には戻らないであろうと、涙している。

現在でも多くの国の貿易では、ドル建てで行われている。
為替相場は、本来、国際決済通貨であるドルを、自国通貨に交換するために利用する。
為替相場のレートは、原則論で言えば、為替交換の実需できまる。
国際間の決済通貨が必要な時には、ドルを買う。
自国通貨に交換するには、ドルを売る。
この実需バランスが、為替相場の原則ながら、一方で変動する国際金融事情によって各国の通貨価値が変動している。
為替相場は、その国の金融事情と財政状況に左右される。
特にその「金融安定度」と「金利」、「通貨発行高」と「外貨保有高」に左右される。
まず、「金利」でみると、日本の金利は相変わらず世界最低である。
しかし日本はデフレ傾向のため、金利がゼロでも、実質プラス金利であり、新興国はインフレ率が金利を上回っているから、実質マイナス金利と判断されている。
「通貨発行高」では、アメリカが、貿易収支で赤字がつづき、また金融緩和策でドルをたくさん刷ったから、相対的にドルの価値が下がった。
貿易収支で膨大な黒字を記録している中国は、通貨高になるはずながら、弱いドルと連動している。 これは、中国の「通貨供給量」が異常に多いからである。1999年を100とすると、2009年では450近くになっている。
通貨供給量が増加するのは、経済成長率が高いことを意味し、インフレ傾向にある。
10年で4.5倍も通貨供給量が増えているから、人民元は高くならない。
その他の国でも、10年で200くらい通貨供給量が増加している。
ところが、日本だけは10年で120程度と通貨供給が押さえられている。
日本の潜在的成長率を2%とすれば、毎年4~5%通貨供給量を増やす必要があるが、金融当局では通貨供給量を抑えている。
こうした金融事情にもとづく為替市場で、その時々の通貨の価値が決められている。

つまり、円高という場合、ドルやユーロと比較して「相対的な評価」が高くなっているということを意味する。また、インフレ率が高ければ、通貨の価値が下がり、インフレ率が低ければ、上がると考えることができる。
そして、長期的にはそれが為替レートに反映される。日本は長期にわたってデフレ傾向にある。
要は、為替レートは、二つの通貨の片方が高くなれば、片方が安くなる総体取引の仕組みである。つまり「円高」の裏側には、安くなっている通貨が存在する。
一方で、為替相場は、実需ではなく「金融の力学」に従って動いている。
つまりは「通貨自体」が金融商品として扱われているのである。
実需以外の投機的な資金は、「相対的な評価」が高い円をターゲットにし、円高を誘導して高くなれば、「利ざや」を稼いで売る。
その利益で、さらに円を買い増しする。
万一、期待通りに利ざやが稼げなくとも、円を保有すること自体が、他の通貨を保有するよりも「リスク回避」と考えられているからである。

では、なぜ円を保有することが「リスク回避」なのか。
かつて日本の金融機関は、バブル崩壊で財務内容が悪化して、90年代後半には「金融危機」と言われる事態になった。
このとき、経済混乱を回避するために、政府は、金融機関の劣後債・優先株買い取りなどで金融機関に「公的資金を強制注入」した。
さらに、省庁再編の際に、旧大蔵省から銀行部門を切り離して「金融庁を設立」し、厳しく監視・監督する政策を実施して、金融機関の自己資本比率は大きく改善し、財務体質を強化してきた。こうした経緯で、現在は「日本の銀行」は世界の銀行の中で、最も安定していると見られている。
近年は、「リスク回避の円買い」傾向となっており、リスク回避的になる時には、全世界の株が下落し、円高となる傾向が強い。
つまり、株式投機に向けられるべき資金が、円買いに流れてくるからである。
国としての債務不履行の可能性はないと判断されているから、世界の経済が非常に悪化した場合でも、資産を日本円で保有しておくのが、最も安全であると判断されているからである。
このため、世界の投資家・投機家の判断が円買い招いている。
ところが一方で、「日本の国家財政」は、国債の発行残高は12年度末で708兆9千億円となる見込みである。
また借入金や政府短期証券などを加えた「国の借金」は、昨年9月末で954.4兆円にのぼっていたが、12年度は国債だけで52.4兆円増える見込みのため、12年度末には1千兆円を超えるのが確実となっている。
来年度予算案では、一般会計90.3兆円とみなされているが、税収見込みは、42兆3460億円を見込んでいる。
単純な計算では、年間税収額の23年分の借金を背負っていることになる。まさに国家財政の観点からは、財務危機といえる状況であろう。
欧州の財務危機が叫ばれているイタリアやフランスよりも、債務残高のGDP比率は日本の方が高い。
債務残高のGDP比率 日本 197.2 イタリア 127
フランス92.5 アメリカ 92.4 などとなっている。

それでも、なぜ円高が続くのか。
つまり日本の国債(債務残高)のほとんどは「日本の金融機関や個人が保有」しているため、売りが殺到する可能性がきわめて低い。
ちなみにアメリカの財務省証券(国債)の大半は、外国が所有している。その筆頭が中国22%、日本21%などとなっている。
また、いま国会で審議されているが、消費税の引き上げ余地が高い。
ドイツ 19%、フランス19.6%、イタリア21%、イギリス20%、あのギリシャでは23%などとなっている。日本の現在の5%が如何に低いかが分かる。
さらには外貨準備高が大きい。
外貨準備高の内訳は、外国債券が1兆1160億ドル、金準備が423億6600万ドル、国際通貨基金(IMF)リザーブポジションが175億5600万ドル、特別引出権(SDR)が203億8000万ドル、その他資産が4億6600万ドルとなっている。
外貨準備高の総合計は、なんと1兆2千億ドルとなる。約2兆ドルの中国に次いで二番目の外貨準備高である。
これらのことから、政府が「赤字国債」を大量に発行し続けていても、その高い評価は揺らいでいないのである。

では、この円高を止める方法は何か。
輸出立国の日本にとって、長期的異常な投機的円高を止める手立ては無いのか。
イギリスのフィナンシャルタイムスも「攻撃的な量的緩和プログラム」を取るべきだと指摘している。
経済学者の竹中平蔵氏も同意見であり、同じく経済学者の高橋洋一氏は、25兆円の政府紙幣を印刷しろと公言している。
いろんな意見があるが、「通貨供給量を増やすべ」きという意見は共通しているようである。
通貨供給量を増やせば、当然、相対的に円の価値が下がり、必然的に円安になる。
日銀の「攻撃的な量的緩和プログラム」によって大量の資金が流通すれば、当然好景気となり、失業者も少なくなる。
とくに東北地方の復興資金として投入すれば、一挙両得であろう。
さらにはGDPが大幅に伸びて、税収は一気に増加するから、国債依存度も低下する。
また、一気に通貨供給量を増やせば、インフレになるから、後進国への投資資金に円建てで融資してもよいだろう。
なぜ、日本の金融当局が、通貨供給量を増やす政策をとらないのか。
これは次の研究テーマとしたい。