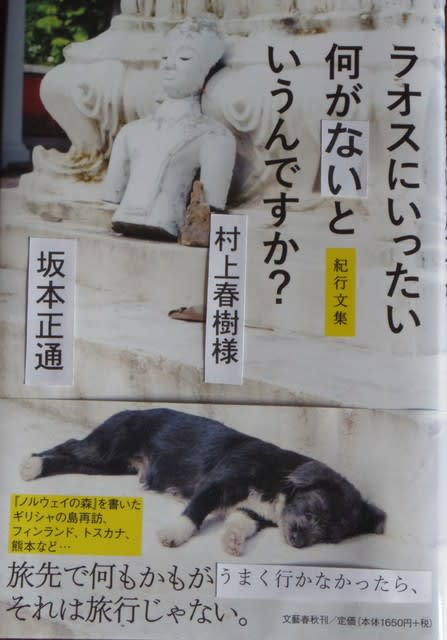旅エッセーのあるべき姿
先日、TVで松本清張原作の「点と線」が放送されていた。
刑事役の北野武のシリアルな演技も見どころであったが、
市原悦子の存在感も申し分ない。
何よりも、時代考証に基づいた当時の「東京駅」が再現されていて感激だった。
残念だが、過去に一度見たこともあり、途中で寝てしまったが。

松本清張「ペルセポリスから飛鳥へ」
松本清張は推理作家と思われているが、ドキュメンタリー作家でもあり、
歴史家でもある、考古学や法律学にも造詣が深い。
若い頃、松本清張の「ペルセポリスから飛鳥へ」を読んで、
実際にイランのペルセポリス遺跡を訪れた。
乗った飛行機がイラク航空だったのが最悪だったが。
実地での調査、取材、記録、資料作成。それらをもとに、
綿密に論理を組み立てていく、彼の思考の深さ、
学術研究にも十分に耐える内容には驚かされた。
綿密に調査し
事実だけを記述する、これが
旅エッセーの原点であると教えられた。
旅の愉しみ
旅とはおもしろいもので、道に迷ったことで、新しいものを発見したり、
突然、大雨にあい仕方なく雨宿りして、普段あまりみていなかったものが、よく観察出来たり。
毎年、同じ街を訪れ、よく知っていると思っていたのに「あれ、こんなものあったかな」
と新しい発見に驚かされたりする。見たハズなのに、すっかり忘れていたりする。
前にも、同じ道路を通ったのに、記憶になかったりする。
ここ数年、毎年のように、ラオスへ旅行しているが、「どうして、又、ラオスに行くんですか」と聞かれる。
その言外にはラオスにどんな魅力があるのですか?というより、よく飽きないですね
というニュウアンスが読み取れる。
ルアンパバーンは村上流に言えば、「趣のある静かな古都」で、幾度、訪れても興味が増すことはあっても、
減少することはない。ここ10年で11回インドシナ半島を旅し、ルアンパバーンには7回滞在している。
街が、少しずつ変化している様が目にとれる。変化しないのは地形と、ゆるやかなメコン川の流れぐらいか。
ナイトマーケットの品揃えも、時代を反映して、少しずつ変化している。
朝の托鉢も、昔は太陽が昇る前から托鉢の列が続き、僧侶のオレンジ色の袈裟が街を染めつくしていたが、
今は観光客向けのセレモニーか?朝の6時に始まり。6時15分頃にはアッサリと終る。
インディゴハウスの斜め向かいにある、「モン市場」は現在、再開発のため閉鎖されているが、
ほぼ、建設も終わっているのに、何時、OPENするのかは誰にも分からない。
いずれにしろ、昔のよき風情はなくなるだろう。
幾度も訪れていると、少しずつ変化していることが分かる。
「アレ、ここにあったジュース屋さんがゲームセンターに替わっている」とか
「こぎたないが美味しかった大衆食堂が、小奇麗になり値段は上がったが、味は落ちた」とか。
これも旅の愉しさかと思う。
見る事、書くこと
高校の美術教師の言葉で印象に残っているのは「よく観察しなさい。
利き手で描いた方が多少は巧く描けるが、見ていないもの、観察していないものは
どちらの手で描こうとしても、描けない」、名言である。
文章を書く時でも、文章の技量に優劣はあっても、
よく見ていないもの、自分が体験していないものは書けない。
中学1年生の時、担任の先生から「君の文章ほど退屈なものはない」と言われた。
なる程、自分が書いた文章が退屈以外の何物でもないことは、十分理解できる。
でも、読後感想文で優秀作に選ばれているのは、みな「金太郎飴」ばかりで、
授業で先生が述べた「感想」を、そのまま自分の「感想」として書き写しているだけではないか。
本人が感じたことなど何処にも書かれていない。
中学生の「冒険ゴッコ」などで、野原を駆け廻っている少年に、芥川龍之介の
「傍観者の自己心理」などと言った、難し言葉は理解できないし、深い心情など書ける訳がないと思った。
旅のエッセーでは旅した時の実体験が大切で、それを、どのように文章化し他の人に分からせるか。
自分が観察していないモノ、体験していないコトは書けない。
それを、勢いで書こうとするから無理が生じ、
ウソ、
でっちあげが生まれる。
村上春樹の文章を評価する
村上春樹の文章を「良くも悪くも独特」と言う人がいるが、
私に言わせれば「悪くも、悪くも独特」な文章である。
彼の文章を「・・・」で引用すれば、自分の書いた文章全体がダラしなくなる。
要約すれば「俺はそんなことを言ってない」と横槍を入れられそうである。
「遠いと言えば遠いが、近いと言えば近い」とか
「遠いと言うほど遠くないが、近いと言うほど近くない」とか、
一例を挙げれば、「・・・
少しばかり、でもけっこう
根幹から
変更してしまうことになる。」(P160)、
少しばかりと根幹からはまったく反対の概念ではないか?
要するに内容がアイマイで判断するのに困る。
読んでいて、突然「です、ます」調の文章になり気が抜ける。
出来の悪い中学生の作文を読んでいるような気分になる。
オヤジギャグ的な軽いノリで充分に観察することもなく調べることもなく、
思いついたまま、勢いで文章を書いているように思える。
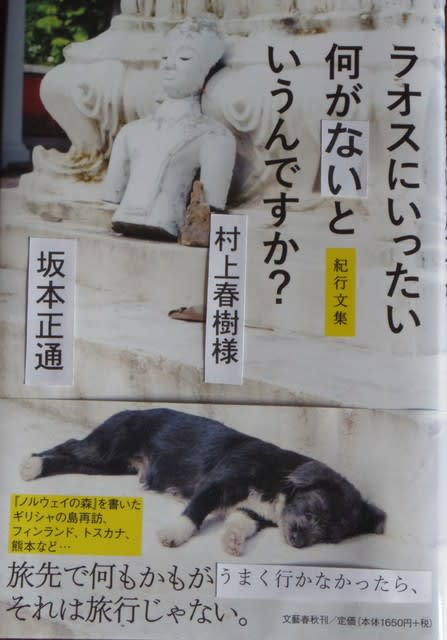 旅のエッセーは「作り話」で具体性がない
旅のエッセーは「作り話」で具体性がない
村上春樹は文章表現がうまい。何も知らない人は、言葉の巧さに、「そうだ」と思い込んでしまう。
心情に訴えかけ、読者の心を揺さぶるような文章だが
具体的なことは、何も書かれていない。
「旅っていいものです疲れることもがっかりすることもあるけれど、そこには何かがあります。」
疲れること、がっかりすることとは、具体的に何なのか?
必ず何かがありますとは、具体的に何があるのか?
例えば、両替でダマされたとか、バスの中に帽子を忘れたとか。
買い物の時500円で安いと思ったが、計算間違いで5,000円だったとか。
具体的な失敗、トラブルなど実体験したことを書くべきだろう。
村上春樹は旅をして、その土地について考察も観察もしていない、
旅をすれば当然出くわすであろうトラブルなどについて、経験していないので、
具体的に書くことが出来ない。
ラオスには何もないと読者が間違った観念を持つ
ブックレビューを読むと、「おもしろそうなタイトルですが、それ以上でもそれ以下でもない。
筆者として(ラオスに)特別な思い入れがあるように見えません」と冷静に判断している読者もいるが、
「その景色が浮かんでくるようで、海外旅行をしている気分になって楽しかった」とか、
「ラオスに行きたくなる気持ちがふっふっと芽生える一冊です」と成績優秀な中学生のような
感想を書く人もいる。
ラオスには何もないと言ったことが伝言ゲームのように伝わり、ラオスには何もないと誤解する人がいる。
この文章で書かれていることが、フィクション(作り話)とは知らず、本当のことと錯覚する人が出てくる。
自ら体験することもなく「ラオスには何もないんだ~」と決めつけ、その国を侮辱する、これほど、不愉快なことはない。
「ラオスに何もないの」ではなく、ラオスの国の素晴らしさを、村上春樹には理解できていない。
細かい事情も分からず、その国に対するリスペクトもないなら、旅エッセーなど書くべきではないと思う。
このエッセーの何が問題なのか!
松本清張の文章を読めば、彼の幅広い学識をもとに、取材、調査に基づいて事実のみを論理的に組み立て記述している。
その対極にあるのが、村上春樹の旅エッセー、「ラオスにいったい何があるというんですか?」である。
一言で言えば「空疎」、内容が何もナイヨーと、つい村上流のオヤジギャグを飛ばしたくなる。
十分に調べることも、取材することも、資料作成をするわけでもなく、思いつくままに適当に文字を書き並べている。
ルアンパバーンの街に高層建築がない理由など、少し調べれば分かることである。
調べもしないから、「景観保護条例」のことも分からず、勢い、「高層建築がない」とラオスを見下した文章を書く。
エッセーの内容は事実誤認も甚だしく、内容が希薄で少しラオスに認識のある人間なら不愉快しか感じない。
メコン川の描写は実に素晴らしい。彼の言語能力と想像力、フィクション作家としての文学的な、あり余る才能を感じる。
これが
作り話であり、
ウソ八百、デタラメであることが分からなければ。
村上の書くメコン川の描写を読み、メコン川がそのような川であると錯覚を持たれることが恐ろしい。
メコン川は黄褐色に濁っていて、けっして美しい水の色ではないが、流れはゆったりと穏やかである、
激流など何処にも存在しない。ルアンパバーンの「市街地図」を見れば一目瞭然だが、
プーシーの丘から眺めるメコン川は直線的で、
蛇行などしていない。
恐らく、メコン川の支流のナムカーン川と間違えているのであろうが、
ナムカーン川はメコン川と比べると、蛇行はしているが川幅はきわめて狭い。
いずれにしろ、杜撰さは否めない。
ルアンパバーンは地球の歩き方、ラオス編でも紹介されているように、
山深い「猫の額」ほどの平地にあり、
密林など何処にも存在しないと断言しておく。
村上春樹「ラオスにいったい何があるというんですか?」はフィクションなんだ!
旅エッセーに「作り話」はいけません。
ウソ、ごまかしで書かれた「旅エッセー」には何の価値もない、文筆家としての良心があるなら、
「このエッセー」は
唾棄すべきであろう。

プーシーの丘から眺めたメコン川、直線的で流れは緩やかで蛇行などしていない

プーシーの丘から眺めたナムカーン川、川幅は狭く蛇行している

市街地図(部分)、「論より証拠」メコン川は直線的で蛇行などしていない