
2
思うにそれは、会津人の狷介ともいえる性格にあったのではないか。それが相手に遺恨の残る結果を招いてしまっ
た、ということではないのか。融通の利かない狷介な性格はともすれば相手の気持ちをおもんばかることのない態度となって現れる。
権力に裏うちされた狷介は怖い。正義の名において、相手に容赦のない規範の順守を求める。それは往々にし、曖昧なもの、不明瞭なこと、欠けたもの一切を許さない、完膚なきまでの恭順を相手に要求する。その結果、当然、相手に遺恨が残る。
日本の政治的対立がピークに達した時、会津藩が京都守護職を引き受けたことが会津の悲劇であった。
西郷頼母は、藩の役割の悲劇的結末を予感して、藩主容保に諌止した。だが容保は聞く耳をもたなかった。自らの大義名分を押し立てた。容保にもある種のかたくなさを感じる。容保という人は、実は大垣藩から入った養子藩主である。会津に住んで、会津気質を身に帯びたのだろうか。
その結果、当時の政治の中心地でとった行動が、会津人気質をいやがうえにも鮮明に敵側である倒幕派に印象づけることになった。会津憎しの怨嗟の声が渦巻いたのも故なしとしない。
風土性というものがある。
山に囲まれた盆地である会津地方は、その自然環境からして、外部と隔絶するきらいがあった。そのうえ自然条件が厳しい。冬の季節が半年近くもつづくという土地柄である。自然環境の閉鎖性は人の気質をかたくなにする。ひらたくいえば頑固者が多い。人心が停滞し、新しいものを採り入れるという性向より、古いものを守り抜こうという姿勢が強くなる。その一典型が会津に生きている。
会津というと、「伝統」というイメージが浮かぶのも、古いものを綿々と育て上げる風土性が、会津の特徴として今も生きているからであろう。
自然条件の厳しさは一方、そこに住む人を辛抱強く、かつ粘り強くする。この性向が、会津気質の芯をかたちづくっている。
明治維新になってから苛酷な運命にさらされた会津の人々の心を支えたものも、皮肉なことに、この性向である。
新政府の追い打ちをかけるような施策によって、維新後、会津藩は解体される。そして東北の一寒村に移封されることになる。
そこは南部藩領から削りとった陸奥三郡およそ三万石の土地であった。斗南藩と呼ばれるその所領に、藩士とその家族一万七千人が移住した。
明治の世になり、陸軍大将に昇進した会津出身の柴五郎はその遺書の中で、少年時の思い出を次のように回想している。
「今はただ、感覚なき指先に念力をこめて黙々と終日縄を綯うばかりなり。今日も明日もまた来る日も、指先に怨念をこめて黙々と縄を綯うばかりなりき」
ひたすら忍従することは、たたかれ打ちひしがれても生きぬこうとする強靭な心をつくりだし、やがて、それは怨念という名の情念と化する。
ここに、その情念を新たな新国家建設に向けて積極的に放出した人物がいる。
そのひとりに旧会津藩家老・山川浩がいる。彼は籠城戦当時、遊撃隊長として、城の外にあって、薩長軍に対し巧妙な戦いを展開した。降伏後、最北の地、斗南藩に移住させられた時、権大参事(藩知事)の要職にあって、藩の実質的な指導者となった人物である。
斗南藩の経営は困難を極めた。自然はあまりにも苛酷であった。新天地に移り住んだ旧会津藩士を待ち構えていたものは飢餓地獄そのものであった。不毛ともいえる荒野は、尋常な手段では人間に服従するような相手ではなかった。
そして、ついに新国土建設は、苛酷な自然を前にして、虚しく潰えてしまう。
この斗南藩経営の失敗のあと、山川は東京に出る。薩長政府への怨みをもう少しちがった形で果たそうとしたのである。それは体制内に入って、いずれの日にか汚名を雪(そそ)ぐという考えであった。
薩長政府に真正面から対決する姿勢ではなく、むしろ、体制内で自己の立場を確立し、藩の汚名を返上しようというリアリストとしての見識である。
山川はこうして官途の道を選ぶ。その企てに手を差しのべたのは、旧敵土佐の谷千城であった。谷の推挙により、山川はまず陸軍省八等出仕を申しつけられる。そして、のちに陸軍裁判大主理に任官することになる。明治六年七月のことである。
その後、山川は異例の出世をはたし、明治十年の西南戦争のおりには、陸軍中佐として参謀職を勤め大いなる功績を残す。
結果、山川が果たそうとした、自己の立場を確立し、そのうえで一定の自己主張をし、自らの存在を認めさせる、という願いがかなうことになるのである。
この山川浩のほかにも、会津出身で、のちに世に出て名をなした人々が数多くいる。
まず、山川浩の弟の健二郎。彼はのちに東京帝国大学の総長になっている。また、この山川兄弟の末妹である咲子(のちの捨松)は津田梅子らと初の女子留学生として渡米し、のちに陸軍卿大山巌と結婚している。
兄弟で名をなした人に、ほかに、山本覚馬、八重子兄妹がいる。覚馬は新島譲とともに同志社大学の創立に貢献した人物であり、八重子は、その新島譲の妻になった人である。彼女自身もその後、幾つもの社会福祉事業に貢献している。
このほかに、『ある明治人の記録』に登場する、のちに陸軍大将になった柴五郎、明治大正期に外交官として活躍した林権助、明治学院の創立者のひとり井深梶之助、クリスチャンとして明治の教育界で活躍した若松賎子などの名を見いだすことができる。
ひと言で生き方の違いということでは片づけられない会津人のこの堅忍の姿勢は、やはり風土性のようなものを考えなければ理解できないと思う。
猪苗代湖を前に、磐梯山を背後に控えた会津という地は、日本の古典的な地方風景が広がる場所である。
貧しさが張りついたような苛酷な風土、時の流れが回遊しているような社会、そうしたものに包み込まれて生きる人間は、ただひたすら忍従することで、日々の苦難を切り抜けるしかないのである。
さらに、そこに長い厳しい冬の季節が加われば、何人と言えども、そこでは、どのように生き、自然の苛酷さにどう耐えなければならないかを身体で知ることになる。かつての日本の田舎は多かれ少なかれ、そうした地の風を備えていたのである。忍従はそうした地に生きる人々の共通の規範でもあった。
会津というと、わたしは猪苗代湖畔の貧しい家に生まれ育った野口英雄を思い浮かべる。貧しい家に生まれたにもかかわらず、やがて、忍従と勤勉を積みかさねて、ついに立身出世していった野口英雄の行跡は、ひとり会津人のみならず、日本人すべてが理想とする姿であった。それゆえに、教科書にも取り上げられ、幾世代にわたって、日本人の鏡でありつづけた人物であった。
会津人が規範とした生き方が、そのまま、日本人の生き方として通用していた時代があったのである。
思うにそれは、会津人の狷介ともいえる性格にあったのではないか。それが相手に遺恨の残る結果を招いてしまっ
た、ということではないのか。融通の利かない狷介な性格はともすれば相手の気持ちをおもんばかることのない態度となって現れる。
権力に裏うちされた狷介は怖い。正義の名において、相手に容赦のない規範の順守を求める。それは往々にし、曖昧なもの、不明瞭なこと、欠けたもの一切を許さない、完膚なきまでの恭順を相手に要求する。その結果、当然、相手に遺恨が残る。
日本の政治的対立がピークに達した時、会津藩が京都守護職を引き受けたことが会津の悲劇であった。
西郷頼母は、藩の役割の悲劇的結末を予感して、藩主容保に諌止した。だが容保は聞く耳をもたなかった。自らの大義名分を押し立てた。容保にもある種のかたくなさを感じる。容保という人は、実は大垣藩から入った養子藩主である。会津に住んで、会津気質を身に帯びたのだろうか。
その結果、当時の政治の中心地でとった行動が、会津人気質をいやがうえにも鮮明に敵側である倒幕派に印象づけることになった。会津憎しの怨嗟の声が渦巻いたのも故なしとしない。
風土性というものがある。
山に囲まれた盆地である会津地方は、その自然環境からして、外部と隔絶するきらいがあった。そのうえ自然条件が厳しい。冬の季節が半年近くもつづくという土地柄である。自然環境の閉鎖性は人の気質をかたくなにする。ひらたくいえば頑固者が多い。人心が停滞し、新しいものを採り入れるという性向より、古いものを守り抜こうという姿勢が強くなる。その一典型が会津に生きている。
会津というと、「伝統」というイメージが浮かぶのも、古いものを綿々と育て上げる風土性が、会津の特徴として今も生きているからであろう。
自然条件の厳しさは一方、そこに住む人を辛抱強く、かつ粘り強くする。この性向が、会津気質の芯をかたちづくっている。
明治維新になってから苛酷な運命にさらされた会津の人々の心を支えたものも、皮肉なことに、この性向である。
新政府の追い打ちをかけるような施策によって、維新後、会津藩は解体される。そして東北の一寒村に移封されることになる。
そこは南部藩領から削りとった陸奥三郡およそ三万石の土地であった。斗南藩と呼ばれるその所領に、藩士とその家族一万七千人が移住した。
明治の世になり、陸軍大将に昇進した会津出身の柴五郎はその遺書の中で、少年時の思い出を次のように回想している。
「今はただ、感覚なき指先に念力をこめて黙々と終日縄を綯うばかりなり。今日も明日もまた来る日も、指先に怨念をこめて黙々と縄を綯うばかりなりき」
ひたすら忍従することは、たたかれ打ちひしがれても生きぬこうとする強靭な心をつくりだし、やがて、それは怨念という名の情念と化する。
ここに、その情念を新たな新国家建設に向けて積極的に放出した人物がいる。
そのひとりに旧会津藩家老・山川浩がいる。彼は籠城戦当時、遊撃隊長として、城の外にあって、薩長軍に対し巧妙な戦いを展開した。降伏後、最北の地、斗南藩に移住させられた時、権大参事(藩知事)の要職にあって、藩の実質的な指導者となった人物である。
斗南藩の経営は困難を極めた。自然はあまりにも苛酷であった。新天地に移り住んだ旧会津藩士を待ち構えていたものは飢餓地獄そのものであった。不毛ともいえる荒野は、尋常な手段では人間に服従するような相手ではなかった。
そして、ついに新国土建設は、苛酷な自然を前にして、虚しく潰えてしまう。
この斗南藩経営の失敗のあと、山川は東京に出る。薩長政府への怨みをもう少しちがった形で果たそうとしたのである。それは体制内に入って、いずれの日にか汚名を雪(そそ)ぐという考えであった。
薩長政府に真正面から対決する姿勢ではなく、むしろ、体制内で自己の立場を確立し、藩の汚名を返上しようというリアリストとしての見識である。
山川はこうして官途の道を選ぶ。その企てに手を差しのべたのは、旧敵土佐の谷千城であった。谷の推挙により、山川はまず陸軍省八等出仕を申しつけられる。そして、のちに陸軍裁判大主理に任官することになる。明治六年七月のことである。
その後、山川は異例の出世をはたし、明治十年の西南戦争のおりには、陸軍中佐として参謀職を勤め大いなる功績を残す。
結果、山川が果たそうとした、自己の立場を確立し、そのうえで一定の自己主張をし、自らの存在を認めさせる、という願いがかなうことになるのである。
この山川浩のほかにも、会津出身で、のちに世に出て名をなした人々が数多くいる。
まず、山川浩の弟の健二郎。彼はのちに東京帝国大学の総長になっている。また、この山川兄弟の末妹である咲子(のちの捨松)は津田梅子らと初の女子留学生として渡米し、のちに陸軍卿大山巌と結婚している。
兄弟で名をなした人に、ほかに、山本覚馬、八重子兄妹がいる。覚馬は新島譲とともに同志社大学の創立に貢献した人物であり、八重子は、その新島譲の妻になった人である。彼女自身もその後、幾つもの社会福祉事業に貢献している。
このほかに、『ある明治人の記録』に登場する、のちに陸軍大将になった柴五郎、明治大正期に外交官として活躍した林権助、明治学院の創立者のひとり井深梶之助、クリスチャンとして明治の教育界で活躍した若松賎子などの名を見いだすことができる。
ひと言で生き方の違いということでは片づけられない会津人のこの堅忍の姿勢は、やはり風土性のようなものを考えなければ理解できないと思う。
猪苗代湖を前に、磐梯山を背後に控えた会津という地は、日本の古典的な地方風景が広がる場所である。
貧しさが張りついたような苛酷な風土、時の流れが回遊しているような社会、そうしたものに包み込まれて生きる人間は、ただひたすら忍従することで、日々の苦難を切り抜けるしかないのである。
さらに、そこに長い厳しい冬の季節が加われば、何人と言えども、そこでは、どのように生き、自然の苛酷さにどう耐えなければならないかを身体で知ることになる。かつての日本の田舎は多かれ少なかれ、そうした地の風を備えていたのである。忍従はそうした地に生きる人々の共通の規範でもあった。
会津というと、わたしは猪苗代湖畔の貧しい家に生まれ育った野口英雄を思い浮かべる。貧しい家に生まれたにもかかわらず、やがて、忍従と勤勉を積みかさねて、ついに立身出世していった野口英雄の行跡は、ひとり会津人のみならず、日本人すべてが理想とする姿であった。それゆえに、教科書にも取り上げられ、幾世代にわたって、日本人の鏡でありつづけた人物であった。
会津人が規範とした生き方が、そのまま、日本人の生き方として通用していた時代があったのである。










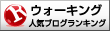


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます