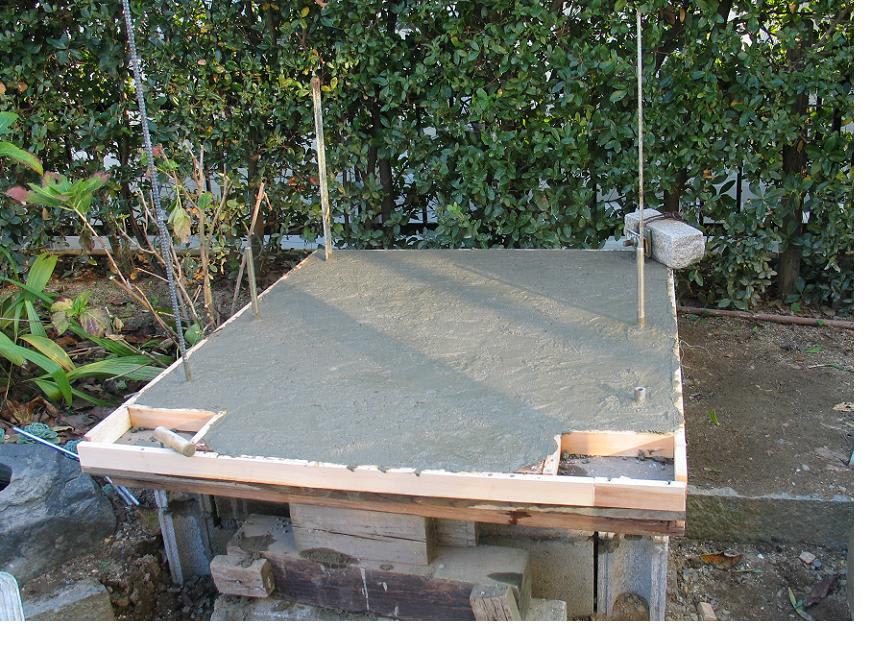我が家の「ピザ石窯」でのピザ焼きも人気が出てきたのか、焼く頻度が多くなってきた。
一年分の薪を用意していたのが、あっと言う間に底をついてしまった。
これから来春に掛け、大急ぎで薪作りをする必要がある。


ピザ窯にしろ暖炉にしろ、薪の木の種類は、ズバリ広葉樹が最適である。
平たく言えば「ナラ」、「くぬぎ」、「樫」なんだけど、中々手に入らない。
購入するのなら簡単だが、無趣味オヤジは、無類の貧乏オヤジでもあるので簡単に購入は出来ない。
一番最適な木種は、ナナカマドと言われている。
【ナナカマド】と言う木は、七回かまどで燃やせるくらい火持ちがいいと言われている。
本当かどうか分からないが、古人からの言い伝えだから・・・・・。
もっともこの木は、紅葉の季節に真っ赤な実で彩りを添えるので、
おいそれと薪などには出来ない・・・と思われる。


そんな折、職場の同僚のMさんが、自宅裏に大きく育ったクヌギの木を伐採し、
その木の処置に困っていると聞き、貰い受ける事になった。
伐ったばかりの生木なので大変重い、乗用車のトランクに積み込むのも重労働だった。
そんな苦労で手に入れたクヌギを今度は、自宅庭で「ヨキ」(斧)を使って、割り木にしなければならない。
これが、また大変だった。節のある生木だから、硬いこと半端でない。
柄の長さ95cmのヨキも、木に打ち込めずに跳ね返されてしまう。


こうして散々苦労して揃えた【薪割り木】も、半年ほど乾燥させておく必要がある。
この「苦労の薪」で美味しいピザが焼けるのは、来年の夏休みの頃かも知れない・・・・・。
一年分の薪を用意していたのが、あっと言う間に底をついてしまった。
これから来春に掛け、大急ぎで薪作りをする必要がある。


ピザ窯にしろ暖炉にしろ、薪の木の種類は、ズバリ広葉樹が最適である。
平たく言えば「ナラ」、「くぬぎ」、「樫」なんだけど、中々手に入らない。
購入するのなら簡単だが、無趣味オヤジは、無類の貧乏オヤジでもあるので簡単に購入は出来ない。
一番最適な木種は、ナナカマドと言われている。
【ナナカマド】と言う木は、七回かまどで燃やせるくらい火持ちがいいと言われている。
本当かどうか分からないが、古人からの言い伝えだから・・・・・。
もっともこの木は、紅葉の季節に真っ赤な実で彩りを添えるので、
おいそれと薪などには出来ない・・・と思われる。


そんな折、職場の同僚のMさんが、自宅裏に大きく育ったクヌギの木を伐採し、
その木の処置に困っていると聞き、貰い受ける事になった。
伐ったばかりの生木なので大変重い、乗用車のトランクに積み込むのも重労働だった。
そんな苦労で手に入れたクヌギを今度は、自宅庭で「ヨキ」(斧)を使って、割り木にしなければならない。
これが、また大変だった。節のある生木だから、硬いこと半端でない。
柄の長さ95cmのヨキも、木に打ち込めずに跳ね返されてしまう。


こうして散々苦労して揃えた【薪割り木】も、半年ほど乾燥させておく必要がある。
この「苦労の薪」で美味しいピザが焼けるのは、来年の夏休みの頃かも知れない・・・・・。