
旧藏内家住宅(県指定建造物・国登録文化財)
去年の4月18日から一般公開始まったそうです
それまでは個人の所有物だったとか

まぁなんと豪壮な佇まいでしょう
このお屋敷は大正8年には全国6位の産出高をほこった
蔵内本家三代の住宅で、明治30年代に主屋などが建てられ、
その後大正5年から宝蔵、炊事場棟、座敷棟、
大広間棟、茶室、大玄関棟の順に
池庭に面して増築していき、同9年に完成しました。

ここはお庭への通用門です
玄関前右手に有ります
お庭はのちほど、、、
では、まず邸内へ上がってみましょう

お鼻が高くな~れ!
つい「うふふ」

床の間の掛軸が素敵!

衝立の素晴らしさも一級品


ふすまに描かれた絵…幽玄、、、ん?

柱材は台湾檜、弓形天井や格天井には屋久杉がふんだんに使われています



廊下の天井をみると、またすごくモダンでしょ
場所によって細工も違う!


ここはお茶室だったっけ?
あまりにも一度にたくさんの説明を聞いたので
ちゃんと覚えていない(^^ゞ

大広間、、、う~~ん何畳あるんだろう
案内をされていた方の話
「ここの硝子は、大正時代のもので
もし割れたりしたら、今は同じものがないんです
台風がくると、大急ぎで雨戸を閉めてまわらないと、、、
この広いお屋敷大変なんですよ~~」

茶室から見たお庭?

大広間から見たお庭?
建築物の良しあしは専門的には全くわからないので
あくまでも感覚的な感想です
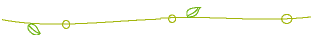
炭鉱王のお屋敷は
麻生本家、旧伊藤傳右衛門邸(飯塚市)、
旧安川敬一郎・松本健次郎邸(北九州市)など
何か所か見学したことがありますが
どのお屋敷をみても、
その贅をつくした数々の装飾品や家具・建築物など
炭鉱王一族の余りある財力を物語っています
直方や田川の石炭記念館で見た
坑内で真っ黒になって
危険と隣り合わせで働いていた
抗夫たちの人生に思いをはせると
ちょっと複雑な気がしました
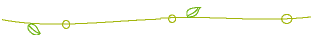
お疲れ様でした












