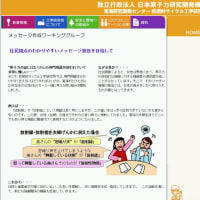先月30日、北海道中央部にある十勝岳の火口付近が明るくなっているのが気象庁が設置したカメラなどで確認されました。
札幌管区気象台では、今のところ火山性微動など噴火に伴う観測データに変化は見られず、「噴火の可能性は低い」としていますが、警察では、念のためふもとの宿泊施設に避難を呼びかけています。
先月30日午後8時ごろ、北海道中央部の大雪山系の南にある十勝岳の火口付近が赤く光り明るくなっているのが、気象庁が設置したカメラの映像などで確認されました。
札幌管区気象台で、これが噴火によるものかどうか確認を進めていますが、これまでのところ、噴火に伴って地下のマグマや水蒸気などの動きを示す火山性微動や空気の振動を捉える空振計の観測データには変化はみられないということです。
気象台では、「火口付近で硫黄が燃えている状態とみられ、噴火の可能性は低い」とし、引き続き観測データの詳しい分析を進めています。
十勝岳の地元の富良野警察署では、念のため十勝岳から5キロ前後離れた上富良野町内にある4つの温泉旅館などに対して避難するよう呼びかけました。
上富良野町役場によりますと、旅館の宿泊者や従業員およそ50人が町役場の隣にある保健福祉総合センターに避難しているということです。
十勝岳とは
十勝岳は、北海道のほぼ中央にある大雪山系の南に位置する標高2070メートルの活火山で、記録が残る1857年以降、ほぼ35年から40年おきに噴火を繰り返しています。
中でも1926年=大正15年5月に起きた大噴火の際は、山の斜面に積もった雪がとけて大規模な泥流が発生し、ふもとの美瑛町と上富良野町で、合わせて144人が、死亡あるいは行方不明になったほか、およそ400棟の建物が壊れるなど大きな被害が出ました。
最近では昭和63年12月に「62-2火口」と呼ばれる火口から噴火し、火砕サージや火砕流が起きたため、泥流の発生を警戒して美瑛町や上富良野町の住民に避難命令が出されました。
噴火は翌年3月まで、合わせて21回に上りました。
その後も平成16年2月から4月にかけて、ごく小規模な噴火が起きています。
気象台によりますと、十勝岳はことしに入り、火山性地震の回数は少なく落ち着いた状態が続いていました。
|
[関連ニュース]
自動検索
|
・ 十勝岳 気象台“噴火の可能性は低い” (7月1日 3時32分)
|