9月になった。明日から国際助産師連盟の合同地域会議(東地中海、東南アジア、西太平洋地域)で通訳のためにドバイに向かう。大変な暑さだった夏が終わり秋に向かいつつあるようだが、まだ夜もエアコンのお世話になっている。明日は台風が来るというので、空港まで無事に行けるか心配している。
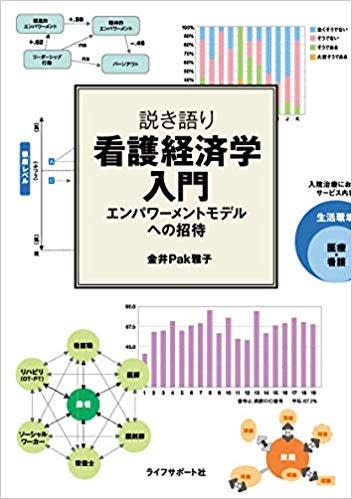
さて、写真の本であるが、一昨日、金井Pak 雅子先生から届いた、新著『説き語り 看護経済学入門 エンパワーメントモデル』である。出版社はライフサポート社だ。編集長の佐藤信也氏は、私の著書『対人コミュニケーション入門 看護のパワーアップにつながる理論と技術』も手がけてくれた。以前は日本看護協会出版会の編集長をしていて『インターナショナル・ナーシング・レビュー』誌を担当していた。自分の本を出してくれた出版社からではないが、ライフサポート社は本当に良い本を出す。今回も良い本ができた。
金井Pak 雅子先生は、看護管理学、システム論の第一人者で、日本で看護経済学という新しい学問分野をリードしてきた。アメリカのペンシルべニア大学のリンダ・エイケンとも共同研究をしていた。国際看護師協会(ICN)の理事を2期務め、2期目は第一副会長であった。
私が最初に金井先生に会ったのは、2009年南アフリカ ダーバンで開催されたICN4年毎大会の各国代表者会議。私は通訳をしていた。金井先生が最初の理事選で当選したときである。小柄な身体でどこからそんなにエネルギーが出てくるのかと不思議に思ったくらいパワーがあって驚いた。
本の中では、大学院での学び、結婚、生活、病院での勤務など、アメリカでの生活を織り交ぜ、やさしい語り口で看護と経済の関係を説いていく。グラフや表だけでなく、オリジナルの図もたくさんあり、おそらく今後、日本の看護文献の中で引用されていくと思う。
順番に読む必要はなく、好むところから読み始めてもよい。とても読みやすいのだが、内容は濃い。おすすめの本である。
https://www.amazon.co.jp/看護経済学入門―エンパワーメントモデルへの招待-金井Pak-雅子/dp/490408439X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1535985073&sr=1-1&keywords=%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80%E3%80%80
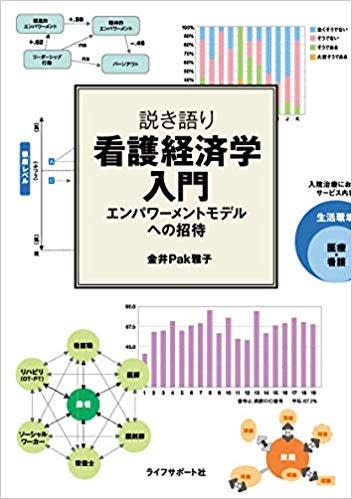
さて、写真の本であるが、一昨日、金井Pak 雅子先生から届いた、新著『説き語り 看護経済学入門 エンパワーメントモデル』である。出版社はライフサポート社だ。編集長の佐藤信也氏は、私の著書『対人コミュニケーション入門 看護のパワーアップにつながる理論と技術』も手がけてくれた。以前は日本看護協会出版会の編集長をしていて『インターナショナル・ナーシング・レビュー』誌を担当していた。自分の本を出してくれた出版社からではないが、ライフサポート社は本当に良い本を出す。今回も良い本ができた。
金井Pak 雅子先生は、看護管理学、システム論の第一人者で、日本で看護経済学という新しい学問分野をリードしてきた。アメリカのペンシルべニア大学のリンダ・エイケンとも共同研究をしていた。国際看護師協会(ICN)の理事を2期務め、2期目は第一副会長であった。
私が最初に金井先生に会ったのは、2009年南アフリカ ダーバンで開催されたICN4年毎大会の各国代表者会議。私は通訳をしていた。金井先生が最初の理事選で当選したときである。小柄な身体でどこからそんなにエネルギーが出てくるのかと不思議に思ったくらいパワーがあって驚いた。
本の中では、大学院での学び、結婚、生活、病院での勤務など、アメリカでの生活を織り交ぜ、やさしい語り口で看護と経済の関係を説いていく。グラフや表だけでなく、オリジナルの図もたくさんあり、おそらく今後、日本の看護文献の中で引用されていくと思う。
順番に読む必要はなく、好むところから読み始めてもよい。とても読みやすいのだが、内容は濃い。おすすめの本である。
https://www.amazon.co.jp/看護経済学入門―エンパワーメントモデルへの招待-金井Pak-雅子/dp/490408439X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1535985073&sr=1-1&keywords=%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80%E3%80%80















