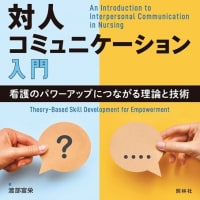シドニーから帰ってきた。毎年恒例の看護労働に関する会議の通訳が終わった。国際看護はまた、少しずつ、動いている。
久しぶりのブログ更新で、医療通訳者や医療通訳に関心のある方にニュースである。これまで医療通訳に関するテキストブックはなかったのだが、今回、500ページのものが出された。
テキスト『医療通訳』
医療通訳者の役割、倫理、身体の仕組みと疾患の基礎、検査、薬、感染症、医療制度、文化理解、自己管理
もちろん、通訳技術については、対話型の逐次通訳をしっかり学べるように例題がたくさん出ている。
医学的な内容は、医療通訳者に必要な関連性のある医学的知識がしっかり押さえられている。医学用語も現場で使う可能性の高いものがおよそ80ページに収められている。
背景を説明すると、今年、厚生労働省が「医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業」を一般財団法人 日本医療教育財団に委託し、その中の医療通訳者用のテキストの作成と研修を多文化共生センターきょうとが受託した。私は通訳技術とコミュニケーション関連のセクションを執筆している。テキストは全500ページ。今のところ非売品なのだが、今後、販売も検討されている。全文は厚労省のホームページからダウンロードできる。今日、前田さんからURLが送られてきた↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html
テキスト作成の経緯は多文化共生センターきょとのHPに掲載されている↓
http://www.tabunkakyoto.org/
久しぶりのブログ更新で、医療通訳者や医療通訳に関心のある方にニュースである。これまで医療通訳に関するテキストブックはなかったのだが、今回、500ページのものが出された。
テキスト『医療通訳』
医療通訳者の役割、倫理、身体の仕組みと疾患の基礎、検査、薬、感染症、医療制度、文化理解、自己管理
もちろん、通訳技術については、対話型の逐次通訳をしっかり学べるように例題がたくさん出ている。
医学的な内容は、医療通訳者に必要な関連性のある医学的知識がしっかり押さえられている。医学用語も現場で使う可能性の高いものがおよそ80ページに収められている。
背景を説明すると、今年、厚生労働省が「医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業」を一般財団法人 日本医療教育財団に委託し、その中の医療通訳者用のテキストの作成と研修を多文化共生センターきょうとが受託した。私は通訳技術とコミュニケーション関連のセクションを執筆している。テキストは全500ページ。今のところ非売品なのだが、今後、販売も検討されている。全文は厚労省のホームページからダウンロードできる。今日、前田さんからURLが送られてきた↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html
テキスト作成の経緯は多文化共生センターきょとのHPに掲載されている↓
http://www.tabunkakyoto.org/