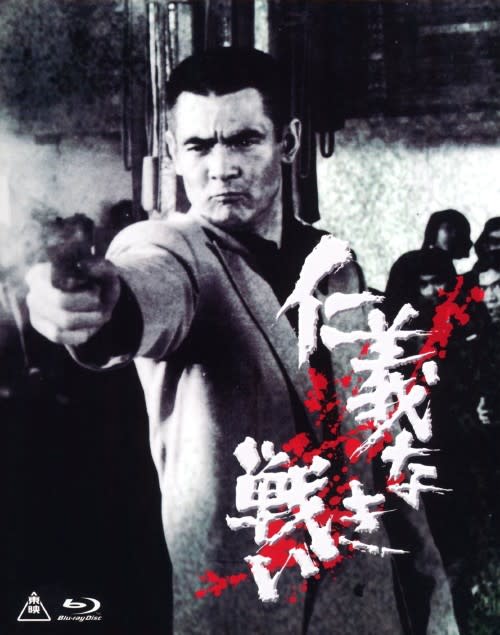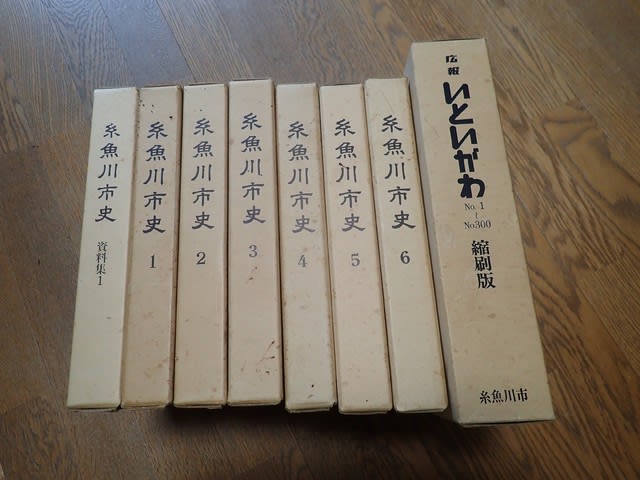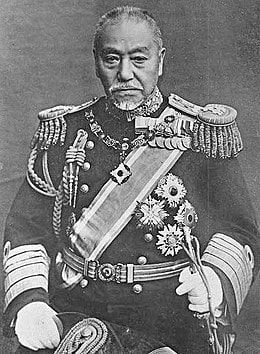国道148号線の新潟・長野の県境を越えたとたんに、プ~ンと硫黄泉の匂いが漂い「猫鼻の湯」の看板があらわれるが、この不思議な名前の温泉の由来がやっとわかった。

越後と信濃の境を姫川が流れる地形が、猫の鼻っ先の三ツ口に似ているからだそうだ。

教えてくれたのは温泉オーナーの清水英雄さんで、私がヒスイ職人だとわかると「三種の神器の勾玉は糸魚川ヒスイだか?どれくらいでかいだ?ヒスイは今でも拾えるだか?」と矢継ぎ早に質問されて、入浴前に一時間以上も懇談。

「家からみえる山はあるだか?」と聞かれたので黒姫山だと答えると、色紙に「黒姫山山頂よ里 鶴千羽 五条松を含み 七福神を引き連れて 山田修家乃 門に入留」と書いて贈ってくれた。

屋根のある湯舟と二つの露天風呂があって入浴料500円!
達筆でスケベな話しが好きなスキンヘッドなので、親鸞聖人みたいですね!お坊さんですか?と言ったら、禅宗のお坊さんだそう。

年中無休24時間営業なので、無人になる夜に泥棒に入られたこともあるようだが、清水和尚は意に介さないのは、衆生へのお布施のつもりなのか?書道家としても有名らしい。

ここは千国街道(ちくにかいどう・松本街道、糸魚川街道ともいう)に位置する集落で、中世以降には「塩の道」とも呼ばれたし、縄文時代には黒曜石ロードやヒスイロードではなかったか?
出雲から逃亡したヌナカワ姫が、このあたりで追っ手に捕まりそうになり、再び糸魚川まで帰えり、拙宅裏の稚児ケ池でお隠れになった伝説にも出てくる土地でもある。
清水和尚の父親は糸魚川市青海区の「油屋」の出身で、私の母方の先祖はすぐ近くの「大海屋」という造り酒屋だったから、ご先祖同士は顔見知りだっただろう。

おまけに私の父親の先祖は、塩田を持つ塩問屋だったから、何かと縁を感じる。
ヌナカワ姫を崇拝しているという近所の常連さんからも、小谷村の歴史を教えてもらった。
小谷村には出雲から逃げて来た姫が、姫川の「姫ケ淵」に入水自殺して以来、姫川と呼ばれるようになったという伝説があり、この淵が実在することを知った。
後日に検証してみたら、武田勝頼の夫人が入水自殺した伝説と、武田勢に敗れた当地の武将の姫君が入水自殺した伝説が、ヌナカワ姫伝説と混じっているようだ。
拙宅からバイクで40分。息抜きにちょうどいい距離、場所、面白い人々。もちろん温泉もいい。