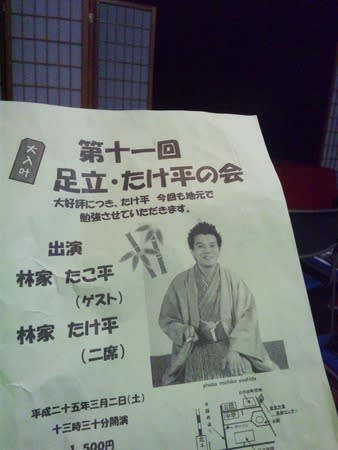昨日は町屋で落語。
~四合わせ二ツ目会~「町屋お笑い寄席」
たらちね 古今亭 志ん吉
紀州 林 家 はな平
中入
ちりとてちん 鈴々舎 八ゑ馬
明烏 春風亭 昇々
今までの黒門亭(上野広小路)から町屋に場所を移しての開催でした。
お客さんは11人、アットホームです。
出演者の四人は芸歴8年から9年の二ッ目さんです。
私自身、落語初心者なので(特に江戸落語は・・)まだいろいろわからないことが多いのです。
だから良し悪しは二の次にして、面白かったか面白くなかったかというと、普通。(笑)
志ん吉さんは、聞くのが二度目。
たらちねって生で聴くのは初めてかも。
上方の延陽泊の方が聴き馴染んでいるからか面白いと思うのは私だけかな。
はな平さんは、紀州なんてどうでもいい話なのに面白かったです。
なんか個性がますます出てきていますね。
八ゑ馬さん、いつもの通り上方落語。
相変わらず自虐マクラが面白い。
ちりとてちんも何か内容が変わってたけど、部分的に創作なのかな。
あのもどしそうになるのは、たまさんがやってたような。
昇々さんは初めて聞きました。
なんかお人形が落語してるみたいで不思議。
もっと盛り上げていい会にしてくださいね。
期待しています。
~四合わせ二ツ目会~「町屋お笑い寄席」
たらちね 古今亭 志ん吉
紀州 林 家 はな平
中入
ちりとてちん 鈴々舎 八ゑ馬
明烏 春風亭 昇々
今までの黒門亭(上野広小路)から町屋に場所を移しての開催でした。
お客さんは11人、アットホームです。
出演者の四人は芸歴8年から9年の二ッ目さんです。
私自身、落語初心者なので(特に江戸落語は・・)まだいろいろわからないことが多いのです。
だから良し悪しは二の次にして、面白かったか面白くなかったかというと、普通。(笑)
志ん吉さんは、聞くのが二度目。
たらちねって生で聴くのは初めてかも。
上方の延陽泊の方が聴き馴染んでいるからか面白いと思うのは私だけかな。
はな平さんは、紀州なんてどうでもいい話なのに面白かったです。
なんか個性がますます出てきていますね。
八ゑ馬さん、いつもの通り上方落語。
相変わらず自虐マクラが面白い。
ちりとてちんも何か内容が変わってたけど、部分的に創作なのかな。
あのもどしそうになるのは、たまさんがやってたような。
昇々さんは初めて聞きました。
なんかお人形が落語してるみたいで不思議。
もっと盛り上げていい会にしてくださいね。
期待しています。