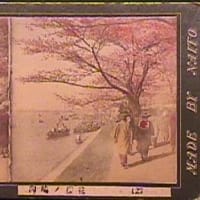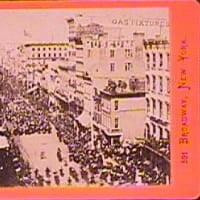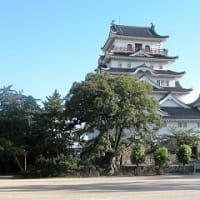長野県の芸術・文化情報センター
![]()
江戸時代の貨幣制度
貨幣制度の統一
関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は貨幣制度の統一に着手し、慶長6(1601)年に慶長金銀貨を発行しました。銭貨については、寛永13(1636) 年、三代将軍家光の時代に「寛永通宝」が造られています。のち、寛文10(1670) 年には渡来銭の通用が禁止され、貨幣制度は完全にわが国独自のものになりました。この金・銀・銭、3種の異なった貨幣からなる貨幣制度を「三貨制度」といいます。
一方、17世紀初め頃、伊勢山田地方の商人の信用に基づいた紙幣(山田羽書(はがき) )が出現し、やがて各藩でも領内で通用する藩札(紙幣)が発行されるようになりました。こうして幕府による三貨制度と、各藩における紙幣の分散発行が併存するという、江戸時代独特の幣制ができあがりました。
貨幣の改鋳
元禄時代になると、幕府は貨幣素材の不足や財政事情の悪化に対処し、金銀貨の質を落とす改鋳をおこないました。貨幣の改鋳はたびたびおこなわれ、貨幣制度は乱れていきました。
三貨制度の体系図(1700年ごろ)
各貨幣の単位
●金貨(計数貨幣)…1両=4分=16朱
●銀貨(秤量貨幣)…1匁=10分、1000匁=1貫(貫目、貫匁)
※秤量貨幣の単位「匁」は、重量の単位そのもの(1匁=約3.75g)
●銭貨(計数貨幣)…1000文=1貫文