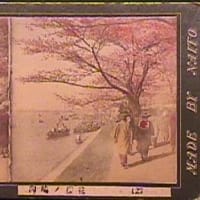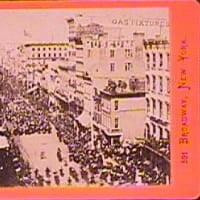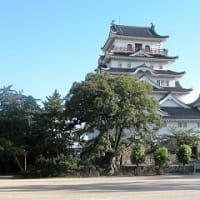<諸氏百家にみる桶狭間の戦い>
(3)藤原京氏の桶狭間 (初出 2008.07.13) 『時代劇のウソ?ホント?』での氏の仮説はかなりユニークです。 その要点は義元軍は陣城を構築中であって、それが完成する前の隙を速攻した信長に衝かれために敗れたというものです。そのために、信長は第一波の攻撃を千秋・佐々ら三百人に行わせ、第二波には前田犬千代が参加しており、自らは第三波となって義元本陣に殺到したというのです。そして、その背後には柴田勝家らの部隊が控えていたとしています。 このような説を唱える理由について、氏は自ら説明して、現在忘れ去られた戦国時代の常識の一つとして、「城は攻めても落ちないもの」というものがあるとされています。そのため、鳴海城・大高城を攻囲し、駿河勢籠城策をとったために必然的に駿河勢による後詰が行われたことにより生起したされており、信長は桶狭間山に着陣した駿河勢が未だ陣城を構築できないでいたその隙をついたのだとされるわけです。そして、反面教師として長篠合戦での信長・家康連合軍による野戦築城を例に出されます。………義元は、本当に桶狭間山に陣城を築こうとしていたのでしょうか?一体、何の目的で? 陣城構築中であったということには否定的な情報が多々あります。 それでも、藤原氏の説には魅力的なものがありました。それは、「桶狭間の戦いは今川義元が鳴海城の後詰を行ったことによって起きた」という主張です。この説は、『信長公記』の天理本が紹介されるまでは、大高城に兵粮を搬入したことは公記に書いてあるのですが、大高城が包囲されていた事は証明できませんでしたから、すこぶる魅力的な見方の一つで有り得ました。大高城の南に付城が築かれたことを明確には証明できなかったからです。 その場合には、丸根・鷲津砦の戦術的な意味は、藤原氏が言われるように、鳴海城への兵粮や兵力を搬入することを妨害するものであったことになり、織田方が大高城を攻撃することは二義的になりますから、義元がこのニ砦を攻略することは取りも直さず鳴海城の封鎖を解くことを目的にしたものであったことになるわけです。………尤も、それでもまだ中島砦が東海道を封鎖していますから、東海道からの搬入は見込めませんし、沓掛城から鎌倉海道によって善照寺砦を攻略した方が楽なように思えることには変わりはないのですが。 ところで、本当に、「城は攻めても落ちないもの」なのでしょうか? これは、基本的には正しいのですが、半分は間違った説明だと思います。戦国時代後半というのは、歴史的に城砦が「落とすべきもの」に変化した時代であり、戦国末期には「落ちない城は無くなった」のです。そして、桶狭間の戦い頃の城は将に「落とすべきもの」になった時代なのです。 城塞というのは古代に「稲城」といわれたものから戦国時代前期までの「城館」まで、一般には本気で戦争するための城塞というものは唐の侵攻に怯えて大宰府に水城を築いた時期を除いては、日本ではあまり作られませんでした。つまり、防御施設というものは簡単なものでも十分に有効であったという事実があったからです。 「落ちない城」の範疇で最も有名なのは楠木正成の千早城・赤坂城ですし、大きなものでは大宰府の水城、平氏の福原防塞、奥州平泉の藤原泰衝が源頼朝の率いる鎌倉軍を迎撃するために築かれた阿津賀志山防塁、元弘時の防塁がある程度のものでしょう。勿論、帝都は中国の城塞都市を真似て作られていますから、一応城塞であります。 これらのことから気づくことは、日本では古代に国際外交の真っただ中にあったとき以外には、城塞に拠って長期にわたって攻防するということは殆ど考えられていなかったということです。そのため、城塞は簡単な設備であっても十分にその役目を果たしてしたということなのです。しかし、これは逆からみますと、日本国内での紛争は殆どが内乱にまでも至らず、ヤクザ同志のシマ争いの喧嘩程度のものでしかなかったからであることが窺えます。つまり、世界的なレベルで見るならば戦国時代より前の日本の城塞の殆どは世界規格に満たないものばかりだったわけです。なぜなら、戦争当事者自体がヤクザみたいなものですから、敵の城塞を徹底的に攻略しようなどという「意図」も兵力差も持たなかったからです。 応仁の乱においても洛中では、首都の都城の内にあっての市街戦で終始したのです。市街戦が行われるということは、市街が焼き尽くされ破壊し尽くされていないことから起こります。近代以前ならば始めから火攻めをおこなったりはしないということですし、近世以降になりますと事前の制圧砲撃で徹底的に破壊したりしない攻撃になります。ところが、戦国時代も深化してきますと、領国の統一から始まって、領国を拡大して隣国をも支配しようとするように目的が変わってきますと、まず、兵力差が広がってきたうえに、それに裏付けられて敵の城塞を完全に攻略する意志持ち始めます。 するとそれまでの、政治・行政・経営を目的とした城館では目的を果たせなくなり、武士は城館の背後に詰城として山城を築き始め、次第に戦術的な意義を最優先する山城が主流になります。こうなると城塞は落とし難かろうが、落とさねばならないものになってきました。それまでは、多大の犠牲を払ってまで落とす意義を感じなかったのですが、終に多大の犠牲を払っても「落とす必要がある時代」になっていくのです ところが、戦術的に有利であると思われた山城も、火縄銃の普及により、反って戦術的には不利になるという逆転現象が起き、城塞は広大な城域と高さを合わせもった平山城に移行します。 註 鉄炮の普及が山城への籠城を不利にしたのは、その威力と射程にあります。山城の地形的有利さは、急な斜面と狭い尾根によって攻撃軍が接近し難く、攻撃路が限定されるということにあります。ところが、その山城の有利な点は攻撃側にも作用しており、迎撃正面を著しく狭いものにしてもいるのです。これは投射兵器の射程距離が短い間は守備側に有利に働きましたが、鉄砲が現れて射程距離が増大すると一気にそれを減殺してしまいました。三角形を想像してください。守備側は三角形の頂点の狭間から底辺を万遍なく射撃できるのですが、それに使用できる武器は一つに限られてしまいます。それに対して三角形の底辺には数倍の射手を並べて、狭間を制圧射撃できるわけです。そして、鉄炮は弓矢より自由な射撃姿勢を採れますから、体を隠し難い攻撃側を非常に有利にしました。つまり、山城では尾根を切って堀にすることにより、攻撃路を極端に狭く限定できても、突撃を援護射撃する正面を狭めることができないのです。そして、守備側は各々の山頂に分散していますから、相互に連携して援護し合えないのです。…この欠陥を是正したのが、平山城であり、山頂に指揮所を作り、山腹を全面的に郭にすることによって、一元的統一的に防御戦闘を指揮できるようにしたわけです。そして、平山城の山腹曲輪の狭さを克服したのが、石垣に支えられた重層櫓なわけです。これにより、敵の攻撃路を狭くして戦闘正面幅を小さくしながら、守備兵を重層的に配置することができるようになり、守備側を有利にしようとしたわけです。 城館時代の城は、長期に渡る攻囲などは始めから想定して作られてはおりません。専ら不意の攻撃に備えたものですし、攻撃側も端から徹底的に攻略しようというような意図は持っておりませんでした。そのような大義も利害もなかったからです。ですから、刈り働きをしたり水利施設を破壊したり復讐であったりといったところで終わっていました。そのため、簡素な城館でも攻め落とすことは困難でした。それでも攻め落とそうとするならば、仕寄せをしたでしょうし、攻囲することも考えられるでしょうがそのようなことに至ることは殆どありませんでした。楠木正成の千早城の攻防をみれば、寄せては仕寄の準備を全く欠いていたことがわかります。これでは城は落ちません。 ところが、領国統一から広域支配の時代になりますと、端から籠城を覚悟した造りに城塞はなってきます。それは、攻撃側が敵を徹底的に攻略しようという意志を持つようになったからです。そのため、力攻めで短期に落とすことが無理ならば、攻囲して経済封鎖をすることによって攻略する必要が生じたわけです。そのために発達したのが付城です。城が物資の集積基地であるから、攻囲するわけではありません。戦国時代になると大大名たちは城攻めには、付城を築いて攻囲戦を行うようになるのですが、それ以外の国人衆以下のレベルでの戦争では、そのような例はそれほど多くないのです。攻囲する側も兵員を張りつけなければなりませんし、その兵粮その他の軍需物資を攻囲軍に補給するのが大変だからです。全てを苅田狼藉で現地調達しようとしても無理があります。 領国統一から広域支配の時代になって、端から籠城を覚悟した城塞を攻囲するようになったのは、我彼に圧倒的な兵力差があるのに敵が降参しないからです。そして、降参しないその理由は初めから敵を拘束する役目を持つ城であるか、敵に服従するのが嫌だからです。つまり、近隣の紛争や中央政治の代理戦争として互いに同等の兵力で戦う時代は終わり、継続的に領土拡大のための争いがはじまったのです。 ですから、信長が活躍し始める時代の城塞は、既に「城は攻めても落ちないもの」などではなくなっていたのです。そして、戦国時代が終わる頃には「城は必ず落ちるもの」になってしまっています。天下分け目の合戦の時代に落ちなかった城は数えるほどしかないはずです。 (4)別動隊説を検証する (初出2 007.12.18) 桶狭間の戦いにおける一方的な大勝利を迂回を考えずに可能にする方法には、「別動隊」を考えることで解決することがあります。 但し、この別動隊説には根本的な問題がいくつかあります。 別動隊による可能性を指摘したのは、橋場日月氏の『再考・桶狭間合戦/歴史群像』『新説・桶狭間合戦』である。 橋場氏の指摘の新しい視点は、これまでの迂回説と異なり、信長自身が迂回したのではなく、配下の武将それも新設して間もない馬廻部隊の武将が迂回挺身を指揮している点である。………それなのに、この後、此の馬廻りの指揮官が支隊を率いて活躍することは伝えられない。馬廻の武将の多くは攻囲戦での周番を担当している。それは馬廻の本来の任務が近衛兵・親衛隊であったからではないかと考える。 橋場氏のこれらの著作では、橋場氏が一般にはこれまで見過ごされてきたか又は触れることを避けられたり、合理的な説明がなされないままできた点に注意を促しているものがある。 逆に、氏が触れなかったり説明していない問題もある。 (2009.01.23 追加) 以下は、小生のブログ「読書三昧」に2008.07.10に書いたことに一部手直しして転載したものである。 『新説・桶狭間合戦』の橋場日月氏は、「信長は時速6kmほどで(清洲から熱田までの)12km弱を移動した計算になる。これは旧日本陸軍の標準的行軍速度の時速4kmより若干早い速度だ。信長は、後続の軍勢が追い付いて来られる速度で進んだのである。p173………信長が善照寺砦から分派して鎌倉往還を東進させた部隊は、途中暴風雨が吹きはじめる中、今川の分遣隊を撃破して沓掛城周辺に至り、さらにこの部隊は大高道を南下して上ノ山に至る。距離はほぼ3km強であり、………旧陸軍が通常行軍を時速4km、「速歩」という強行軍を時速5kmと規定していた事から見ても、それと比較して無理のない移動速度と距離だと言える。p215」と書かれる。 『作戦要務令・第321』には、「一般兵団の一日行程は、普通行軍に於いて8時間32粁、強行軍に於いては10乃至12時間以上(大休止の時間を増加す)とす。…」とあり、戦場到着後直ちに戦闘に入れる状況にあるわけではない。現に、賤ケ岳の場合も21時に全軍が着陣したといわれているのだが、秀吉は軍勢に喚声をあげさせはしたが、総攻撃を命じたのは夜明けを期して行うということであった。ところが、それに驚いた佐久間盛正は23時に総退却を始めた。それでも、秀吉が佐久間勢退却中の報を得たのは翌日am2時であり、賤ケ岳にいた既存の秀吉方守備隊は、それぞれ対応して逐次攻撃を開始したらしい。それでも佐久間盛正の部隊は、am3時には総退却を無事に完了しているのである。ですから、大垣から駆け付けて疲労困憊した部隊が戦闘に参加し始めたのは、もっと後になる。 (6)鈴木信哉氏『戦国十五大合戦の真相』 (初出 2009.02.01) (p18)「常識的に考えても、織田家との間で国境の城砦を取ったり取られたりしているような状況では、一気に上洛するなど到底無理である。」 ………この指摘は重要である。尾三国境の北部・品野城などでは信長の攻勢にあって防衛一辺倒であり、後詰がされたという話がない。南部の大高城の攻防は早い時期から始まっていて、笠寺台地の駿河勢は駆逐されている可能性があることを考えると、鈴木氏の指摘は看過できないものがある。信長の軍事力は三河・遠江・駿河の辺境に派遣された軍勢とではあるが、互角に戦えるだけの実力を備えつつあったことになる。そして、その信長の軍隊が七~八百の歴々からなる常備軍を中核とした二~三千の兵力であった可能性があるようにも思える。 (p18)「(清須城を)力攻めにすれば膨大な損害を覚悟しなければならない。といって兵糧攻めなどしていたなら、大変な手間と時間が必要となる。義元にそれだけの準備と余裕があったとは考えられないから、尾張一国の制覇でも。まだ目的として大きすぎるだろう。」 ………これについては、「天理本信長記」の「(2)軍議があった夜」で詳しく論じたとおりだが、安城も刈谷も落ちているのだから、平城で一重堀の舘城である清須城を攻め落とすのに時間はかからなかったろう。 (p18)「この時代、優勢な敵が迫ってくれば、領民はパニックを起こすのが普通である。…このときの織田領内では、まったくそうした形跡が見当たらない。それどころか熱田の町人たちなどは、今川に与党して海上から攻めてきた一向宗徒と戦って追い返したりしている。本当に今川軍が迫ってくるなら、報復が恐ろしくて、そんなことはできないだろうし、そもそも大勢の町民が街のなかに止まっていたはずがない。」 ………この視点も重要である。もし熱田の町人でさえ義元が尾張との国境を踏み越えて熱田にまで侵出することなどあり得ないと考えており、且つ『天理本信長記』のいうように町民らが動員されて、のこのこ善照寺までもついて行ったことが事実ならば、一つ考えねばならないことは、義元の軍勢は牛一が今に伝えるような四万五千もの大軍などではなかったことであり、もう一つは、熱田は湊町であり自由港としての性格を持っており、港町を無暗に攻めて商人・町人を追い散らすことはしないだろうという見込みがたっていたかも知れないということである。熱田は港であるから役に立つのであり、信長ですら堺幕府があった堺衆に対しては交渉(矢銭を課した)から入っているのだ。これが戦国時代も終盤に近くなると見境もまくなり、博多湊などは1580年には竜造寺氏が、1586年には島津氏が焼き討ちを行って灰燼に帰している。 (p20)「そもそも戦闘を始めた時点では、信長は義元が何処に居るのかということも知らなかったと思われる」 ………鈴木氏が言われる「戦闘を始めた時点」が午後二時頃のことであるならば、具体的な居場所を知らなかったとはいえる。しかし、善照寺に参陣した時点では桶狭間山に本陣を置いていたことも知らなかったとは断定できない。何故なら、山上には総大将の居所を示す旗幟が立っていたものと思われるからである。だから、牛一は「御敵、今川義元は、四万五千引率し、桶狭間山に人馬の休息これあり、」と書いたのだと思うのだ。単に、敵勢が屯していたことを義元に代表させたわけではないと思うのだ。 (p20)「信長の狙いは…とりあえず今川軍に打撃を与えて追い返すことだったろう。…くたびれた敵部隊を自軍の主力で叩くことによって、確実にポイントを稼ごうとしたのである。」 ………とりあえず今川軍に打撃を与えることが目的ならば、付城を攻めている背後を攻撃することが常道だろうが、これについての説明は藤本氏も十分になされたとは言えない。 ………「自軍の主力」と言われるが、たった二千が信長の主力なのだろうか? (p20)「本拠を遠く離れてやってきている彼らの半ば以上は、補給要員などを含めた非戦闘員だったと考えるべきである。相手の信長勢は清須から真っ直ぐやってきたのだから、馬丁・槍持などを除けば、大部分が戦闘員だったであろう。」 ………彼等駿河・松平同盟軍の根拠地は岡崎城であるのだから、非戦闘員が多かったということはできまい。先鋒を務めた松平勢のことはどう考えるのだろうか? (p20)「信長勢は一団となっていたが、今川の部隊は各所に分散していた。」 ………これが、暴風雨のために統率が乱れたというのならば問題は少ないが、移動中であったためとか、布陣が各所にバラバラであったというのであるのならば、それには根拠がないと言わざるを得ない。 (p22)「 (清須城における前夜の)籠城の議論にしても…前線で苦戦している味方を見捨てたまま大将が城に逃げ籠ってしまうことなど考えられない。もしそんなことをしたら、信長はたちまち部下たちから見放されてしまったに違いない。」 ………では何故、信長は後詰に出かけないのに部下に見放されなかったのか。それとも、雑兵二百人にしか随伴しなかったのが見放された結果なのか。 ………この鈴木氏の著書は『天理本信長記』が公にされる前のものではありますが、籠城しないことが常識であるとしたならば、信長や清洲城にいたと思われる重臣たちの行動は異常であると言わざるを得ません。
戦国時代の人々の身体能力は本当のところはよく分からない。江戸期の旅行記録をみると昔の日本人は驚異的に強靭な身体を持っていたらしい。昭和の陸軍も同様であったらしいことは知られている。従って、その明治以降の陸軍が定めた作戦要務令が合理的に戦争を継続して遂行するための行軍速度を時速4km、強行軍を時速5km、急行軍を時速8kmと定めたことは無視できない。
『作戦要務令・第320』「撃兵団の前進速度は1時間4粁、兵の負担量を軽減せる場合は1時間5粁とす。大隊以下の小部隊にして負担量を軽減せる場合は、急行軍の速度は1時間8粁に達す」とあり、兵の負担量を軽減し大隊以下の小部隊にしなければ、急行軍の速度は達成できないなのである。
通常、歩兵の行軍は一時間で4kmを50分歩いて10分小休止するペースで行軍する。昼食の休憩は1時間大休止し、連日行軍の場合は一日24kmである。『太閤記』高麗陣ニ就イテノ掟條々でも「一、人数おし之事、六里を一日之行程とす。」とあるから戦国時代と旧軍も各国陸軍も概ね変わらない。
強行軍は行軍時間を長くしたり、休憩時間を短くすることで行い、一日に十時間の行軍で40kmの距離を進む。が、実際にはそんな決まりは無いに等しかったらしい。行軍速度を上げることも強行軍と言わないこともないが、急行軍という。急行軍になると駆け足になるが、休息時間も減らす点は強行軍とさして違わない。
つまり、時速6kmという速度は、若干早いなどという行軍速度ではない。駆け足に近いのですから、時速6kmは完全武装した歩兵が追い付ける速度などではありません。
旧日本陸軍の強行軍は時速5kmなのだ。時速6kmというのは、ほとんど走っている状態だ。
信じられないことなのだが、旧日本軍の兵士たちは通常装備30kgを背負い、そのうえで機関銃隊ならば機関銃を、砲兵隊ならば砲身を担いで、そのような強行軍を実際に行ったといわれている………。
行軍速度というものは部隊の規模が大きくなるにつれて遅くなるし、異兵種と連合する場合は遅い速度の部隊を基準とすることになる。(分進することが効率的ではあるのだが、敵に遭遇する状況では致命的な結果を招来することになる場合もあり、そう簡単に兵力を分散させるわけにもいきません。)歩兵が追い付けないから、信長は熱田でその参集を待つ必要があったのだろうと考えるべきです。もし、信長に常備軍があってそれが清洲に駐屯していたならば、であるのですが………。そうでなければ、余りあてにできない国人衆が熱田に集合するのを待っていたと考えなければならないことになります。
だから、信長が小姓や馬廻など乗馬身分の者だけで挺身したのならば、三里を時速6kmは十分に可能であるでしょうが、歩兵を随伴した場合には強行軍を超えているのですから、到着した戦場で直ちに戦闘に入ったのでは、兵士たちは使い物にならないのではないかと危惧されるわけです。一般に戦国時代の軍勢に占める騎兵の割合は一割程度であるといわれるからです。
戦史を見ても強行軍の例は多く、一日に80~100km以上という行軍速度の例がある。
何れも時速に換算すると2~3kmというのが多い。
時速4kmを超える例は、第二次ポエニ戦争のローマの武将クラウディウス・ネロが、精兵7千を選り抜いて可能な限り軽装にさせ、食料も携帯せずに道筋にある町に食事を用意させ、800kmを一昼夜に100km(時速4km)以上の速度で強行軍させたものぐらいしかない。
橋場氏は、「秀吉の賤ヶ岳合戦の際の移動速度が時速8kmだった事、旧陸軍の早足(時速6km)・駆け足(時速8km以上)を勘案すれば、今川別働隊を風雨に乗じて撃破した地点から沓掛まで4km、さらに沓掛から4kmを移動するのにそれほど無理があるとは思えない。」とされるのだが、背後から吹き飛ばされる場合はまだ良い。嫌でも運ばれるのだから。しかし、沓掛から大脇村曹源寺へ南下するときには横風を受けて吹き飛ばされたであろうし、曹源寺から上ノ山へは向かい風の中を進まなければならないのだ。信長が義元本陣に突撃したのは風雨が止んでからのことであるのだから、それを、楠が吹き倒される強風の中を挺身したというのだからスーパーマンとしか言いようがない設定である。
著作権 かぎや散人