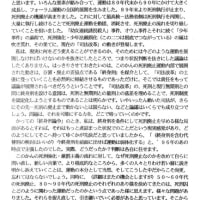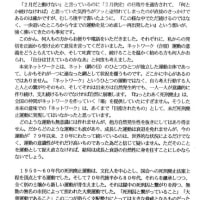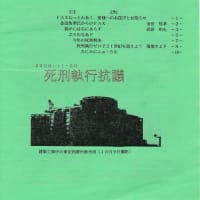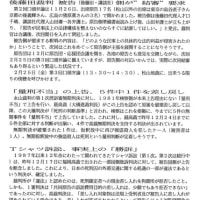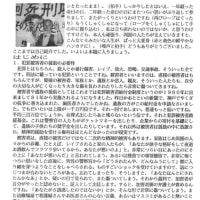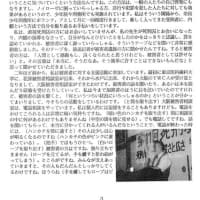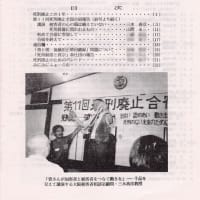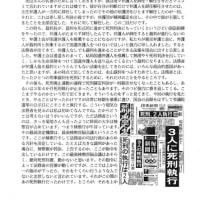死刑廃止団体『麦の会』が出していた会報。1991年11月24日発行。(この表紙絵は、佐川和男刑死囚が描いた。)
上会報に、永山則夫元支援者武田和夫氏のご意見文があったので、以下、全文載せます。
…が、『飯田博久』と『とらえなおし』が出てきますが、それがよくわからない方は、こちらを参考にされてください。
-----------------------------------------------------------------
今、あえて問う
獄外事務局 武田和夫
一、
死刑を廃止しなければいけない理由の一つに、「人は変わるものだ」ということがあります。
このこと自体は一般的に正しく、何ら反論する余地はないと思います。
しかし運動の中でしばしば、「変わった、反省した死刑囚」の具体例があげられる時、私は非常に危ういものを感じないではおれないことがあります。
人は変わります。それは、人はたえず、新たな自己を選びとるべく生かされている存在だという意味においてそうなのであって、誰かれは変わったが、誰かれはまだ変わっていないという評価の対象という意味でそうなのではないと思います。そうした人間存在の本質ゆえに、どんな人に対しても死刑は間違っているのです。
「人は変わりうる」実例としてある死刑囚があげられる時、「『変わる』以前の彼を知っていたのかな」と思うことがあります。
多くの場合、「殺人者・死刑囚」という一般的イメージ=市民感覚からの偏見が無意識に前提となってはいないでしょうか。「会ってみると、普通の人だ」というのもこれにつながります。当り前なのです。「普通の人」が、ある日なぜ殺人をおかすのかを問題にしないといけないのです。
「変わった・反省した」と一般に言われている人を含め、人はそう簡単に変わるものではなく、彼が「普通の人」=善良な市民としての存在を踏み破るに至った問題性は、彼が意識する、しないにかかわらずそのまま抱え込まれている場合がほとんどです。人々がそれに「気付かない」のは、その領域に踏み込もうとすれば、自分自身の「善良な市民」としての存在も、根底から問い直されずにはすまないからにほかなりません。
「彼は変わった」という時、何か、どのように「変わった」というのか。自分達市民存在をその基準とする時、自分達は結局変革の対象とはならないのです。
人はある状況におかれた時、誰でも人を殺します。しかし人のおかれた状況には差異があり、またその人の成長過程にも差異があって、同じ状況であってもすべての人が殺人を犯すとは限りません。
どのような状況で人は人を殺すのか、その状態はどうすれば避けられるか。また同じ状況で、殺す人と思いとどまる人とは、どこが違うのか。どうすれば殺人にたいする内面の抑止力は強まるのか。それは、全社会的規模での、政策と予算の裏付けをもって、究明されなくてはなりません。人が人を殺さず、共に生きることのできる社会を作っていく過程で、実際の「事件」に向き合いつつ、殺人を犯した人と対話しつつ、そうしたことを徐々に明らかにしていく事は、どうしても必要なこととなるでしょう。死刑制度がそれに全く逆行するものであることは、いうまでもありません。
「何故人を殺せたのかと、私達に問い続けて下さい。」という、飯田博久氏(元麦の会正会員、二審で無期に減刑後、諸般の事情からオブザーバーに。自ら上告し、89年10月、確定し下獄。)の言葉の重みは、以上のような意味においてもあらためて認識されるべきでしょう。
二、
初期の『麦の会通信』を見ると、「反省」「償い」という言い方がよく出て来ます。その中で、「とらえなおし」ということを最初に提唱したのが飯田博久氏でした。「反省」『償い』ということから更に、何を基準とした、何のための反省、償いであるのかをはっきりさせていくものとして、一とらえなおし」ということがあったと思います。それは、まず事実ありのままに向き合うことであり、新しい自己への具体的な第一歩につながるものでした。そしてそれは口先だけの『反省』でごまかしたり逃げたりできないものでした。
この飯田博久氏を排除しようとする動きから、以降4年間にわたって麦の会を悩まし、除名者と謹慎者を出した紛争が起こったのです。その発端は、飯田氏が他の仲間の「とらえ直しの援助」をしようとして反発されたことにありましたが、それが仲間を糾合しての排除行為にまで発展したところに、この問題の、それ以前の麦の会発足以来あった様々なトラブルとは違った性格があったといえると思います。
獄外(当時、東京定例会)は、この排除行為には極力反対しました。
それは「不当な介入」「死刑囚の主体性の無視」と反発されました。
そして彼らは、その自分達の「主体性」が通らないのなら「会がつぶれてもよい」とさえ言いきり、「主導権」をとろうと会運営を混乱させ続けた末、批判されて退会した会員、除名された会員が今度は「排除はいけない」という論理を使って、外から「反麦活動」を開始したのです。
このかんの過程が単なるトラブルとは異なるという意味は、麦の会にとって、内部で死刑囚の真の「とらえ直し」という事が提起されたことをめぐって始まり、その解決には麦の会の、一死刑囚による死刑廃止運動」としての新たな脱皮がかかっていたといえるということです。
本当の意味での「反省・とらえ直し」というのは、そうたやすいことではありません。ありのままの自己に正面から向き合える人が、どれだけいるでしょうか。それはほとんどの場合、他者による一対一の、長期の忍耐強い援助によって一歩一歩前進する作業なのです。かつての麦の会運動でも、そういうことぬきにコトバだけの「反省」が語られることが多かったと思います。そうしたかたちでの「死刑囚アピール」や、「死刑囚の声」を発することが「死刑囚による死刑廃止運動」だと安易に考えられてこなかったでしょうか。
このことは、最初の麦の会の運動のつくり方が、各正会員が自分の裁判をはなれた所で結集する形をもっていたこととも関連しています。裁判は、死刑囚が事件に向き合い、その「とらえ直し」を裁判に活かし〈生き直す〉たたかいを展開する場です。ところが麦の会は、そうした裁判とは切り離された「運動」として出発しました。麦の会は、そうした死刑囚の生きる為のたたかいを獄外者が共に担う運動の核として、再編成されなければならない時期にきていると思います。それなしにかっての麦の会の二番煎じをやり、「反省、とらえ直し「をお題目のようにかかげても、そういう「運動」が死刑廃止に対して持つ役割は既に終わっていると言っていいでしょう。
三、
以前少し述べたように、このかんの事態には、獄外の市民の対応が、もう一つの主要な問題として出てきていることを、あらためて指摘したいと思います。 ある人(達?)は、「死刑囚が死刑囚を排除するな」と言い「排除された死刑囚」による反麦活動を、積極的に支援しました(現在はどうしてるか知りませんが)。
このかん、麦の会を再建しようと努力してきた現運営委員をはじめ麦の会正会員にとって、彼らのいう「死刑囚が死刑囚を排除するな」ということは、「死刑囚の運動の中では、意図的な運動のかく乱者がいても、排除してはいけない。その結果、運動が破壊されても、私の知った事ではない。」ということに等しいものでした。こんなことを「善艮なる市民」からおしつけられた上、ねじれた情報によって、確定した正会員の一部からも全く見当外れな見解が出され続けている現状(死刑確定者には、麦の会関係の文書は一切入らず、「反麦」文書は無制限に入ります。関係者には再三注意したのですが…)に、現正会員が「いい気なものだ」(佐川氏)と嘆くのも当然でしょう、さらに言えば、飯田氏排除策動以降の紛争の過程で、ある人達はその「消耗さ」を理由として、麦の会を離れたのでした。彼らは、紛争に悩みつつ「逃げる]訳にはいかずそれに直面して解決してきた現正会員を『切り捨てた』のではなかったのでしょうか。その彼らが、経過を理解しようともせず、問題を単なる「死刑囚同士のいざこざ]と勝手にきめつけて、「死刑囚は排除をするな」などと言う「いい気」さかげんこそが、問題なのです。
こうした困難な中で、麦の会は、「死刑囚による死刑廃止運動とは何か」を考え、また具体的に追求してきました。そのことは、『麦の会通信』の正会員の姿勢からうかがうことが出来ると思います。
もちろん、このかんの麦の会が最善の途をとってきたというつもりはありません。それは自分の目で見て、具体的に指摘してほしいと思います。そして「死刑囚」を本当に、意識面でも実際にも切り捨てることなく、「死刑囚の死刑廃止運動」を麦の会とともに育てていってください。 死刑が制度として廃止された時、私達の手にあるのは、「死刑囚と共に生きる」という事実なのですから。 (11月19日)
------------------------------------------------------------------------------
抜粋以上
【管理人より】
「一、」の文章までは、当時の死刑廃止運動や麦の会のことをよく知らなくても私達にとって教訓になる文章だと思いますが…「二、」以降は当時の麦の会内部のことがわからないと、よくわからない内容ですね なんだか、獄中者同士でイザコザがあったようで…
なんだか、獄中者同士でイザコザがあったようで…

↑『魔法陣グルグル』に出てくる、ドサクサ妖精
よく、一般市民(シャバの人達)が、犯罪者(獄中者)に、「反省しろ!反省しろ!」って、ナントカの1つ覚えみたいに言うけど…確かに、人を殺めたり犯したりしたら、“被害者にダイレクトに手を下した者”が反省したり、被害者と遺族に謝罪したりするのは当然なんだけど…。シャバの一般市民が獄中者(犯罪者)に対して抱くイメージも、マスコミから洗脳されてるに過ぎないし(マスコミからの情報が全部間違ってるとまでは言わないけど)、そして、マスコミだけじゃなく、子供の頃から見ている勧善懲悪ドラマ・アニメから価値観を固定されてるだけかもしれない。「あの犯罪者は反省したようだ(変わったらしい)」とか偉そうに言ったとしても、元々、その犯罪者がどういう人で、どういう生い立ちだったのかも私達は知らないわけで。
リベラル系の人たちがツイッター等で訴え続けていますが、“『犯罪』っていうのは、私達が形作っている社会から生まれている現象だ”…ということは、認識しておくべき。
ネット掲示板見てると、保守系、特にネトウヨとか、極刑厨みたいな人達(自己責任主義者ら)が「こいつ1人が悪い!極刑に!」とか騒いでるけど、それを真に受けたりしないように。とくに、ネトウヨではない一般市民も、私の友人や家族を見てても、すぐに「死刑にしろ!もしくは、一生閉じ込めておけ!」って言うのを聞きますが…。
まあ、私も偉そうなこと言ってるけど…“直接、自分に加害行為を下してきた人間を集中的に憎み、恨む”という感情は持っている。私も“偏見ゼロの天使か神みたいな性格の人間”ではないし。そして、言うまでもないですが、私たちもいつ突然罪を犯してしまうかわからないということ。