【映画「市民ケーン」】 4/15(土)「毎日」が、直木賞作家長部日出雄(おさべ・ひでお)による、この映画の紹介と批評を載せていた。読んで首を傾げた。この御仁には世界的な名画「市民ケーン」がぜんぜん分かっていないと思われたからだ。
見出しに大きく「謎と嘘だらけの名作」とある。
読んで見ると映画冒頭で、病床の老人が「ローズ・バッド(バラのつぼみ)」と呟く場面が出て来る。その直後、付添看護婦が入ってくると老人(ケーン)はもう死んでいた。
そこで長部は、「出発点から重大な疑問があって最後まで合点がいかない。全篇のキーワードである<バラのつぼみ>という言葉はいったい誰が耳にしたのか…>と書いている。
「看護婦が部屋に入ってくるのは老人が息を引き取った後だ。つまり直前のつぶやきを聞いた人は存在するはずがない」と続けている。
分かってないなあ。書物が読者なくしては存在しないように、映画も観客なくしては存在しない。ここで天才オーソン・ウェルズは、観客そのものに主人公ケーンの最後の言葉を聞かせているのだ。この謎の言葉により、観客は映画そのものにのめり込んで行くのである。
それまでの映画は、スクリーンと観客が別々に存在していて、観客は第三者として物語を見ていた。オーソン・ウェルズは老人の最後の言葉を観客に聞かせることで、観客そのものが物語の一部になるという新しい技法を開拓したのだ。
それを「映画の観客以外は知る人のない言葉が客観的な事実のように扱われて一人歩きを始める」と決めつけるようでは、救いがたい御仁だ。
映画中の新聞王C.F.ケーンのモデルは実在の人物、ロサンゼルスの新聞王ハーストだ。俗受けする記事を満載して、刊行部数を伸ばし、「イエローペーパー(赤新聞)」と呼ばれた。
(D. ナソー, 井上廣美訳:「新聞王ハーストの生涯」, 日経BP社, 2002/9)
娘のパトリシア・ハーストは1970年代ロサンゼルスの超過激派の学生運動に加わり、投獄された。
城塞のようなケーンの館には「ザナドゥー」という名称がついている。これを長部は「フビライ・ハーンの城」になぞらえて理解して、「同時代の米国人なら大笑いするところであるらしい。」と書いている。
「ザナドゥー」はマルコ・ポーロ「東方見聞録」に出てくるモンゴル帝国(元)のフビライの夏の都(上都)の名前である。「市民ケーン」はハーストの妨害もあって、興行的には成功しなかった。だが当時のアメリカ人は教養のレベルが高く、マルコ・ポーロを読んでいたから、ザナドゥーを知っていた。米国人が大笑いするのは、よりによってこの大邸宅に黄色人種の都の名前を付けたからだろう。1941年は日米開戦の年である。(河出書房新社「世界探険全集1:東方見聞録」では“上都”と訳されている。)
「Rose Bud (バラのつぼみ)」というケーンの臨終の言葉の謎を解明するのが、全篇を貫く物語となっている。謎解きはラストシーンででなされる。
もうひとつ映画史上に特記すべきことは、この映画で初めて「パンフォーカス・レンズ技法」が使用されたということだ。演壇の上のケーンと会場のはるか奧にいる聴衆まで、すべて焦点が合っている。カメラがパンしても焦点が変わらない。写真ならフォーカスを絞ればパンフォーカスになるが、映画でこれをやるのは画期的なことだった。
「市民ケーン」は戦争のため、日本公開は1966(昭和41)年になった。手元にある「キネマ旬報1946〜1996ベスト・テン全史」という雑誌では、世界映画の1位が「七人の侍」、2位が「市民ケーン」、3位が「2001年宇宙の旅」となっている。別の資料では「市民ケーン」が1位になっている。
確かシアトル近郊にある、マイクロソフトのビル・ゲーツの邸宅にも「Xanadu」という名前がついていたはずだ。一代で成り上がった彼も「市民ケーン」に憧れていたのだろう。
「記事転載は事前にご連絡いただきますようお願いいたします」
見出しに大きく「謎と嘘だらけの名作」とある。
読んで見ると映画冒頭で、病床の老人が「ローズ・バッド(バラのつぼみ)」と呟く場面が出て来る。その直後、付添看護婦が入ってくると老人(ケーン)はもう死んでいた。
そこで長部は、「出発点から重大な疑問があって最後まで合点がいかない。全篇のキーワードである<バラのつぼみ>という言葉はいったい誰が耳にしたのか…>と書いている。
「看護婦が部屋に入ってくるのは老人が息を引き取った後だ。つまり直前のつぶやきを聞いた人は存在するはずがない」と続けている。
分かってないなあ。書物が読者なくしては存在しないように、映画も観客なくしては存在しない。ここで天才オーソン・ウェルズは、観客そのものに主人公ケーンの最後の言葉を聞かせているのだ。この謎の言葉により、観客は映画そのものにのめり込んで行くのである。
それまでの映画は、スクリーンと観客が別々に存在していて、観客は第三者として物語を見ていた。オーソン・ウェルズは老人の最後の言葉を観客に聞かせることで、観客そのものが物語の一部になるという新しい技法を開拓したのだ。
それを「映画の観客以外は知る人のない言葉が客観的な事実のように扱われて一人歩きを始める」と決めつけるようでは、救いがたい御仁だ。
映画中の新聞王C.F.ケーンのモデルは実在の人物、ロサンゼルスの新聞王ハーストだ。俗受けする記事を満載して、刊行部数を伸ばし、「イエローペーパー(赤新聞)」と呼ばれた。
(D. ナソー, 井上廣美訳:「新聞王ハーストの生涯」, 日経BP社, 2002/9)
娘のパトリシア・ハーストは1970年代ロサンゼルスの超過激派の学生運動に加わり、投獄された。
城塞のようなケーンの館には「ザナドゥー」という名称がついている。これを長部は「フビライ・ハーンの城」になぞらえて理解して、「同時代の米国人なら大笑いするところであるらしい。」と書いている。
「ザナドゥー」はマルコ・ポーロ「東方見聞録」に出てくるモンゴル帝国(元)のフビライの夏の都(上都)の名前である。「市民ケーン」はハーストの妨害もあって、興行的には成功しなかった。だが当時のアメリカ人は教養のレベルが高く、マルコ・ポーロを読んでいたから、ザナドゥーを知っていた。米国人が大笑いするのは、よりによってこの大邸宅に黄色人種の都の名前を付けたからだろう。1941年は日米開戦の年である。(河出書房新社「世界探険全集1:東方見聞録」では“上都”と訳されている。)
「Rose Bud (バラのつぼみ)」というケーンの臨終の言葉の謎を解明するのが、全篇を貫く物語となっている。謎解きはラストシーンででなされる。
もうひとつ映画史上に特記すべきことは、この映画で初めて「パンフォーカス・レンズ技法」が使用されたということだ。演壇の上のケーンと会場のはるか奧にいる聴衆まで、すべて焦点が合っている。カメラがパンしても焦点が変わらない。写真ならフォーカスを絞ればパンフォーカスになるが、映画でこれをやるのは画期的なことだった。
「市民ケーン」は戦争のため、日本公開は1966(昭和41)年になった。手元にある「キネマ旬報1946〜1996ベスト・テン全史」という雑誌では、世界映画の1位が「七人の侍」、2位が「市民ケーン」、3位が「2001年宇宙の旅」となっている。別の資料では「市民ケーン」が1位になっている。
確かシアトル近郊にある、マイクロソフトのビル・ゲーツの邸宅にも「Xanadu」という名前がついていたはずだ。一代で成り上がった彼も「市民ケーン」に憧れていたのだろう。
「記事転載は事前にご連絡いただきますようお願いいたします」












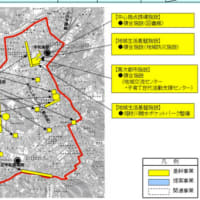
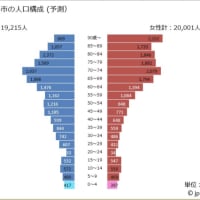



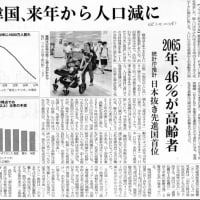










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます