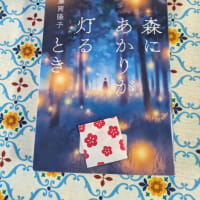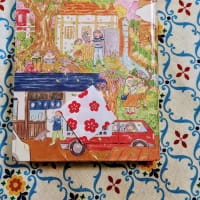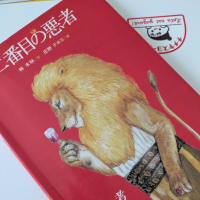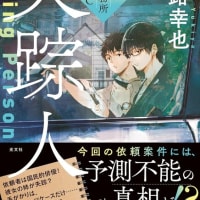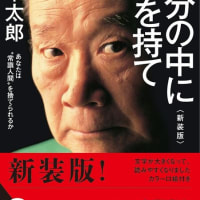「水車小屋のネネ」津村記久子
18歳で8歳の妹を連れて家を出る、というところから始まる。
これまた、しんどい、つらい話が続くのかと覚悟した。
でも、趣は違った。
住居と仕事を求めて移り住んだところには
ネネというヨウムがいた。
ヨウムという鳥を私は知っていた。
なんでだろう、と考えたら
多分、「月曜から夜ふかし」で出てきたような気がした。
1981年から10年ごとの40年間を淡々と優しく綴る小説だった。
蕎麦屋の夫婦はとても良い人たちだったし
妹の律の担任は、きちんとした思考の教師だった。
結局、親以外はみんないい人っていう皮肉ね。
大人になった律の
「恵まれた人生だと思った。
母親の婚約者に家から閉め出されて、
夜の十時に公園で本を読んでいた子供が、
大人になって自分の稼ぎで特急に乗って、輝く渓谷をぼんやり眺めている。
自分を家から連れ出す決断をした姉には感謝してもしきれないし、
周囲の人々も自分たちをちゃんと見守ってくれた。」という思いが
そうだよねえと思わずにはいられない。
私は律の担任の藤沢先生を
何処で読み誤ったのか、ずっと男性だと思っていた。
最後の最後に女性とわかって
「ええ、そおなの?」ってなる。
だめだ、こんな読み方してちゃだめだね。
いろんな、印象的な台詞が要所要所であって
いちいち感動して
ずるずる鼻水垂らしながら読んだのにね。
律の友達のお父さんがいう「子離れも悪くありません」とか
律が思う「杉子さんのような大人になりたい」とか
杉子さんも素敵な人だった。
研司くんという少年も良かったなぁ
律が本当に自然に勉強を教えてるのも
よかった。
知ることの喜びを知っている人が
その先の知ることを諦めてしまうのは辛い。
律の町の裏路地を歩いて、
家の裏側を見るのが好きっていうのも
とても、印象深かった。
私の娘にそういうところがある、と勝手に思ってる。
ということを再認識した。勝手に。
いろんな音楽と映画と役者の名前が出てきた。
日常に音楽を聴いたり、
映画を観たりすることのある生活は
いい、そういいんだなぁ。
ヨウムのネネは生き続けて、
18歳で8歳の妹を連れて家を出る、というところから始まる。
これまた、しんどい、つらい話が続くのかと覚悟した。
でも、趣は違った。
住居と仕事を求めて移り住んだところには
ネネというヨウムがいた。
ヨウムという鳥を私は知っていた。
なんでだろう、と考えたら
多分、「月曜から夜ふかし」で出てきたような気がした。
1981年から10年ごとの40年間を淡々と優しく綴る小説だった。
蕎麦屋の夫婦はとても良い人たちだったし
妹の律の担任は、きちんとした思考の教師だった。
結局、親以外はみんないい人っていう皮肉ね。
大人になった律の
「恵まれた人生だと思った。
母親の婚約者に家から閉め出されて、
夜の十時に公園で本を読んでいた子供が、
大人になって自分の稼ぎで特急に乗って、輝く渓谷をぼんやり眺めている。
自分を家から連れ出す決断をした姉には感謝してもしきれないし、
周囲の人々も自分たちをちゃんと見守ってくれた。」という思いが
そうだよねえと思わずにはいられない。
私は律の担任の藤沢先生を
何処で読み誤ったのか、ずっと男性だと思っていた。
最後の最後に女性とわかって
「ええ、そおなの?」ってなる。
だめだ、こんな読み方してちゃだめだね。
いろんな、印象的な台詞が要所要所であって
いちいち感動して
ずるずる鼻水垂らしながら読んだのにね。
律の友達のお父さんがいう「子離れも悪くありません」とか
律が思う「杉子さんのような大人になりたい」とか
杉子さんも素敵な人だった。
研司くんという少年も良かったなぁ
律が本当に自然に勉強を教えてるのも
よかった。
知ることの喜びを知っている人が
その先の知ることを諦めてしまうのは辛い。
律の町の裏路地を歩いて、
家の裏側を見るのが好きっていうのも
とても、印象深かった。
私の娘にそういうところがある、と勝手に思ってる。
ということを再認識した。勝手に。
いろんな音楽と映画と役者の名前が出てきた。
日常に音楽を聴いたり、
映画を観たりすることのある生活は
いい、そういいんだなぁ。
ヨウムのネネは生き続けて、
姉妹と共に音楽を鑑賞し、歌い
姉妹と共に歳を重ねていくのが
この物語の主人公って感じがした。
長い小説だった、読む人に寄り添うような小説だった。
ちょっと本を読むことに自信がでたよ。
あとがきの「本書が誰かの良い友となることを願います」
という津村さんの言葉がやさしい。
姉妹と共に歳を重ねていくのが
この物語の主人公って感じがした。
長い小説だった、読む人に寄り添うような小説だった。
ちょっと本を読むことに自信がでたよ。
あとがきの「本書が誰かの良い友となることを願います」
という津村さんの言葉がやさしい。