今日10月26日は「東京都文化財ウィーク2008」の特別企画事業「江戸を体感する~江戸の町人の暮らしと遊び」が、清澄庭園(きよすみていえん)の大正記念館で午後1時から行われました。往復葉書で申し込んだところ当選したので、訪れることにしました。

企画事業は二つあり、一つは講演会「江戸を語る~江戸の町人の暮らしと知恵~」。もう一つは落語「江戸を聞く」です。私は講演会に出席しました。
講師は高校教諭の河合敦先生。歴史作家、歴史研究家であり著書も数多く出しています。テレビ番組「世界一受けたい授業」のスペシャル講師でもあります。歴史の意外なエピソードや真実を分かりやすく説明してくれるので有名です。
43歳ということですが、大変に若々しく見え、弁舌爽やかで1時間半の授業は江戸の庶民の生活を話を楽しく語ってくれました。
「江戸の庶民の住まいは、五軒ほどの長屋の四畳半の1DKで家賃は7000円~15000円。押し入れさえなかった。そのため、床屋や風呂屋が社交場であった。しかし、夜はほとんど灯りがなく風呂屋も湯船に入るときは真っ暗だった。・・・・・」

公演が行われた大正記念館。終わった後は、時間があったので庭園内を巡ってみることにしました。

清澄庭園は江戸の豪商、紀伊国屋文左衛門の屋敷跡とも伝えられます。明治時代には三菱財閥の創業者岩崎弥太郎が社員の慰安や貴賓を招待する「深川親睦園」を造成したのが始まりであり、明治を代表する「回遊式林泉庭園」となっています。昭和54年に東京都の名勝に指定されました。これは入り口近くにある、しし落とし。

庭園は広い池があり3つの島があります。昔はすぐ脇を流れる仙台堀川から水を引いていたのですが、今は雨水ということです。

入り口方向から見た対岸には「涼亭」と呼ばれる数寄屋造りの建物があります。

庭園内で最も大きな築山が「富士山」で五月初旬には全山にツツジとサツキが美しく咲きます。

庭園内には名石、奇石が数多く配置されています。これらは岩崎家が自社の汽船で全国各地から集めたものです。伊豆磯石、生駒石、伊豆式根島石、備中御影石、京都保津川石・・・・写真は、紀州青石です。

その中でも、もっとも目立った石は佐渡赤玉石。「幻の石」と呼ばれ現在は採取が禁止されているそうです。

庭園の奥まったところに、有名な芭蕉の句「古池や かわづ飛び込む 水の音」の石碑があります。もとは、墨田川の川べりにあっものを護岸工事の際に移したものだそうです。
PENTAX K20D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO で撮影
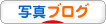 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。

企画事業は二つあり、一つは講演会「江戸を語る~江戸の町人の暮らしと知恵~」。もう一つは落語「江戸を聞く」です。私は講演会に出席しました。
講師は高校教諭の河合敦先生。歴史作家、歴史研究家であり著書も数多く出しています。テレビ番組「世界一受けたい授業」のスペシャル講師でもあります。歴史の意外なエピソードや真実を分かりやすく説明してくれるので有名です。
43歳ということですが、大変に若々しく見え、弁舌爽やかで1時間半の授業は江戸の庶民の生活を話を楽しく語ってくれました。
「江戸の庶民の住まいは、五軒ほどの長屋の四畳半の1DKで家賃は7000円~15000円。押し入れさえなかった。そのため、床屋や風呂屋が社交場であった。しかし、夜はほとんど灯りがなく風呂屋も湯船に入るときは真っ暗だった。・・・・・」

公演が行われた大正記念館。終わった後は、時間があったので庭園内を巡ってみることにしました。

清澄庭園は江戸の豪商、紀伊国屋文左衛門の屋敷跡とも伝えられます。明治時代には三菱財閥の創業者岩崎弥太郎が社員の慰安や貴賓を招待する「深川親睦園」を造成したのが始まりであり、明治を代表する「回遊式林泉庭園」となっています。昭和54年に東京都の名勝に指定されました。これは入り口近くにある、しし落とし。

庭園は広い池があり3つの島があります。昔はすぐ脇を流れる仙台堀川から水を引いていたのですが、今は雨水ということです。

入り口方向から見た対岸には「涼亭」と呼ばれる数寄屋造りの建物があります。

庭園内で最も大きな築山が「富士山」で五月初旬には全山にツツジとサツキが美しく咲きます。

庭園内には名石、奇石が数多く配置されています。これらは岩崎家が自社の汽船で全国各地から集めたものです。伊豆磯石、生駒石、伊豆式根島石、備中御影石、京都保津川石・・・・写真は、紀州青石です。

その中でも、もっとも目立った石は佐渡赤玉石。「幻の石」と呼ばれ現在は採取が禁止されているそうです。

庭園の奥まったところに、有名な芭蕉の句「古池や かわづ飛び込む 水の音」の石碑があります。もとは、墨田川の川べりにあっものを護岸工事の際に移したものだそうです。
PENTAX K20D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO で撮影



















