太田姫稲荷神社、古名は一口稲荷神社(いもあらいいなりじんじゃ)。
神田駿河台の地に、ひっそりと古びた小さな神社が建っていました。
しかし、この神社は縁起をひもとくと、霊験あらたかで、古い由緒があります。

①平安時代・・・承和6年(839)、百人一首で知られる小野篁(おののたかむら)は、えん罪で隠岐の島に流される。
隠岐の国にながされける時に、舟にのりていでたつとて、京なる人のもとにつかはしける
「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人のつり舟」 (古今和歌集)
途中、海は荒れ、雷鳴はとどろき、船は沈みそうになった。 篁は 衣冠を正して、船首に座り観音経を熱心に唱えた。すると、波間から白髪の老翁が現れ、「あなたは才能がたぐいまれな人だから、流刑されても都に呼び戻されるであろう。ただし疱瘡(ほうそう=天然痘・・・当時はとてもおそれられていた伝染病)を患えば一命が危うくなる。私は太田姫の命である。わが像を常にまつれば、この病にかかることはないであろう」とのお告げを言って姿を消した。
篁は一年後、都に呼び戻され、その後、参議(朝廷組織の最高機関である太政官の職の一つ)まで出世する。
彼は翁の像を自ら刻み、常に持っていたが、後に山城国 (京都)の南にある一口(いもあらい)の里に神社を造り祀った。
②室町時代・・・長禄元年(1457)、江戸城を築き、江戸の開祖として知られる太田道灌。その最愛の姫君が重い疱瘡にかかった。ある人が山城国の一口稲荷神社の話をした。道灌は、すぐに山城国に使いを送り、祈祷の一枝と幣(ぬさ)を持ち帰らせたところ、それを境に娘の重かった病気がぬぐうように治癒した。道灌は城内本丸に一社建立して篤く敬い、姫君も深く信心した。
ある時、この神が白狐となって現れ、「我この城の鬼門を守るべし」と託宣があったので、この社を鬼門に移して「太田姫稲荷大明神」と奉唱するようになった。
③江戸時代・・・慶長11年(1606)、徳川家康 は江戸城に入城後、江戸城の大改造を行い、城内にあったこの社を西丸の鬼門に当たる神田駿河台東側の急な坂に移した。そのため、この坂は一口坂(いもあらいざか)と呼ばれた。
代々の将軍はこれを崇拝し、修理造営を行った。この社は、駿河台の鎮守として数々の霊験があり、神威がいちじるしく、筆にも絵にも書き尽くすことは出来ないと古絵巻は伝えている。
④昭和時代・・・昭和6年(1931)、御茶ノ水駅から両国駅間の総武線が建設される事になり、一切の建築物が現在の地に移転されることになった。

白狐が飾られ、稲荷神社らしい雰囲気。

手水所にも歴史が感じられます。

この神社は、まさにビルの谷間にありますが、狭いながらも落ち着いた雰囲気があり、社務所も絵になります。
PENTAX K20D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC MACROで撮影
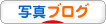 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
神田駿河台の地に、ひっそりと古びた小さな神社が建っていました。
しかし、この神社は縁起をひもとくと、霊験あらたかで、古い由緒があります。

①平安時代・・・承和6年(839)、百人一首で知られる小野篁(おののたかむら)は、えん罪で隠岐の島に流される。
隠岐の国にながされける時に、舟にのりていでたつとて、京なる人のもとにつかはしける
「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人のつり舟」 (古今和歌集)
途中、海は荒れ、雷鳴はとどろき、船は沈みそうになった。 篁は 衣冠を正して、船首に座り観音経を熱心に唱えた。すると、波間から白髪の老翁が現れ、「あなたは才能がたぐいまれな人だから、流刑されても都に呼び戻されるであろう。ただし疱瘡(ほうそう=天然痘・・・当時はとてもおそれられていた伝染病)を患えば一命が危うくなる。私は太田姫の命である。わが像を常にまつれば、この病にかかることはないであろう」とのお告げを言って姿を消した。
篁は一年後、都に呼び戻され、その後、参議(朝廷組織の最高機関である太政官の職の一つ)まで出世する。
彼は翁の像を自ら刻み、常に持っていたが、後に山城国 (京都)の南にある一口(いもあらい)の里に神社を造り祀った。
②室町時代・・・長禄元年(1457)、江戸城を築き、江戸の開祖として知られる太田道灌。その最愛の姫君が重い疱瘡にかかった。ある人が山城国の一口稲荷神社の話をした。道灌は、すぐに山城国に使いを送り、祈祷の一枝と幣(ぬさ)を持ち帰らせたところ、それを境に娘の重かった病気がぬぐうように治癒した。道灌は城内本丸に一社建立して篤く敬い、姫君も深く信心した。
ある時、この神が白狐となって現れ、「我この城の鬼門を守るべし」と託宣があったので、この社を鬼門に移して「太田姫稲荷大明神」と奉唱するようになった。
③江戸時代・・・慶長11年(1606)、徳川家康 は江戸城に入城後、江戸城の大改造を行い、城内にあったこの社を西丸の鬼門に当たる神田駿河台東側の急な坂に移した。そのため、この坂は一口坂(いもあらいざか)と呼ばれた。
代々の将軍はこれを崇拝し、修理造営を行った。この社は、駿河台の鎮守として数々の霊験があり、神威がいちじるしく、筆にも絵にも書き尽くすことは出来ないと古絵巻は伝えている。
④昭和時代・・・昭和6年(1931)、御茶ノ水駅から両国駅間の総武線が建設される事になり、一切の建築物が現在の地に移転されることになった。

白狐が飾られ、稲荷神社らしい雰囲気。

手水所にも歴史が感じられます。

この神社は、まさにビルの谷間にありますが、狭いながらも落ち着いた雰囲気があり、社務所も絵になります。
PENTAX K20D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC MACROで撮影




















私ブログを作ってみたいです!お話しした音来アルバムのURLをつけさせていただきます。ぜひご覧下さい。http://album.pentax.jp/175924178/albums/51955/ です。
これらの写真にコメントをつけて、ブログにしたら良いものができると思います。思い出も充実させて残すことが出来ます。
神田の散策でどのような写真を撮られたのかに、とても興味があります。