旅の5日目は、レマン湖の周辺を訪ねました。レマン湖は中央ヨーロッパで2つめに大きい湖。氷河湖で三日月湖になっています。
最大水深は310mもあります。
レマン湖というとスイスを代表する湖と思っていましたが面積は5分の2がフランス、5分の3がスイスです。
レマン湖はフランス語。英語、ドイツ語、イタリア語ではジュネーブ湖です。

シオン城はレマン湖の東にあるモントルーの岩山の上にある古城。どこか、写真で見たことがあるような気がします。
遊覧船は湖の西に位置するジュネーブからのものでしょうか。


シオン城から15Kmほど行ったところにある「ラウォー地区」は、「レマン湖畔にあるぶどうの段々畑と豊富な種類のワイン作りの技術」により、
2007年に世界遺産に指定されています。
このようなぶどうの段々畑はヨーロッパでは他に、いくつもあるでしょうから、風光明媚なことも、その要因になったと思います。
詳しいことは「めいすいの海外旅日記 スイス第5日」をご覧下さい。
![]() 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。

旅行4日目は、朝3時45分のモーニングコール。
ツェルマット(1620m)のホテルを4時30分に徒歩で出発、5時に近くにある地下ケーブルカーでスネガ展望台(2288m)へ。
そこからロープウェイでブラウヘルド(2571m)へ、さらにロープウェイを乗り継いででロートホルン展望台(3103m)に上りました。
この展望台はマッターホルン(4810m) を最も美しい角度で見ることが出来るといわれています。
朝、夏だというのに気温は氷点下。その時を待ち、6時に”朝焼けのマッターホルン”を写真に納めました。

ロートホルン展望台で、そのほぼ一時間ほどたった頃に、雲海に丸い虹が現れました。
日の出が後ろの山から始まった頃のようなのですが、珍しい事象のような気がします。

ロートホルン展望台からブラウヘルドに下り、「逆さマッターホルン」の見られるシュテリー湖へのハイキングすることになりました。
その道の両側は、高山植物のお花畑になっていました。上空はブラウヘルドとロートホルン展望台を結ぶロープウェイ。

シュテリー湖では、着いた当初は雲がかかり何も見えず、しばらくして雲が晴れて湖とマッターホルンは、
よく見えるようになったのですが、今度はさざ波が立ち、湖面にはマッターホルンの姿が映りません。
待つこと20分、湖面が鏡のように静かになり、見事な「逆さマッターホルン」を見ることが出来ました。
ハイキングで見た花々など詳しいことは「めいすいの海外旅日記 スイス第4日」をご覧下さい。

スイスの旅3日目は、サンモリッツから氷河特急に乗り、クールへ。
そこから、マイエンフェルトにある「アルプスの娘 ハイジ」の「ハイジ村」に行きました。
小説「ハイジ」の作者のハンナ・シュビリは、この周辺の風景の中を散歩しながら、着想を得たと言われています。
ハイジの絵は、日本のアニメとはちょっと異なっています。

村の入り口には、「ハイジの泉」があります。

しばらく田園風景の中をを歩いて行くと「ハイジの家」があります。
これは古い民家に手を加え、内部を”ハイジの博物館 ”としたものです。

仲良しのハイジとペーターの人形が飾られた部屋。

こちらは屋根裏部屋。奥の女性は見学者。

1880年に書かれた小説「ハイジ」は、世界各国で翻訳され累計出版部数は5000万部以上。
各国の言葉で翻訳された本が飾られていました。
詳しくは、「めいすいの海外旅日記 第3日」をご覧下さい。
ベルニナ線のモルテラッチ駅から巨大なモルテラッチ氷河を間近に見られるハイキングをしました。

駅を出発して、すぐのところの岩に赤いペンキで1878と書いてあるのは132年前には、ここまで氷河があったことを意味しています。
温暖化の影響もあって、氷河が後退に後退を続けている事が実感できます。

途中には高山植物のお花畑がつづき、楽しむことが出来ます。

こちらはヤナギラン。

わずかに上りの道を50分ほど歩いて氷河の先端にたどり着きました。帰りは40分ほどかかりました。
氷河の先端は絶えず変化していて、添乗員のAさんが2~3週間前に来たときには、表面は灰色のまま、崩れてはいなかったとのことです。
また去年に比べると、この氷河は50mは後退してしまっているそうです。
この氷河も環境を守らなければ消失してしまうのかという思いにさせられました。
他に咲いていた高山植物など、詳しいことは「めいすいの写真日記 2日目」をご覧下さい。
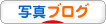 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。

駅を出発して、すぐのところの岩に赤いペンキで1878と書いてあるのは132年前には、ここまで氷河があったことを意味しています。
温暖化の影響もあって、氷河が後退に後退を続けている事が実感できます。

途中には高山植物のお花畑がつづき、楽しむことが出来ます。

こちらはヤナギラン。

わずかに上りの道を50分ほど歩いて氷河の先端にたどり着きました。帰りは40分ほどかかりました。
氷河の先端は絶えず変化していて、添乗員のAさんが2~3週間前に来たときには、表面は灰色のまま、崩れてはいなかったとのことです。
また去年に比べると、この氷河は50mは後退してしまっているそうです。
この氷河も環境を守らなければ消失してしまうのかという思いにさせられました。
他に咲いていた高山植物など、詳しいことは「めいすいの写真日記 2日目」をご覧下さい。

ベルニナ鉄道のディアボレッツァ駅からロープウェイで20分ほど上がったところにディァボレッツァ展望台(2944m)があります。
そこから見るベルニナの4000m前後の山々が行儀良く並ぶ様子は圧巻です。左手に隠れてはいますがビッツ・バリュー(3905m)、その右隣にベラヴィスタ(3922m)、中央に主峰ビッツ・ベルニナ、右隣はビッツ・モルテラッチ(3751m)です。

主峰ビッツ・ベルニナの前で記念写真を撮りました。

ビッツ・バリューとその右のベラヴィスタの足下から流れ出るのはベルス氷河です。
その氷河はモルテラッチ氷河に合流します。
冬場はこれらの氷河の上を滑り降りると10Km ものダウンヒルコースになるといいます。
スイスやイタリアのアルペン・スキー選手の実力が高いのも頷けます。

展望台の建物の窓は大きなガラスでこれらの山々が映っています。
中には山を撮さずにガラスに映る山と自分たちの姿をカメラに納めている人もいました。
詳しくは「めいすいの海外旅日記 第2日」をご覧下さい。


ベルニナ線の路線図

旅の始まりは、サンモリッツからレーティシュ鉄道ベルニナ線に乗り、途中のディアボレッツァ駅でおりロープウェイでディアボレッツァ展望台へ。
そこからスイス東部のベルニナアルプスの主峰ビッツ・ベルニナ(4048m)などの山々を眺望します。
再びベルニナ線に戻り、終点のイタリア、ティラノまで行き昼食をとります。
今度は、元来た路線を引き返し、途中のモルテラッチ駅で「モルテラッチ氷河へのハイキング」を行い、サンモリッツに戻るという行程です。
つまり、世界遺産になっている「レーティシュ鉄道ベルニナ線とその周辺」を全線、往復するツァーでした。
上の写真はモルテラッチ駅に入ってくるベルニナ線の列車。

サンモリッツ駅を出て、しばらくすると右手にベルニア・アルプスの山々が見えてきます。
右手前がビッツ・ロゼック(3937m)、左手にビッツ・ベルニナ(4049m)、さらにはベルス氷河も見えてきます。
間近に初めて見るアルプスの山々と氷河は迫力十分です。

車窓からは、氷河で出来たU字谷や氷河湖の雄大な景色が広がります。

ところで、レーティシュ鉄道ベルニナ線は今年で開業100周年です。
車内には路線の中のハイライト、オープンループ橋のポスターが貼ってあります。

この高低差を解消するための橋、オープンループ橋に近づくと車内は写真を撮ろうとする人のために騒然とします。
走っている車内から写真を撮るの大変ですし、ましてどのような風に現れるかも分かっていないので集中が必要です。
「上手く撮れなかった」と嘆く声も・・・。私は何とか撮れました。撮れなかった人も帰りにもう一度チャンスがあります。
帰りの車内では、私はこの風景をビデオに収めました。
詳しくは「めいすいの海外旅日記 第2日」をご覧下さい。
7月15日から24日までの10日間、H社のパッケージツァーでスイスを旅しました。
天候に恵まれ、ツァーの人たちにも恵まれ、楽しい旅をすることが出来、スイスの素晴らしい景観を堪能しました。
その内容を十回程度に綴っていく予定です。まずは、そのあらましから・・・。

旅の目的の一つはアルプスの4大名峰、マッターホルン、ユングフラウ、モンブラン、ビッツ・ベルニナを各展望台から眺めることです。
写真は「モンブランの夕焼けと半月」。シャモニーの宿泊したホテルの部屋の窓から撮影。モンブラン ( 4810m ) は中央の奥の丸い形の白い峰。

もう一つは、美しい高山植物が咲き乱れるアルプスの高原をハイキングすることです。
写真は「シュテリー湖に写る逆さマッターホルンと羊たち」。ブラウヘルドとシュテリー湖間のハイキングは3 km の2時間でした。
この湖に着いたときにはうっすらと雲がかかっていました。雲がようやく切れると湖面には、そよ風でさざ波が立ち、
マッターホルンの姿が映りませんでした。しかし、驚いたことに、しばらくすると湖面は鏡のようになりました。

ハイキングの途中に咲いていた「エーデルワイスの花」。6、7輪咲いていました。数が少なく探すのは大変です。


もう一つはスイスの4つの世界遺産を訪れることです。
写真は「ラヴォー地区」。「レマン湖畔に広がる丘陵地帯の葡萄畑」。レマン湖とアルプスと葡萄農家の小さな村の美しい風景。
ローマ時代までさかのぼる古いワイン作りの伝統が評価され、2007年に世界遺産に登録されました。

最後の一つは、スイスの4つの絶景列車、氷河特急 、ベルニナ線、ユングフラウ鉄道、ロートホルンSL鉄道に乗車することです。

私たちは、サンモリッツからクールまで世界一遅い(時速35Km)速度で走る氷河特急に7月17日に乗りました。

氷河特急のサンモリッツとトゥージス間は「アルブラ線と周辺の景観」として世界遺産に登録されています。
写真は89mの高さと42mのカーブのソリス橋を渡る私たちの乗った「氷河特急」。
「氷河特急の事故」
私たちが帰国途中の7月23日正午頃、ツェルマットとアンデルマット間で氷河特急の脱線事故が起き、
日本人一人が亡くなり日本人やその他、多くの方々が負傷をされました。
私たちの乗ったコースとは異なるのですが、同じ会社の同じ型の列車でしたので、とても驚きました。
お亡くなりになった方のご冥福をお祈りするとともに、怪我をされた方々に対し心からお見舞い申し上げます。
詳しくは「めいすいの海外旅日記」をご覧下さい。
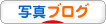 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
天候に恵まれ、ツァーの人たちにも恵まれ、楽しい旅をすることが出来、スイスの素晴らしい景観を堪能しました。
その内容を十回程度に綴っていく予定です。まずは、そのあらましから・・・。

旅の目的の一つはアルプスの4大名峰、マッターホルン、ユングフラウ、モンブラン、ビッツ・ベルニナを各展望台から眺めることです。
写真は「モンブランの夕焼けと半月」。シャモニーの宿泊したホテルの部屋の窓から撮影。モンブラン ( 4810m ) は中央の奥の丸い形の白い峰。

もう一つは、美しい高山植物が咲き乱れるアルプスの高原をハイキングすることです。
写真は「シュテリー湖に写る逆さマッターホルンと羊たち」。ブラウヘルドとシュテリー湖間のハイキングは3 km の2時間でした。
この湖に着いたときにはうっすらと雲がかかっていました。雲がようやく切れると湖面には、そよ風でさざ波が立ち、
マッターホルンの姿が映りませんでした。しかし、驚いたことに、しばらくすると湖面は鏡のようになりました。

ハイキングの途中に咲いていた「エーデルワイスの花」。6、7輪咲いていました。数が少なく探すのは大変です。


もう一つはスイスの4つの世界遺産を訪れることです。
写真は「ラヴォー地区」。「レマン湖畔に広がる丘陵地帯の葡萄畑」。レマン湖とアルプスと葡萄農家の小さな村の美しい風景。
ローマ時代までさかのぼる古いワイン作りの伝統が評価され、2007年に世界遺産に登録されました。

最後の一つは、スイスの4つの絶景列車、氷河特急 、ベルニナ線、ユングフラウ鉄道、ロートホルンSL鉄道に乗車することです。

私たちは、サンモリッツからクールまで世界一遅い(時速35Km)速度で走る氷河特急に7月17日に乗りました。

氷河特急のサンモリッツとトゥージス間は「アルブラ線と周辺の景観」として世界遺産に登録されています。
写真は89mの高さと42mのカーブのソリス橋を渡る私たちの乗った「氷河特急」。
「氷河特急の事故」
私たちが帰国途中の7月23日正午頃、ツェルマットとアンデルマット間で氷河特急の脱線事故が起き、
日本人一人が亡くなり日本人やその他、多くの方々が負傷をされました。
私たちの乗ったコースとは異なるのですが、同じ会社の同じ型の列車でしたので、とても驚きました。
お亡くなりになった方のご冥福をお祈りするとともに、怪我をされた方々に対し心からお見舞い申し上げます。
詳しくは「めいすいの海外旅日記」をご覧下さい。
夏休みとして10日間のスイスへの旅  に今日から出発します。海の日、土日が入り休暇の取得は6日間。
に今日から出発します。海の日、土日が入り休暇の取得は6日間。
このため「めいすいの写真日記」は、しばらくお休みしますが、帰国後この旅行記を本欄に連載するつもりです。
良い写真を撮ってきたいと思っています。よろしく

今回の旅行はH社のパッケージツァー、今回は自由時間も少なく、お任せツァーになりました。

ガイドブックは、書店で購入したものと旅行社でもらったものを航空機の中やホテルの部屋で読んで予習する予定です。
いつも旅行の際には、昔の試験勉強と同じように一夜づけです。

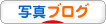 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
 に今日から出発します。海の日、土日が入り休暇の取得は6日間。
に今日から出発します。海の日、土日が入り休暇の取得は6日間。このため「めいすいの写真日記」は、しばらくお休みしますが、帰国後この旅行記を本欄に連載するつもりです。
良い写真を撮ってきたいと思っています。よろしく


今回の旅行はH社のパッケージツァー、今回は自由時間も少なく、お任せツァーになりました。

ガイドブックは、書店で購入したものと旅行社でもらったものを航空機の中やホテルの部屋で読んで予習する予定です。
いつも旅行の際には、昔の試験勉強と同じように一夜づけです。



京都駅に着き、新幹線で東京へ帰る前に夕食を取ることにしました。
地下街「PORTA」にある京風ラーメンの「麺屋 甘心堂(かんじんどう)」(075-344-3647)という店が目に止まったので入ることにしました。

頼んだのは「柚子切特製つけ麺」(850円)。
柚子切麺は「和の食の伝統、更級そばの柚子切そばを中華麺で表現した、上品でさわやかな柚子の香りの自家製の柚子練り込み麺」。
スープは「薩摩若シャモの丸鶏をベースに、老鶏を丸ごとミンチにしたものを加えて煮出し、仕上げに鰹、鯖の厚削り節を加えた重層型和風スープ」。
香り油は「良質のオリーブオイルから造られている香り高い特製香味油です。オリーブオイルは通常の動物性オイルよりも融点が低く、
サラリとしており、体に良いオレイン酸を多く含み、コレステロール低下に役立つ」と色々な説明書きがありました。
麺には東寺揚(えびのすり身を湯葉で包んで揚げたもの)、焼豚、煮卵半分などが載っていました。
柚子の香りがかすかに漂い、「京の麺屋」というにふさわしい、さっぱりとした和風のつけ麺で、好感が持てました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影


世界遺産である「竜安寺」。臨済宗妙心寺派の禅寺です。応仁の乱の東軍の総帥であった細川勝元が1450年に創建しました。
応仁の乱(1467-1477)といえば、世の中が乱れに乱れて京都中が焼け野原になってしまったと学んだことがあります。
当然のことながら竜安寺も、この時に消失し、1488年に再建されました。
竜安寺といえば、石と白砂で造られた枯山水の方丈庭園が世界的に有名です。幅22m、奥行き10m の広さです。
廊下に座って石庭を眺めると限りなく広い大海と大きな山々を感じてくるのが不思議です。

写真をクリックすると拡大します。 (1788×400 ピクセル)

こちらは背後の客間のふすま絵です。

龍安寺の南側は回遊式庭園になっていて、その中心に広大な鏡容池(きょうようち)があります。この池には蓮の花がきれいに咲いていました。

この池の岩の上に大きな亀も二匹いました。動かないので彫像かと思ってしまいます。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影


久しぶりに世界遺産となっている金閣寺を訪れて、とても懐かしく金閣寺を見ることが出来ました。
ところで、私の若いときによく読んだ三島由紀夫の小説「金閣寺」。その中には、金閣寺を描いた美しい文体が散りばめられ、実物の金閣寺と同じように、あるいはそれ以上に「金閣寺の美」に感動したものでした。その一部をここ載せることにします。
夜空の月のように、金閣は暗黒時代の象徴として作られたのだった。そこで私の夢想の金閣は、その周囲に押し寄せている闇の背景を必要とした。闇の中に、美しい細身の柱の構造が、内から微光を放って、じっと物静かに座っていた。人がこの建物にどんな言葉で語りかけても、美しい金閣は、無言で、繊細な構造をあらわにして、周囲の闇に耐えていなければならぬ。
私はまた、その屋根の頂に、長い歳月を風雨にさらされてきた金銅の鳳凰を思った。この神秘的な金色の鳥は、時もつくらず、羽ばたきもせず、自分が鳥であることを忘れてしまっているにちがいなかった。しかしそれが飛ばないようにみえるのはまちがいだ。ほかの鳥が空間を飛ぶのに、この金の鳳凰はかがやく翼をあげて、永遠に時間の中を飛んでいるのだ。時間がその翼を打つ。翼を打って、後方に流れていく。飛んでいるためには、鳳凰はただ不動の姿で、眼を怒らせ、翼を高くかかげ、尾羽をひるがえし、いかめしい金色の雙の脚を、しっかと踏んばっていればよかったのだ。
そうして考えると、私には金閣そのものも、時間の海をわたってきた美しい船のように思われた。美術書の語っている「壁の少ない、吹き抜けの建築」は、船の構造を空想させ、この複雑な三層の屋形船が臨んでいる池は、海の象徴を思わせた。金閣はおびただしい夜を渡ってきた。いつ果てるともしれぬ航海。そして、昼の間というもの、この不思議な船はそしらぬ顔で碇を下ろし、大ぜいの人が見物するのに任せ、夜が来ると周囲の闇に勢いを得て、その屋根を帆のようにふくらませて出帆したのである。
・・・・・ 三島由紀夫 「金閣寺」
小説「金閣寺」は、日本文学を代表する傑作の一つ。金閣寺は1950年(昭和25年)7月に放火により消失しましたが、その犯人、金閣寺の美にとりつかれた「私」こと林養賢を描いています。「三島の美学」と賞賛された三島由紀夫の数多くの作品群の中でも、この部分はとりわけ美しいと思います。
なお、現在の金閣は、1904年(明治37年)から1906年(明治39年)の解体修理の際に作成された旧建物の詳細な図面や写真・古文書・焼損材等の資料を基に再建されました。ただ、消失前の金閣寺は、国宝でしたが、金箔がほとんど剥げ落ちた質素な風情で、今のように光り輝く姿ではなかったとのことです。

帰り際に金閣寺の鐘楼に立ち寄り、鐘突き料を払って鐘を突き、煩悩を払って出ることにしました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影

金閣寺と竜安寺、仁和寺の世界遺産を結ぶ「きぬかけの路」に面してある「権太呂 金閣寺店」( 京都市北区平野宮敷町26 TEL 075-463-1039 )。
京風料理の店ですが、そばの美味しい店でもあります。 今回の旅では、ここで昼食を取ることにしました。

「湯葉あんかけそば」( 1300円 )は湯葉の下にかまぼこ、たけのこ、椎茸などの具材が入ったあんかけそば、ショウガの味も良く利いて、
さっぱり味の美味しいそばです。

こちらは「にしんそば御膳」( 1500円 )。身欠きにしんの入った「にしんそば」は京都名物です。
ニシンの干物である身欠きニシンは保存食。その昔、山間地にある京都などでは貴重なタンパク源でした。
京都では、特に年越しそばというとにしんそばになるようです。
右が具の入った豆腐と左は混ぜご飯。京都らしい食事を食べることが出来ました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影


世界遺産であり、国宝でもある「銀閣寺」。正式名は東山慈照寺です。室町幕府第八代将軍、足利義政が創立しました。
第三代将軍、足利義満が創立した鹿苑寺の金閣舎利殿を模して造営したものです。
この写真の観音殿を「銀閣」と呼び、寺全体を「銀閣寺」と呼ぴます。これは、中学や高校の日本史で誰もが学んだ内容ですね。
なお、科学的調査により、創建当時から銀箔は貼られていなかったということですが、「銀閣」とよばれるのは諸説があるようです。
「銀閣」の前の石庭、円錐台の形をした造営物は「向月台」、平場の波の形をしたものは「銀沙灘」(ぎんしゃだん)と呼ばれます。
平成19年2月から行われていた大規模な修復工事が今年4月半ばに完了して、創建当時の美しい姿を見せてくれるようになりました。

この銀閣寺には、「東求堂」(とうぐどう)と呼ばれる、もう一つ国宝があるということを訪れて初めて知りました。
義政の持仏堂で、三間半四方の大きさです。池に面して建てられており、書院造りや茶室の源流となっているとのことです。

銀閣寺の庭は池泉回遊式庭園になっていて、庭園には苔で覆われた部分が広がっています。「苔寺」として知られる西芳寺を模したとのことです。
苔がこんなに見事に生えるのは自然が豊かだということでしょう。

奥の山道を登り、振り返ると銀閣寺の全景が見渡せ、その先に京都市街が広がっています。

この山道には、箱根空木(はこねうつぎ)の花が数カ所に咲いていました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影


「哲学の道」は、京都市左京区にある琵琶湖疎水に沿った小道。熊野若王子神社から銀閣寺まで約2km の道を歩きました。
歩き始めて半分のあたりまでは、緑が深く、とても自然が豊かです。
銀閣寺に近づくにつれて、店が多くなり俗化し、終わりの頃は、遊歩道部分も何故か閉鎖されているか所が多くなります。
下の写真は、熊野若王子神社からの出発地点にある「哲学の道」の石柱。
土曜日のお昼前の時間でしたが、人通りは意外に少なく、とても良い雰囲気でした。

哲学の道は、春は桜が美しく、秋はモミジなどの紅葉が美しいとのことですが、初夏の新緑もなかなかのものです。
ところどころにシャリンバイ (車輪梅)の花が咲いていて、目を楽しませてくれました。
 |
 |
疎水の水は澄んでいて、魚影も濃く、サギも姿を見せていました。
ここには、カワニナがいるためゲンジボタルが自生しているようです。

「哲学の道」は哲学者の西田幾太郎がこの道を歩きながら、思索にふけったことから、「思索の道」そして「哲学の道」となったとのことです。
この道の中間点付近に「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」という西田幾太郎の歌の石碑がありました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影
「 南禅寺 」 は臨済宗南禅寺派の大本山。京都五山および鎌倉五山の別格上位とされ、日本の全ての禅寺のなかで最も高い格式を持っています。

南禅寺 三門 。南禅寺の正門で高さが22mあります。上層部からは境内や京都市内が一望できて見事です。
歌舞伎の『楼門五三桐』(さんもん ごさんのきり)の中で、大泥棒の石川五右衛門は煙管を吹かして、「絶景かな、絶景かな。
春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両」という名科白を吐き、
夕暮れ時の満開の桜を悠然と眺めている場面が、この三門の屋上とのことです。

この三門の入り口への通路にある石碑。 「この門を入れば涼風おのづから」 杉洞
禅宗の高僧、ホトトギス派の同人で選者、門弟三千人といわれる人の句。

法堂 (はっとう)。 明治28年(1895年)焼失した後、明治42年(1909年)に再建されたもの。

南禅寺境内にある「水路閣」。琵琶湖疎水の事業の一環として建設された水道橋です。
明治23年の疎水開通とともに完成。古代ローマの水道橋を参考に設計された赤煉瓦の橋です。延長93.17メートル、幅4.06メートル、
水路幅2.42メートルで、今も毎秒2トンの水が流れ、用水として利用されています。優れた土木遺産といえるでしょう。
南禅寺には、国宝の「方丈」があり、見事な枯山水の庭園があるのですが入るのを躊躇してしまいました。今となっては残念なことをしました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影
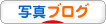 「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。
「にほんブログ村」人気ランキングに参加しています。バナー(左のボタン) をクリックしていただければ幸いです。

南禅寺 三門 。南禅寺の正門で高さが22mあります。上層部からは境内や京都市内が一望できて見事です。
歌舞伎の『楼門五三桐』(さんもん ごさんのきり)の中で、大泥棒の石川五右衛門は煙管を吹かして、「絶景かな、絶景かな。
春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両」という名科白を吐き、
夕暮れ時の満開の桜を悠然と眺めている場面が、この三門の屋上とのことです。

この三門の入り口への通路にある石碑。 「この門を入れば涼風おのづから」 杉洞
禅宗の高僧、ホトトギス派の同人で選者、門弟三千人といわれる人の句。

法堂 (はっとう)。 明治28年(1895年)焼失した後、明治42年(1909年)に再建されたもの。

南禅寺境内にある「水路閣」。琵琶湖疎水の事業の一環として建設された水道橋です。
明治23年の疎水開通とともに完成。古代ローマの水道橋を参考に設計された赤煉瓦の橋です。延長93.17メートル、幅4.06メートル、
水路幅2.42メートルで、今も毎秒2トンの水が流れ、用水として利用されています。優れた土木遺産といえるでしょう。
南禅寺には、国宝の「方丈」があり、見事な枯山水の庭園があるのですが入るのを躊躇してしまいました。今となっては残念なことをしました。
PENTAX K7 + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC で撮影









