俳句の表現法 ~切字「かな」の転換的用法~
永田満徳
「連体形+名詞かな」という表現は、比喩や擬人などと同じく、レトリックの一つと考えられるが、しかし、これまで何ら明確な名称を付けられていない。
「連体形+名詞かな」という句形には以下の俳句がある。
田一枚植ゑて立ち去る柳かな 松尾 芭蕉
さまざまの事おもひ出す桜かな 松尾 芭蕉
遠山に日の当たりたる枯野かな 高浜 虚子
武蔵野の空まさおなる落葉かな 水原秋桜子
傘もつ手つめたくなりし牡丹かな 富安 風生
道づれの一人はぐれしとんぼかな 久保田万太郎
さしいれて手足つめたき花野かな 赤尾 兜子
後ろにも髪脱け落つる山河かな 永田 耕衣
生涯を恋にかけたる桜かな 鈴木真砂女
松尾芭蕉や高浜虚子の有名な句を知っている私にとって、「連体形+名詞かな」の句形は特に違和感なく、むしろ好んで使う句形である。
例えば、私の『肥後の城』という一句集の中で、
象の鼻地に垂れてゐる残暑かな
ペンギンのつんのめりゆく寒さかな
ひたひたと闇の満ちくる螢かな
じんわりと夜の迫り来る蜥蜴かな
ペンシルの芯折れやすき夜学かな
なお、この句集は「文學の森大賞」を受賞したので、選考委員の方もこの句形に親しんでいたと言っても過言でない。
特に「阿蘇見ゆる丘まで歩く師走かな」は、坪内稔典氏も「李語刻々」(毎日新聞2021/12/14 東京朝刊)で普通に取り上げているので、何ら疑問を持つ句形ではない。
永田耕衣の句には「連体形+名詞」という別バージョンがある。
近海に鯛睦み居る涅槃像
「涅槃像」は「涅槃かな」という表現も成り立つ。
現に中西亮太の「足振つてスリッパ脱ぎし涅槃かな」という俳句がある。
「連体形+名詞かな」は「二物仕立て」であっても「一句一章」である。
みづうみの水のつめたき花野かな 日野 草城
は
みづうみの水のつめたし
花野
という二物の取合わせに対して、切字「かな」終助詞(やや強調)を持って来た場合は、「かな」は体言・連体形に付くので、
みづうみの水のつめたき花野かな
のように、「一句一章」の俳句になる。
さらに言えば、連用形で二物を繋げるやり方では、
北斎の波の逆巻き寒戻る 満徳
があり、同じく「一句一章」の俳句となる。
ちなみに、普通は「二物仕立て」と言えば「二句一章」である。しかし、「二物仕立て」で「一句一章」という俳句は意外とある。
夏草に機罐車の車輪来て止る 山口誓子
山口誓子の俳句は、「夏草」と「機罐車の車輪」という二つの言葉から成り立っていて、「一句一章」と言っても、「二物仕立て」である。
もちろん、「一物仕立て」の「連体形+名詞かな」の句形は本来の句形である。
狙ひうちしたるやうなる夕立かな
「夕立」が狙ひうちする
一点を見つめてゐたる案山子かな
「案山子」が一点を見つめる
首もたげ太古をのぞく蜥蜴かな
「蜥蜴」が首もたげ太古をのぞく
いずれも、『肥後の城』から抜き出した句であるが、「かな」が主語に付く「一物仕立て」の「一句一章」の句形は特に意味のずれはなく、特に問題はない。
今、問題にしているのは「二物仕立て」で「連体形+名詞かな」という句形である。
「二物仕立て」の「連体形+名詞かな」は、二物の言葉を繋げ、「切れ」を最後に持って来るとともに、感動の中心を表す切字「かな」を使いたい時にこの句形になるのである。
「二物仕立て」の「連体形+名詞かな」という句形を意識的に使っているのは岸本尚毅である。『舜』(花神社、1992年)から「連体形+名詞かな」の用法を拾ってみる。
本あけて文字の少なき木槿かな 「文字」と「槿」
久々に青空を見し秋刀魚かな 「青空」と「秋刀魚」
避雷針高々とある海鼠かな 「羅針盤」と「海鼠」
「連体形+名詞かな」という句形は、一見無関係に思える、大胆な二物の言葉を取合せて、「切れ」を最後に持って来るため、または感動の中心を置きたいための切字「かな」を使う俳句表現法と言ってよい。
手をつけて海のつめたき桜かな 岸本尚毅 『舜』所収
「海」と「桜」という二物の取合せ
「手をつけて海のつめたき」と「桜かな」の関係を述べようとすると、例えば、若杉朋哉が「手をつけてみた春の海の冷たさと、そこから少し高いところに見える桜のひややかな美しさ」と鑑賞したように、二つの要素の対比、対照の効果として読み取るしかない。
しかし、両者の関係を敢えて意味として取ろうとすれば、別の言葉に言い換えるときに用いる「〜というところの〜」という言葉を補って読むと幾分理解出来る。 つまり、「 手をつけて海のつめたいというところの桜だな」という意味になる。
いずれにしても、「連体形+名詞かな」という句形は、「省略」というよりも、「転換」に近く、「句切れ」がなく、切字の「かな」で言い切ってしまう句法である。
従って、「切字『かな』の転換的用法」と名付け、下記のように定義する。
「かな」の転換的用法とは、二つの異なった二物仕立ての言葉を連体形によって繋ぎ、「かな」で言い切ってしまう俳句表現法である。
なお、攝津幸彦に
路地裏を夜汽車と思ふ金魚かな
という俳句あるが、「露地裏」、「夜汽車」、「金魚」というふうに、三つの物を取合せて、「一句一章」としている。
「路地裏を」の句もまた、「連体形+名詞かな」という句形を取っていて、切字「かな」の転換的用法の一つと数えていいだろう。
















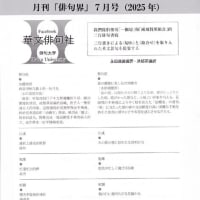
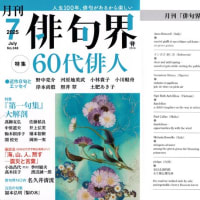


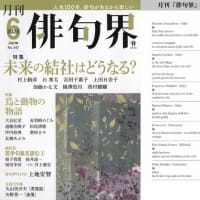





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます