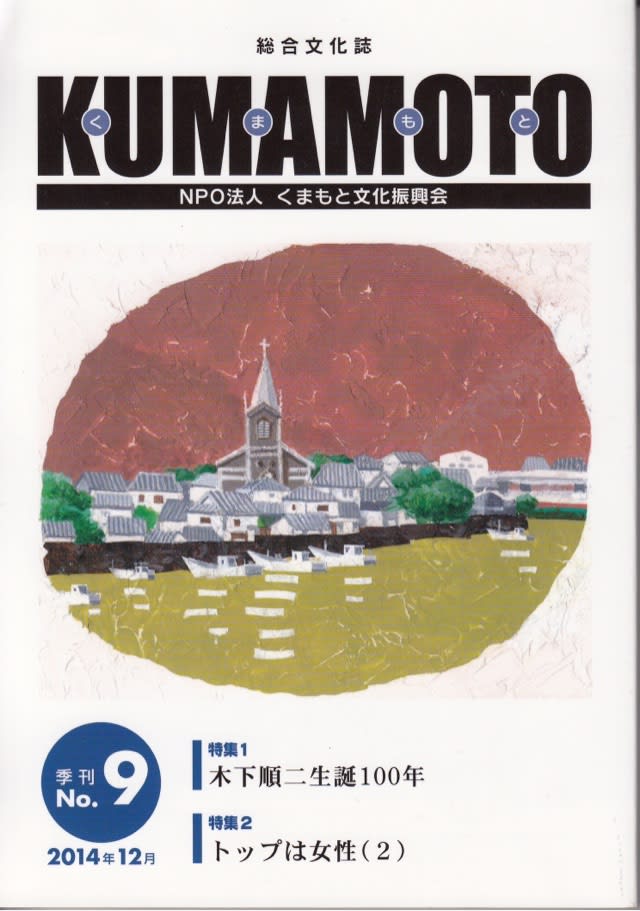NPO法人 くまもと文化振興会
2014年12月15日発行
《はじめての夏目漱石「草枕」》
〈俳句の方法〉を駆使した俳句的小説
永田満徳
始めに 俳句=漱石文学の底流
夏目漱石は熊本時代、多くの俳句を作り、全体の四割、つまり千句あまりを作っている。漱石文学における、その俳句の影響については一過性のものとは考えられない。漱石文学の底流に流れていて、漱石文学に滋養を与えていると考える。小森陽一氏が「昔」(『永日小品』)を取り上げて、俳句が記憶装置として働いて、文章を書いたのではないかと述べている。阿蘇の旅の経験を元にした「二百十日」にしても、小天に訪れた経験を活かした「草枕」にしても、その折りに詠んだ俳句が背景にあることは周知の事実である。
一 子規派の潮流の一派としての俳句的小説
「草枕」は雑誌『新小説』(春陽堂・明治三十九年九月一日発行)に発表された。この時期の俳句界の状況は正岡子規亡き後、子規の後継者争いの様相を呈してくる。河東碧梧桐が『日本』俳句欄を、高浜虚子が『ホトトギス』を受け持つわけだが、四十年頃から碧梧桐が従来の五七五調の形にとらわれない新傾向の句を発表するようになり、虚子が碧梧桐派の行きすぎを尻目に、大正元年頃から〈守旧派〉の立場を明らかにして俳壇に復帰し活動を開始する。こうした子規派の分裂、抗争の中で、漱石は漱石なりの俳句観を示す必要があった。夏目漱石自身が「草枕」を「余が『草枕』」で「俳句的小説」と宣言することによって、後継者の高浜虚子や河東碧梧桐らとは違った子規派の潮流を歩み始めたことを意味する。
寺田寅彦が「夏目漱石先生の追憶」の中で漱石の言として述べているように、まさしく「俳句はレトリックの煎じ詰めたもの」である。漱石がどれだけ「俳句の方法」(レトリック・以下省略)に習熟していたかは、漱石俳句に対して、門下生と呼ばれる寺田寅彦・松根豊次郎・小宮豊隆が標語している『漱石俳句研究』が参考になる。そこには、「写生」「季語」「取り合せ」「省略」「デフォルメ」「連想」「擬人化」「同化」などの、あらゆる「俳句の方法」が使われている。
いみじくも、画工は小説の読み方として、「初から読んだつて、仕舞から読んだつて、いゝ加減な所をいゝ加減に読んだつて、いゝ訳ぢやありませんか」[九章]と那美に教える。これを俳句的観点からみると、この小説の読みが決して人を食っていないことがわかる。一章、一場面が俳句の一句に近い世界と考えたらどうだろうか。「草枕」でよく話題になる峠の茶屋の場面、風呂場の場面、髪結床の場面、鏡が池の場面、観海寺の場面、最後の場面など、その代表的な場面が鮮やかに脳裏に浮かぶのはそれら場面が俳句の一句のような世界を持っているからである。ということは、「草枕」の一章、一場面は、それぞれが独立した世界であるということである。もしそうであれば、「草枕」そのものがどこから、どこを読んでもいいことを証明した小説ということになる。この常識を覆す読み方ができる小説を書くことはかなり実験的なものであったに違いない。それを可能にしたのが「俳句の方法」を縦横に駆使したことにあったのである。
二 「草枕」における「俳句の方法」の主な使用例
写生=そもそも、「俳句の方法」の根本的なものは「写生」である。「写生」とは西洋画家中村不折に教わった正岡子規が俳句に応用したものである。「写生」が意味を持つのは、子規が、長編時評「明治二十九年の俳句界」で説いているように、「非情の草木」や「無心の山河」には「美を感ぜしむる」ものがあるからである。「草枕」の第一章の中で、すでに「わかる丈の余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ芝居は観て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げて居る。見たり読んだりする間丈は詩人である。」と出てきて、画工が「第三者の地位」で物を見るという基本姿勢を示している。この画工の「余裕のある第三者の地位」を言い換えるならば「第三者」の立場に置くことである。「草枕」で決まって問題視される「非人情」は「第三者」の立場になることで、「不人情」とは似ても非なるものである。それは、「草枕」の中で、「非人情」と「不人情」とを使い分けられていることからもわかる。
季語=俳句では「季語」は「俳句の生命」(寺田寅彦)で、俳句は「季題を主題として詠ずる詩」(高浜虚子)と定義づけられるほど、必須の条件となっている。「草枕」では、現代の『歳時記』には〈春〉の項に載っていない季語もあるが、「季語」がこれでもか、これでもかと出てくる。画工自身が詠んだ俳句の「季語」を入れたとしても、これほど多くの「季語」を使っている小説は多くない。画工が「余が心は只春と共に動いて居る」〔六章〕と言い、〈春〉という季節をことさら強調している。特に俳句的小説「草枕」にとって、「季語」は作品の善し悪しを決めるうえで重要な要素である。「季語」の面からいえば、那古井の旅は四季の内ではどうしても〈春〉でなければならなかった。多くの〈春〉の季語を散りばめた「草枕」は〈春〉という季節の普遍的な情緒、美意識のエッセンスを堪能させてくれる。その点で、〈春〉という「季語」の選択は間違っていなかったというべきである。
取り合せ=俳句の実作経験のない方には理解し難いものの一つに「取り合せ」がある。俳句という韻文が散文と区別される方法である。特に、芭蕉が強く唱えている〈雅〉と〈俗〉との対比が「取り合せ」の基本中の基本である。「草枕」ではその代表が「今わが親方は限りなき春の景色を背景として、一種の滑稽を演じて居る。」〔五章〕とあるように、「春」の景色と髪結床の親方の「滑稽」との関係も一種の「取り合せ」である。章単位でも、観海寺の場面を〈雅〉とすれば、その髪結床の場面は〈俗〉ということになる。〈雅〉の世界だけでは古色蒼然でありすぎるが、そこに〈俗〉なる物を取り合せることで、なんと生き生きとしてくるではないか。
省略=俳句は五・七・五という、わずか十七文字(十七音)の言葉が一篇の詩として独立するには言いたいことを抑えて、核心部分だけを表現する。冗漫さを取り除くことによって余韻を生み、読み手の想像力を引き出し、表現したいものを鮮明に浮かび上がらせるのが「省略」の効果である。「草枕」では第七章の「白い姿は階段を飛び上がる。ホヽヽヽと鋭どく笑ふ女の声が、廊下に響いて、静かなる風呂場を次第に向へ遠退く」、あるいは第九章の「女はすらりと立ち上る。三歩にして尽くる部屋の入口を出るとき、顧みてにこりと笑つた」といった終末部分は、いずれも「飛び上が」り、「立ち上が」った後、「風呂場を次第に向へ遠退」き、「部屋の入口を出る」といった感じで、気懸かりな立ち去り方をする。あたかも舞台劇のような、鮮やかな幕切れである。画工ならずとも、「茫然」となるのは致し方がない。この各章の終わり方はまさしく「省略」の方法が用いられているといえる。「草枕」はこれ以外の章でも例として挙げることができるので、この効果を十二分に考慮して書かれていると思われる。
同化=俳句の方法で最も難しいのは「同化」である。徹底した「写生」を通して、どれだけ対象と〈一体化〉することができるかどうかで、句境の深化が見て取れる。「草枕」において、「同化」の問題を考える場合、漱石の「余が『草枕』」で述べている次の文章は重要である。「中心となるべき人物が少しも動かぬのだから、其処に事件の発展しようがない」というものの、「草枕」にストーリー展開をもたらしているのは、画工という「観察する者の方が動いてゐる」主体が那美という「少しも動かない」対象に対して、「非人情」、あるいは「第三者」の立場でどれほど「同化」できたかである。「余が胸中の画面は咄嗟の際に成就した」〔十三章〕という有名ながあるとはいえ、あくまでも「画面」の「成就」であって、「十三章に亘って描かれるすべてが画工の心理のフィルタ越しでしか、那美という対象を見ることができなかった。
終わりに
従って、「草枕」は那古井の温泉場で、「非人情」という「第三者」の立場を通して、「御那美さん」という他者を理解しようとして、理解することができなかった他者了解不能の物語であると言ってよい。そこにこそ、人情世界の普遍性があって、この「草枕」の最大の魅力となっている。たとえ「草枕」が他者了解不能の物語で終ったにしても、多様な「俳句の方法」を小説に応用するといった「天地開闢以来類のない」(小宮豊隆宛書簡)小説にあえて挑戦し、子規の提唱した「美なる処のみ」(「俳諧反故籠」)を詠む俳句説に従って、「美を生命とする俳句的小説」(「余が『草枕』」)を仕立て上げた漱石の手腕はお見事である。漱石自身が「草枕」を「俳句的小説」と述べているのは嘘偽りのないことであると言っても差し支えがない。
(ながた みつのり/熊本近代文学研究会会員)