今日は私がTAをやっている、Utterback先生のDisruptive Technologyの授業を紹介。
授業では、イノベーションがどのように起こり、普及し、進化していくか、の普遍的な基本法則を学ぶ。
現代技術だけじゃなく、電球、ガラス工業、氷産業など、ボストン発の歴史的な技術を振り返って学ぶんだけど、
昔の技術からの学びが、現代の技術にも通じるところがたくさんあって、非常に面白い。
先週は、白熱電球の技術を振り返り、技術が進化や普及の過程に現代の技術との共通点を学び、
現代の技術に生かせる教訓を学ぶ。

当時の電球を見せて、電球の歴史を解説するUtterback先生。
右側のスクリーンに写ってるのは、テレコンで授業に参加してる学生。
1) 技術力だけでは勝てない。業界や消費者の動き方を変えないのは新技術普及の鍵
白熱電球を発明して、最初に発明した普及させたのはご存知エジソン。
1880年代の半ばの話だ。
ところがこの電球ってのは、発明したからってすぐ評価されて、わーって普及したわけではない。
当時、人々は長いこと、鯨油や灯油を燃やして燈すランプを使っていた。
それが巨大な天然ガス会社が、ガスのインフラを整備し、ガス灯に置き換わろうとしていた。
公共の施設だけでなく、家庭でもガス灯が使われ始めていた。
価格も、それまで使っていた鯨油や灯油に比べれば安いし、明るいから、人々はどんどんガス灯に移行していた。
白熱電球が発明されたのは、まさにこの頃なのだ。
ちょうど次世代DVDは、HD-DVDかBlurayかと争われていたように、、
次世代ランプは、ガスか電気かという争いが行われたわけである。
エジソンの一番の敵は、ガス会社だった。
この戦いに、エジソンは、消費者や業者の動きを出来るだけ変えないで普及させる方法をもって望んだ。
例えば、電球のソケットって、灯油機器のソケットにそっくり。
これはエジソンが、灯油ランプを使ってた人々が、同じ感覚でランプの交換が出来るように工夫したものだ、と言われる。
それに、灯油ランプと同じ形であれば、それまで灯油ランプを作っていた人たちに、電球を作ってもらうことが可能だ。
電球が普及しても、灯油ランプを作っていた人たちは失業せずにすむだろう。
灯油ランプ業界団体から、強い反対を受けずに技術をサポートしてもらうことが出来るだろう。
このように、消費者やサプライヤーなど、バリューチェーンの自分以外のプレーヤーの動き方を変えない工夫を凝らす、というのは技術を普及させる上で重要なポイントだ。
これは現代の技術でも同じことが言える。(注:追記)
例えば半導体では、長いことCISCと呼ばれる論理演算方式が使われていたが、半導体の規模が大きくなるにつれ、複雑性が増してきた。
そこでRISCと呼ばれる、簡略化された演算方式の半導体が開発された。
これは技術的には非常に優れたものだった。
ところが、RISCは、CISCと異なる言語のため、顧客は新しい言語を学ばなければRISCが使えない。
サプライヤーもRISCには新しい設計装置や製造装置が必要になり、新たな投資が必要だった。
CPUの周囲のチップなどを提供してた会社も、RISCに併せた対応チップの開発が必要になった。
そんなわけで、RISCによって、バリューチェーンの全てのプレーヤーが今までのCISCと異なる動き方と投資を要求されたので、結局RISCは限定的なところでしか普及しなかった。
このように、新技術によって、バリューチェーンの他のプレーヤーの負荷が出来るだけ少ないことは、技術普及に非常に大切な要素なのだ。
(追記)「はてな」の一部の人がCISC/RISCの話にこだわってるみたいなんで、続きを書いておく。
その後、演算容量が増えるにつれ、チップメーカーにとってはCISCは非常に非効率になってきた。
で、どうしたかというと、Intelが「CISCの皮をかぶせたけど中身はRISC」というチップを開発して普及させたのだ。
つまり、中身はRISCで効率的に動くけど、サプライヤーや顧客など周囲の人たちが、CISCのときと動き方を変えなくてすむようにしたのだ。
この話も、如何にバリューチェーンの他のプレーヤーの負荷が少ないことが重要かを物語っている。
(追記:CISC/RISCの例は、授業でカバーしたものではなく、私が以下の文献を元に書き加えました。
Allan Afuah, Nik Bahman (1995) "The Hypercube of Innovation" Reserach Policy
詳しくはこの論文を参照してください。
こちらにはバリューチェーンの他のプレーヤーの負荷を減らすことが技術普及にどのような影響を与えるかについて、スパコン、電気自動車など他の例も載ってます)
2)既存技術は新技術が出てきたとき、大幅に性能アップする
エジソンが電球を商用化したときに使っていたのは、炭のフィラメントだった。
特に日本産の竹を燃やして作った炭が、最も耐久時間が長かった、というのは有名な話だ。
炭のフィラメントのおかげで、エジソンの作った会社(現在のGE)は大きなシェアを獲得していた。
ところがここに、強力な「次世代技術」が現れる。
1910年、ヨーロッパのガス会社がタングステンのフィラメントを発明した。
タングステンの方が、炭よりもずっと明るく、長時間持続することが分かってきた。
それがこれ。
ところが、頑固なエジソンは、炭のフィラメントにこだわった。
炭を使って、タングステンよりも明るく、長時間持続するフィラメントを作ろうと研究開発を進めたのである。
その結果、うまれたのがこちらの写真の左側にある、炭のフィラメント。
右側のタングステンより、より明るいのが分かると思う。

Sカーブでは、ひとつの技術が限界を迎え、新技術の性能がだんだん上がり、旧技術のパフォーマンスを超える、というのが典型パターンである。

ところが実際には、新技術に追い立てられた旧技術は、新技術よりも高いパフォーマンスを見せたりするのである。

この「旧技術プレーヤーによるあがき」も現在のいろんな技術分野で見られる。
新技術が出てくることで、旧来の技術の性能は圧倒的に進化したりするのだ。
大体、旧技術を持ってるプレーヤーの方が大企業で、たくさん投資できるので、進化も大きくなる。
新規プレーヤーは常に、この旧技術のあがきを覚悟しておく必要がある、と言う話。
また、普通の技術論などの授業では、よく技術はSカーブの形で進化する、と習うが、
実際の技術のパフォーマンスメジャーを見てみると、Sカーブに沿わない形で進化する技術はたくさんある。
Sカーブは概念的には正しいが、ちゃんとみると反例もたくさんあるという話。
3) 技術以外の要素が大切。最終的には技術でなく、システム・アーキテクチャ管理力で勝つ。
タングステンに追い立てられて、劇的な進化をとげたエジソンの炭のフィラメントも、結局技術的限界を迎える。
長期間耐久性のあるタングステンに勝つことは、どうしても出来なかったのだ。
GEの炭のフィラメントは、タングステンフィラメントにとって変わられていった。
それで、GEも遅らばせながら、タングステンフィラメントの開発・販売に着手する。
ところが、技術で負けたGEは、シェアを落とすことなく、電球事業で他社に勝ち続ける。
何故か?
それは、GEは、電球だけでなく、電球ソケットや電線やヒューズといった、システム全体を提供できる会社だったからだ。
それに長年のトップシェアのおかげで、GE系列の電気屋さんがたくさんあった。
タングステンフィラメントを開発した企業は、耐久時間や明るさ、という技術的にはGEより優れていたが、
人々はそういう技術力より、「GEにお願いすれば全て整う」という理由でGEを選んだのだ。
要素技術ではなく、アーキテクチャを支配し、システム全体を提供する力が重要、というのは現代のどの技術にも言える。
例えば、マイクロソフトのWindows OSは、技術的にはAppleのマッキントッシュに劣っていたかもしれないが、
Windowsのほうが対応アプリケーションが豊富だったなどの理由で、人々はWindowsを選んだりした。
あるいは、インテルよりNECの半導体の方が技術的には優れていたかもしれないが、
PC全体のアーキテクチャを支配し、他の要素との整合性が高かったインテルが顧客に選ばれた、など。
(追記:こちらの事例も他の論文などを参考に、私が追加しました)

真剣に授業を聞く学生たち。30代、40代の学生も多い。
以上、白熱電球なんて100年も前の技術から、現代の技術にも生かせる教訓が導き出せる、という話でした。
まとめておくと
1) 業界や顧客などの動き方を出来るだけ変えない工夫は、新技術普及の鍵
2) 新技術が出てくると、旧技術は圧倒的な進化を遂げたりするから、新技術は覚悟しておくべき。
あとSカーブは概念的には正しいが、全ての技術がそういうTrajectoryを経るわけではない。
3) 技術力より、システムの総合力やアーキテクチャーの管理力が、顧客に選ばれる鍵
ということでした。
白熱電球の歴史については下記の先生の本にも詳しくかかれてるのでご参考まで。
Mastering the Dynamics of Innovation: How Companies Can Seize Opportunities in the Face of Technological Change Harvard Business School Pr (画像をクリックするとAmazonのページに行きます)

James M. Utterback











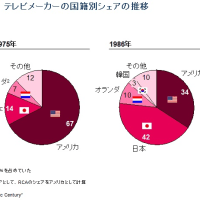
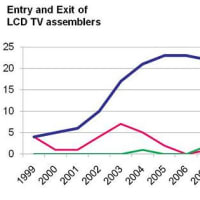
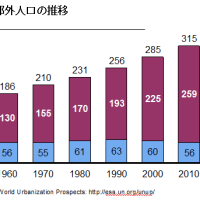
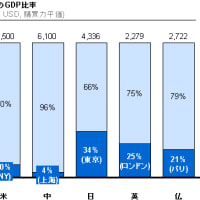

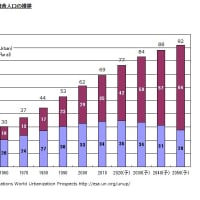
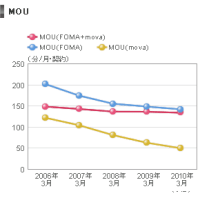
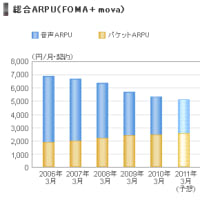
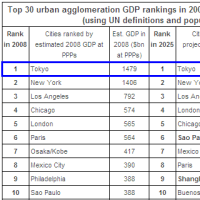
あと、アマゾンにリンクを張ってある本ですが、ハードカバー版にリンクが張られていて品切れ状態になっています。ソフトカバー版があるみたいですよ。
早速リンク貼りなおしてみました。(ついでに画像も大きいのに変えてみました)
オープンコースウェアに授業をアップってのもあるといいですけど、それやるとMBAが潰れますよね(笑)
何でもフリーってのは、本来は良貨を駆逐するんですよね。
本当はこういうブログに授業内容を書くのも物議をかもすとこなんです。
私の場合は日本語であり、授業内容の詳細と言うよりは、私がそこから学んだことを中心に書いてるし、何よりMBAの宣伝になってるので許されてるって感じだと思います。
だからこれを読んで「あーMBA面白そうだな」と思ってもらえれば本望というとこでしょうか。
>何でもフリーってのは、本来は良貨を駆逐するんですよね。
??
何をいまさら、っていうかそれを言うならOCW自体成立しないんじゃないんでしょうか??
2) 新技術が出てくると、旧技術は圧倒的な進化を遂げたりするから、新記述は覚悟しておくべき
超Nで細かいことを気にしない私は誤字が多いので(Nとか言っていい言い訳ができた)、こうやって指摘をもらえるのは助かります。
米国MBAみたいな形でお金を取ってるところが、OCWをどこまでやるかと言うのは議論の余地があります。
MBAのあり方論については、今年MBA受けてる人たちのRoundが終わったら書きますから、そのときにでも議論しましょ。
私はまがいなりにも情報工学を学んでいたので、新技術を普及させる際にシステムアーキテクチャを考慮することに強い興味を持ちました。
是非とも一度講義を受けてみたいです。
相手の土俵で違うことをする→○
相手の土俵で同じことをする→×
ということなのかな。
それは良かったです!
余談ですがアーキテクチャ支配の重要性については、Michael CusumanoのPlatform Leadershipが詳しいです。
日本語版も出てるはず
>相手の土俵で違うことをする→○
相手の土俵で同じことをする→×
そうですねー、「相手の土俵」がどこを指すかに寄りますが、顧客や周囲のプレーヤーの負担は減らした方が有利って話だと思います。
へー!エジソンは灯油機器のソケットと同じく電球のソケットを作ったんですね!!知らなかった・・・でも納得です。とても参考になりました。