クロード・シャノン 情報時代を発明した男 ジミー・ソニ、ロブ・グッドマン 小坂恵理・訳 インターネット時代を切り開いた知られざる先駆者
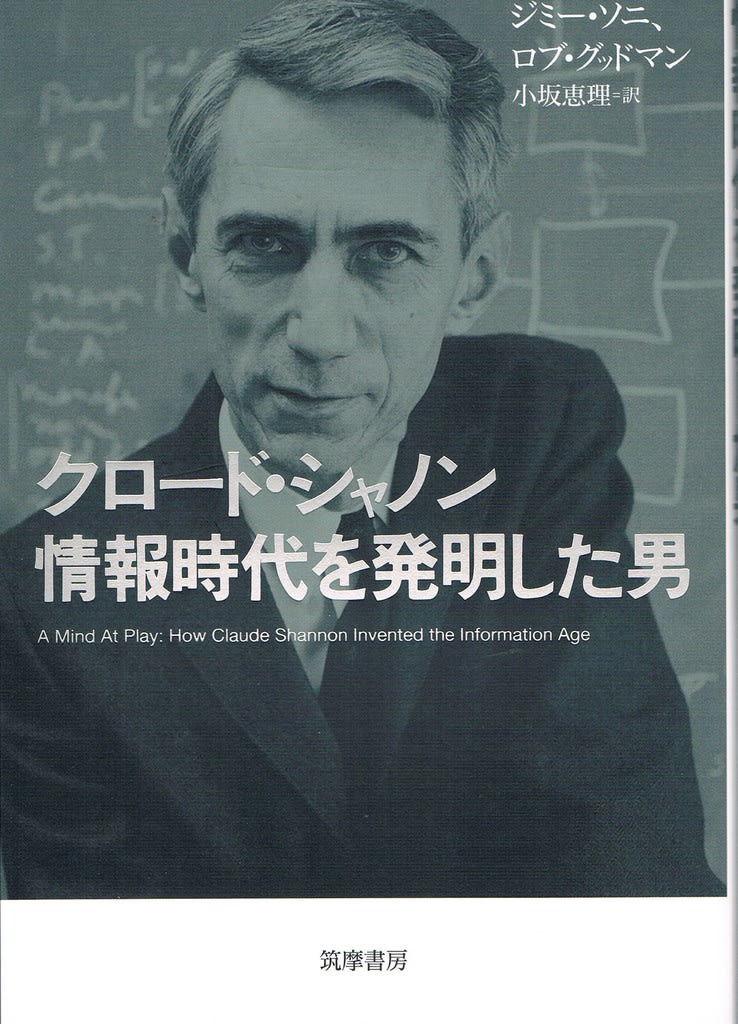
クロード・シャノンは20世紀後半の情報の世紀の礎を築いた「情報理論」の発案者として著名だ。でも、有名なわりに人柄や業績が知られていない。本の帯には「パソコン、携帯電話、インターネット、電子メール、DVDにストリーミング。すべて、シャノンなしには実現しなかった」。さらに大きな文字で、「影響力の大きさは、アインシュタイン以上。」とある。
ジミー・ソニ氏は編集者、ジャーナリスト、ライター。ロブ・グッドマン氏が元スピーチライターとあるが、どういう人かはわからない。二人には古代ローマ時代の政治家カトに関する共著がある。なぜシャノンを取り上げたのか、その理由はわからないが、あとがきに「私たちは伝記作家であり、数学者でも物理学者でもエンジニアでもない。私たちは素人だが、執筆作業にはできる限りの努力を惜しまなかった」。その直後に、「インターネットや情報の氾濫が不自然なのではない。これらの起源は何か。なぜ、どのようにして存在するようになったのか、歴史の流れのなかでどこに位置づけられるのか、どんな男性や女性が実現に関わったのか、考えようとしないことが不自然なのである」と書かれている。伝記作家として対象を探すうち、ネット時代の功労者ながらあまり知られていないシャノンを発見して、取材に取り組んだのだろうか。
クロード・シャノンは1916年にアメリカ中西部ミシガン州の小さな町で生まれ、2001年に他界した。評者は工学部の情報系学科出身でシャノンの専門に近いところで仕事をしていたこともあった。情報理論の論文をきちんと読んだことはないが、名前と業績のおおよそは知っているつもりだ。だが、活躍した時代は戦後まもなくから70年代ごろまでという印象が強く、21世紀まで存命とは知らなかった。伝記作家の常とう手段だろうが、筆者はシャノンの両親を含め、その生い立ちから詳しく記述する。シャノンが出会う人物についても同じ手法で、評者にはこれがやや読みにくく感じられたこともあった。
若くして頭角を現したシャノンは地元のミシガン大学に進学し、数学と電気工学の学位をとった。卒業後、東海岸の名門マサチューセッツ工科大(MIT)大学院に進学する。院生であると同時に、開発が進んでいた微分解析機の助手という仕事だった。MITへの進学がその後の彼の運命を変えたといっても過言ではない。MITにはアメリカ科学界を牛耳っていたヴァネヴァー・ブッシュが在籍していた。彼はブッシュをメンター(恩師)とする。評者にはヴァネヴァー・ブッシュという名前が妙に懐かしかった。MIT副学長などを務めたが、第二次大戦開戦直前、ルーズベルト大統領に直談判して政府に国防研究委員会(NRDC)という機関をつくらせ、科学者と軍との連携を強力に推進した。マンハッタン計画の推進役でもある。
シャノンはマンハッタン計画と直接の関係はないが、戦時中、数学者、電気工学者として、ATTベル研究所で、暗号開発や暗号解読などの機密研究に従事していた。本書で評者がもっとも興味深かったのは、「デジタル時代のもう一人の巨人、アラン・チューリングとの出会いだ」。チューリングはイギリス人数学者で、やはり戦時中、イギリスで暗号開発や解読の機密業務に従事していた。チューリングが発案した「チューリングマシン」は今日のデジタル・コンピュータの理論的基礎として知られている。戦後になって同性愛の罪で逮捕され、1954年に41歳で自殺した悲劇の人でもある。アメリカ計算機学会(ACM)は情報科学者に贈る最高の賞としてチューリング賞を創設し、その栄誉をたたえている。
本書によると、戦中の1942年、アメリカの暗号開発の様子などを視察するため、訪米したチューリングはベル研のシャノンを訪れ、カフェで親しく言葉を交わしたという。だが、戦時下の厳しい軍の統制のもと、「僕たちは、暗号技術に関してはいっさい話し合わなかった」とシャノンは語っている。チューリングとシャノンはお互いの才能や仕事ぶりを認め合い、「シャノンは、チューリングの思考力のレベルの高さに舌を巻いた。『チューリングは偉大な人物、すごい人物だと思う』と、後に語っている」。
二人は戦後、一度だけ会っている。こんどはシャノンがイギリスにチューリングを訪ねた。「1950年、シャノンが会議のためにロンドンを訪れ、そのとき時間を割いてチューリングを研究所に訪問した。「このとき彼はチェス指しコンピュータのプログラム開発に興味を持っていた……僕もこの問題にはかなり関心があった。(中略)当時はコンピュータの揺籃期だった」とシャノンは回想している。
「情報時代の土台を築いたふたりの巨人は、戦後の再会を心から楽しんだ。しかしこれは、ふたりがじかに話し合う最後の機会になった。同性愛が違法とされる時代に、チューリングは『わいせつ行為』で有罪判決を受け、シャノンの訪問を受けた四年後に青酸中毒で死亡した。彼の死は自殺と断定されたが、詳しい状況は今日に至るまで謎に包まれている」。この二人に交遊があり、互いに尊敬し合っていたことはあまり知られていない事実だろう。
当時のベル研は企業の研究所ながら、素晴らしい才能が集まっていた。戦後、何人かがその業績を認められてノーベル賞を受賞している。シャノンはベル研でも才能を高く評価され、充実した研究者生活を送った。1948年、シャノンは最大の業績とされる「情報理論」の最初の論文を発表する。著者は情報理論創始者としてサイバネティックスという言葉をつくった情報科学者ノーバート・ウィナーとの間で角逐があったと書くが、本当にそうだったのかという気もする。予断を持たず、さまざまな情報を集めたことは評価できるが、ふたりの業績比較は専門家の手に委ねるべきだ。ちなみにウィーナーはシャノンの22歳年長だった。
シャノンは数学者として理論を組み立てるだけの人ではなかった。本書には家族やベル研から提供されたさまざまな写真が登場する。その中にはベル研時代の「機械仕掛けのネズミを迷路に置くシャノン」というものもある。小さなロボットを迷路に置き、脱出させるゲームだ。このネズミはベル研のPRビデオにシャノンとともに出演した。シャノンはネズミを自作した。数学者としてだけでなく、アイデアマンの電気工学者で手先の器用な人だったようだ。
シャノンはチェスを指す機械も自作している。後にIBMのディープブルーというシステムが人間のチャンピオンを打ち負かす半世紀ほども前のことだ。彼は機械が人間をいつの日か追い越すと考えていた。「僕は、人間は機械だと思う。冗談ではない。コンピュータと同じではないし、仕組みも異なるが、人間は非常に複雑な機械だと考えている。そして、人間は簡単に複製できる。人間には10の10乗、すなわちおよそ100億個の神経細胞があるが、このすべてを電子機器でモデル化すれば、人間の脳のように作用するだろう」。脳の研究が飛躍的に進んだ現代から見ると楽観論すぎるように思うが、技術の進歩に楽観的で、技術万能主義者だった。アメリカではキリスト教の信仰を持つ人が多いが、彼は無神論者だったという。
生前から高名だったにもかかわらず、回想録の類をほとんど何も残していない。自伝に最も近いのは後に、ベル研で行った講演だという。創造的思考をテーマにした講演で、彼は冒頭、「全人口の一握りの人たちから、重要なアイデアのほとんどは生み出されます」と話し始めた。ただ彼は「自分など、そんなとびきり優秀な頭脳集団に入る資格はないと補足し、該当するのは、ニュートンやアインシュタインのように、歴史上極めて稀な人物だと説明した」。やや謙遜したのかもしれないが、彼は決して傲慢な人物ではなく、数学と電気工作を愛する内向的な紳士だったようだ。シャノンは才能と訓練という前提条件が満たされても、成功には第三の条件が必要と考えていた。それは「モチベーション、すなわち解答を見つけようとする熱意、物事を進行させる仕組みを理解しようとする情熱」だとみていた。
さまざまな証言からも、彼は数学と電気工作を愛する、控えめな紳士だったようだ。10年ほどをベル研で過ごすと、母校MITから教授のオファーを受ける。MITはボストン郊外のケンブリッジにあるが、彼や家族がニュージャージー州の田舎よりケンブリッジでの生活を望んだことも理由だったようだ。シャノンはMITから10キロほど離れた町の19世紀半ばに建てられた3階建ての邸宅に住み、MITに通うとき以外はここで暮らした。邸宅はエントロピーハウスと名付けられた。彼の情報理論が情報量を情報エントロピーと考えることからすると、この名前にも強いこだわりがあったはずだ。
シャノンはここで株式市場に興味を持つ。60年代から70年代にかけてシャノンは株への投資にとりつかれていた。それも彼だけでなく家族全員がそうだった。もちろん、金に困っていたわけではない。MITとベル研から給与を得ていたばかりか、今でいうIT企業の設立にも関わり、十分すぎる収入を得ていた。とくに熱心だったのはやはり数学者である妻のベティで、株価の動向についてグラフを作り、株式投資の仕組みを探求したという。ある時、シャノンがMITで株式市場についての講演を申し出ると、講堂は超満員になった。彼は「価値が減少している銘柄から投資家が利益を出せる理論について紹介した。取引をコンスタントに繰り返し、価格の変動をうまく利用するのだ」という。聴衆からは「自分の投資活動で利用しましたか」と質問が飛んだが、「『いや、手数料が馬鹿にならない』とシャノンは答えた」。
アイデアマンの彼は、ウエァラブルコンピュータの原型のようなものも自作している。カジノのルーレットゲームにも興味を持ち、MITの若手教授を相棒に「8か月をかけて、ルーレットのボールが最後に落ち着く場所を予測する装置の開発に挑戦した」。1961年6月には試作機を完成させ、「カジノに持っていって、交代で賭けに挑戦した」。見つかったら大変なので、二人の妻が見張りをしたそうだ。MIT教授の名声に傷がつかなかったのは何よりだった。
シャノンは一時期、ジャグリング(輪投げ)にも熱中していた。本書には3つの大きな輪を投げるシャノンの写真が載っている。遊ぶだけには終わらず、ボール(輪でも同じだろう)が空中にとどまる時間、ボールが手の中にある時間、手の数などを変数に代数方程式を導き出す「ジャグリングの定理」まで発案した。
情報科学への貢献で、シャノンはさまざまな顕彰を受けた。85年には京セラの稲森和夫氏が創設した京都賞の第一回受賞者になった。京都賞はノーベル賞を意識して創設され、高額賞金で知られているが、ノーベル賞の対象ではない情報科学や工学分野を積極的に顕彰することでも有名だ。シャノンは受賞を喜んだが、「いつもと同じく旅行に神経質で、とくに日本食には不安を募らせた」。そのため、シャノンには妻と数学者の姉の二人が同行することになった。表彰式の受賞講演は晴れ舞台だった。シャノンは「科学の発見そのものは『素晴らしい成果だとしても、エジソンやベル、マルコーニなど、エンジニアや発明家が仲介役にならない限り、一般人の生活には影響が及ばない」とイノベーターや発明家の役割の重要性を指摘した。「『チェスを指す機械やジャグリングをするロボットのような装置を作ることは、趣味としても時間と金の無駄のように思えるかもしれません』とシャノンは認め、『しかし、貴重な結果はしばしば単純な好奇心から生み出されることを、科学の歴史は教えてくれます』」と述べた。
晩年のシャノンはアルツハイマー病におかされた。80年代半ばから病気が進行し、外出する機会が減った。最初は自宅で、病気が進んでからは介護施設で、妻が献身的に介護した。彼は葬式についても、「6人の担ぎ手によって棺が運ばれてくるが、全員が一輪車に乗って、棺を落とさないようにバランスをとっている」という奇妙なアイデアを持っていた。「当然ながら家族は、もっと落ち着いた形の追悼を好んだ」。
シャノンの情報理論は著名だが、その人柄や詳しい業績がそれほど知られていないのは回顧録を書くこともなく、80年代半ば以降、表舞台から突然、姿を消してしまったことも影響しているのだろう。筆者は、「従来からは考えられないほど専門化が進んだ私たちの時代にとって、シャノンの研究は良いお手本になる」と偉大なジェネラリストをたたえる。数学者、エンジニア、ジャグラー、一輪車乗り、機械製作者、未来学者、ギャンブラーだった。彼は、「旺盛な好奇心に導かれるまま行動しただけである。したがって、情報理論から人工知能、さらにはチェスやジャグリングやギャンブルへと興味の対象が飛躍するのはきわめて自然だった」。
MITの後輩で人工知能研究のパイオニアであるマーヴィン・ミンスキー教授は訃報を聞いて、「彼は、問題が難しく見えるほど、何か新しいものを発見するチャンスが広がったと考える人だった」と語ったという。筆者は、「仕事に喜びを見出す姿勢」を彼の成功の秘密と指摘する。「20代の数年間を除けば、シャノンは深刻に考えこみ、時にはうつ状態になりながら研究と格闘する時期をいっさい経験せず、人生も仕事も絶え間のないゲームとして考えているようだった。彼は尋常ではなく才気煥発であると同時に、いたって人間的だった」。
ここまで読んで、つくづくいい時代に生きた人だと思った。研究者としての全盛期は戦中から戦後間もなくで、ちょうどアメリカの黄金時代にあたる。戦争に敗れた日本人はひもじい思いをしながら、カラー映画に登場するアメリカの中流家庭の優雅な生活に強く憧れていた。今日の深く分断されたアメリカを見ないまま亡くなったのは幸せだったのだろう。
情報科学者の評伝としてはやや冗長なところもあるが、彼の人となり、そして彼を支えた家族や周囲の人々、当時の研究環境についてよく理解できる。ただこの本を読んだだけでは情報理論がどんなものかわからない人が多いかもしれない。業績をきちんと知りたければやはり専門家による解説書や啓もう書を読むべきだと思う。訳文はこなれていて読みやすい。原注や参考文献がすべて掲載されているのは親切だ。









