投稿歴三十四年―私の文学彷徨
李耶シャンカール
私がそもそも、小説を書き始めたのは中学一年の十三歳のとき、昭和四十二年(一九六七)当時、女子中学生の間ではジュニア小説が流行っており、自身も夢中になって片っ端から読みふけるうちに書いてみたくなり、大学ノートに鉛筆で綴ったのが始まりである。出来上がって級友の一人に見せると、彼女はそれを別の友達に回した。結局クラス中の女子に回覧され、面白いと大評判になった。
私は気をよくして、第二弾に取り掛かった。ジュニア小説の模倣(まね)ごとはたちまち、クラスじゅうに広がった。私に続けとばかり、ほか三名ほどの書き手が現れ、なかには、私が読んでうまいと思うライバル予備軍もおり、競争心をあおりたてられ、いっそう創作に集中するようになった。が、一番人気なのはいつも私で、次はいつできるのと矢のような催促が飛び交い、いっぱしの売れっ子作家気取りだった。ちなみに、当時流行っていたジュニア小説作家には、富島健夫や川上宗薫、津村節子などがいた。
高校に上がっても、私の一般書籍への繰上げ慣習はなかなか培われず、進学校だったこともあって、本を読んでる時間がなかったのだが、大学ノートにせっせとものを書くことだけはやめなかった。少女マンガのファンでもあったので、真似をして下手糞な絵につける吹き出しのセリフを考えたりするのが楽しかった。
高校二年のとき、カフカの「変身」を読んで書いた感想文が国語教師の目に留まり、読書感想文コンクールに出品されわくわくしたが、選には漏れた。
女子大の英文科に進み、上京した私は遅ればせながら読書に目覚め、翻訳文庫の虜になった。好きな作家は、D・H・ロレンス、ヘミングウェイ、グレアム・グリーンなど、卒業論文は、ロレンスの「チャタレイ夫人の恋人」(伊藤整訳)だった。十九歳のとき、百枚ほどの小説を書き、「誰か私の小説を批評してくれませんか」と地元紙の広告欄で募ったところ、六名ほどの男性が電話をくれて、そのうちの一人の詩人かつ同人誌の主宰者だったSの会に参加することになった。トレペに書き手本人が鉛筆やペンでしたためた原稿を青焼きコピーして綴じただけの、素朴な手作りミニコミ誌「青い宇宙船」に、私は詩をよく発表した。卒業後は、ものを書く仕事につきたいと思っていたため、その近道としては出版社の編集が一番だろうと考えていた。
しかし、コネで入った教科書出版・M図書では、希望と裏腹の経理部に回されたため、一年で辞め、以後医家向け新聞の編集嘱託を経て、経済誌を発行するK社に勤め出す。そこでの仕事は主に割付だったが、慣れてくるにしたがって、二ページもののインタビュー記事も書かせてもらえるようになった。初めて自分の書いたものが活字になったときは感激した。文学への情熱は衰えず、東京では「中央文学」という、作家志望者の間でわりと有名だった同人誌に参加した。当時売れていた新進気鋭の増田みず子などが同人だった。すでに日本文学に目覚め、虜になっていた私は、古井由吉にひとしおのめり込んでいたが、自分の書き物は純文学というにはあまりに稚拙で、それでも中央文学に詩と小説が一編ずつ掲載されたのがうれしかった。
一九八一年、初めてインドに渡った。その頃読んだ書物のどれもが期せずして、「インドはすごい!」と持ち上げたものばかりだったからだ。そんなにすごいところなら一度見ておかねばと、生来の好奇心が頭をもたげたわけである。
私の期待を裏切ることなく、インドは予想以上に凄まじかった。灼熱の風土とカオスの渦巻く坩堝地獄に頭にかっと血が上り、ぼられまくれて怒り狂い、インドに比して天国とみなされるネパールに逃げてほっと安らげたにもかかわらず、何かが物足りない、日本に帰ると、いよいよインドが恋しくてならなかった。私はインドでの初体験を基に小説を書き、初めて文学界に投稿した。二十六歳のときだった。
二年後、男性雑誌創刊の名目のもとに掻き集められたメンバーに加わることになった。B社はマンションの一室がオフィス代わりの小さな出版社だったが、ちょうど科学誌創刊ブームが相次ぎ、それにあやかって娯楽の要素も取り入れた科学誌を創刊しようとの賭けに打って出たのだった。総勢八名の新編集部の一員となった私は、スプーン曲げの超能力者・清田益明の取材や、禅僧の脳波をとってアルファ波が出るのを調べる実験ルポや、取材記者として飛び回ったが、この雑誌はあえなく二号でつぶれた。
ここで本業の余暇に校閲者を請け負っていた年配男性Sから、角川書店発行の「月刊カドカワ」主宰の「掌編小説大賞」が毎月締め切りで十枚内の原稿を募集しているから投稿してみるよう薦められた。原稿枚数が短いので勤めの傍ら書くのはもってこいで、休日のたびにペンを振るって多いときで月五、六作送った。選者は故吉行淳之介氏で尊敬する作家だったし、川端康成の「掌の小説」を読んでいた私は、百篇書こうと意気込んだ。毎月の発表が楽しみで、佳作欄に名前が載ると、いっそう発奮し、そのうち月間優秀賞(朱に交われば)というのを戴いた。エロチックな題材の掌編で、吉行氏のお気に召したようだった。二十八歳で初めて小説が商業文芸誌に掲載された私は、有頂天になった。
八三年、二度目のインドへはSと渡ることになった。私より十七歳も年上のSには妻があり、本職は業界紙の編集長だったが、五年ほど前彷徨したカナダを永住の地と定め、再渡航する機会を窺っていた。文学界新人賞の受賞者という前歴と、良質の叙情あふれる恋愛小説の名手であるSに私は師を見出し、魅入られたのだ。「五年で作家にしてやる、女流のほうが出やすいんだ。おまえはバンクーバーでただ書いていればいい。後のことは俺がすべて面倒見るから」と太鼓判を押され、作家として立ちたい野心を膨らませていた私はころりとなびいた。男性的魅力にしびれてのことではなく、多分に若い女性としての打算が働いた上でのことだった。
私は、カナダの前の手慣らしとしてインドに行きたいと男に告げ、受け入れられた。しかし、三ヶ月のインド行脚は、地獄巡りとなった。私が裏でこっそり、別の若い男にラブレターを書き送っていたせいである。相手は三歳年下のIだったが、やはり小説家志望で、先の倒産したB社で一時期同僚として働いていたいきさつがあった。つまり、SとIは一面識があったわけで、一気にドラマはカタストロフの終焉へ、私が旅の渦中書き溜めていた原稿をびりびりに引き裂かれたことで、張り詰めていたたががどっと外れた。帰国後、すでに妻を実家に送り返し、私を最後の恋人と目していた男からは、復縁を望む手紙が舞い込んだが、私は後を振り返らなかった。
ほどなく大手メーカー傘下のPR誌編集に携わるようになるが、一年後勤めを辞して、三度目のインドに単身で渡る。
そして、ベンガル湾沿いの風光明媚な聖地プリーで、王宮ホテルを経営する現地男性オーナーと二十代の総決算のような烈しい恋に陥るのである。しかし、運命の皮肉か、私が日本への駆け落ちを敢行したのは、ひと回りも年下の別の若いインド学生だった。未熟なインドの若者との仲は早晩破局、この経緯を作品化して吉行氏に読んでもらおうと思い立った私は失恋の傷手を癒すように執筆、上野毛の自宅まで届けた。しかし、ひと月置いて電話で感想を恐る恐る問い合わせる私に、受話器の向こうの大御所作家は「君、あれはだめだよ」と冷ややかなひと声、さすがにがくりと来た。
めげずに月刊カドカワ編集部に持ち込んだ。当時編集長だった見城徹氏に、「しょうがないなあ。ちゃんとコピーとってきたあ?」と冷淡にあしらわれつつ、何とか受領してもらった。恥も外聞もなく、ただただ必死だったが、その後しばらくして、森瑤子の書いた小説に私の持ち込んだ原稿と似たようなテーマを見つけたときは、思い過ごしかもしれなかったが、アイディアを盗まれたようで憤慨ともつかぬやるせない心地に見舞われた。
八七年三月、日本に帰らない永住覚悟の元に通算四度目のインドに渡る。その少し前に、小説現代新人賞の予選通過と、早稲田文学新人賞の最終選考を通過していた私は、これから先はインドで書いていこう、このものすごい国は私の文学に必ずや深みと豊饒をもたらしてくれるはずだと確信していた。
現地での生活手段として、ホテルを建てるためのビジネスパートナーを捜していたとき、偶然レストランで一人の男と行き合わせた。地味で物静かな風貌、かしましい地元衆の一団から離れて、ひっそりとティーを啜っていた。ウェイターの少年を呼び止めてこっそり男の素性を尋ねると、向かいのロッジのマネージャーだとの返事が返ってきた。その瞬間、私は霊感に打たれたようにこの人とならパートナーを組めるかもしれないと閃いた。あくまでビジネス上のパートナーのつもりだったが、予想外の成り行きで恋が芽生え結婚、私は最終的に三番目に現れたインド男性のもとに嫁ぐことになった。条件は、書かせてくれること、これだけだった。
しかし結婚後は、オープンした宿を軌道に乗せるのと現地に順応するのに予想以上に時間を取られ、思うように書けない文学不毛の時代が続いた。予選通過すらままならぬ紆余曲折の二十余年が過ぎ、メジャーな文学賞が若手偏重なのを苦々しく思っていたとき、とある文学賞の存在を知る。それこそが文芸思潮主宰の、四十五歳以上に投稿対象が限られる、いわばシルバー世代向けの「銀華文学賞」だった。
二○○九年当時、私はインド関連エッセイを経済誌時代の同僚が主宰しているネット新聞に連載中だったが、同じ著者仲間で闘病記を書いていたNが、銀華文学賞の佳作賞に輝き、作品が転載されたのである。私には銀華文学賞は、福音以外の何物でもなかった。早速投稿したが、その年は三次予選通過止まりで終わった。
翌年、移住前小説現代新人賞の予選を通過した作品「サダルストリート・ブローカー」を、タイトルを「虹の魔窟のブローカー」に変えて改筆し投稿した。幸運にもこの作品が奨励賞を射止め、二十四年の折々の推敲の後にとうとう旧作が活字となって報われたのであった。
以来、銀華文学賞の常連投稿者となり、二〇一三年にはエッセイ賞で奨励賞を戴いたが、ほかにも、やまなし文学賞の最終選考に残ったり、ふくい新進文学賞の佳作賞も受賞して地元紙に連載されたりと、作家の卵にとっては長く暗い道筋に一筋の光明が見えるような、「李耶シャンカール」という異色のペンネームがほのかに注目されだした年だった。
浅田二郎氏の投稿歴三十年は有名だが、私は自慢にもならない、それを越すことにもなり、やっと長年書き続けてきた努力が認められ、少し日の目を見るようになったかと感慨深い昨今、しみじみ思うのは、そのときどきで辛い体験も決して無駄ではない、素材としての貴重な体験を与えられているということ、なんだか自分は、波乱万丈に生きて、それを小説に書くと決めて生まれてきたような気さえするのである。
このごろ周囲に八十半ばになっても創作意欲が衰えないアマチュア作家を幾度か見る機会があり、そのたびに鼓舞され、ということは、私にはまだ二十六年あるということだな、さてあと四半世紀で私の文学はどこまで進化するだろうと、楽しみなような苦しいような、瀬戸内寂聴氏が八十五歳で書いた金字塔「秘花」にはとうてい及ばずとも、最高峰に近い、渾身の力を出し切った作品を仕上げて、悔いなく息絶えたいと思うのである。作家にはこれが至上ということはないのだろう、ひとつの作品が昇華したら、次はそれ以上のものを目指す、そしてどこまでも上を窮めていく、芸術家の窮極志向、アートの厳しさにほかならないが、少なくとも死ぬ前、これが私の限界ぎりぎりまで出し切ったと悔いのない最高の傑作を仕上げて、思い残すことなく逝きたいと思うのだ。
*解説
自分の長い投稿人生をテーマにしたエッセイだが、今読み返すと、稚拙で出来としてはいまいち。それに、本を四冊出したことにも触れていない。当時は、投稿者が45歳以上に限られるという特異な文学賞、「銀華文学賞」が私にとって、いかに福音をもたらしたということを一番に書きたかったようである(つまり、文芸思潮誌を持ち上げるという不純な動機がなきにしもあらず)。
あれから、三年以上たって、運命の急変に見舞われ、八十半ばまで書き続けたいなどというのんきなことは言っていられなくなり、急遽これまでの三十数年間で書き溜めた百編ほどの小説を、ブログで公表する成り行きになった(E全集の発願)。
「インドで作家業」を十年書き継いできてよかったとしみじみ思う。昔のように作品を埋もれさせずにすむからである。そういう意味では、これが今の私にとっては、最大の福音である。
李耶シャンカール
私がそもそも、小説を書き始めたのは中学一年の十三歳のとき、昭和四十二年(一九六七)当時、女子中学生の間ではジュニア小説が流行っており、自身も夢中になって片っ端から読みふけるうちに書いてみたくなり、大学ノートに鉛筆で綴ったのが始まりである。出来上がって級友の一人に見せると、彼女はそれを別の友達に回した。結局クラス中の女子に回覧され、面白いと大評判になった。
私は気をよくして、第二弾に取り掛かった。ジュニア小説の模倣(まね)ごとはたちまち、クラスじゅうに広がった。私に続けとばかり、ほか三名ほどの書き手が現れ、なかには、私が読んでうまいと思うライバル予備軍もおり、競争心をあおりたてられ、いっそう創作に集中するようになった。が、一番人気なのはいつも私で、次はいつできるのと矢のような催促が飛び交い、いっぱしの売れっ子作家気取りだった。ちなみに、当時流行っていたジュニア小説作家には、富島健夫や川上宗薫、津村節子などがいた。
高校に上がっても、私の一般書籍への繰上げ慣習はなかなか培われず、進学校だったこともあって、本を読んでる時間がなかったのだが、大学ノートにせっせとものを書くことだけはやめなかった。少女マンガのファンでもあったので、真似をして下手糞な絵につける吹き出しのセリフを考えたりするのが楽しかった。
高校二年のとき、カフカの「変身」を読んで書いた感想文が国語教師の目に留まり、読書感想文コンクールに出品されわくわくしたが、選には漏れた。
女子大の英文科に進み、上京した私は遅ればせながら読書に目覚め、翻訳文庫の虜になった。好きな作家は、D・H・ロレンス、ヘミングウェイ、グレアム・グリーンなど、卒業論文は、ロレンスの「チャタレイ夫人の恋人」(伊藤整訳)だった。十九歳のとき、百枚ほどの小説を書き、「誰か私の小説を批評してくれませんか」と地元紙の広告欄で募ったところ、六名ほどの男性が電話をくれて、そのうちの一人の詩人かつ同人誌の主宰者だったSの会に参加することになった。トレペに書き手本人が鉛筆やペンでしたためた原稿を青焼きコピーして綴じただけの、素朴な手作りミニコミ誌「青い宇宙船」に、私は詩をよく発表した。卒業後は、ものを書く仕事につきたいと思っていたため、その近道としては出版社の編集が一番だろうと考えていた。
しかし、コネで入った教科書出版・M図書では、希望と裏腹の経理部に回されたため、一年で辞め、以後医家向け新聞の編集嘱託を経て、経済誌を発行するK社に勤め出す。そこでの仕事は主に割付だったが、慣れてくるにしたがって、二ページもののインタビュー記事も書かせてもらえるようになった。初めて自分の書いたものが活字になったときは感激した。文学への情熱は衰えず、東京では「中央文学」という、作家志望者の間でわりと有名だった同人誌に参加した。当時売れていた新進気鋭の増田みず子などが同人だった。すでに日本文学に目覚め、虜になっていた私は、古井由吉にひとしおのめり込んでいたが、自分の書き物は純文学というにはあまりに稚拙で、それでも中央文学に詩と小説が一編ずつ掲載されたのがうれしかった。
一九八一年、初めてインドに渡った。その頃読んだ書物のどれもが期せずして、「インドはすごい!」と持ち上げたものばかりだったからだ。そんなにすごいところなら一度見ておかねばと、生来の好奇心が頭をもたげたわけである。
私の期待を裏切ることなく、インドは予想以上に凄まじかった。灼熱の風土とカオスの渦巻く坩堝地獄に頭にかっと血が上り、ぼられまくれて怒り狂い、インドに比して天国とみなされるネパールに逃げてほっと安らげたにもかかわらず、何かが物足りない、日本に帰ると、いよいよインドが恋しくてならなかった。私はインドでの初体験を基に小説を書き、初めて文学界に投稿した。二十六歳のときだった。
二年後、男性雑誌創刊の名目のもとに掻き集められたメンバーに加わることになった。B社はマンションの一室がオフィス代わりの小さな出版社だったが、ちょうど科学誌創刊ブームが相次ぎ、それにあやかって娯楽の要素も取り入れた科学誌を創刊しようとの賭けに打って出たのだった。総勢八名の新編集部の一員となった私は、スプーン曲げの超能力者・清田益明の取材や、禅僧の脳波をとってアルファ波が出るのを調べる実験ルポや、取材記者として飛び回ったが、この雑誌はあえなく二号でつぶれた。
ここで本業の余暇に校閲者を請け負っていた年配男性Sから、角川書店発行の「月刊カドカワ」主宰の「掌編小説大賞」が毎月締め切りで十枚内の原稿を募集しているから投稿してみるよう薦められた。原稿枚数が短いので勤めの傍ら書くのはもってこいで、休日のたびにペンを振るって多いときで月五、六作送った。選者は故吉行淳之介氏で尊敬する作家だったし、川端康成の「掌の小説」を読んでいた私は、百篇書こうと意気込んだ。毎月の発表が楽しみで、佳作欄に名前が載ると、いっそう発奮し、そのうち月間優秀賞(朱に交われば)というのを戴いた。エロチックな題材の掌編で、吉行氏のお気に召したようだった。二十八歳で初めて小説が商業文芸誌に掲載された私は、有頂天になった。
八三年、二度目のインドへはSと渡ることになった。私より十七歳も年上のSには妻があり、本職は業界紙の編集長だったが、五年ほど前彷徨したカナダを永住の地と定め、再渡航する機会を窺っていた。文学界新人賞の受賞者という前歴と、良質の叙情あふれる恋愛小説の名手であるSに私は師を見出し、魅入られたのだ。「五年で作家にしてやる、女流のほうが出やすいんだ。おまえはバンクーバーでただ書いていればいい。後のことは俺がすべて面倒見るから」と太鼓判を押され、作家として立ちたい野心を膨らませていた私はころりとなびいた。男性的魅力にしびれてのことではなく、多分に若い女性としての打算が働いた上でのことだった。
私は、カナダの前の手慣らしとしてインドに行きたいと男に告げ、受け入れられた。しかし、三ヶ月のインド行脚は、地獄巡りとなった。私が裏でこっそり、別の若い男にラブレターを書き送っていたせいである。相手は三歳年下のIだったが、やはり小説家志望で、先の倒産したB社で一時期同僚として働いていたいきさつがあった。つまり、SとIは一面識があったわけで、一気にドラマはカタストロフの終焉へ、私が旅の渦中書き溜めていた原稿をびりびりに引き裂かれたことで、張り詰めていたたががどっと外れた。帰国後、すでに妻を実家に送り返し、私を最後の恋人と目していた男からは、復縁を望む手紙が舞い込んだが、私は後を振り返らなかった。
ほどなく大手メーカー傘下のPR誌編集に携わるようになるが、一年後勤めを辞して、三度目のインドに単身で渡る。
そして、ベンガル湾沿いの風光明媚な聖地プリーで、王宮ホテルを経営する現地男性オーナーと二十代の総決算のような烈しい恋に陥るのである。しかし、運命の皮肉か、私が日本への駆け落ちを敢行したのは、ひと回りも年下の別の若いインド学生だった。未熟なインドの若者との仲は早晩破局、この経緯を作品化して吉行氏に読んでもらおうと思い立った私は失恋の傷手を癒すように執筆、上野毛の自宅まで届けた。しかし、ひと月置いて電話で感想を恐る恐る問い合わせる私に、受話器の向こうの大御所作家は「君、あれはだめだよ」と冷ややかなひと声、さすがにがくりと来た。
めげずに月刊カドカワ編集部に持ち込んだ。当時編集長だった見城徹氏に、「しょうがないなあ。ちゃんとコピーとってきたあ?」と冷淡にあしらわれつつ、何とか受領してもらった。恥も外聞もなく、ただただ必死だったが、その後しばらくして、森瑤子の書いた小説に私の持ち込んだ原稿と似たようなテーマを見つけたときは、思い過ごしかもしれなかったが、アイディアを盗まれたようで憤慨ともつかぬやるせない心地に見舞われた。
八七年三月、日本に帰らない永住覚悟の元に通算四度目のインドに渡る。その少し前に、小説現代新人賞の予選通過と、早稲田文学新人賞の最終選考を通過していた私は、これから先はインドで書いていこう、このものすごい国は私の文学に必ずや深みと豊饒をもたらしてくれるはずだと確信していた。
現地での生活手段として、ホテルを建てるためのビジネスパートナーを捜していたとき、偶然レストランで一人の男と行き合わせた。地味で物静かな風貌、かしましい地元衆の一団から離れて、ひっそりとティーを啜っていた。ウェイターの少年を呼び止めてこっそり男の素性を尋ねると、向かいのロッジのマネージャーだとの返事が返ってきた。その瞬間、私は霊感に打たれたようにこの人とならパートナーを組めるかもしれないと閃いた。あくまでビジネス上のパートナーのつもりだったが、予想外の成り行きで恋が芽生え結婚、私は最終的に三番目に現れたインド男性のもとに嫁ぐことになった。条件は、書かせてくれること、これだけだった。
しかし結婚後は、オープンした宿を軌道に乗せるのと現地に順応するのに予想以上に時間を取られ、思うように書けない文学不毛の時代が続いた。予選通過すらままならぬ紆余曲折の二十余年が過ぎ、メジャーな文学賞が若手偏重なのを苦々しく思っていたとき、とある文学賞の存在を知る。それこそが文芸思潮主宰の、四十五歳以上に投稿対象が限られる、いわばシルバー世代向けの「銀華文学賞」だった。
二○○九年当時、私はインド関連エッセイを経済誌時代の同僚が主宰しているネット新聞に連載中だったが、同じ著者仲間で闘病記を書いていたNが、銀華文学賞の佳作賞に輝き、作品が転載されたのである。私には銀華文学賞は、福音以外の何物でもなかった。早速投稿したが、その年は三次予選通過止まりで終わった。
翌年、移住前小説現代新人賞の予選を通過した作品「サダルストリート・ブローカー」を、タイトルを「虹の魔窟のブローカー」に変えて改筆し投稿した。幸運にもこの作品が奨励賞を射止め、二十四年の折々の推敲の後にとうとう旧作が活字となって報われたのであった。
以来、銀華文学賞の常連投稿者となり、二〇一三年にはエッセイ賞で奨励賞を戴いたが、ほかにも、やまなし文学賞の最終選考に残ったり、ふくい新進文学賞の佳作賞も受賞して地元紙に連載されたりと、作家の卵にとっては長く暗い道筋に一筋の光明が見えるような、「李耶シャンカール」という異色のペンネームがほのかに注目されだした年だった。
浅田二郎氏の投稿歴三十年は有名だが、私は自慢にもならない、それを越すことにもなり、やっと長年書き続けてきた努力が認められ、少し日の目を見るようになったかと感慨深い昨今、しみじみ思うのは、そのときどきで辛い体験も決して無駄ではない、素材としての貴重な体験を与えられているということ、なんだか自分は、波乱万丈に生きて、それを小説に書くと決めて生まれてきたような気さえするのである。
このごろ周囲に八十半ばになっても創作意欲が衰えないアマチュア作家を幾度か見る機会があり、そのたびに鼓舞され、ということは、私にはまだ二十六年あるということだな、さてあと四半世紀で私の文学はどこまで進化するだろうと、楽しみなような苦しいような、瀬戸内寂聴氏が八十五歳で書いた金字塔「秘花」にはとうてい及ばずとも、最高峰に近い、渾身の力を出し切った作品を仕上げて、悔いなく息絶えたいと思うのである。作家にはこれが至上ということはないのだろう、ひとつの作品が昇華したら、次はそれ以上のものを目指す、そしてどこまでも上を窮めていく、芸術家の窮極志向、アートの厳しさにほかならないが、少なくとも死ぬ前、これが私の限界ぎりぎりまで出し切ったと悔いのない最高の傑作を仕上げて、思い残すことなく逝きたいと思うのだ。
*解説
自分の長い投稿人生をテーマにしたエッセイだが、今読み返すと、稚拙で出来としてはいまいち。それに、本を四冊出したことにも触れていない。当時は、投稿者が45歳以上に限られるという特異な文学賞、「銀華文学賞」が私にとって、いかに福音をもたらしたということを一番に書きたかったようである(つまり、文芸思潮誌を持ち上げるという不純な動機がなきにしもあらず)。
あれから、三年以上たって、運命の急変に見舞われ、八十半ばまで書き続けたいなどというのんきなことは言っていられなくなり、急遽これまでの三十数年間で書き溜めた百編ほどの小説を、ブログで公表する成り行きになった(E全集の発願)。
「インドで作家業」を十年書き継いできてよかったとしみじみ思う。昔のように作品を埋もれさせずにすむからである。そういう意味では、これが今の私にとっては、最大の福音である。
























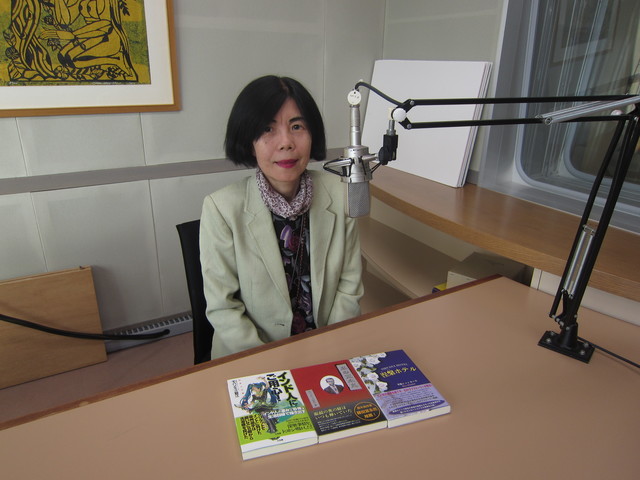
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます