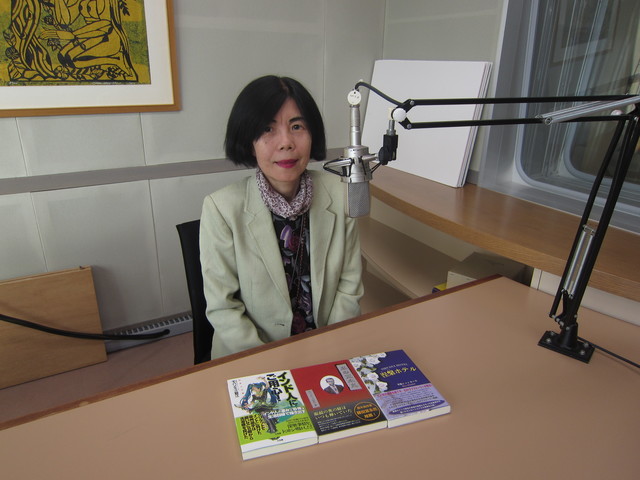直木賞作家の藤田宜永さん死去ー福井出身
私とは縁のあった作家の訃報の続編をお届けします。
一夜明けて、動画ニュースがアップされていたので、ご紹介。
昨日はさすがに落ち込んで、ベンガル湾に白い野菊を流した後、眠れない深夜に弔い酒。
なんといっても、12月4日にメールを戴いてすぐにお返事せず、お亡くなりになった翌日に返信したことが悔まれる。
人は待ってくれない、やはりこちらの事情はどうであれ、二ヶ月近くも放置すべきではなかった。
結局、一期一会のご縁を大切に出来なかったということで。
軽井沢まで訪ねようと思えばいつでも訪ねられたのに、遠慮してしまい、果たせなかったことも残念。
それ以前に福井での講演会のときに、サイン会が終わるまで辛抱強く待ってご挨拶すべきだった。もっともっといろいろお話したいこともあったのに、ぐずぐずしたり、先延ばしにしたりで永久にチャンスを喪ってしまった。
今後の執筆のことなど、相談に乗ってもらいたかったのだが、メールでそうお願いしたときはもう亡き人だった。
が、今頃は向こうの世界で病苦から解放されてほっと寛ぎ、安らいでおられることだろう。
四月に戻り、金沢に半年間滞在する予定なので、この間、故人の作品を読み直してみたい。著書が八十数冊あるので、未読のものもたくさんある。
昨年11月身内を亡くした私にはダブルショックだったが、いくら嘆いても故人が生き返るわけでないので、天国で幸せに暮らしていると考えて、諦めるしかない。
★藤田宜永先生へ
宜永先生、生前は拙作を何度もご拝読いただき感想をお送りくださるなど、ひとかたならぬお世話になり誠にありがとうございました。
拙著「車の荒木鬼」の帯への推薦文も改めて篤く御礼申し上げます。
僭越ながら、作家として成功された人生をまっとうされたこと、大変慶ばしく思います。
大勢の読者を喜ばせる使命を果たされた今は、天国でどうか安らかにお眠りくださいますように。
もう一度お目にかかりたかったと残念ですが、ご高著を紐解かせてていただき、在りし日の先生を偲ばせていただきます。
合掌!
(私の感謝の祈りがどうか、先生に伝わりますように!)
私とは縁のあった作家の訃報の続編をお届けします。
一夜明けて、動画ニュースがアップされていたので、ご紹介。
昨日はさすがに落ち込んで、ベンガル湾に白い野菊を流した後、眠れない深夜に弔い酒。
なんといっても、12月4日にメールを戴いてすぐにお返事せず、お亡くなりになった翌日に返信したことが悔まれる。
人は待ってくれない、やはりこちらの事情はどうであれ、二ヶ月近くも放置すべきではなかった。
結局、一期一会のご縁を大切に出来なかったということで。
軽井沢まで訪ねようと思えばいつでも訪ねられたのに、遠慮してしまい、果たせなかったことも残念。
それ以前に福井での講演会のときに、サイン会が終わるまで辛抱強く待ってご挨拶すべきだった。もっともっといろいろお話したいこともあったのに、ぐずぐずしたり、先延ばしにしたりで永久にチャンスを喪ってしまった。
今後の執筆のことなど、相談に乗ってもらいたかったのだが、メールでそうお願いしたときはもう亡き人だった。
が、今頃は向こうの世界で病苦から解放されてほっと寛ぎ、安らいでおられることだろう。
四月に戻り、金沢に半年間滞在する予定なので、この間、故人の作品を読み直してみたい。著書が八十数冊あるので、未読のものもたくさんある。
昨年11月身内を亡くした私にはダブルショックだったが、いくら嘆いても故人が生き返るわけでないので、天国で幸せに暮らしていると考えて、諦めるしかない。
★藤田宜永先生へ
宜永先生、生前は拙作を何度もご拝読いただき感想をお送りくださるなど、ひとかたならぬお世話になり誠にありがとうございました。
拙著「車の荒木鬼」の帯への推薦文も改めて篤く御礼申し上げます。
僭越ながら、作家として成功された人生をまっとうされたこと、大変慶ばしく思います。
大勢の読者を喜ばせる使命を果たされた今は、天国でどうか安らかにお眠りくださいますように。
もう一度お目にかかりたかったと残念ですが、ご高著を紐解かせてていただき、在りし日の先生を偲ばせていただきます。
合掌!
(私の感謝の祈りがどうか、先生に伝わりますように!)