「焼かれる花嫁」解説(あとがきに代えて)
オリジナル作品(原題「ウイドウフッド」)は三十代後半から四十代の頃に書かれたもので、インドが舞台で登場人物もインド人という、自称エスニック作品(インド物)である。
1987年9月4日、ラジャスタン州・デオララ村で実際に発生した事件が基になっている。すなわち、18歳の美貌の未亡人、ループ・カンワールが夫のなきがらが納められた火葬の薪(まき)の間に横たわって、寡婦殉死制度の風習(サティー・SATI)にのっとって共に荼毘に付されていった、二十世紀の現代の震撼すべき事件(英語のウイキはこちらのRoop Kanwarをどうぞ。日本語の事件のあらましはこちら)である。
まるで人間バーベキュー、生きながら焼かれていくいけにえにも等しく、野蛮で非人道的行為と異人の私の衝撃は計り知れなかったが、インド全土をも揺るがせたショッキングな出来事でもあった。州政府は当初、宗教的儀式との口実のもとに動かず、女性運動家などから槍玉に挙げられ、やっと親族や僧など45名の事件関与者の検挙に取り掛かったが(主犯とされた義父は現場にいなかったとのアリバイが通り、最終的に11名)、証拠不十分で後日釈放を余儀なくされた。
サティが敢行された翌日には(デオララ村では七十年後の二度目だった)火葬現場には五万名以上の信者が殺到、その後五十万以上と膨れ上がり、寺院建立の寄付金も300万ルピー集まったといわれる。火葬現場が聖地化され後続の被害者を出さないためにも州政府は立ち入り禁止措置をとったが、訪問者は跡を絶たず、夫妻が住んでいた部屋は博物館と化し、新郎新婦の額写真が飾られ、サティ前ループがまとった銀色のサリーが展示されたという。
聖女伝説に拍車がかかり、結婚生活が八ヶ月と短かったせいか、ループは処女だったとのまことしやかな噂まで流れ(真偽は定かでない)、物書きの私の創作意欲を刺激せずにはおかなかった。
外人の異教徒である私は、ループの本心を、親族に強制されてやむをえず行った、あと寡婦の峻厳な生活いやさからサティマター(女神)となって蘇る道を選んだと解釈し、この線で筋書きを進めたが(強制説は安易ながらもサスぺンスタッチの面白みもあるように思えた)、自ら進んでサティを行ったとの証言もあり、夫の死後(小説と違って、現実にはループは夫<マル・シン24歳>の死亡時<胃痛と嘔吐の急病で急遽入院>実家に帰っており、死に目に会えなかった)、即座に殉死願望を明確にしたループを、僧侶らが真意をただすため訪問、親族が翻意を促したともいわれるが、ゆるがなかったとの証言もある。それと、火葬の槙の間に座したループが夫のなきがらの頭部をひざの間に抱えるようにし、15歳の義弟に点火を促したものの、火が槇になかなかつかず、ループ自身も手助けしたが不可能で、見守る群集が家にギー(精製バター油、食用のほか聖なる火をたく儀式に使われる)をとりに戻って与えたという真偽の定かでない証言もあったことを付け加えておく。
父親がトラック運送業を営む裕福な家庭で育ったループは教育を受けたモダンな娘の一面、サティ寺院で一日四時間のお祈りを欠かさない敬虔さも持ち合わせていたため、天に召されて神となった夫の後を追うのは自然で、自発心からサティ宣言したというのが、自発説をとる側の主張のひとつである。
第三者で外人異教徒である私には、仮にそれが真実だとしても、宗教的洗脳としか思えず、二十世紀の現代インドの極度の女性差別、女性を一個の人間と見ない非人道的で野蛮な因習と反感を覚えるばかりだが、ループ亡きあとは真偽の確かめようもなく、後に遺された者が貧しい想像をするしかない。というわけで、この事件をフィクション化した私も、作品としてどこまでループの真意に肉迫できたかははなはだ危ういところで、今思うのは、自発心から行ったとのアングルもとることができたということである。もしかしてそのほうが面白くなったかもしれないと思うこともあるわけだが、ただ、ヒンドゥ教徒でない私には、こちらのアングルで行くと、創作が至難になることは目に見えている。心理の綾に分け入ることは異教徒には難しく、ただの良妻の鑑で終わってしまう危惧がある。真意に近づけず、上滑りに終わってしまう可能性もあるわけで、この辺が私の限界、とりあえず強制説でいった作品が、受賞したことでそのまま活かして公表させてもらうことにした。
力不足で書ききれていないところもあり、まだ言い足りない部分もたくさんあるし、後年もう少し納得行く形で作品化できるかもしれないが、とりあえずは現在のスタイルで出すことにした。
最初百枚くらいの長さで「ウィドウフッド」(寡婦)というタイトルだった同作品は、文学界新人賞はじめのいくつかの文学賞に投稿し、落選、2014年に短編に改筆推敲して(ヒンドゥ寡婦の悲惨な境遇からサティに的を絞り直した)、銀華文学賞に送り、佳作を射止めたものである。
このショッキングな出来事をフィクション化して、日本人に知らしめたいと長年思っていたため、ひとまず受賞を果たせてほっとしたものだ。
18歳の寡婦の世間の思惑と本人の生きたいという欲求との板ばさみになって懊悩する心理を想像して書いたが、先にも言ったように、所詮外国の異教徒である私には強制説をとったにしろ、どこまで肉迫できたたかとの疑問は残る。
二十世紀のインド社会にいまだになごる野蛮極まりない風習を作品化して、日本人にも知ってもらいたいとの意図だけはひとまず果たせたようである。
エッセイの題材にもなったテーマでもあり(「インド人にはご用心!」中に発表)、インドという国は、ある意味題材の宝庫である。ぎょっと目をむくような奇習がいくつもあり、いずれも作品のテーマになっている(イスラム教徒の婚姻制度についても、二作仕上げ、その一作が先に発表した「ダブルマリッジ」だったが、巷間に知れ渡った重婚制度と違って明らかに異様としかいえない奇習もあり、その他サティのみならずヒンドゥ教の奇習もあって、それらをテーマにした作品は今後発表する予定でいる)。
*豆知識(ウイキから要約引用)
サティーは、ヒンドゥー社会における慣行で、寡婦が夫の亡骸とともに焼身自殺をすることである。日本語では「寡婦焚死」または「寡婦殉死」と訳されている。本来は「貞淑な女性」を意味する言葉であった。
古くは紀元前4世紀のギリシア人は西北インドで寡婦焚死の風習があった記録を残しており、中世にはインドの各地方に広まった。17世紀のムガル帝国で支配者層であったムスリムは、サティーを野蛮な風習として反対していたが、被支配者層の絶対多数であるヒンドゥー教徒に配慮し、完全に禁じていたわけではなかった。必ずしも寡婦の全てがサティーを望んだわけではなく、中にはヨーロッパ人や家族の説得に応じて寸前で思いとどまった者もいたが、ほとんどの志願者は夫と共に焼け死ぬ貞淑な女性として自ら炎に包まれた。炎を前に怖気づいた者は、周りを囲むバラモンに無理やり押し戻されるか、仮に逃げたとしても背教者としてヒンズー社会から排除されるため、その最下層(アウト・カースト)の者に身を委ねざるを得なかった。
18世紀の初めにはサティーはほとんど行われなくなったが、イギリス植民地時代の18世紀末以降、ベンガル地方の都市部で再び盛んになる。理由は諸説あり、植民地時代の混乱の中で寡婦が夫の幽鬼を宿す不吉な存在として不安の矛先が向けられたという説や、ベンガル地方の法律が寡婦に相続権を認めており、夫の親族によってサティーを強制されたという説もある。1829年にベンガル総督ベンティンクによって、サティー禁止法が制定された。また、1830年にはマドラス、ボンベイにおいても禁止法が制定された。結果、禁止法の普及に伴って20世紀の初めにはサティーはほとんど行われなくなったが、禁止法が近代法制化された現在においてなお、稀にではあるが慣行として行われ続けている。
中世において、サティーはその家族の宗教的な罪科を滅する功徳ともされていたが、必ずしも自発的なものではなく、生活の苦難さによるもの、あるいは親族の強要によるもの、さらには、薬物を利用したものもみられた。ヒンドゥーにおける理想的な女性とは、貞節を守り、献身的に夫に尽くす女性である。サティーが盛んになった19世紀ごろ、再婚は堕落とみなされ、寡婦は厳しい禁欲生活を余儀なくされていた。また、上位カーストでは寡婦は不吉な存在とされた。
オリジナル作品(原題「ウイドウフッド」)は三十代後半から四十代の頃に書かれたもので、インドが舞台で登場人物もインド人という、自称エスニック作品(インド物)である。
1987年9月4日、ラジャスタン州・デオララ村で実際に発生した事件が基になっている。すなわち、18歳の美貌の未亡人、ループ・カンワールが夫のなきがらが納められた火葬の薪(まき)の間に横たわって、寡婦殉死制度の風習(サティー・SATI)にのっとって共に荼毘に付されていった、二十世紀の現代の震撼すべき事件(英語のウイキはこちらのRoop Kanwarをどうぞ。日本語の事件のあらましはこちら)である。
まるで人間バーベキュー、生きながら焼かれていくいけにえにも等しく、野蛮で非人道的行為と異人の私の衝撃は計り知れなかったが、インド全土をも揺るがせたショッキングな出来事でもあった。州政府は当初、宗教的儀式との口実のもとに動かず、女性運動家などから槍玉に挙げられ、やっと親族や僧など45名の事件関与者の検挙に取り掛かったが(主犯とされた義父は現場にいなかったとのアリバイが通り、最終的に11名)、証拠不十分で後日釈放を余儀なくされた。
サティが敢行された翌日には(デオララ村では七十年後の二度目だった)火葬現場には五万名以上の信者が殺到、その後五十万以上と膨れ上がり、寺院建立の寄付金も300万ルピー集まったといわれる。火葬現場が聖地化され後続の被害者を出さないためにも州政府は立ち入り禁止措置をとったが、訪問者は跡を絶たず、夫妻が住んでいた部屋は博物館と化し、新郎新婦の額写真が飾られ、サティ前ループがまとった銀色のサリーが展示されたという。
聖女伝説に拍車がかかり、結婚生活が八ヶ月と短かったせいか、ループは処女だったとのまことしやかな噂まで流れ(真偽は定かでない)、物書きの私の創作意欲を刺激せずにはおかなかった。
外人の異教徒である私は、ループの本心を、親族に強制されてやむをえず行った、あと寡婦の峻厳な生活いやさからサティマター(女神)となって蘇る道を選んだと解釈し、この線で筋書きを進めたが(強制説は安易ながらもサスぺンスタッチの面白みもあるように思えた)、自ら進んでサティを行ったとの証言もあり、夫の死後(小説と違って、現実にはループは夫<マル・シン24歳>の死亡時<胃痛と嘔吐の急病で急遽入院>実家に帰っており、死に目に会えなかった)、即座に殉死願望を明確にしたループを、僧侶らが真意をただすため訪問、親族が翻意を促したともいわれるが、ゆるがなかったとの証言もある。それと、火葬の槙の間に座したループが夫のなきがらの頭部をひざの間に抱えるようにし、15歳の義弟に点火を促したものの、火が槇になかなかつかず、ループ自身も手助けしたが不可能で、見守る群集が家にギー(精製バター油、食用のほか聖なる火をたく儀式に使われる)をとりに戻って与えたという真偽の定かでない証言もあったことを付け加えておく。
父親がトラック運送業を営む裕福な家庭で育ったループは教育を受けたモダンな娘の一面、サティ寺院で一日四時間のお祈りを欠かさない敬虔さも持ち合わせていたため、天に召されて神となった夫の後を追うのは自然で、自発心からサティ宣言したというのが、自発説をとる側の主張のひとつである。
第三者で外人異教徒である私には、仮にそれが真実だとしても、宗教的洗脳としか思えず、二十世紀の現代インドの極度の女性差別、女性を一個の人間と見ない非人道的で野蛮な因習と反感を覚えるばかりだが、ループ亡きあとは真偽の確かめようもなく、後に遺された者が貧しい想像をするしかない。というわけで、この事件をフィクション化した私も、作品としてどこまでループの真意に肉迫できたかははなはだ危ういところで、今思うのは、自発心から行ったとのアングルもとることができたということである。もしかしてそのほうが面白くなったかもしれないと思うこともあるわけだが、ただ、ヒンドゥ教徒でない私には、こちらのアングルで行くと、創作が至難になることは目に見えている。心理の綾に分け入ることは異教徒には難しく、ただの良妻の鑑で終わってしまう危惧がある。真意に近づけず、上滑りに終わってしまう可能性もあるわけで、この辺が私の限界、とりあえず強制説でいった作品が、受賞したことでそのまま活かして公表させてもらうことにした。
力不足で書ききれていないところもあり、まだ言い足りない部分もたくさんあるし、後年もう少し納得行く形で作品化できるかもしれないが、とりあえずは現在のスタイルで出すことにした。
最初百枚くらいの長さで「ウィドウフッド」(寡婦)というタイトルだった同作品は、文学界新人賞はじめのいくつかの文学賞に投稿し、落選、2014年に短編に改筆推敲して(ヒンドゥ寡婦の悲惨な境遇からサティに的を絞り直した)、銀華文学賞に送り、佳作を射止めたものである。
このショッキングな出来事をフィクション化して、日本人に知らしめたいと長年思っていたため、ひとまず受賞を果たせてほっとしたものだ。
18歳の寡婦の世間の思惑と本人の生きたいという欲求との板ばさみになって懊悩する心理を想像して書いたが、先にも言ったように、所詮外国の異教徒である私には強制説をとったにしろ、どこまで肉迫できたたかとの疑問は残る。
二十世紀のインド社会にいまだになごる野蛮極まりない風習を作品化して、日本人にも知ってもらいたいとの意図だけはひとまず果たせたようである。
エッセイの題材にもなったテーマでもあり(「インド人にはご用心!」中に発表)、インドという国は、ある意味題材の宝庫である。ぎょっと目をむくような奇習がいくつもあり、いずれも作品のテーマになっている(イスラム教徒の婚姻制度についても、二作仕上げ、その一作が先に発表した「ダブルマリッジ」だったが、巷間に知れ渡った重婚制度と違って明らかに異様としかいえない奇習もあり、その他サティのみならずヒンドゥ教の奇習もあって、それらをテーマにした作品は今後発表する予定でいる)。
*豆知識(ウイキから要約引用)
サティーは、ヒンドゥー社会における慣行で、寡婦が夫の亡骸とともに焼身自殺をすることである。日本語では「寡婦焚死」または「寡婦殉死」と訳されている。本来は「貞淑な女性」を意味する言葉であった。
古くは紀元前4世紀のギリシア人は西北インドで寡婦焚死の風習があった記録を残しており、中世にはインドの各地方に広まった。17世紀のムガル帝国で支配者層であったムスリムは、サティーを野蛮な風習として反対していたが、被支配者層の絶対多数であるヒンドゥー教徒に配慮し、完全に禁じていたわけではなかった。必ずしも寡婦の全てがサティーを望んだわけではなく、中にはヨーロッパ人や家族の説得に応じて寸前で思いとどまった者もいたが、ほとんどの志願者は夫と共に焼け死ぬ貞淑な女性として自ら炎に包まれた。炎を前に怖気づいた者は、周りを囲むバラモンに無理やり押し戻されるか、仮に逃げたとしても背教者としてヒンズー社会から排除されるため、その最下層(アウト・カースト)の者に身を委ねざるを得なかった。
18世紀の初めにはサティーはほとんど行われなくなったが、イギリス植民地時代の18世紀末以降、ベンガル地方の都市部で再び盛んになる。理由は諸説あり、植民地時代の混乱の中で寡婦が夫の幽鬼を宿す不吉な存在として不安の矛先が向けられたという説や、ベンガル地方の法律が寡婦に相続権を認めており、夫の親族によってサティーを強制されたという説もある。1829年にベンガル総督ベンティンクによって、サティー禁止法が制定された。また、1830年にはマドラス、ボンベイにおいても禁止法が制定された。結果、禁止法の普及に伴って20世紀の初めにはサティーはほとんど行われなくなったが、禁止法が近代法制化された現在においてなお、稀にではあるが慣行として行われ続けている。
中世において、サティーはその家族の宗教的な罪科を滅する功徳ともされていたが、必ずしも自発的なものではなく、生活の苦難さによるもの、あるいは親族の強要によるもの、さらには、薬物を利用したものもみられた。ヒンドゥーにおける理想的な女性とは、貞節を守り、献身的に夫に尽くす女性である。サティーが盛んになった19世紀ごろ、再婚は堕落とみなされ、寡婦は厳しい禁欲生活を余儀なくされていた。また、上位カーストでは寡婦は不吉な存在とされた。
























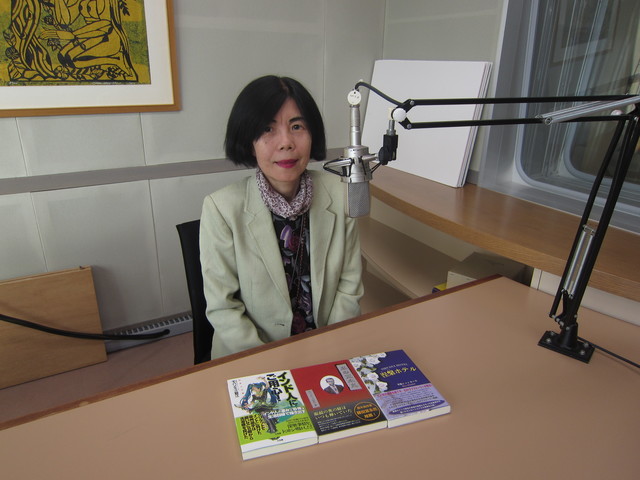

寡婦の殉死に見物客が集まるというところが本当に恐ろしいです。
近年の若者のなかには持参金(ダウリー)制度を拒否する者も出てきているようですが、保守的な田舎では、ダウリーがらみの自殺や殺人事件が後を絶ちません。
宗教、カースト、言語、民族の相違による差別といい、いろいろと問題の多い国です。インドは顕著な差別国です。近年では、中央政府が右寄りのヒンドゥ至上主義を標榜するインド人民党なので、イスラム教徒やダリットといわれるアウトカーストの殺人事件も頻発してます。ヒンドゥ教では牛は神様、しかし、ムスリムは牛肉を食べるので、ターゲットになってるんです。
同じインド人なのに、北東州の人たちも異国人扱い、アジア系の顔立ちなので、チン(中国人)と見下されています。
あと、レイプ地獄です。それも、被害者は赤ん坊や少女が多い、嘆かわしい実情です。周囲の者や親族による性虐待も。当オディッシャ州でも、私が帰国中に未成年少女のレイプ事件が大きな問題になったようです。
三十年もいると、粗ばかり目立ってきて、ほんと私自身辟易しているところもあるんですよ。三十年たっても、汚いし、当地プリーは悪いほうに変わっています。
昔の穴場的静けさよ、今いずこです。
ベンガル海もごみだらけ。
それでも、日印一長一短ということになるのでしょうけど。
長くなってすみません。
寡婦に殉死を強いたり、花嫁を焼き殺したりするのが、無学で貧しく迷信深い人々だけなら、まだしもわかりやすいのですが、この事件の花嫁は高学歴というところがまたおそろしいです。
我が家の近所の国立大学にもインド人留学生がたくさんいますが、彼らの中にもそういうことをしかねない人がいるのかもしれないのでしょうか?
日本人から見て「その手の人」は見分けられますか?
寡婦殉死制度の場合は、二番目の王侯貴族・戦士カースト、とくにラジャスタン州のラジプート間の風習で、古来敢行されてきた宗教的な因習ですが、シバ神の奥さんが貞操を疑う夫に、身の潔白を証明するため火中に飛び込んだという神話伝説が由来らしいです。
しかし、ダウリー関連の自殺や焼死事件は、主に中産階級が強欲に駆られて持参金の追加要求、嫁いびり、虐待に耐えられず、嫁本人が自殺したり、あるいは自殺に見せかけて婚家が焼き殺したりと、人としてもモラルを疑う、いわば人間の心の闇があらわになったもので、悪慣習が横行する社会環境に多分に触発された部分はあると思います。
でも、どんな性質の事件にしろ、人を殺してはいけないというモラルがからきし欠如しているわけで、そういう意味では特殊な人間、加害者は意識していなくても精神異常者、病的な人たちでしょうね。
当州では、近年高名な州大臣である男性の長男の嫁がダウリー騒動を引き起こし、論議をかもしました。嫁がダウリーの追加要求に反発して公に告発、大臣は辞職に追い込まれましたが、後年和解、今は子どももできて万事首尾よく納まったようです。
政治家って、インドでは大金持ちの特権階級ですよ。にもかかわらず、恥さらしなダウリー追加、まあ、政治家は選挙に莫大な費用が要るのでいくら金があっても足りないというところかもしれませんが。
外見から見分けるのは難しいです。
日本に留学するような志の高い人たちにはそういう人はいないと思いたいですが。近年の若者にはダウリーを要求しない人も増えているようです。
確かにこうした一種の女性迫害は、保守的な男尊女卑のインド社会では頻発していますが、殺人にいたるというのは、人間としてやはり異常の少数派です。インド人の大多数はノーマルですよ。
ただ差別国なので、宗教・カースト・民族の相違に端を発する殺人事件は頻発します。近年は、牛を食べたとか、牛を(とさつ)したというイスラム教徒が、ヒンドゥ右翼のリンチにあって殺される事件がたびたび起きています。
インド人はごみ捨てぽいといい、公衆のモラルに欠ける人種でもありますね。自分の家さえきれいであればいいんです。まあ、人間としてのレベルは開発途上、遅れてますね。けど、反面、いいところもあるわけで。
日印、一長一短と思います。