某元首相が言及したことで一時話題となった「鈍感力」。先日買い物へ行ったついでに立ち寄った本屋さんで、パラパラと立ち読みをしました。まぁ全部を読んだわけではないので文句言うのもなんなのですが、おそらく「悪い意味で」鈍感な人たち(某元首相を含む)が、「オレたち、間違ってないよね」と正当化、あるいは自己肯定するためには恰好の本です。
「鈍感力」読まずともだいたい内容を推測できる方も大勢いらっしゃると思いますが、要するにストレス社会を生き抜くためには、ストレスに対して、あるいはストレスフルな状況において「気がつかない」「過敏に反応しない」という戦略をとるべきだという論旨なんですね。言い換えれば、センサーを可能な限り下げておくべきであるといっているんです。
ストレス社会において、実際にこのような戦略が最も生存率を高めるかどうかというのはさておき(少なくとも自然界では、最も生存率の低い戦略だと思われる)、私個人としては「そのような人と一緒に仕事をしたくないし、家庭生活もしたくない」と思います。なぜなら常にセンサーの低い人間というのは、ひとや状況に対して「無関心」であり、結果的に周囲に対しての配慮を欠く「気の利かない」人間であるということだからです。あなたはそんな人と一緒に働いたり、生活したいと思いますか?
そもそもストレスというものは、常に「取り除かれるべき悪」であるというわけではありません。なぜならストレスとは、「人が、何か、誰かを大切に思うこと」から生じてくるものだからです。例えば、あなたが愛する人を突然亡くす。その状況というのは、ものすごくストレスです。それというのも、あなたが亡くなったその人を大切に思っているからであって、もしその人のことをあなたがどうでもいいと思っているならば、その人が亡くなってもストレスに感じることはないでしょう。「鈍感力」の論旨でいえば、もしあなたがストレスを引き受けたくないのであれば、「その人をどうでもいいと思え」ばいいというわけです。そんな馬鹿な!ですよね。少なくとも私は、ストレスを避けるために「何か、誰かを大切に思う」ことのない人生を選ぶなんて、まっぴらごめんです。
私たちは多かれ少なかれ、「何か、誰かを大切に思うこと」とひきかえに、そこから生じるストレスを引き受けなければならないようになっているのです。ストレスの原因(私たちが大切に思う何か、誰か)を取り除くことはできない。しかし、折り合いをつけていくことはできる。ストレスとは、そういう性質のものです。その折り合いをつけていく過程(ストレス・コーピング)で、戦略的にセンサーを上げたり下げたりすることはあるかもしれませんが、ストレスを引き受けることを避けるために、はじめからセンサーを下げて無関心でいることを選べというのはあんまりだと思うのです。
また話は少しかわりますが、この本の中で「母親とは鈍感の最たるものだ」ということが書かれていました。赤ちゃんのためならば人目を憚らずにおっぱいを出す、赤ちゃんの泣き声をうるさく思わない・・・などの例が挙げられていました。ここでもまた「しょーもないなぁ、この人は」と憤りを通り越して呆れたのですが・・・母親こそ、センサーを高く保っておかないといけない存在なんですね。それはもう、種の存続のために絶対的に必要なことなのです。赤ちゃんが泣いていることに気がつかなければ、赤ちゃんが死んでしまう可能性もあります。またその泣き声も、お腹がすいて泣いているのか、おしめがぬれているから泣いているのか、はたまた常とは違うことが赤ちゃんに起こっているのか、敏感に察知しなければなりません。母親が赤ちゃんの泣き声をうるさく思わないのは、それが赤ちゃんからの必死なサインであるからであり、それをキャッチして読み解く必要があるからです。センサーを低くしていては、赤ちゃんからのサインをキャッチすることはとうていできません。そして母親が赤ちゃんのためにセンサーを高くしておけるのは、ー先ほどは種の存続のためといいましたがそれだけではなくー赤ちゃんを大切に思う気持ち、すなわち愛の存在なんです。赤ちゃんへの愛が母親のセンサーを高め、結果的にそれが赤ちゃんの生存率を高めることにつながるという仕組みになっているのだと思われます。
こう書いてきて気がつきましたが・・・
要するに鈍感力を発揮できる人=センサーが低い人=愛のない人、なんだ。
だから「ダメ」なんだね。
愛がなければ、どれだけ正しそうなことを言っていてもアウトです。そういう意味でも、フェミニズムにも愛が必要だと思う今日この頃なのですが、長くなるので今日のところはこれにて失礼・・・
「鈍感力」読まずともだいたい内容を推測できる方も大勢いらっしゃると思いますが、要するにストレス社会を生き抜くためには、ストレスに対して、あるいはストレスフルな状況において「気がつかない」「過敏に反応しない」という戦略をとるべきだという論旨なんですね。言い換えれば、センサーを可能な限り下げておくべきであるといっているんです。
ストレス社会において、実際にこのような戦略が最も生存率を高めるかどうかというのはさておき(少なくとも自然界では、最も生存率の低い戦略だと思われる)、私個人としては「そのような人と一緒に仕事をしたくないし、家庭生活もしたくない」と思います。なぜなら常にセンサーの低い人間というのは、ひとや状況に対して「無関心」であり、結果的に周囲に対しての配慮を欠く「気の利かない」人間であるということだからです。あなたはそんな人と一緒に働いたり、生活したいと思いますか?
そもそもストレスというものは、常に「取り除かれるべき悪」であるというわけではありません。なぜならストレスとは、「人が、何か、誰かを大切に思うこと」から生じてくるものだからです。例えば、あなたが愛する人を突然亡くす。その状況というのは、ものすごくストレスです。それというのも、あなたが亡くなったその人を大切に思っているからであって、もしその人のことをあなたがどうでもいいと思っているならば、その人が亡くなってもストレスに感じることはないでしょう。「鈍感力」の論旨でいえば、もしあなたがストレスを引き受けたくないのであれば、「その人をどうでもいいと思え」ばいいというわけです。そんな馬鹿な!ですよね。少なくとも私は、ストレスを避けるために「何か、誰かを大切に思う」ことのない人生を選ぶなんて、まっぴらごめんです。
私たちは多かれ少なかれ、「何か、誰かを大切に思うこと」とひきかえに、そこから生じるストレスを引き受けなければならないようになっているのです。ストレスの原因(私たちが大切に思う何か、誰か)を取り除くことはできない。しかし、折り合いをつけていくことはできる。ストレスとは、そういう性質のものです。その折り合いをつけていく過程(ストレス・コーピング)で、戦略的にセンサーを上げたり下げたりすることはあるかもしれませんが、ストレスを引き受けることを避けるために、はじめからセンサーを下げて無関心でいることを選べというのはあんまりだと思うのです。
また話は少しかわりますが、この本の中で「母親とは鈍感の最たるものだ」ということが書かれていました。赤ちゃんのためならば人目を憚らずにおっぱいを出す、赤ちゃんの泣き声をうるさく思わない・・・などの例が挙げられていました。ここでもまた「しょーもないなぁ、この人は」と憤りを通り越して呆れたのですが・・・母親こそ、センサーを高く保っておかないといけない存在なんですね。それはもう、種の存続のために絶対的に必要なことなのです。赤ちゃんが泣いていることに気がつかなければ、赤ちゃんが死んでしまう可能性もあります。またその泣き声も、お腹がすいて泣いているのか、おしめがぬれているから泣いているのか、はたまた常とは違うことが赤ちゃんに起こっているのか、敏感に察知しなければなりません。母親が赤ちゃんの泣き声をうるさく思わないのは、それが赤ちゃんからの必死なサインであるからであり、それをキャッチして読み解く必要があるからです。センサーを低くしていては、赤ちゃんからのサインをキャッチすることはとうていできません。そして母親が赤ちゃんのためにセンサーを高くしておけるのは、ー先ほどは種の存続のためといいましたがそれだけではなくー赤ちゃんを大切に思う気持ち、すなわち愛の存在なんです。赤ちゃんへの愛が母親のセンサーを高め、結果的にそれが赤ちゃんの生存率を高めることにつながるという仕組みになっているのだと思われます。
こう書いてきて気がつきましたが・・・
要するに鈍感力を発揮できる人=センサーが低い人=愛のない人、なんだ。
だから「ダメ」なんだね。
愛がなければ、どれだけ正しそうなことを言っていてもアウトです。そういう意味でも、フェミニズムにも愛が必要だと思う今日この頃なのですが、長くなるので今日のところはこれにて失礼・・・

















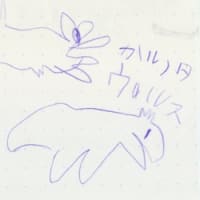
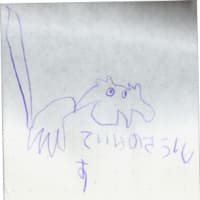





最後の方程式、同感です!あと無関心と云う件も。
TVのワイドショーなどで、ひとつの事件の容疑者などについて関係者にインタビューして、その返答に「普通の人でしたよ」って言葉をよく聞きます。
この“普通”ってどう普通だったのか?いつも疑問で、きっとその感覚としては“よく知らない”と言う無関心なのではないかしら?と感じます。
近所付き合いも気薄となってきている昨今の症状、無関心。著者はTVで鈍感力の意図する事を言ってましたが、忘れました…(まさに鈍感)
最後にワタシも緊張感と云うストレスは持っていたい方です。
長くなってスミマセン。
ありがとう!!
鈍感になんか、なりたくないですよね。でも身体って、鈍感にさせようと必死なんです。
昔「人に愛されなくなるのと、愛せなくなるのと、どっちがいい?」と聞かれた時のことを思い出しました。どっちも嫌だけど…
普段はのほほ~んと暮らしている初々さんですが、たまーにスイッチが入ると(刺激があると)書きながらものを考えます。なので今回もそうですが、書き終わるまで自分が何を考えているのか分からなかったりします・・・へんなこと言っていたら、ご指摘お願いします!
「よく知らない」という無関心・・・確かにそうですね。関心をもって見なければ見えてこないものってたくさんありますね。関心を持てること・・・つまり自分以外の対象に愛情を向けられるのは、昨今では本当に狭い人間関係に限られてきてしまっているのでしょうか。(だからご近所づきあいも希薄になっているのでしょうか)
お久しぶりです!ブログ読ませて頂いています。一度こ初々さんとともに下鴨サプライズに遊びにいきたいな~なんて思っております。
「身体は鈍感にさせようと必死」それはそうなんだと思います。身体にとっては、必要以上のセンシビリティは死活問題ですものね。意味をなさない雑音を拾ってしまっても大変ですし、問題にならないくらいの侵入物(花粉とか)に反応してしまうのもしんどいですし・・・状況によって、戦略的に(自覚的にも無自覚的にも)センサーを上げたり下げたりすることができるといいのですけれども、なかなかこれは高度すぎる技であって・・・私を含めて普通の人が出来るのは、せいぜい「フレキシブルであること」かなぁと思っております。
愛されないのと愛せないのを選ぶとしたら、私は「愛されない」かなぁ。愛されないのに愛すことが出来たら、あらゆるものを超えられそうな気が・・・
その中で、何が正しく何が間違っているのか?それを見誤ってしまうと、行きつく場所が幸せから遠ざかってしまう気がします。
今は子供相手に育自の日々ですが、自分を育てる道は子育てと違って終わり無き道。
毎日を葛藤しながら、世の中の矛盾に怒りながら、自分育てをしていこうと思っています。
鈍感では、人は成長できませんから!
何が正しく、何が間違っているのか?という判断は、とても難しいものでしょうが・・・「ん?おかしいぞ」という感覚を持っていられるためにも、そんなにセンサーを下げていたのではいけないなぁと思います。
「育自」というのは、ふる~る・じゅ~るさんが考えられた言葉ですか?確かに子育てをしていると、自分について考えさせられるとき、また「これは試練だぞ」と思うようなときがあります。
子育てを通して、また違った自分に気づく、出逢える、変わっていく、ということを楽しめるといいなぁと思います。