精神科医師中井久夫先生の「こんなとき私はどうしてきたか」を読み始めました。中井久夫先生といったら、「医者が治せる患者は少ない。しかし看護できない患者はいない。」という書き出しから始まる「看護のための精神医学」があまりにも有名ですが、「こんなとき私はどうしてきたか」もその延長線上にあるような本です。
それにしても中井先生は医師であるにも関わらず、「看護できない患者はいない」と看護の本質をずばり言い表すことができるんですね。すごいなぁと思います。看護職でもそのように表現し、言いきることのできる人って少ないのでは・・・とすら思うくらい。そしてそれは精神科だけに限ったことではもちろんなく、どんな診療科においても等しく普遍的に言えることでもあります。
医師が病気を診断し治療するーつまり、病気(や障害)そのものを扱うのに対し、看護が扱うのは「病気(や障害)から派生する、生活を営む上で困ること」です。例えばがんの患者さんがいるとしましょう。医師はがんという診断を下し、それに対して治療を行いますが、看護が問題にするのは「がん」という病気ではありません。がんという病気を患うことによって生じること、例えば痛みがあって夜よく眠れないだとか、食事をとることができないだとか、あるいは死への恐怖を感じるだとか、そういった患者さん自身が感じたり体験している生活上の「困ったこと」に焦点を当てて、病気を体験する以前とは違った新しい生活を再構築していくお手伝いをするのが看護の仕事です。ですから、「病気になったけど、何も変わらないし、困っていないよ」という方は別として、どんな状況、どんな人でもーたとえ病気が治らず死にゆくときも(つまり医師が治療を断念するときも)ー看護という営みはなされ得ます。そういう意味で、「看護できない患者はいない」んですね。
精神科でも同様です。例えば幻聴や妄想のある患者さん。医師はそれに対して治療を行いますが、看護ではそれ自体を問題として扱うことはなく、それは「ある」ものとして関わり、援助を行います。つまり、幻聴にしても妄想にしても、それをどうこうするというのは看護の仕事ではないということです。では何を問題にするのかというと、幻聴なり妄想があることによって患者さんが「困ること」。おそらく患者さんが幻聴なり妄想があることで困っているのは、まず一番には「怖い」ということでしょう。幻聴や妄想の内容によっても異なりますが、例えば「テレビで死ねと言われている」などという内容でしたら、患者さんが怖くて仕方が無いというのは当然です。そういった患者さんが感じている恐怖を、多少なりとも和らげてあげる。これは看護の仕事になります。その方法は、患者さんによっても、関わる看護師によっても、千差万別。一般に教科書には「幻聴や妄想に対しては、否定も肯定もしないこと」などと書いてありますが、もし実際に「テレビで死ねと言われている」と言われた場合、みなさんだったらどう答えますか?否定も肯定もしないということは、「そうですか、テレビで死ねと言われているんですね。私には聞こえないのに不思議だなぁ。」という受け答えが無難になってくるでしょうが、それだけでは5分と間がもちません。そうですよね?「テレビで死ねと言われています」「そうですか?私には聞こえませんけど。」「でも私には聞こえるんです。」「あなたには聞こえるんですね。私には聞こえないのに不思議だなぁ。」「不思議でもなんでもなくて、私には聞こえるんです。」・・・これをえんえんと繰り返すというのも、繰り返すことにこちらが耐え得るのならば「あり」だとは思うのですが、私にはちょっと出来そうにありません。そんな私がよく手段として選ぶのは、「問題一時棚上げ法」。ひととおり患者さんの不安や怖さの訴えを聞いたら、「ちょっと、違うことしてみませんか?」と誘ってみる。例えば絵を描いたり、手作業を一緒にしてみたり。そうすることで幻聴や妄想がなくなるわけではありませんが、幻聴や妄想から一時でも気がそれることができれば、その間だけでも不安や恐怖を感じずに過ごすことができます。そんな時間を少しづつ増やしていけたら。根本的な問題解決にはなりませんが、そう願いながら関わっていることが多いです。とにかく幻聴や妄想があっても、本人が日常生活で困っていないならそれでいい。困っていたら、日常生活が破綻せずに営めるようにお助けする。もしかしたら一般の方には、それが看護?と驚かれることかもしれませんね。
でもね、問題を一時棚上げにできるっていうのは健康な証拠なんです。答えのない問いを問い続け、解決できない問題を解決しようともがきながらも、お腹がすいてご飯が食べられる。これは「生活を営む上で、優先順位を間違えていない」っていうことですよね。これこそ人間のもつたくましい能力。ときに精神科の患者さんたちにかわってその能力を発揮することも、仕事のうちにしてしまっているナース初々です。
で、何が言いたかったんだっけな・・・またしても変なところに着地してしまったようです。
それにしても中井先生は医師であるにも関わらず、「看護できない患者はいない」と看護の本質をずばり言い表すことができるんですね。すごいなぁと思います。看護職でもそのように表現し、言いきることのできる人って少ないのでは・・・とすら思うくらい。そしてそれは精神科だけに限ったことではもちろんなく、どんな診療科においても等しく普遍的に言えることでもあります。
医師が病気を診断し治療するーつまり、病気(や障害)そのものを扱うのに対し、看護が扱うのは「病気(や障害)から派生する、生活を営む上で困ること」です。例えばがんの患者さんがいるとしましょう。医師はがんという診断を下し、それに対して治療を行いますが、看護が問題にするのは「がん」という病気ではありません。がんという病気を患うことによって生じること、例えば痛みがあって夜よく眠れないだとか、食事をとることができないだとか、あるいは死への恐怖を感じるだとか、そういった患者さん自身が感じたり体験している生活上の「困ったこと」に焦点を当てて、病気を体験する以前とは違った新しい生活を再構築していくお手伝いをするのが看護の仕事です。ですから、「病気になったけど、何も変わらないし、困っていないよ」という方は別として、どんな状況、どんな人でもーたとえ病気が治らず死にゆくときも(つまり医師が治療を断念するときも)ー看護という営みはなされ得ます。そういう意味で、「看護できない患者はいない」んですね。
精神科でも同様です。例えば幻聴や妄想のある患者さん。医師はそれに対して治療を行いますが、看護ではそれ自体を問題として扱うことはなく、それは「ある」ものとして関わり、援助を行います。つまり、幻聴にしても妄想にしても、それをどうこうするというのは看護の仕事ではないということです。では何を問題にするのかというと、幻聴なり妄想があることによって患者さんが「困ること」。おそらく患者さんが幻聴なり妄想があることで困っているのは、まず一番には「怖い」ということでしょう。幻聴や妄想の内容によっても異なりますが、例えば「テレビで死ねと言われている」などという内容でしたら、患者さんが怖くて仕方が無いというのは当然です。そういった患者さんが感じている恐怖を、多少なりとも和らげてあげる。これは看護の仕事になります。その方法は、患者さんによっても、関わる看護師によっても、千差万別。一般に教科書には「幻聴や妄想に対しては、否定も肯定もしないこと」などと書いてありますが、もし実際に「テレビで死ねと言われている」と言われた場合、みなさんだったらどう答えますか?否定も肯定もしないということは、「そうですか、テレビで死ねと言われているんですね。私には聞こえないのに不思議だなぁ。」という受け答えが無難になってくるでしょうが、それだけでは5分と間がもちません。そうですよね?「テレビで死ねと言われています」「そうですか?私には聞こえませんけど。」「でも私には聞こえるんです。」「あなたには聞こえるんですね。私には聞こえないのに不思議だなぁ。」「不思議でもなんでもなくて、私には聞こえるんです。」・・・これをえんえんと繰り返すというのも、繰り返すことにこちらが耐え得るのならば「あり」だとは思うのですが、私にはちょっと出来そうにありません。そんな私がよく手段として選ぶのは、「問題一時棚上げ法」。ひととおり患者さんの不安や怖さの訴えを聞いたら、「ちょっと、違うことしてみませんか?」と誘ってみる。例えば絵を描いたり、手作業を一緒にしてみたり。そうすることで幻聴や妄想がなくなるわけではありませんが、幻聴や妄想から一時でも気がそれることができれば、その間だけでも不安や恐怖を感じずに過ごすことができます。そんな時間を少しづつ増やしていけたら。根本的な問題解決にはなりませんが、そう願いながら関わっていることが多いです。とにかく幻聴や妄想があっても、本人が日常生活で困っていないならそれでいい。困っていたら、日常生活が破綻せずに営めるようにお助けする。もしかしたら一般の方には、それが看護?と驚かれることかもしれませんね。
でもね、問題を一時棚上げにできるっていうのは健康な証拠なんです。答えのない問いを問い続け、解決できない問題を解決しようともがきながらも、お腹がすいてご飯が食べられる。これは「生活を営む上で、優先順位を間違えていない」っていうことですよね。これこそ人間のもつたくましい能力。ときに精神科の患者さんたちにかわってその能力を発揮することも、仕事のうちにしてしまっているナース初々です。
で、何が言いたかったんだっけな・・・またしても変なところに着地してしまったようです。

















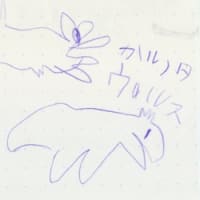
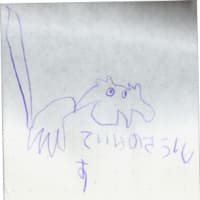





子供ちゃんが邪魔しなければ、もっとはかどるけれど・・・・。(笑)
でも、無い時間をどうにかして都合して、何とか自分の時間を創り出すことは制限がないとやらないでしょうから、これは子供が出来てから得た智慧かな。
ありがたいことです。(*^_^*)
たまたま『時のしずく』というエッセーを読んで感激し、『治療文化論』を買ったところです。読んでみようっと。
そっかあ、そういう点で高名な方なんですね。私は門外漢ですが、でもエッセーから、人間性の豊かさと確かさのようなものを感じて、感銘を受けました。
医療や看護の現場にいるということは、剥き出しの生と接し続けるということなんですね。大変だと思いますが、素晴らしい仕事ですね。そしてそれはそのまま育児に通じる、かな?
医療・心理関係者ではないのに、中井久夫先生をご存知とは!さすが読書家のカナさんですね。
中井先生には私も相当影響を受けていて・・・色々な名言のある方ですが、私が何よりも好きなのは「患者の中にあるまともさを信じられるといい。信じられないなら、念じるだけでもいい」。相手を信じ(あるいは信じたいと思い)、治療に祈りや願いをこめられる(あるいはこめたい)医師なんだなぁと思いました。しかし変わった人であることは確かで、自分で抗精神病薬を試しに飲んでしまったりするそうです。
私は看護師であることにこだわりが全然ないのですが・・いい手段だなぁとは思っています。そして思いがけず結婚をして子どもを与えられてみて、仕事で得られる喜びも、家庭生活や育児で得られる喜びも、その本質はそうかわりはないと気づきました。だからきっとカナさんがニーニャちゃんとの日々で感じる喜びは、そのまま看護の楽しさや喜びに通じると思います。
子どもちゃんがいると、なかなか本を読む時間て作ることが難しいですよね・・・でも合間をぬって読書ができると、気分転換にもなっていいものですね。時間を上手に使う術、私も身につけたいです。
中井久夫や初々さんのことば、沁みるんです。いやもうこれ以上乱暴な表現はないんですが、愛が、あるからなんだろうなあ。相手を無力化して守る、のは簡単、でも、信じる、のは大変ですよね。
私も結婚、出産、ともに思いがけなくやってきてくれたプレゼントでした。基本的に人なのですが、これらの経験を通して、遅ればせながら人間になりつつあるかなと思っています。……って、わしゃ妖怪人間か!
いえいえこちらこそ、妊娠をきっかけにカナさんのブログにお邪魔するようになって、もう本当に色んなことに共感しながら、毎回楽しみに記事を読ませて頂いていました。ありがとうございます、そしてこれからも楽しみに立ち寄らせて頂きます。
ところで中井先生の名言でもうひとつ。『「理解」はついに「信」に及ばない。信なき理解は関係を損ない、相手を破壊する。』ほんとにそうだなぁと思います。結局理解って自分の枠の中に入れることですし、信じるとはそれを超えることなんだろう・・・と頭では分かっていても、それを血肉化するのって難しいですよね。私も結婚、出産、育児をとおして得た出逢いによって、「信」を深めていけたらなぁと願ってやみません。