當る丑歳吉例顔見世興行東西合同大歌舞伎(京都・南座)

歌舞伎を見るのは、だいたい仁左衛門と玉三郎が揃うときだけ。南座の顔見世については5年ぶりだった。
昼の部は後半に見ることにして、今日は夜の部。
相変わらず始まりが慌ただしい。開場が遅れようがどうしようが、時間になると拍子木が高らかになって幕が開く。プログラムを買って、イヤホンガイドを借りて、化粧室へ行って、荷物はどこかへ預けてなど、悠長に準備する暇はほとんどない。とりあえず、座席を見つけたら荷物を抱えたまま座ってただ舞台を見るのみ。
「傾城反魂香 土佐将監閑居の場」
又平のどもりの演技がくどくて、あまり好きになれないのだけれども、あれがないと後半のハッピーエンドも際だたないのだろうか。
手水鉢の石を絵が擦り抜ける仕掛けはどうなっているのだろうかと、そういえば以前見たときも思ったのだった(五年前の顔見世、同じ又平夫婦の配役だった)。
この又平さんと、〈傾城反魂香〉という題目の関係がよくわからなくて、調べたらこんなことだった。
→参考
「元禄忠臣蔵 大石内蔵助最後の一日」
内蔵助以下赤穂の義士たちに裁断が下り、いよいよ覚悟して死に臨むという男たちのシリアスなストーリーの脇から、ただ〈私の恋の真実〉にしか興味のない娘おみのが男装までして潜り込んでくるというちぐはぐさが奇妙で、けれども娘の必死の訴えを聞くうちに、義士たちの大義も娘の恋の真実も等価なのだと思われてくる。
義士たちは死に、吉良家もお家断絶、おみのも自害して、みな滅ぶのに、それこそがハッピーエンドだというところが実に日本的。かなり楽しめた演目。
「信濃路紅葉鬼揃」
お能「紅葉狩」の詞章をそのまま用い、杵屋巳吉が曲を付け、田中傳左衞門が作調、藤間勘十郎が振付をしたとのこと。昨年の歌舞伎座が初演。
舞台の書き割りは能舞台を模した鏡の松。さりげなく蔦紅葉が巻き付けてある。能舞台の屋根も書き割りで吊されている。こうしたお能由来の曲を〈松羽目もの〉と呼ぶらしい。囃子方が舞台後方にずらりと並ぶ。小鼓は傳左衞門、太鼓は傳次郎。
冒頭、玉三郎を筆頭に唐織壺折姿の上臈が六名、花道から登場。玉三郎を除くと、後ろから二番目に出てきた春猿が一番綺麗だった。皆、面をつけたつもりの無表情。
海老蔵は個人的にはあまり好きではないのだけれども、さすがに歌舞伎メイクをして装束をつけると美男子ぶりが堂に入る。「岩木ではないので」上臈たちに誘われてクラッとするあたり、真に迫っていて、芸の肥やしの豊富さを思わせます。
玉三郎が中の舞から急の舞へと進みつつ、酩酊して眠る維茂の様子を何度もうかがい確かめる仕種がユーモラスで笑える。彼の眠りを確認すると、上臈たちは怪しいムードを漂わせていったん消えて中入り。
ここへ仁左衛門扮する山神がやってきて、さかんに維茂をゆすり起こそうとするも、彼はいっこうに起きない。山神は呆れ果てて、太刀だけ置いてその場を去る。
後場、お能ならば般若の面をかけてくるところ、歌舞伎なので隈取り。玉三郎は黒頭、他の五名は赤頭。連獅子のように毛を振って威嚇する。維茂は山神にもらった太刀で鬼たちをばったばったとなぎ倒してめでたしめでたし。
後場の玉三郎の装束はモダンな感じもして可愛らしい色柄だった。
でも、結局のところ、わたしは玉三郎に隈取りしてガオーッと唸ったりしてほしくない。普通の歌舞伎がよいし、普通の舞踊がいい。昼の部に期待。
「源氏物語 夕顔」
これも舞踊劇らしい。源氏物語千年紀を記念して作られた新作で、作者はだいたい「信濃路紅葉鬼揃」と同じ。
舞踊というわりには、それらしいのは第二場の御息所(玉三郎)だけで、それ以外は何なのかな、中途半端なお芝居といったような。もともと、歌舞伎の源氏物は、平安朝の姫君の振るまいが軽すぎてピンとこない。いくら中流の女性とは言っても、夕顔自身が草履を引っかけて外に出て来るというのは馴染めない。
御息所が登場する場面ではぐっと照明が落とされ、暗い青い光の中で生霊の雰囲気満点。ただあまりに暗すぎて、連れの老母にはあまり見えなかった様子。
夕顔は元気で丈夫そうだったけれども、いつの間にか死んだらしい。第三場は、なんだか付け足しのようで存在意義がよくわからない。ちょっと尻切れトンボというか、ひょっとして海老蔵の光源氏姿を見せるためだけの演目なのか。
★今日の豆知識:お能由来の演目は〈松羽目もの〉と呼ぶ。
*****
『傾城反魂香 土佐将監閑居の場』
又平女房おとく:坂田藤十郎 又平:中村翫雀 他
『元禄忠臣蔵 大石内蔵助最後の一日』
内蔵助:中村吉右衛門 十郎左衛門:中村錦之助
おみの:中村芝雀 他
『信濃路紅葉鬼揃』
鬼女:坂東玉三郎 平維茂:市川海老蔵 山神:片岡仁左衛門
鬼女:市川門之助、上村吉弥、市川笑也、市川春猿、市川笑三郎 他
『源氏物語 夕顔』
光の君:市川海老蔵 六条御息所:坂東玉三郎
夕顔:中村扇雀 惟光:市川猿弥 他

歌舞伎を見るのは、だいたい仁左衛門と玉三郎が揃うときだけ。南座の顔見世については5年ぶりだった。
昼の部は後半に見ることにして、今日は夜の部。
相変わらず始まりが慌ただしい。開場が遅れようがどうしようが、時間になると拍子木が高らかになって幕が開く。プログラムを買って、イヤホンガイドを借りて、化粧室へ行って、荷物はどこかへ預けてなど、悠長に準備する暇はほとんどない。とりあえず、座席を見つけたら荷物を抱えたまま座ってただ舞台を見るのみ。
「傾城反魂香 土佐将監閑居の場」
又平のどもりの演技がくどくて、あまり好きになれないのだけれども、あれがないと後半のハッピーエンドも際だたないのだろうか。
手水鉢の石を絵が擦り抜ける仕掛けはどうなっているのだろうかと、そういえば以前見たときも思ったのだった(五年前の顔見世、同じ又平夫婦の配役だった)。
この又平さんと、〈傾城反魂香〉という題目の関係がよくわからなくて、調べたらこんなことだった。
→参考
「元禄忠臣蔵 大石内蔵助最後の一日」
内蔵助以下赤穂の義士たちに裁断が下り、いよいよ覚悟して死に臨むという男たちのシリアスなストーリーの脇から、ただ〈私の恋の真実〉にしか興味のない娘おみのが男装までして潜り込んでくるというちぐはぐさが奇妙で、けれども娘の必死の訴えを聞くうちに、義士たちの大義も娘の恋の真実も等価なのだと思われてくる。
義士たちは死に、吉良家もお家断絶、おみのも自害して、みな滅ぶのに、それこそがハッピーエンドだというところが実に日本的。かなり楽しめた演目。
「信濃路紅葉鬼揃」
お能「紅葉狩」の詞章をそのまま用い、杵屋巳吉が曲を付け、田中傳左衞門が作調、藤間勘十郎が振付をしたとのこと。昨年の歌舞伎座が初演。
舞台の書き割りは能舞台を模した鏡の松。さりげなく蔦紅葉が巻き付けてある。能舞台の屋根も書き割りで吊されている。こうしたお能由来の曲を〈松羽目もの〉と呼ぶらしい。囃子方が舞台後方にずらりと並ぶ。小鼓は傳左衞門、太鼓は傳次郎。
冒頭、玉三郎を筆頭に唐織壺折姿の上臈が六名、花道から登場。玉三郎を除くと、後ろから二番目に出てきた春猿が一番綺麗だった。皆、面をつけたつもりの無表情。
海老蔵は個人的にはあまり好きではないのだけれども、さすがに歌舞伎メイクをして装束をつけると美男子ぶりが堂に入る。「岩木ではないので」上臈たちに誘われてクラッとするあたり、真に迫っていて、芸の肥やしの豊富さを思わせます。
玉三郎が中の舞から急の舞へと進みつつ、酩酊して眠る維茂の様子を何度もうかがい確かめる仕種がユーモラスで笑える。彼の眠りを確認すると、上臈たちは怪しいムードを漂わせていったん消えて中入り。
ここへ仁左衛門扮する山神がやってきて、さかんに維茂をゆすり起こそうとするも、彼はいっこうに起きない。山神は呆れ果てて、太刀だけ置いてその場を去る。
後場、お能ならば般若の面をかけてくるところ、歌舞伎なので隈取り。玉三郎は黒頭、他の五名は赤頭。連獅子のように毛を振って威嚇する。維茂は山神にもらった太刀で鬼たちをばったばったとなぎ倒してめでたしめでたし。
後場の玉三郎の装束はモダンな感じもして可愛らしい色柄だった。
でも、結局のところ、わたしは玉三郎に隈取りしてガオーッと唸ったりしてほしくない。普通の歌舞伎がよいし、普通の舞踊がいい。昼の部に期待。
「源氏物語 夕顔」
これも舞踊劇らしい。源氏物語千年紀を記念して作られた新作で、作者はだいたい「信濃路紅葉鬼揃」と同じ。
舞踊というわりには、それらしいのは第二場の御息所(玉三郎)だけで、それ以外は何なのかな、中途半端なお芝居といったような。もともと、歌舞伎の源氏物は、平安朝の姫君の振るまいが軽すぎてピンとこない。いくら中流の女性とは言っても、夕顔自身が草履を引っかけて外に出て来るというのは馴染めない。
御息所が登場する場面ではぐっと照明が落とされ、暗い青い光の中で生霊の雰囲気満点。ただあまりに暗すぎて、連れの老母にはあまり見えなかった様子。
夕顔は元気で丈夫そうだったけれども、いつの間にか死んだらしい。第三場は、なんだか付け足しのようで存在意義がよくわからない。ちょっと尻切れトンボというか、ひょっとして海老蔵の光源氏姿を見せるためだけの演目なのか。
★今日の豆知識:お能由来の演目は〈松羽目もの〉と呼ぶ。
*****
『傾城反魂香 土佐将監閑居の場』
又平女房おとく:坂田藤十郎 又平:中村翫雀 他
『元禄忠臣蔵 大石内蔵助最後の一日』
内蔵助:中村吉右衛門 十郎左衛門:中村錦之助
おみの:中村芝雀 他
『信濃路紅葉鬼揃』
鬼女:坂東玉三郎 平維茂:市川海老蔵 山神:片岡仁左衛門
鬼女:市川門之助、上村吉弥、市川笑也、市川春猿、市川笑三郎 他
『源氏物語 夕顔』
光の君:市川海老蔵 六条御息所:坂東玉三郎
夕顔:中村扇雀 惟光:市川猿弥 他










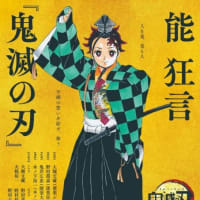









臨場感もいただきました。
松羽目ものだなんて、
芸能・芸術にもいろいろな相互の影響があるんですね。
今の言葉で言えば、パクリとか、いいとこ取りとか、いうのかな。
収益拡大のためにたゆまず努力か、単に手抜きか。
行った(結果的に滅亡)という事実もあります。
歌舞伎の演目って、大きく分けると、歌舞伎オリジナル、浄瑠璃由来、能曲由来があるのでしょうか。なんとなく、そんなふうに思っていますけれども。
お能には、歌舞伎からの逆輸入ってないのかしら。なにかあったような気もするけれど、思い出せません。
ちょうど日曜日に歌舞伎座で観てきた「高杯(たかつき)」も狂言のパロディのようでした。(えっと、どの狂言だったか、今名前が出てこない...)「たのうだお方」も「太郎冠者」も出てくるし、お装束も狂言装束^^。
歴史的にいえば武士主体の能楽を庶民も歌舞伎で楽しんだってことなんでしょうね。
掲示板の書き込みもありがとうございました!
東京の歌舞伎座ですね。
今の形であるうちに、もう一度行っておきたいと思います。